

料理を引き立てる“さやえんどう”



市場から
中央アジアから中近東地域が原産で、古代ギリシャ、ローマ時代から栽培されていた歴史ある野菜です。地中海地方と中国で栽培種が発達し、日本へは8世紀前後に中国から穀物として伝えられたとされていますが、野菜として栽培され始めたのは江戸時代になってからです。
成熟するまでの各過程が楽しめる作物で、あんみつや豆大福などによく用いられる完熟実のえんどう豆のほか、野菜としてのえんどうには、若い茎芽を利用する豆苗や若いさやを実が入ったままの状態で食用とするさやえんどう、未熟な青いうちに収穫し中の実を食用とするグリーンピースがあります。
日本で江戸時代に栽培が始まった当初は、収穫初期に若さやを食べ、次にグリーンピースとして料理に使い、最後に完熟豆を穀物として収穫していましたが、明治時代に入ってからは、欧米各国からさや用、青豆用、完熟豆用と様々な品種が導入され、全国各地で栽培されるようになりました。
料理の彩りや付け合わせに用いられることが多い関東地方で流通の大半を占めるのは、小型種の絹さやえんどうです。一方、甘煮や和え物などおかずとして食卓にのぼることが多い関西地方では絹さやえんどうのほか、大型種のおおさやえんどうや生鮮のグリーンピースの流通量が多いのが特徴です。また、直売所での売れ筋野菜の一つで、地場消費量が多いことも特徴です。
産地の移行や施設の利用のほか、輸入ものも含め一年中出回っていますが、おいしい時期は4~6月にかけて。この時期は栄養価が高まり、甘味も強くなります。
生産者の高齢化や安い輸入ものの増加によって、作付面積・収穫量ともに減少傾向で推移していましたが、今年は国産回帰の流れのほか、重油高騰の影響で加温温度の高い施設栽培から転換した農家の増加により、一部の産地で作付面積が増えています。
もっとおいしく! オススメの食べ方
汁の実や炒め物、煮びたし、卵とじのほか、美しい緑色を生かしてちらし寿司や五目ご飯などに入れてもおいしいです。
おいしい“さやえんどう”を選ぼう!
全体が緑鮮やかで、さやにハリとツヤがあり、ひげが白くピンとしたものが新鮮です。
絹さやえんどうは、豆が極力小さく板のようにさやが板のように薄いものを、スナップえんどうとグリーンピースは、さや全体に豆がぎっしり詰まりさやがふっくらとしたものを選びましょう。
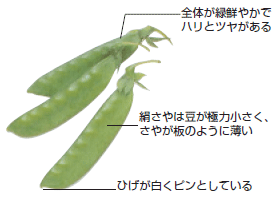
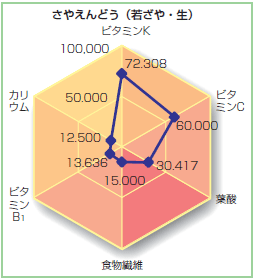
さやえんどうは、老化やがんの抑制に効果的なカロテンを豊富に含む緑黄色野菜です。また、免疫力を高め、風邪の予防に効果的なビタミンCはトマトの4倍の含有量です。そのほか、エネルギー代謝や疲労回復に効果的なビタミンB群や整腸効果が期待できる食物繊維も豊富に含みます。
「五訂日本食品標準成分表」 さやえんどう(若ざや・生)より
30歳の女性1日当たりの食事摂取基準を100とした場合におけるさやえんどう(若ざや・生)100グラム中に含まれる主な栄養素の割合(ただし、ビタミンK、食物繊維、カリウムは目安量の値を、その他は推奨量の値)。
さやえんどうは、グルタミン酸を非常に多く含むことも特徴で、その含有量は野菜の中でも多いとされるトマトの6倍ほど。
グルタミン酸は、うま味成分としても利用される非必須アミノ酸で、さやえんどうを食べたときにうま味や甘味を感じるのはグルタミン酸によるものです。グルタミン酸には脳や神経の機能を活性化したり、尿の排泄を促す作用があります。
~成長期には欠かせない さやえんどうの‘リジン’~
さやえんどうは、成長期に欠かせない必須アミノ酸のリジンを含みます。リジンには、体組織の修復に関与して体の成長を促進する作用があるため、唇の荒れや皮膚炎を予防する効果が期待できます。さやえんどうのいろいろ 種類・品種の特徴 ※クリックすると拡大します。
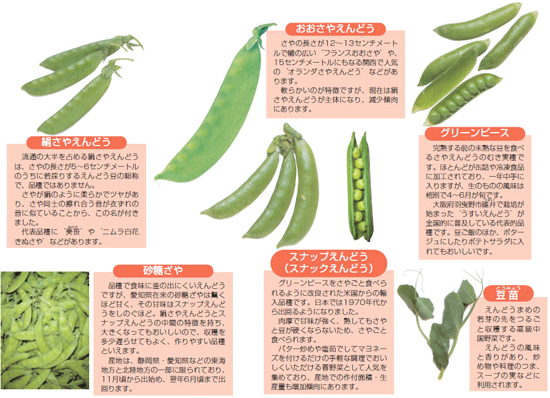
※クリックすると拡大します。
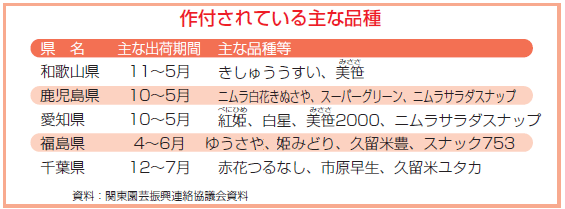
2007(平成19)年の全国の作付面積は4,370ヘクタール、収穫量は27,500トンです。
冬作物であるさやえんどうの生育適温は、10~20度で冷涼な気候を好み、低温伸張性が高い作物です。
寒地・寒冷地では5~10月まで、暖地・温暖地では10月から翌春まで収穫・出荷され、産地連携により周年供給が成立しています。5~6月は福島県産、7~9月頃は北海道産、10~12月頃は鹿児島県産、1~4月は愛知県が多くなりますが、施設栽培により入荷の平準化が進んでいます。また、年間を通して中国からの輸入ものも多く出回っています。
一晩で2~3センチメートルも育つため、出荷の時期には、朝早くから夕方まで1日中収穫作業が行われます。
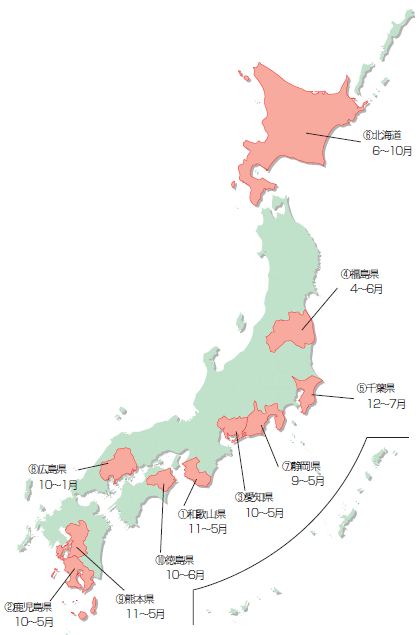

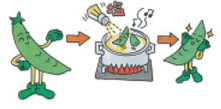 絹さやえんどうとスナップえんどうは、さやごと食べるので筋があると食味が悪くなります。下ごしらえとしてヘタの部分を手で折り、そのまま静かに引いて筋を取ります。たっぷりの熱湯に一つまみの塩を入れ、短時間にさっと茹でます。鮮やかな緑色と歯触りの良さが身上なので、茹で上がったら手早く盆ざるなどに上げ、冷水にサッとくぐらせます。グリーンピースは、さやから外し、ひと粒ずつにして同様に茹でますが、豆ご飯の場合は、炊く前に生のまま加えます。
絹さやえんどうとスナップえんどうは、さやごと食べるので筋があると食味が悪くなります。下ごしらえとしてヘタの部分を手で折り、そのまま静かに引いて筋を取ります。たっぷりの熱湯に一つまみの塩を入れ、短時間にさっと茹でます。鮮やかな緑色と歯触りの良さが身上なので、茹で上がったら手早く盆ざるなどに上げ、冷水にサッとくぐらせます。グリーンピースは、さやから外し、ひと粒ずつにして同様に茹でますが、豆ご飯の場合は、炊く前に生のまま加えます。
【保存方法】
 なるべく早く食べ切りましょう。保存する場合は、乾燥しないようキッチンペーパーなどに包んでからビニール袋に入れ野菜室(5~10度)で保存します。1~2日が目安です。冷凍保存する場合は、硬めに茹でて水気をしっかり切り、袋に入れて密閉します。
なるべく早く食べ切りましょう。保存する場合は、乾燥しないようキッチンペーパーなどに包んでからビニール袋に入れ野菜室(5~10度)で保存します。1~2日が目安です。冷凍保存する場合は、硬めに茹でて水気をしっかり切り、袋に入れて密閉します。みなべいなみ農業協同組合(さやえんどう)
 監修:実践女子大学教授
監修:実践女子大学教授