

江戸の昔から食されてきた伝統的野菜“かぶ”

関東地方を中心に全国で周年栽培されています。

市場から
世界中の温帯地域で広く栽培されている“かぶ”の原産地は、アフガニスタン周辺か、これに地中海沿岸の南ヨーロッパを加えた地域といわれています。
日本には弥生時代に伝わったといわれており、『日本書紀』(720年)によると五穀(主食)を補う重要な根菜として栽培が奨励されていました。すずしろ(大根)とともに春の七草‘すずな’に数えられ、江戸時代には、大衆野菜として各地で特産的な栽培品種が数多く誕生し、現在の品種の基礎ができあがったといわれています。
根の大小、形状(丸~縦長)、色合い(白、赤、紫、緑、淡黄)などの違いによりさまざまな品種が全国各地に見られますが、大別すると、中国経由で西日本に渡来した日本型とヨーロッパから朝鮮半島を経て東日本に渡来した西洋型があり、関ヶ原付近の愛知県~岐阜県~福井県を結ぶラインを境に分布が大きく分けられます。中尾佐助氏は、このような日本の東と西でかぶの品種分布の明らかな違いを見つけ、“かぶらライン”と呼びました。西日本に分布する日本型は、気温に敏感でとうが立ちやすい品種が多く、葉や茎に毛があり、葉は立ち性。全体的に中型から大型のかぶが多いようです。東日本に分布する西洋型は耐寒性が強く、日本型に比べるとツルツルしています。また、境界線地域には中間種が存在しています。
だいこんが青首系一色になりつつあるのに対し、80余種を数えるかぶの地方品種は健在で、今でも京都の聖護院かぶを薄切りにした千枚漬、滋賀の日野菜の桜漬けなど特産の漬物や郷土料理になくてはならない素材として、守り続けられています。
現在、流通の大半を占めるのは、東京都葛飾区金町の特産だった‘金町小かぶ’を品種改良したものです。露地とハウスの併用で周年出回っていますが、おいしい時期は、3~5月と10~12月。
食生活の洋風化とともに、家庭で漬物を作る機会も減少し、産地での生産者の高齢化もあり、生産量は近年減少傾向で推移していますが、根も葉もすべて食べられるムダのないかぶは、栄養的にも優れており、冷蔵庫を使えば低塩分の漬物の保存もできるので、見直したい野菜の一つです。
もっとおいしく! オススメの食べ方
生のシャッキリ感を楽しむには、サラダや菊花かぶなどの酢の物、漬け物に。また、火を通したときの軟らかなほっくり感を楽しみたいときは、クリーム煮やそぼろあんかけなどがおすすめです。葉もあくが少なく軟らかいので、和え物、みそ汁の実のほか、ちりめんじゃこやベーコンなど旨味が出るものとの炒め煮などにするとおいしいです。
おいしい“かぶ”を選ぼう!
葉の色が鮮やかでみずみずしいものを選びましょう。茎がしっかりしていて、根は肌のきめが細かく、ツヤがあるものが新鮮です。表皮に傷や割れ目があるものや、触って軟らかいものは避けましょう。
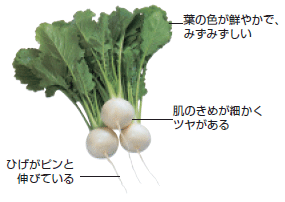
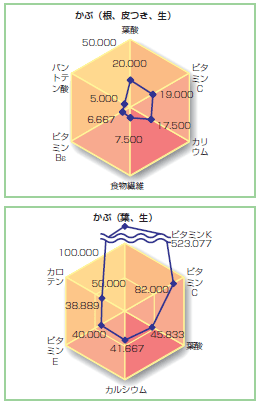
かぶは葉と根で栄養成分が大きく異なります。
昔は根の部分より葉のほうが重要視されていたように、かぶの葉はカロテン、ビタミンC・B1・B2などを豊富に含む、野菜の中でも突出した高ビタミン食品です。また、カルシウム、鉄などのミネラルも比較的多く含み、かぶ1束分の葉は、ほうれんそうやしゅんぎくに十分匹敵するぐらいの優れた緑黄色野菜です。
一方、淡色野菜である白い根の部分は、糖質や繊維などの炭水化物のほか、胸やけや胃もたれの改善が期待できる消化酵素を多く含みます。
その他、アブラナ科野菜に共通した特徴として、刺激性辛み物質の元となるグルコシノレートという成分を含みます。グルコシノレートは肝臓の解毒作用を活性化させるため、がん予防が期待できます。
「五訂日本食品標準成分表」かぶ(根・皮つき・生、葉・生)より
30歳の女性1日当たりの食事摂取基準を100とした場合におけるかぶ(根・皮つき・生、葉・生)100グラム中に含まれる主な栄養素の割合。(ただし、カリウム、食物繊維、パントテン酸、ビタミンK・Eは目安量の値を、その他は推奨量の値を用いた。)
かぶの根には、でんぷんの消化酵素であるジアスターゼが豊富に含まれており、胃酸をコントロールして消化・吸収を助ける働きがあります。そのため、かぶと一緒に、ご飯や麺、パンなどの主食を食べると胸やけや胃もたれがしません。また、昔から、お腹の薬として広く利用されており、腹痛のとき、かぶをおろした汁を2~3杯飲むとよいといわれていますが、胃腸を温める作用があるので、冷えが原因の腹痛にも効果があります。
これらの酵素を生かすには、生で食べるのが一番です。
かぶのいろいろ 種類・品種の特徴
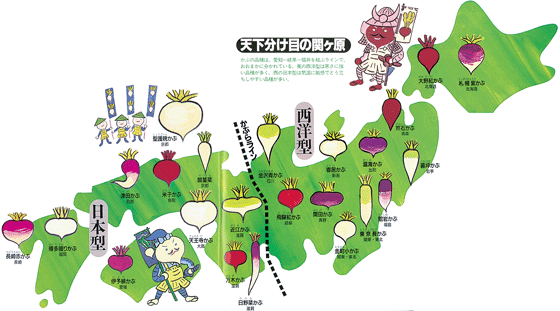
※クリックすると拡大します。
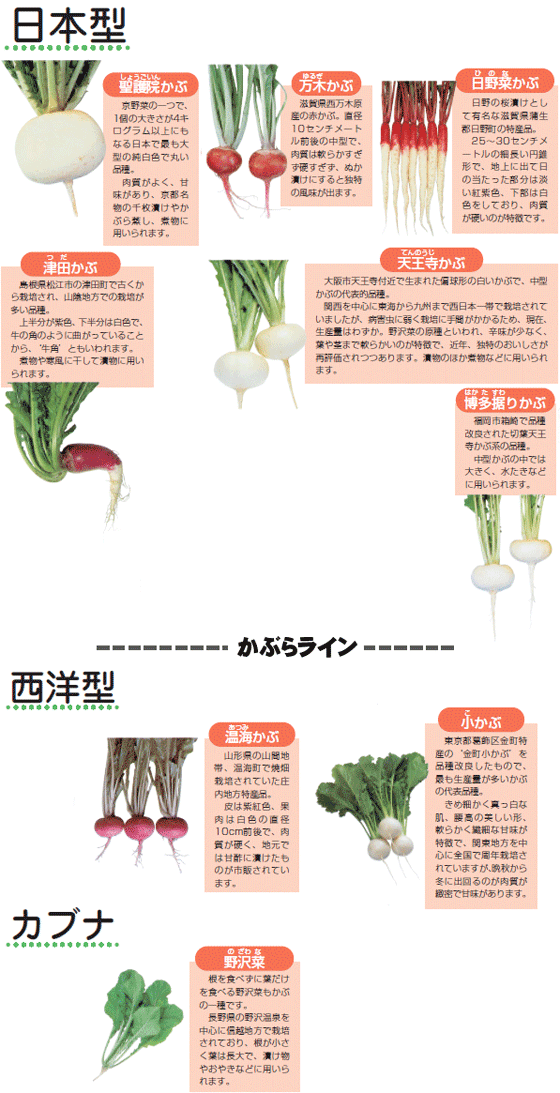
※クリックすると拡大します。
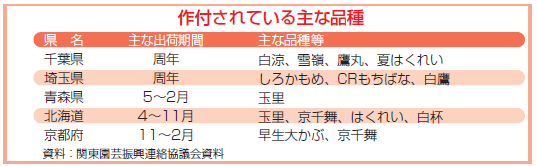
2007(平成19)年の全国の作付面積は5,360ヘクタール、収穫量は159,300トンとなっており、近年減少傾向が続いています。
生育適温は、15~20度。冷涼な気候を好み、高温や低温条件下では根の肥大が劣ります。最近は品種改良が進んで、耐暑性が強く夏播きに向く品種や低温でもよく太る品種があり、栽培農家は季節によって多くの品種を使い分けています。
主産地は、千葉が全国の生産量の約30%、全国の作付面積の約20%を占め、次いで埼玉、青森、北海道、京都と続きます。主産地では専業化が進み、被覆資材などを利用して夏場も含めて周年出荷が行われています。
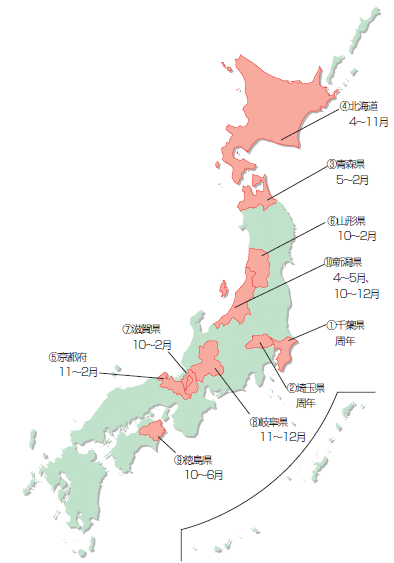

【保存方法】 葉を付けたままにしておくと、葉が水分を吸収し、ス入りの原因になります。買ったらすぐに根と葉を切り分け、霧吹きで水分を与えてから、葉は濡れた新聞紙などに包み、根はビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で別々に保存しましょう。葉は沸騰した湯に塩をひとつまみ入れ、下ゆでした後水にさらし、十分に絞ってからラップで包んで冷凍すると、いつでも使えて便利です。
いるま野農業協同組合(かぶ)
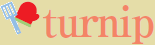 監修:実践女子大学教授
監修:実践女子大学教授