

ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 信州大学発「信大BS8-9」夏秋いちごの常識を覆し、全国に栽培拡大!
国立大学法人信州大学 総務部総務課 広報室
1 四季成り品種のイメージを根底から覆す
いちごの品種は、冬春に収穫する一季成りと呼ばれるものと、主に夏秋に収穫する四季成りに大別される。冬にスーパーマーケットなどの店頭でよく見かける「とちおとめ」や「あまおう」といった品種はすべて一季成りである。対して四季成りは、名前の通り周年を通じて収穫が可能な品種であり、その特性から一季成りの栽培が難しい夏秋に収穫できるよう栽培されてきた。
いちごは、ケーキなどの業務用を中心に一年を通して需要があり、国内では、数種類の四季成り品種が栽培されてきたが、かつてその味はいずれも一季成りの足元にも及ばないものとされ、夏秋の市場の80~90%を米国産の輸入品が占めていたが、それは、国産より発色がいいという程度の理由からデコレーションアイテム用としてであったという。
そんな従前の四季成り品種のイメージを根底から覆したのが、国立大学法人信州大学(以下「信州大学」という)の大井美知男名誉教授(以下「大井名誉教授」という)が開発し、信州大学が品種登録した夏秋いちご「信大BS8-9」である(写真1)。

いちごは、ケーキなどの業務用を中心に一年を通して需要があり、国内では、数種類の四季成り品種が栽培されてきたが、かつてその味はいずれも一季成りの足元にも及ばないものとされ、夏秋の市場の80~90%を米国産の輸入品が占めていたが、それは、国産より発色がいいという程度の理由からデコレーションアイテム用としてであったという。
そんな従前の四季成り品種のイメージを根底から覆したのが、国立大学法人信州大学(以下「信州大学」という)の大井美知男名誉教授(以下「大井名誉教授」という)が開発し、信州大学が品種登録した夏秋いちご「信大BS8-9」である(写真1)。

2 長野県の生産者の夏の収入を支えたい
信大BS8-9開発のきっかけは、「長野県の生産者の夏の収入を支えたい」という大井名誉教授の想いだった(写真2)。大井名誉教授が信州大学に赴任した昭和の終わり頃、夏季の葉物野菜の生産は、東京など大消費地との交通網が発達していた長野県の独壇場だった。しかし高速道路が開通して、東北に大きな産地が続々とでき、価格が一気に下落してしまった。この危機的な状況に対し、「長野県の生産者のために、葉物に代わって夏の農業を支える作物が必要だ」と感じ、色々と検討を重ねた末に決意したのがおいしい夏秋いちごの開発だった。
当時、いちごといえば冬春の作物であり、夏秋の国産品種もあるにはあるが、味も色味も優れる輸入品の独壇場だった。それを国産品に置き換えられれば、国の農業という点からも意味があると考えたという。
「輸入品が優れるといっても、それは例えば夏場のケーキのいちごに誰も手を付けないレベル。冬春いちごに負けない夏秋いちごを作れば必ず売れると思った」と考え、大井名誉教授は、まず一季成り、四季成りを問わず在来品種の収集から始めた。そして、集まった約60品種の苗を掛け合わせたり、余計な遺伝子を取るなどして、試行錯誤の末に信大BS8-9が誕生した。
「目指したのは『冬春を超えるいちご』。具体的には糖度が高く、甘酸バランスがいいこと。色は美しい赤で、断面も赤いこと。きれいな円錐形をしていること。ケーキ屋さんが使いやすい一粒12~23、24gくらいのサイズ感も重視した」と言う。
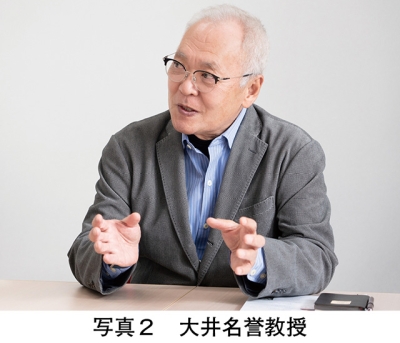
当時、いちごといえば冬春の作物であり、夏秋の国産品種もあるにはあるが、味も色味も優れる輸入品の独壇場だった。それを国産品に置き換えられれば、国の農業という点からも意味があると考えたという。
「輸入品が優れるといっても、それは例えば夏場のケーキのいちごに誰も手を付けないレベル。冬春いちごに負けない夏秋いちごを作れば必ず売れると思った」と考え、大井名誉教授は、まず一季成り、四季成りを問わず在来品種の収集から始めた。そして、集まった約60品種の苗を掛け合わせたり、余計な遺伝子を取るなどして、試行錯誤の末に信大BS8-9が誕生した。
「目指したのは『冬春を超えるいちご』。具体的には糖度が高く、甘酸バランスがいいこと。色は美しい赤で、断面も赤いこと。きれいな円錐形をしていること。ケーキ屋さんが使いやすい一粒12~23、24gくらいのサイズ感も重視した」と言う。
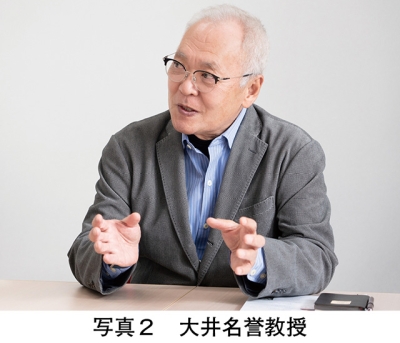
3 「生産者主体」の仕組みで、栽培者が全国に拡大
大井名誉教授は、「生産者を主体としたものにしたい」という理念に基づき、信大BS8-9の開発を行い、普及に取り組んでいる。
開発面では、生産者が生産しやすいように耐病性を意識しており、うどん粉病や炭疽病などの土壌病などに強いという。販売面では、硬度があって日持ちがしやすいようにしたそうだ。
また、ネーミングという面からも、品種登録を行った信州大学と協議し、信大BS8-9のネーミングを自由にできるようにした。例えば、広島県庄原市のナチュラルファームタニグチでは「タカノプリンセス」「タカノクイーン」、北海道足寄町の足寄ぬくもり農園では「スウィーティ・アマン」と名付けられている。
さらに、当初の品種の共同管理者であった株式会社アグリスとは、生産者が自由に自家増殖できるライセンスフリーとすることを協議し、自家増殖を認めるようにした。「自分だけの名前の方がやりがいが出るし、自分が栽培しやすい苗の方が愛着も湧くでしょう。何より国立大学らしいと思いませんか?」と大井名誉教授は話す。
開発面では、生産者が生産しやすいように耐病性を意識しており、うどん粉病や炭疽病などの土壌病などに強いという。販売面では、硬度があって日持ちがしやすいようにしたそうだ。
また、ネーミングという面からも、品種登録を行った信州大学と協議し、信大BS8-9のネーミングを自由にできるようにした。例えば、広島県庄原市のナチュラルファームタニグチでは「タカノプリンセス」「タカノクイーン」、北海道足寄町の足寄ぬくもり農園では「スウィーティ・アマン」と名付けられている。
さらに、当初の品種の共同管理者であった株式会社アグリスとは、生産者が自由に自家増殖できるライセンスフリーとすることを協議し、自家増殖を認めるようにした。「自分だけの名前の方がやりがいが出るし、自分が栽培しやすい苗の方が愛着も湧くでしょう。何より国立大学らしいと思いませんか?」と大井名誉教授は話す。
4 全国に広がる信大BS8-9
こうした生産者主体の取り組みが奏功し、北は北海道猿払村から南は沖縄県読谷村まで全国で約60カ所で8万6000株(2024年時点)が栽培されている。以下、主な生産者の例を紹介する。
(1)ナチュラルファームタニグチ(広島県庄原市)
~G7サミットでも提供されたトップランナー~
まず、ナチュラルファームタニグチを紹介する。同農園の谷口博紀氏(以下「谷口氏」という)が栽培する信大BS8-9は、そのおいしさが高い評価を受け、数多くの受賞実績がある。
2019年、農林水産省が国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体等の優れた取り組みを表彰する「フードアクションニッポンアワード」を受賞し、20年、作物の栄養価を競う「オーガニックエコフェスタ栄養価コンテスト2020」のいちご部門で最優秀賞を受賞している(写真3)。
さらに、23年に開催されたG7広島サミットでは、首相夫人主催の夕食会においてコース料理の最初に出てくるアミューズとして採用された。アミューズはシェフのセンスの見せどころとなるため、谷口氏の栽培した信大BS8-9への信頼がうかがえる。
谷口氏は「日本一の夏秋いちごを作る」と決意し、独立以来ずっと信大BS8-9に情熱
を注いできた。その出荷方法は、非破壊糖度計で一粒ずつ糖度を計測するのが基本で、6月中旬~11月中旬にかけて収穫した糖度9度以上のいちごを「タカノプリンセス」、11月下旬~12月中旬に収穫した糖度15度以上のものを「タカノクイーン」と名付け、2ブランド展開している。
圃場は5アールで、毎年きっちり2980株を栽培しており、この半端に思える株数は、「しっかり30cm間隔を確保したらたまたまそうなった」というこだわりからである。「梅雨時などは毎日。おそらく他の生産農家さんの倍以上は撒く」という栄養分の葉面散布など、品質を重視したいちごづくりを目指しているという。
夢は、夏場に糖度20度以上のいちごを安定的につくり、巷を賑わせる冬春いちごの大型品種同様に、1粒5万円のタカノプリンセスを生み出すこと。谷口氏が暮らす高野町の活性化という願いも込められたトップランナーのいちごに、信大BS8-9のさらなるバリューの向上が期待される。

(2)足寄ぬくもり農園(北海道足寄町)
~温泉熱利用で通年栽培、加工品も人気~
冬期は最低気温がマイナス25℃にも達することがある足寄町で、苗の生産と合わせ15棟のハウスでいちご栽培をする足寄ぬくもり農園では、敷地内からも湧出する55℃の温泉の熱を利用した暖房を設置することで、通年栽培を実現している。「年々技術も向上し、2万5000株(うち信大BS8-9は1万5000株)に対して、2020年は12トンだった収量が、23年には20トンになった。単純計算で1株800gという好成績です」と、JAあしょろ農産部施設課の佐々木俊次氏は言う。一株で採れるいちごの平均は600g程度と言われる中でこの数字はかなり優秀なのだとか。同園では、信大BS8-9に「スウィーティ・アマン」というオウンネームを付け、JAが運営するAコープの他、十勝管内のデパートやスーパーなどで購入ができる。その他、ふるさと納税の返礼品としても高い人気を誇っているそうだ。
また、同園ではスウィーティ・アマン100%の加工品を製造している。収量の約20%を加工品に回し、ハウス横に設置した冷凍設備で冷凍した採れたての信大BS8-9だけを使い、委託先で製造したジャム(「赤いちごジャム」と「赤いちごバタージャム」の2種類)とジェラート(「ストロベリーミルク」、「ストロベリーチーズケーキ」など5種類)は、押しも押されぬ看板商品なのだという(写真4)。「人気の秘密は、高糖度な信大BS8-9の含有量で、ジャムは全体の50~60%が、ジェラートは1カップに2~3粒のスウィーティ・アマンが使われ、信大BS8-9ならではの豊かな香りと自然な甘さが魅力」と佐々木氏は語る。次なる新商品も検討中だ。

(3)MHCトリプルウィン(株)食・農事業部 沖縄事業所(沖縄県読谷村)
~沖縄でもいちごの地産地消を~
農家向けのファイナンスを行ってきた東京の企業MHCトリプルウィン株式会社が、2017年3月、実際に自分たちも農業に携わろうと、沖縄・読谷村に事業所を設立した。その圃場で育てる信大BS8-9に「Berry Moon(ベリームーン)」というオウンネームを付け、今では読谷村産のいちごとして地元で定着している。「どうせなら、栽培には不向きな南国でやってみようと考えました」と語るのは、2022年春まで事業所長を務めた長部晃典氏である。冒険的なその考えの裏には「沖縄のいちごはそれまでほとんどが県外産。地産地消できるようになれば、地域貢献になる」という想いがあったそうだ。
台風対策など沖縄ならではの苦労を3年がかりで乗り越えて、当初300坪(約10アール)だったハウスをさらに2020年に240坪(約8アール)増床させ、計540坪(約18アール)までに成長させた。現在は1万500株のBerryMoonを栽培し、生鮮品の出荷に加えて加工品向けの原料も生産し、リゾートホテルで供されたり、県内の有名飲料メーカーの原料として主に沖縄県内で消費されていると言う。
「沖縄の方は酸味を好まれるのですが、信大BS8-9のほどよい酸っぱさと強い香りを気に入っていただいています」と長部氏の言う通り、オリオンビール株式会社が缶チューハイ「WATTA」の「いちごスパークリング」として、フォーモストブルーシール株式会社が信大BS8-9をメインに読谷村で栽培された他品種も加えた「読谷村いちご」を使ったカップアイス「沖縄ストロベリー&クッキー」として、いずれも大人気の限定商品となっている(写真5)。その他、地元の高級リゾートホテルや洋菓子店でもウェルカムフルーツや各種スイーツに使用され、県外からの観光客にも愛されている。

(4)(株)苗香屋(のうかや)(長野県伊那市)
~バス会社の農業部門でも栽培に乗り出す~
長野県伊那市で「恋姫」というオウンネームで信大BS8-9の栽培を行っているのは、株式会社苗香屋(以下「苗香屋」という)で、計1万株の信大BS8-9を栽培している。苗香屋は、地域の交通を支える伊那バス株式会社(以下「伊那バス」という)の中に2015年に新設されたアグリ事業部から分社化され、22年にできた会社である。伊那バスの創業100周年の記念事業が、信大BS8-9の生産だった。
苗香屋が栽培する信大BS8-9のおいしさは折り紙つきで、2023年12月に日本野菜ソムリエ協会主催の「クリスマスいちご選手権」で入賞した。「夏いちご=まずい!という認識をきっちり覆し、冬いちごと肩を並べたことは間違いありません」と取締役の青木一徳氏は話す。
また、「恋姫」の栽培が元々伊那バスの事業を発端とすることから、そのPRにラッピングバス※を制作した(写真6)。中まで赤い信大BS8-9の巨大な姿が強烈な真っ赤なバスで、伊那市の友好締結都市である新宿区の宝塚大学東京メディア芸術学部の学生たちがデザインしたものである。学生たちは、まず伊那を知ろうと何度も伊那に足を運び、2年半以上をかけて延べ数百ものデザインを起こしてくれたという。その甲斐があり、「恋姫」の認知に一役も二役も買った。
(※現在はバスの老朽化に伴い、惜しまれながら退役した)

(1)ナチュラルファームタニグチ(広島県庄原市)
~G7サミットでも提供されたトップランナー~
まず、ナチュラルファームタニグチを紹介する。同農園の谷口博紀氏(以下「谷口氏」という)が栽培する信大BS8-9は、そのおいしさが高い評価を受け、数多くの受賞実績がある。
2019年、農林水産省が国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体等の優れた取り組みを表彰する「フードアクションニッポンアワード」を受賞し、20年、作物の栄養価を競う「オーガニックエコフェスタ栄養価コンテスト2020」のいちご部門で最優秀賞を受賞している(写真3)。
さらに、23年に開催されたG7広島サミットでは、首相夫人主催の夕食会においてコース料理の最初に出てくるアミューズとして採用された。アミューズはシェフのセンスの見せどころとなるため、谷口氏の栽培した信大BS8-9への信頼がうかがえる。
谷口氏は「日本一の夏秋いちごを作る」と決意し、独立以来ずっと信大BS8-9に情熱
を注いできた。その出荷方法は、非破壊糖度計で一粒ずつ糖度を計測するのが基本で、6月中旬~11月中旬にかけて収穫した糖度9度以上のいちごを「タカノプリンセス」、11月下旬~12月中旬に収穫した糖度15度以上のものを「タカノクイーン」と名付け、2ブランド展開している。
圃場は5アールで、毎年きっちり2980株を栽培しており、この半端に思える株数は、「しっかり30cm間隔を確保したらたまたまそうなった」というこだわりからである。「梅雨時などは毎日。おそらく他の生産農家さんの倍以上は撒く」という栄養分の葉面散布など、品質を重視したいちごづくりを目指しているという。
夢は、夏場に糖度20度以上のいちごを安定的につくり、巷を賑わせる冬春いちごの大型品種同様に、1粒5万円のタカノプリンセスを生み出すこと。谷口氏が暮らす高野町の活性化という願いも込められたトップランナーのいちごに、信大BS8-9のさらなるバリューの向上が期待される。

(2)足寄ぬくもり農園(北海道足寄町)
~温泉熱利用で通年栽培、加工品も人気~
冬期は最低気温がマイナス25℃にも達することがある足寄町で、苗の生産と合わせ15棟のハウスでいちご栽培をする足寄ぬくもり農園では、敷地内からも湧出する55℃の温泉の熱を利用した暖房を設置することで、通年栽培を実現している。「年々技術も向上し、2万5000株(うち信大BS8-9は1万5000株)に対して、2020年は12トンだった収量が、23年には20トンになった。単純計算で1株800gという好成績です」と、JAあしょろ農産部施設課の佐々木俊次氏は言う。一株で採れるいちごの平均は600g程度と言われる中でこの数字はかなり優秀なのだとか。同園では、信大BS8-9に「スウィーティ・アマン」というオウンネームを付け、JAが運営するAコープの他、十勝管内のデパートやスーパーなどで購入ができる。その他、ふるさと納税の返礼品としても高い人気を誇っているそうだ。
また、同園ではスウィーティ・アマン100%の加工品を製造している。収量の約20%を加工品に回し、ハウス横に設置した冷凍設備で冷凍した採れたての信大BS8-9だけを使い、委託先で製造したジャム(「赤いちごジャム」と「赤いちごバタージャム」の2種類)とジェラート(「ストロベリーミルク」、「ストロベリーチーズケーキ」など5種類)は、押しも押されぬ看板商品なのだという(写真4)。「人気の秘密は、高糖度な信大BS8-9の含有量で、ジャムは全体の50~60%が、ジェラートは1カップに2~3粒のスウィーティ・アマンが使われ、信大BS8-9ならではの豊かな香りと自然な甘さが魅力」と佐々木氏は語る。次なる新商品も検討中だ。

(3)MHCトリプルウィン(株)食・農事業部 沖縄事業所(沖縄県読谷村)
~沖縄でもいちごの地産地消を~
農家向けのファイナンスを行ってきた東京の企業MHCトリプルウィン株式会社が、2017年3月、実際に自分たちも農業に携わろうと、沖縄・読谷村に事業所を設立した。その圃場で育てる信大BS8-9に「Berry Moon(ベリームーン)」というオウンネームを付け、今では読谷村産のいちごとして地元で定着している。「どうせなら、栽培には不向きな南国でやってみようと考えました」と語るのは、2022年春まで事業所長を務めた長部晃典氏である。冒険的なその考えの裏には「沖縄のいちごはそれまでほとんどが県外産。地産地消できるようになれば、地域貢献になる」という想いがあったそうだ。
台風対策など沖縄ならではの苦労を3年がかりで乗り越えて、当初300坪(約10アール)だったハウスをさらに2020年に240坪(約8アール)増床させ、計540坪(約18アール)までに成長させた。現在は1万500株のBerryMoonを栽培し、生鮮品の出荷に加えて加工品向けの原料も生産し、リゾートホテルで供されたり、県内の有名飲料メーカーの原料として主に沖縄県内で消費されていると言う。
「沖縄の方は酸味を好まれるのですが、信大BS8-9のほどよい酸っぱさと強い香りを気に入っていただいています」と長部氏の言う通り、オリオンビール株式会社が缶チューハイ「WATTA」の「いちごスパークリング」として、フォーモストブルーシール株式会社が信大BS8-9をメインに読谷村で栽培された他品種も加えた「読谷村いちご」を使ったカップアイス「沖縄ストロベリー&クッキー」として、いずれも大人気の限定商品となっている(写真5)。その他、地元の高級リゾートホテルや洋菓子店でもウェルカムフルーツや各種スイーツに使用され、県外からの観光客にも愛されている。

(4)(株)苗香屋(のうかや)(長野県伊那市)
~バス会社の農業部門でも栽培に乗り出す~
長野県伊那市で「恋姫」というオウンネームで信大BS8-9の栽培を行っているのは、株式会社苗香屋(以下「苗香屋」という)で、計1万株の信大BS8-9を栽培している。苗香屋は、地域の交通を支える伊那バス株式会社(以下「伊那バス」という)の中に2015年に新設されたアグリ事業部から分社化され、22年にできた会社である。伊那バスの創業100周年の記念事業が、信大BS8-9の生産だった。
苗香屋が栽培する信大BS8-9のおいしさは折り紙つきで、2023年12月に日本野菜ソムリエ協会主催の「クリスマスいちご選手権」で入賞した。「夏いちご=まずい!という認識をきっちり覆し、冬いちごと肩を並べたことは間違いありません」と取締役の青木一徳氏は話す。
また、「恋姫」の栽培が元々伊那バスの事業を発端とすることから、そのPRにラッピングバス※を制作した(写真6)。中まで赤い信大BS8-9の巨大な姿が強烈な真っ赤なバスで、伊那市の友好締結都市である新宿区の宝塚大学東京メディア芸術学部の学生たちがデザインしたものである。学生たちは、まず伊那を知ろうと何度も伊那に足を運び、2年半以上をかけて延べ数百ものデザインを起こしてくれたという。その甲斐があり、「恋姫」の認知に一役も二役も買った。
(※現在はバスの老朽化に伴い、惜しまれながら退役した)

5 一般社団法人の設立や、海外輸出も
このように、全国で栽培が広がっている信大BS8-9だが、さらなる発展に向けた取り組みも出てきている。
その一つが、新たに「一般社団法人信大BS8-9協議会」が設立されたことである。これにより、今後は信大BS8-9に関わるすべての事業が、信州大学の管理の下、同協議会が担っていくかたちが検討されている。従来の苗の育成・販売に加え、気候変動の影響などにより、夏秋いちごの栽培が難しくなってきていることから、生産者の元に指導に赴き、栽培に関する情報発信も行っていきたい考えだ。このほかにも、資材の高騰や、販売先の確保など、栽培農家の頭を悩ます課題は山積しており、栽培農家が一丸となって打開するサポートを行っていきたいと協議会は考えている。
一方で、農産物の海外輸出が国策として推進されている中で、東南アジアや北米に向けた輸出に取り組んでいこうとしている信大BS8-9生産者も出てきている。その品質は国内では既に高い評価を得ているだけに、今後、信大BS8-9が世界でも従来の常識を覆すおいしい夏秋いちごとして、多くの人に驚きを与えることを期待する。
その一つが、新たに「一般社団法人信大BS8-9協議会」が設立されたことである。これにより、今後は信大BS8-9に関わるすべての事業が、信州大学の管理の下、同協議会が担っていくかたちが検討されている。従来の苗の育成・販売に加え、気候変動の影響などにより、夏秋いちごの栽培が難しくなってきていることから、生産者の元に指導に赴き、栽培に関する情報発信も行っていきたい考えだ。このほかにも、資材の高騰や、販売先の確保など、栽培農家の頭を悩ます課題は山積しており、栽培農家が一丸となって打開するサポートを行っていきたいと協議会は考えている。
一方で、農産物の海外輸出が国策として推進されている中で、東南アジアや北米に向けた輸出に取り組んでいこうとしている信大BS8-9生産者も出てきている。その品質は国内では既に高い評価を得ているだけに、今後、信大BS8-9が世界でも従来の常識を覆すおいしい夏秋いちごとして、多くの人に驚きを与えることを期待する。











