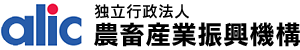ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 世界のトウガラシ類とその機能性
信州大学 学術研究院農学系 准教授 松島 憲一

1 はじめに
日本は2018年頃から第4次激辛ブームに突入しているのだそうだ。今回の激辛ブームが、これまでのものと異なるのはシビカラ、すなわち辛いだけではなく山椒、花椒の痺れる感覚も加味された上でのブームであることだ。しかし、これまで同様にトウガラシの辛味がその主役であることは違いない。
そのトウガラシの強烈な辛味はカプサイシンと呼ばれる辛味成分によるものであるが、正確にはカプサイシンだけではなく、その関連物質であるジヒドロカプサイシンおよびノルジヒドロカプサイシンを含めたカプサイシノイドと総称で呼ばれる成分によるものである。しかし、多くの場合、果実中に存在する三つのカプサイシノイドの中ではカプサイシンが最も含有量が多いし、ノルジヒドロカプサイシンに至っては含有量が他より少ない上、辛味強度もカプサイシンの半分程度とされているのであまり影響はない。ちなみに、このカプサイシノイドは植物の中でもトウガラシ属(Capsicum属)植物のみに存在し、さらにその植物体の中でも果実だけに存在する。もっと細かく言うと、トウガラシ果実中の空洞を分ける板状の組織である隔壁と呼ばれる部位で合成蓄積されるので、その部分が最も辛いということにある。この隔壁は、種子が付いている胎座と呼ばれる組織と連続して存在するので、どこからが隔壁で、どこからが胎座かわからない場合もあり、カプサイシノイドが合成蓄積される部位は「胎座・隔壁」と表現することも多い。一般に、トウガラシは種子が最も辛いと言われることがあるが、種子は、本来、最も辛い胎座・隔壁に付着しているだけで、カプサイシノイドを合成することも蓄積することもできない。乾燥唐辛子から種子を取り出すと胎座・隔壁も同時に取り除かれて辛味が弱くなるために、種子を取れば辛味が弱まると勘違いされて、そう思われてきたのかもしれない。
さて、このカプサイシノイドを唯一含む植物であるトウガラシ属植物は分類上5種の栽培種が存在する。まず、この五つの栽培種について紹介していきたい。
そのトウガラシの強烈な辛味はカプサイシンと呼ばれる辛味成分によるものであるが、正確にはカプサイシンだけではなく、その関連物質であるジヒドロカプサイシンおよびノルジヒドロカプサイシンを含めたカプサイシノイドと総称で呼ばれる成分によるものである。しかし、多くの場合、果実中に存在する三つのカプサイシノイドの中ではカプサイシンが最も含有量が多いし、ノルジヒドロカプサイシンに至っては含有量が他より少ない上、辛味強度もカプサイシンの半分程度とされているのであまり影響はない。ちなみに、このカプサイシノイドは植物の中でもトウガラシ属(Capsicum属)植物のみに存在し、さらにその植物体の中でも果実だけに存在する。もっと細かく言うと、トウガラシ果実中の空洞を分ける板状の組織である隔壁と呼ばれる部位で合成蓄積されるので、その部分が最も辛いということにある。この隔壁は、種子が付いている胎座と呼ばれる組織と連続して存在するので、どこからが隔壁で、どこからが胎座かわからない場合もあり、カプサイシノイドが合成蓄積される部位は「胎座・隔壁」と表現することも多い。一般に、トウガラシは種子が最も辛いと言われることがあるが、種子は、本来、最も辛い胎座・隔壁に付着しているだけで、カプサイシノイドを合成することも蓄積することもできない。乾燥唐辛子から種子を取り出すと胎座・隔壁も同時に取り除かれて辛味が弱くなるために、種子を取れば辛味が弱まると勘違いされて、そう思われてきたのかもしれない。
さて、このカプサイシノイドを唯一含む植物であるトウガラシ属植物は分類上5種の栽培種が存在する。まず、この五つの栽培種について紹介していきたい。
2 栽培5種
5種の内、世界で最も広く分布している栽培種がC.annuumである。この種が世界で最も広く分布することができたのは、日長にかかわらず開花することができたことや、熱帯、亜熱帯のみならず温帯域でも栽培が可能であったということで、広域適応性が高かったことがその理由として考えられる。トウガラシ属植物の種同定はさまざまなキーキャラクターとなる形質から総合して行うが、C.annuumについては、まずは白い花弁をつけることで他の種と区別できる。日本で栽培されるトウガラシもほとんどがこの種なので、この白い花は見慣れている方も多いであろう(写真1)。

日本で栽培されるトウガラシのほとんどがC.annuumと書いたが、日本でも南西諸島で栽培されている島とうがらしといった、花弁が緑白色で、小型果実を付ける品種はC.frutescensに属し(写真2)、正確に言うとトウガラシではなくキダチトウガラシという和名が付与されている。タイのプリッキーヌー(ネズミの糞の意味、その果実形状から)をはじめとした、東南アジアの小粒で辛い果実を付ける品種はこの種に属することが多い。また、単にタバスコと呼ばれることの多い、マキルヘニー社のタバスコペッパーソースについても実はタバスコと呼ばれる品種を原料に製造されていることからこの名がついているが、この品種もC.frutescensに属している。

C.frutescenと同じく緑白色の花弁を付けるC.chinenseという栽培種もよく話題にのぼるが(写真3)、この種が話題になるときは、おおむねその辛味の強さが話題の中心となる。日本では激辛スナックに使われたことで知名度の高いハバネロもこの種に属しているし、現在、ギネスワールドレコードで最も辛いと認定されているキャロライ・ナリーパーも、その前のチャンピオンであるトリニダード・スコーピオン・ブッチT、さらに、その前のチャンピオンであるブート・ジョロキアもすべてC.chinenseに属している。ちなみにキャロライ・ナリーパーより辛いとされているペッパーXやドラゴンズ・ブレスといった品種もあるようだが、未だギネスブックには登録されていない。

以上の3種が起源地のアメリカ大陸を離れて世界に広がっていった栽培種であるが、中南米にとどまった栽培種である。その一つがC.baccatumであり、花弁に緑色の斑点があることで他種と区別できる(写真4)。ペルーの黄色い果実の品種アヒ・アマリーリョなど、辛味もマイルドなものが多く、鮮やかで美味しい品種も多いのにもかかわらず、南米での栽培、利用に限られている。さらに栽培地域が限られている栽培種としてはC.pubescensがある。この種は、花弁が紫色で種子が黒色であり、他種とは遺伝的関係も遠縁であるとされている(写真5)。このC.pubescensはアンデス山麓の冷涼な高標高地域が起源地であり、現地では「ロコト」と呼ばれ、辛味は強いものの肉詰めなどにして好んで食べられている。日本の露地栽培では暑すぎて果実収穫を伴う栽培は難しいとされており、筆者らは信州の高冷地での栽培に向けて有望品種を選抜中である。


3 日本の在来品種
日本のトウガラシはC.annuumがほとんどで、そのC.annuumは広域適応性があると書いたが、実際に日本では北は北海道の札幌大長なんばんから、南は鹿児島の花岡胡椒まで、島とうがらしはC.frutescensであるがそれを含めれば沖縄まで、日本国中の幅広い地域でさまざまな在来品種が伝承され栽培されている。筆者の承知している品種だけでも数えてみると40品種が確認できる。この中には京野菜として知られる万願寺や伏見甘長など辛味のない(もしくは極少ない)野菜用品種も含まれている。
筆者は長野県農政部が設ける長野県内の在来野菜の保護制度である信州の伝統野菜の認定委員会座長でもある。79品目ある信州の伝統野菜のうち8品種ものトウガラシが選ばれており、他府県の同様の認証制度と比べて非常に多い。これらは長野県の北から順にししこしょう(栄村)、ぼたんこしょう/ぼたごしょう(中野市/信濃町)、ひしの南蛮およびそら南蛮(小諸市)、高遠てんとうなんばんおよび芝平なんばん(伊那市)、大鹿唐辛子(大鹿村)、そして、鈴ヶ沢南蛮(阿南町)の8品種である。辛味はあるがピーマンに似た形で野菜的に使われるぼたんこしょう/ぼたごしょうから、乾燥させて香辛料として使われる高遠てんとうなんばんまで、また、全く辛くないそら南蛮から鷹の爪の2倍以上の強い辛味を持つ芝平なんばんや鈴ヶ沢南蛮まで、果実の形や辛味の強さなど非常にバラエティに富んでおり、それにあわせた用途や郷土料理が存在する。長野県内だけでも、このような状態であるので、トウガラシの多様性が感じられる(写真6)。

4 ピーマン・パプリカもトウガラシ
日本の在来品種の中には、先に記した万願寺、伏見甘長やそら南蛮などのような辛くない(もしくは辛味が非常に弱い)野菜用品種があるが、ししとうも同様に野菜用トウガラシ品種としては日本で最もメジャーな品種の一つである。このししとうは普段は辛くないのだが、時より辛味果実が発生することが特徴であり、問題でもある。筆者らの研究グループでは、その不時辛味果の発生理由を解明する研究をしており、これまでの研究の結果で、栽培時のストレスなどにより種子が少なくなった果実が辛くなることや、その際にカプサイシン合成関連遺伝子がどのように発現するかを明らかにしてきたところである(Kondoら2021、Kondoら2020)。さらに研究が進めば、ししとうをはじめとしたトウガラシの辛味のコントロールが出来るようになるかもしれない。
さて、ししとうと違って栽培時にストレスが与えられても辛くならないトウガラシがピーマンやパプリカの類である。ピーマンやパプリカがトウガラシであると言えば驚かれることがあるが、辛味が発生しない果実の大きい野菜用のトウガラシ品種がピーマンやパプリカだと思ってもらっても差し支えない。一般的なピーマン・パプリカ類はカプサイシン合成経路の末端の遺伝子に変異が起こって働かないためにカプサイシンを合成できないので辛くならないのだ。
このパプリカ類は、ヨーロッパの地中海沿岸諸国や東ヨーロッパで在来品種が多く栽培され、食べられている。例えばスペインでは10品種のトウガラシが同国農業食料環境省により原産地呼称制度デノミナシオン・デ・オリヘンに登録されている。この中にはピミエント・デ・パドロンというししとうに少し似たような品種も含まれるが、ほとんどがいわゆるパプリカの類いである。それぞれの品種にあった料理法があり、その食文化に感嘆する。また、東ヨーロッパのハンガリーの郷土料理にはグヤーシュという煮込み料理が有名であるが、これにはパプリカ粉が欠かせない材料となっている。このように辛い食文化が少ないヨーロッパではあるが、しっかりとトウガラシが姿を変えて定着しているのだ。
5 トウガラシの機能性
このように、世界中でさまざまなトウガラシが使われているわけであるが、トウガラシはただ辛いだけ、ただおいしいだけではなく、さまざまな健康効果、いわゆる機能性が知られている。特に有名なのはカプサイシンによるダイエット効果である。2000年代に捲き起こった第3次激辛ブームの際には、ダイエットを目指す女子高生がマイトウガラシを持ち歩いていたという逸話もある。このダイエット効果は体熱産生亢進作用によるものであり、その機作は科学的にも証明されている。簡単に説明すると、トウガラシを食べること、すなわちカプサイシンを摂取することにより交感神経が刺激され、体内でアドレナリンが放出される。これにより、体脂肪が分解され遊離脂肪酸となるエネルギー源として血中に供給するのである。また、同時に褐色脂肪組織という体熱産生をつかさどる器官が活性化されることもわかっている。この二つの作用による体熱産生の亢進が体脂肪の減少に寄与するというのだ。しかし、実際に消費が促進される体脂肪の量はしれているし、食事制限をする方が効果的であると邪推してしまうのは、何度もトウガラシダイエットに失敗している筆者の感想である。なお、カプサイシンの機能性についてはこの他に、持久力の増強効果(Kimら1997)、血漿中コレステロール低減作用(Huangら2014)、塩分の少ない食事であってもトウガラシを添加することで満足する効果をはじめとして、さまざまな効果が報告されている他、イタリアで行われた大規模コホート研究によると、トウガラシを週4回以上食べる人たちは、全く食べない人に対して、虚血性心疾患および脳血管疾患の死亡リスクとも低下していたとの報告もある(Bonaccioら2009)。
また、トウガラシで意外に知られていない利点の一つがビタミンC含量の多いことだ。ビタミンCと言えばレモンのイメージであるが、文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」(食品分析データベースhttps://fooddb.mext.go.jp/index.pl)で比較してみると、レモンのビタミンC含有量が100グラム当たり100ミリグラムであるのに対して、パプリカの一種トマピーでは200ミリグラム、赤ピーマンが170ミリグラム、黄ピーマンが150ミリグラム、とうがらしは120ミリグラムとなり、成熟した果実では、いずれもレモンを超える含有量となっている。そもそもビタミンC(アスコルビン酸)はハンガリーのセント=ジョルジ・アルベルトによりパプリカから最初に単離されており、その功績により彼はノーベル賞を受賞している。
6 最後に
激辛ブームはブームではなくすでに日本で多様な辛味食文化が定着している段階に達していると筆者は判断している。さらに、最近、各地で伝統野菜が注目されてきており、地域の在来トウガラシ品種も数多く復活を遂げているところである。そんな背景が重なり、さまざまなトウガラシを目にする機会、口にする機会も多くなってきていると感じている。日本のさまざまなトウガラシ、世界のさまざまなトウガラシについて、辛さの違いはもちろん、辛さ以外の味、文化背景などを楽しんでいただきたい。食べることを楽しむことは何よりの機能性でもあるので。
<参考文献>
松島憲一.2020『とうがらしの世界』講談社.
岩井和夫,渡辺達夫.2008『改訂増補トウガラシ辛味の科学』幸書房.
<引用文献>
Kondo, F., K. Hatakeyama, A. Sakai, M. Minami, K. Nemoto, K. Matsushima. 2021. The pungent-variable sweet chili pepper ‘Shishito’ (Capsicum annuum) provides insights regarding the relationship between pungency, the number of seeds, and gene expression involving capsaicinoid. Mol. Genet. Genomic (https://doi.org/10.100 7/s00438-021-01763-4.): 1-13.
Kondo, F., K. Hatakeyama, A. Sakai, M. Minami, K. Nemoto, K. Matsushima. 2020. Parthenocarpy Induced Fluctuations in Pungency and Expression of Capsaicinoid Biosynthesis Genes in a Japanese Pungency-variable Sweet Chili Pepper ‘Shishito’ (Capsicum annuum). Hort. J. 90:48-57.
Kim,K. M., T. Kawada, K. Ishihara, K. Inoue, T. Fushiki. 1997. Increase in Swimming Endurance Capacity of Mice by Capsaicin-induced Adrenal Catecholamine Secretion. Biosci. Biotechnol. Biochem. 61: 1718-1723.
Huang, W., W. S. Cheang, X. Wang, L. Lei, Y. Liu, K. Y. Ma, F. Zheng, Y. Huang, Z-Y. Chen. 2014. Capsaicinoids but Not Their Analogue Capsinoids Lower Plasma Cholesterol and Possess Beneficial Vascular Activity. J. Agric. Food Chem. 62: 8415−8420.
Bonaccio, M., A. D. Castelnuovo, S. Costanzo, E. Ruggiero, A. De Curtis, M.
Persichillo, C. Tabolacci, F. Facchiano, C. Cerletti, M. B. Donati, G. De Gaetano, L. Iacoviello. 2009. Chili Pepper Consumption and Mortality in Italian Adults. J. Ame. College Cardiology . 7 4: 3139 –3149.
松島 憲一(まつしま けんいち)
博士(農学)
【略歴】
平成5年4月 農林水産省入省(農林水産技術会議事務局)
平成14年10月 信州大学大学院農学研究科助手
平成17年4月 同助教授
平成26年4月より現職
<参考文献>
松島憲一.2020『とうがらしの世界』講談社.
岩井和夫,渡辺達夫.2008『改訂増補トウガラシ辛味の科学』幸書房.
<引用文献>
Kondo, F., K. Hatakeyama, A. Sakai, M. Minami, K. Nemoto, K. Matsushima. 2021. The pungent-variable sweet chili pepper ‘Shishito’ (Capsicum annuum) provides insights regarding the relationship between pungency, the number of seeds, and gene expression involving capsaicinoid. Mol. Genet. Genomic (https://doi.org/10.100 7/s00438-021-01763-4.): 1-13.
Kondo, F., K. Hatakeyama, A. Sakai, M. Minami, K. Nemoto, K. Matsushima. 2020. Parthenocarpy Induced Fluctuations in Pungency and Expression of Capsaicinoid Biosynthesis Genes in a Japanese Pungency-variable Sweet Chili Pepper ‘Shishito’ (Capsicum annuum). Hort. J. 90:48-57.
Kim,K. M., T. Kawada, K. Ishihara, K. Inoue, T. Fushiki. 1997. Increase in Swimming Endurance Capacity of Mice by Capsaicin-induced Adrenal Catecholamine Secretion. Biosci. Biotechnol. Biochem. 61: 1718-1723.
Huang, W., W. S. Cheang, X. Wang, L. Lei, Y. Liu, K. Y. Ma, F. Zheng, Y. Huang, Z-Y. Chen. 2014. Capsaicinoids but Not Their Analogue Capsinoids Lower Plasma Cholesterol and Possess Beneficial Vascular Activity. J. Agric. Food Chem. 62: 8415−8420.
Bonaccio, M., A. D. Castelnuovo, S. Costanzo, E. Ruggiero, A. De Curtis, M.
Persichillo, C. Tabolacci, F. Facchiano, C. Cerletti, M. B. Donati, G. De Gaetano, L. Iacoviello. 2009. Chili Pepper Consumption and Mortality in Italian Adults. J. Ame. College Cardiology . 7 4: 3139 –3149.
松島 憲一(まつしま けんいち)
博士(農学)
【略歴】
平成5年4月 農林水産省入省(農林水産技術会議事務局)
平成14年10月 信州大学大学院農学研究科助手
平成17年4月 同助教授
平成26年4月より現職