 今月の話題
今月の話題
野菜価格安定事業の意義と今後の課題

東京農業大学 国際食料情報部
教授 藤島 廣二
1.はじめに
昭和41年(1966年)、野菜生産出荷安定法が制定され、野菜価格安定事業が本格的に始まった。この事業の直接的なねらいは、当時、大きな社会問題となっていた野菜価格の大幅な変動(特に価格の高騰)を、供給の安定化によって緩和・防止することであった。
が、その後、野菜貿易が活発化するなどの国際情勢の変化の中で、そうした本来の目的とは別に、関係者もあまり意識していなかったと思われる新たな役割を担うことになった。それは国産野菜の安定供給を通して高自給率の維持に寄与することであった。
本稿では、これらの目的等との関連で価格安定事業の意義を改めて確認し、さらに同事業の今日的な課題をも指摘することによって、今後における同事業のあり方等の検討に資することにしたい。
2.野菜価格安定事業の意義
(1) 野菜価格の安定化の推進
昭和30年代、経済の高度成長の下、都市部での人口の集積が進み、食料に対する需要が増大した。しかし、その需要の増加に対し、全ての食料の供給が順調に増加したわけではなかった。とりわけ野菜の場合、天候の影響で単位面積当たり収穫量が変動することに加え、それぞれの品目の前年の価格の高低に応じて当該年の品目別作付面積が変動するなど、各品目の供給量が年によって大きく変化した。その結果が年々の著しい価格変動となって現れ、大きな社会問題の一つとなったのである。
この問題を解決するために実施されたのが野菜価格安定対策事業であった。その主な方法は、ある品目(事前に決められた品目)の販売価格が保証基準価格(過去の平均価格の90%)を下回って低落した時、国、県、生産者の3者で造成した資金の中から、その販売価格と保証基準価格の差額の90%または100%を補てんし、それによって当該品目の翌年の生産量を確保しようというものである。すなわち、生産者に一定の収入を保証することによって年々の作付面積の変動を極力抑制し、それによって生産量、すなわち供給量を極力安定化し、結果として価格変動を抑えようという方法である。
その効果の程度を簡単にみるために作成したのが図1と図2である。両図とも東京都中央卸売市場におけるキャベツの月平均価格(1kg当たり価格)を5年間(60ヵ月)にわたって示したものであるが、図1は昭和36年から40年まで、すなわち野菜生産出荷安定法制定の直前5年間を対象としたものであり、図2は平成13年から17年までの直近5年間を対象にしたものである。
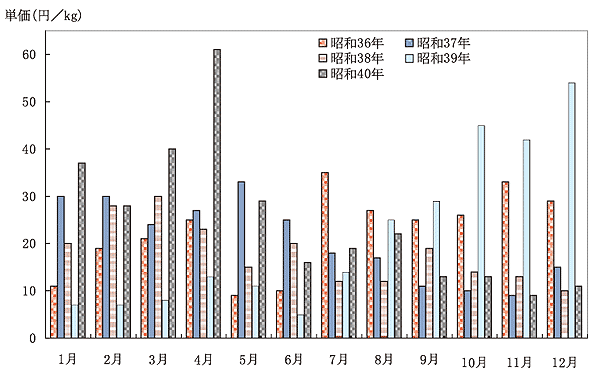
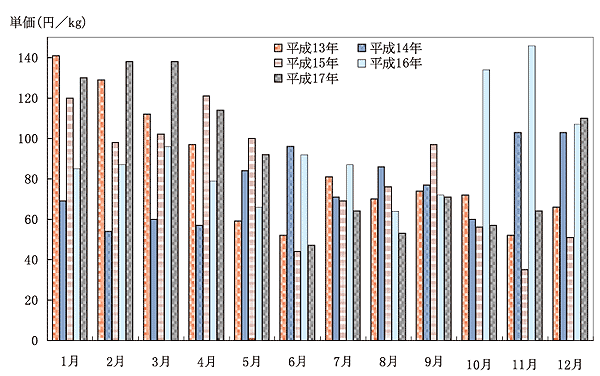
図1、図2とも、月平均価格で示しているので、日々の価格変動に比べると、変動はかなり穏やかな形で現れているといえるが、それでも図1では年々の価格変動がかなり激しいことがわかる。例えば前年の同じ月との比較で価格が2倍以上または半分以下になった月を数えると、昭和37年から40年の48ヵ月中25ヵ月、5倍以上または5分の1以下になった月でさえ4ヵ月もあった。これに対し、図2の平成14年から17年までの48ヵ月では、前年同月に比べ価格が2倍以上または半分以下になった月は11ヵ月、そして5倍以上または5分の1以下になった月は1ヵ月もなく、4倍以上になった月が1ヵ月だけであった(この1ヵ月を除くと、3倍以上または3分の1以下になった月も存在しなかった)。明らかに、平成13年~17年の方が価格変動がずっと穏やかであるといえる。
しかし、これでは1品目だけなので、キャベツも含めた5品目(キャベツ以外は、だいこん、はくさい、レタス、にんじん)を新たに取り上げ、上記の2期間(昭和36年~40年と平成13年~17年)のそれぞれの月平均価格を基に変動係数を計算した。指摘するまでもなく、変動係数が小さい方の期間において月々の価格の変動が穏やかである、あるいは価格が安定的であるということになるが、その結果は以下のとおりであり、いずれの品目においても平成13年~17年の方が変動係数が小さく、価格は安定的であったといえる
これらのことから、価格安定事業の実施前に比べ、実施後において野菜価格の安定化が明らかに進展したと判断することができよう。
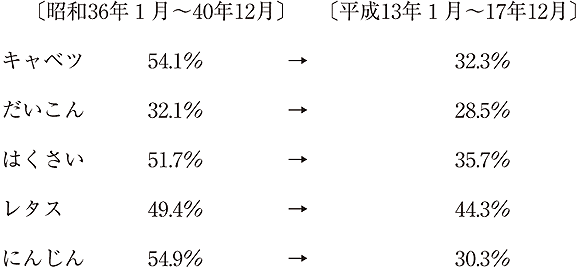
(2) 野菜の高自給率の維持
野菜の輸入と自給率の方に話を移すと、輸入が目立って増えるようになったのは、昭和60年(1985年)以降であった。その最大の要因は同年9月のプラザ合意に起因する円高といえる。同年の為替レートは1ドルが240円前後であったが、円高が最も進んだ平成7年(1995年)4月19日には1ドルが79円75銭となり、円の価値はわずか10年ほどの間に3倍になった。当然、輸入物の価格は下落し、図3にみるように野菜輸入量が過去に例がないほど急速に増加した。
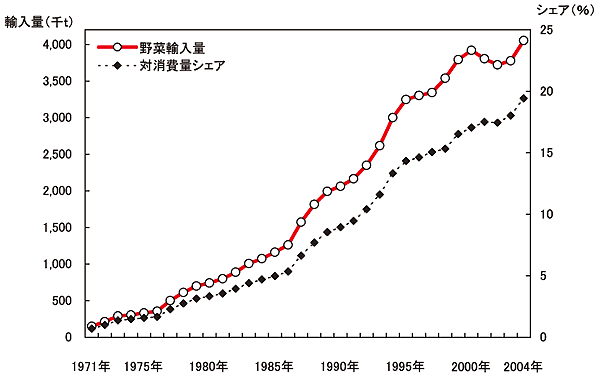
1)「食料需給表」、市場課資料による
2)3ヵ年移動平均値で示しているが、基の値は暦年値でなく、会計年度(4月~3月)値である。
3)対消費量シェア=輸入量÷国内消費仕向量×100
4)「対流通量シェア」の算出にあたっては、果実的野菜を除いた。
5)輸入量等の算出にあたっては生鮮物と加工物を合計しているが、ここでの加工物の数量は生鮮換算数量である。
しかし、輸入物が増加したとはいえ、野菜の自給率は現在でも他の品目に比べると相対的に極めて高いといえる。例えば「食料需給表」から平成15年の自給率をみると、野菜(いも類ときのこ類を含む)の82%を上回るのは米(95%)と鶏卵(96%)といった特殊な品目だけに限られる。昭和60年当時、野菜の95%と同程度もしくはそれに近い高自給率を示していた魚介類(93%)、牛乳・乳製品(85%)、肉類(81%)、果実(77%)も、平成15年にはそれぞれ50%、69%、54%、44%に低下した。
しかも、野菜の場合、生鮮品の自給率が特に高い。上記と同じ平成15年を例にみてみると、輸入量は生鮮品が90万トン、加工品が252万トン(ここでは生鮮品と比較するため、加工後の製品数量ではなく、原料段階の生鮮換算数量を用いた)であったが、国産野菜は加工に仕向けられたのが275万トンで、生鮮品として消費されたのが1,180万トンにのぼった(ここでのデータは農林水産省「食料需給表」、「野菜生産出荷統計」等によるが、きのこ類は除いた)。すなわち、加工品の自給率は52%(275万トン÷(252万トン+275万トン))と、ようやく50%台を維持しているにすぎないのに対し、生鮮品の場合は93%(1,180万トン÷(90万トン+1,180万トン))と、昭和60年当時とほとんど変わらない比率を保っているのである。
生鮮品の自給率が大幅に低下しなかったのは、輸入量の増減が円高よりも国産野菜の供給量の変化の影響を強く受けていたからであろう。例えば、平成13年の暫定セーフガードの発動で注目されたねぎの輸入量の推移をみると、図4に示したようにそれが著増し始めたのは平成10年10月からであった。前述の円高期が既に過ぎ、逆に1ドルが110円台や120円台になろうとする円安期に入ってから輸入量が急増し始めたのである。それゆえねぎ輸入量の増加は円高によるものということはできず、同図からも読み取れるように、国産ねぎの出荷量(ないし収穫量)が減少し、価格が高騰した(平成10年10月の国産ねぎの卸売価格は474円/kgで、前月9月の327円/kgの1.45倍、前々月8月の276円/kgの1.72倍に急騰した)ことによるものと考えるしかない。もちろん、こうしたことはねぎだけでなく、生鮮野菜の多くで同様に確認できる。輸入生鮮野菜の代表ともいえるたまねぎの場合などは、図5にみるように、国産物の収穫量が減少した年または翌年に輸入量が増え、国産物が増加した年には逆に輸入量は減少しているほどである。
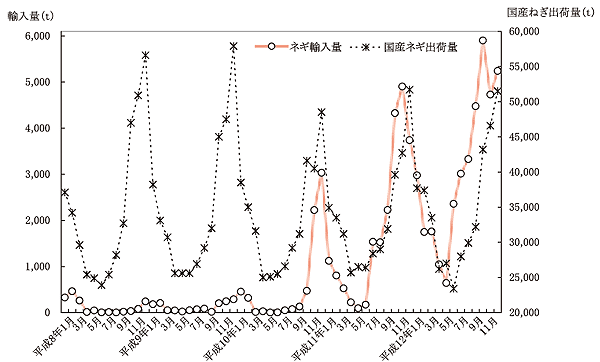
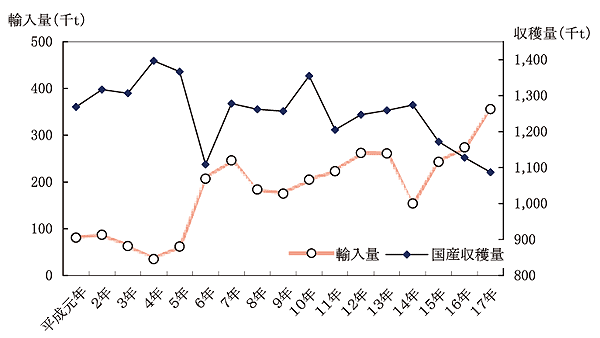
注:「輸入量」は暦年で、「収穫量」は生産年(当該年4月~翌年3月)である。
すなわち、国産野菜の供給量が比較的安定していたことが生鮮野菜の輸入量の急激な増加を防ぎ、結果として野菜の高自給率を維持することにつながったのである。そして、その供給の安定化を推進したのが価格安定事業であった。この意味において、同事業は価格の安定化に関してだけでなく、自給率の維持に関しても大きな役割を果たしてきたと判断できるのである。
3.野菜価格安定事業の課題と今後の具体的方向
(1) 加工原料用野菜対策強化の必要性
先に平成15年の輸入生鮮品と輸入加工品の数量に触れたが、野菜輸入となると常に加工品が極めて多い。昭和60年の野菜輸入量の中で生鮮品13万トンに対し、加工品は96万トン、平成16年には同順で102万トン対296万トンであった。
なぜ加工品の輸入量が多いのか。主な理由の一つは、円高の影響を受け易かったことであろう。生鮮品であれば、収穫後、日数がたつほど鮮度が低下するため、円高による価格の低下が販売面でそのまま有利になるとは限らない。が、加工品は鮮度の低下という問題がないため、価格の低下がそのまま競争力の強化となって現れるのである。
もうひとつは、加工食品産業と外食・中食産業の伸長であろう。外食・中食企業の多くが輸入加工品や輸入生鮮品を大量に利用していることはよく知られているが、加工食品企業も生鮮品だけでなく、輸入加工品を原料(中間製品)として利用し加工食品を製造することが多い。しかも、現在では消費者が生鮮品として購入する野菜は、野菜総消費量の45%程度にすぎない。今日の加工食品産業や外食・中食産業が利用する野菜の量は膨大なのである。
しかし、これらの理由だけでなく、さらにもう一つの重視すべき理由が考えられる。それは加工原料用野菜を対象とした価格安定事業がこれまで行われなかったことである。現在では指定野菜、特定野菜、あるいは契約指定野菜等のそれぞれについて価格安定事業(あるいは安定供給事業)が行われているが、それらの保証基準価格(小売店向け生鮮野菜の9年間平均卸売価格の90%)等から判断する限り、そのいずれの場合もいわゆる「一般家庭向け」(小売店仕向けと一部の業務用仕向け)の生鮮野菜が対象と考えざるを得ないのである。
確かに、作付面積が20~30aに満たないような大多数の小規模な野菜農家に「一般家庭向け」生鮮野菜の生産に代えて加工原料用野菜の生産を勧めても、収入を考えれば転換は困難であろう。その意味では、「一般家庭向け」生鮮野菜生産を対象とした価格安定事業は決して間違いではなかったと思う。
しかし、その結果、国内産地の加工需要への対応が遅れ、加工野菜の輸入が増大したことによって自給率が低下したとなると、このままで良しとすることはできない。特に今後、社会の高齢化が一段と進む中で加工食品や外食・中食に対する需要が増加することも考慮するならば、加工原料用野菜(カット業者、冷凍食品業者、漬物業者等の加工業務向け野菜)を対象とする価格安定事業を行わない限り、自給率の向上はもちろんのこと、現比率の維持さえも困難にならざるを得ないであろう。
平成15年産の国産野菜の加工仕向量が200万トンを超えていたことからもわかるように、現在でも加工原料用野菜を生産している生産者は存在しているし、関東においてさえ加工原料用契約野菜生産に力を入れようとしている農協も増えようとしている。こうした生産者や農協を力付け、かつより多くの大規模生産者を育て、加工原料用野菜を大量に供給できる仕組みを創り出すためにも、加工原料用野菜へのよりきめ細やかな対応策が強く望まれるのである。
(2) 課題の具体化のための対応方向
上述の点を単なる指摘にとどめないようにするために、ここでは加工原料用野菜を取り込む価格安定事業の具体的なあり方について、さらに私見を2点ほど記しておきたい。
一つは、現在の指定野菜等の価格安定事業や契約野菜の安定供給事業において、野菜の小売店仕向けと加工仕向け(または加工・業務仕向け)とを区分し、それぞれに応じた保証基準価格を設定するなど、業務内容の細分化を推進するというものである。いい方を変えると、一般野菜価格と加工業務用野菜価格の違いに基づいて、後者の低い価格に対応した保証基準価格を設定し、(例えば、現在の保証基準価格の半分程度とする)、資金造成のための生産者の負担額を抑えることによって(保証基準価格に合わせて、単位重量当たりの生産者負担金を現在の半分程度とするなど)、大量の交付予約を必要とする加工原料用野菜生産者(大規模生産者、JA等)が価格安定事業等に参加しやすくするということ、要するに「加工原料用野菜専用の仕組みを新たに創る」ということである。ただし、これを実践するに当たっては、加工原料用野菜の低コスト生産システムはもちろんのこと、低コスト出荷システム(例えば、無選別野菜を大型コンテナで一括大量出荷するシステム)の構築も前提になろう。
もう一つは、加工原料用野菜の面積契約で、不作のために収穫量が予定量を大幅に下回った場合、その予定量を確保する範囲内において(当然、国産品で確保する場合に限られるが)、面積契約に基づく算出価格(面積契約価格を平均収穫量または予定収穫量で除した単価)と卸売市場からの買入価格(当該地域の平均卸売価格または全国平均卸売価格)との差額を補てんする、というものである。もちろん、これは不足分を輸入品で代替されないようにするための方策である。ただし、不作時には著しく暴騰することも考えられるので、補てん対象となる買入価格は面積契約に基づく算出価格の何倍までにするか、また差額の何割を補てんするか等も十分に検討しておく必要があろう。ちなみに、この場合には資金造成の負担金を加工企業から徴収することが可能となるので、そのことの検討もすべきであろう。
なお、加工原料取引は通常、契約取引であることから、契約取引のメリット((1)数量や価格を取引前に決めるため、収入の予測が可能である。(2)カット野菜原料や冷凍野菜原料等、多様な加工・業務用需要があるため、産地の事情に応じて取引先を選択できる。(3)高品質原料を求める加工業者もいるので、高価格取引も可能である等)を、様々な機会を利用してより多くの生産者・産地に説明し、それを通して加工原料用野菜の価格安定事業への参加を促す努力も重要であろう。
4.おわりに
以上、野菜価格安定事業の意義を価格の安定化と高自給率の維持の2点において確認し、その上で今後の課題として加工原料用野菜を取り込む方向での価格安定事業の一層の拡充を指摘するとともに、そのための具体的な対応方法を2点ほど示した。なお、こうした方法にしても、またこれら以外の方法にしても、加工原料用野菜を取り込む方向での価格安定事業の拡充は決して容易ではないであろう。しかし、国産野菜の加工原料用市場(または加工・業務用野菜市場)でのシェアを回復させ、自給率を向上させるためには、それらの方法の実現を強く希望したい。
プロフィール
ふじしま ひろじ
最終学歴 北海道大学大学院農学研究科博士課程
1980年農林水産省東北農業試験場研究院、農林水産省中国農業試験
場主任研究官、研究室長
農林水産省農業総合研究所流通研究室長を経て、1996年6月~
1998年3月 東京農業大学農学部教授、1998年4月~現職