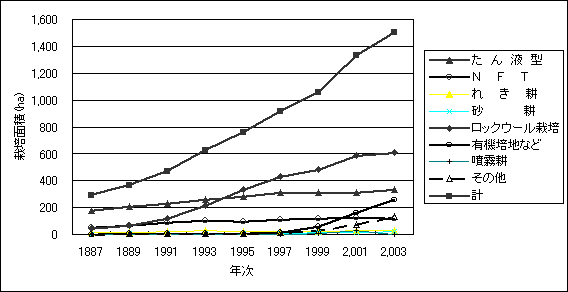今月の話題
今月の話題
野菜施設栽培に求められるもの
千葉大学 園芸学部
教授 篠原 温
1.はじめに
最近園芸産品の輸入が急速に増加し、野菜については、自給率80%を切るのも時間の問題と言われており、野菜園芸という産業は戦後最大の曲がり角にさしかかっている。家族労働を前提とし、経営規模もあまり大きくなく、さらに農業者の平均年齢が65才を超えた日本の農業をいかに維持発展させていくかは、我々関係者にとっても最大の課題となっている。冷凍加工を含めた野菜の輸入は、国内との価格差によってこれからも増加していくと思われるので、国内産業はある程度の淘汰がおきるのは致し方ないことであろう。しかし、これまで以上に国際競争力のある価格で、より安全な生鮮野菜を作ることが必要であり、また一方では、付加価値の高い商品を作りだし、販売方法を工夫することによって、価格は高いが消費者はそれらを支えるというようなしくみにも可能性がある。政治的な配慮としては、FTAにもとづく野菜生産の海外との生産分業体制を含め、新しい時代に対応し、情報網を駆使した国際的な野菜の生産体制を考える必要もあろう。
本稿では、以上のような観点を踏まえ、わが国の施設園芸の将来に求められるものについて私見を述べさせていただく。
2.施設園芸の現状
わが国の施設栽培の実面積は、現在約52,000ヘクタールである(図1)。最近の30年間で約5倍もの驚異的な増加を示した。しかし、1999年に53,516ヘクタールに達した後は減少に転じている。先に述べたように、すでに淘汰による減少が見てとれるのである。
図1 施設園芸実面積の年次推移
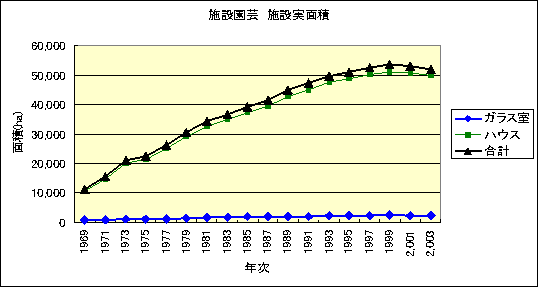
このような状況の中で日本の野菜生産のとるべき方向は二つに大きく分けられ、一つは、規模の拡大、あるいは設備投資・機械化などによる生産の効率化・省力化によって、生産コストを抑え国際競争力をつけていく方向であり、もう一つは、経営規模は小さくとも、輸入あるいは一般的な生産物と明確に差別化できる高品質野菜の生産ではないかと筆者は考えている。この両者に共通な将来的な問題としては、生産物を工業製品と同じように商品と位置づけ、しっかりとした品質管理を行った上で、売るところまで考えざるを得なくなったことではないだろうか。これまでは、行政の手厚い保護のもとで技術指導なども受け、施設の建設にも補助金を出してもらい、できた生産物はそのままJAに出荷を依頼すればそれで終わりであった形態が、行き詰まりを見せている。そうした中成功している生産者を見ると、ほとんど例外なく生産物を商品と位置づけ、自信を持って自ら売り先まで考えて、出荷をしていることが多い。JAもしかりである。今までのように、生産者の持ち込んだ荷を自動的に市場に送っていた時代は終わりを見せている。JA自らがマーケティング戦略とそれにふさわしい営農指導を始めているところは活気があり、旧態依然としているJAははっきり言って行き詰まっているところが多い。行政に、手厚い経済的支援やきめ細かい営農指導が期待できなくなってきている今、JAおよび生産者こそ目覚めないと産地ごと淘汰されかねないのである。
3.施設栽培の二極化
ここでは、上記の二極化してきている施設栽培のそれぞれについて、求められるものを述べてみたい。
1)大型施設栽培
施設栽培農家数は、1988年の21万5千戸をピークに下がりつづけ、現在は20万戸を割ってきているが、一戸あたりの栽培面積は、プラスチックハウスで約20アールから25アール、ガラス室で約27アールから40アールと増加しており、確実に規模拡大が進んでいることがうかがえる。しかし、わが国の施設はこれまで単棟の小型プラスチックハウスを主体として発展してきたため、1棟の平均面積は約5アールであり、多連棟の欧米諸国のそれに比べると極めて小さい。
大規模施設には様々なメリットがある。建設コストの単価を引き下げることができ、コンピュータなどを駆使して施設内の環境を均一に、植物の生育に好適な環境条件(地上・地下部とも)に維持することができ、結果的には生産性も大幅に改善される。先進のオランダの温室(栽培装置、暖房装置、選果機などすべてを含む)の設置コストをみると、1ヘクタール規模で1平方メートル当たりの建設単価は1万円以下であり、2ヘクタールでは7千円にまで低下する。これはわが国の実情の1/2~1/3レベルである。オランダで使われる温室は軒高4~5メートルのフェンロー型のガラス室であり、しかも仕様が統一されているため、最小単位の構造を縦、横に自由に伸ばすことで、いかなる大きさの温室も建設できるようになっている。内部はロックウールを用いた養液栽培、栽培ベッドをつり下げて床から離したバンキング・ガター方式、3.5メートルの高さにワイヤーを張り、その高さまで誘引整枝するハイワイヤー方式、通路には高所作業台車や収穫用台車が走行するためのレールをかねた暖房用の温湯管など、栽培のノウハウに関してもほぼ共通でわかりやすいマニュアルもついているのが普通である。
では、なぜわが国では低コストの施設が作れないのであろうか。様々な要因はあろうが、これまでは大規模施設建設といえば公的補助が不可欠という思いこみがあり、企業もそれに依存するあまりコストに対する配慮が欠けており、企業同士の協議で共通な部分(規格なども)を共有するというような工夫をしてこなかったことなどが大きな原因ではないだろうか。下手をすると材料の確保のために、企業内の事業部間で売買が行われ、雪ダルマ式にコストがアップしてしまうというようなこともあると聞く。
カゴメが全国にトマトの大型生産施設(3~10ヘクタール規模で、すでに7カ所に建設済み)を作っているが、ほぼ完全に施設・栽培方法はオランダのものである。国内企業が参入できなかったことは残念なことである。彼らも様々に可能性を検討したに違いないが、大型施設に経験の浅い日本の企業によってこれらの施設を作る危険性よりも、規格や栽培法、またそれらのマニュアル類がしっかりしているオランダの栽培を導入したのではないだろうか。むろんオランダと日本では気候条件が著しく異なる。そこで彼らは、夏場の気候がオランダに類似し、冬場の日照時間の長い地域を選定して施設を作るようにしたそうである。これを手をこまねいて見ていたのでは、日本の施設栽培の先行きが危うい。
このような情勢の中、農林水産省は、「国際競争にうち勝つ新たな日本型施設園芸」に理解を示し、農政推進の考え方を公表した「農政改革基本構想」の中で、「新たな工法を用いた低コストハウス」や「大規模ハウスでの生産性向上につながる技術」などの開発研究普及を進め、「国際競争にうち勝ち」、「国産農産物のシェア奪回」することを打ち出している。すでに、低コスト耐候性ハウスの開発や大型高軒高ハウスによるトマトの栽培技術の確立などの研究は進んできている。また日本施設園芸協会は、「スーパー・ホルト・プロジェクト(仮称)」を立ち上げ、施設園芸の生産コストの5割減を目標とした技術開発を行うプロジェクトを、オールジャパンの産官学で取り組むことを提唱している。このプロジェクトは、具体的にハードとソフトの項目別に部会を置き、目標達成のために業種を越えたフォーラムを設置し、オランダで見られたようにノウハウの共通部分(プラットホームとでも呼ぶべき)を明らかにする。個別企業は共通プラットホームから派生して様々なハードとソフトの低コスト化を個々に実現する技術開発を実践し、最終目標である国際競争力のある施設園芸の実現を図ろうとするものである。これらがある程度進展すれば、補助金に頼らずに低利の融資だけで大型施設の建設は可能となり、栽培産業が企業的な経営として確立できるのではないかと期待される。同時に、栽培現場は快適な労働環境を持つ職場として、地域住民にとっても福音になるものと思われる。
2)小規模施設栽培
あるJAで部会長がこう挨拶をしていた。「いわし(鰯)は魚偏に弱いと書く。いわし一匹一匹は非常に弱いけれど、群れになって大きな姿を示し、敵にやられないような工夫をしている。我々中小の農家も同じで、今こそ結束して仲間を大切にしてこの難局を乗り切らなければならない」と。いわしの例は、誠に言い得て妙である。現在も小規模な生産者が日本の野菜生産を担っていることに変わりはないが、高齢化や後継者不足はますます深刻である。このまま時が流れれば、中小の農家はその多くが淘汰されてしまうであろう。一方、「地産地消」、「有機無農薬」、「直売所」、「旬の野菜」、「地方品種」、「市民農園」、「安心安全」などというキーワードが頻繁に目や耳に飛び込んでくるようになっている。私は小規模施設栽培こそ、これら地域に密着した流通や、ネットを利用した新しい販売に基づく営農形態として発展が期待できると思っている。「連帯」とか「結束」などと言う言葉は、私が学生時代には毎日聞かれた言葉であり、今では核家族化などによって忘れ去られてしまった感がある言葉であるが、今再び重要な意味を持ってきていると思われる。
先にJAにも元気なところがあると書いたが、営農部を「マーケティング営農事業部」という名にした島根県のJA雲南では、地域で自信のある野菜、特徴のある野菜の栽培を指導し、売り先はJA会員と一緒になって考えるというシステムを作った。このJAでは、特に水耕ねぎやチンゲンサイの栽培と集出荷施設にJA独自に決めたGAP(適正農業規範)を設定し、徹底した安全な野菜作りを指導した結果、視察をしたイオンをはじめとする流通関係者がこぞって「この野菜ならいくらでも引き取るから、どんどん増産してくれ」とコメントしていた。立派な商品を作ることによって経営は向上するといういい例ではないだろうか。
規模が小さいから何もできないというのは口実にしかすぎない。小さいなりに工夫の道はいくらでもあるのであるし、小さいからできることも多いはずである。
4.養液栽培
施設栽培面積は減少に転じているにもかかわらず、養液栽培の施設面積は、年々順調に増加し、2003年統計で約1,500ヘクタールとなっている(図2)。養液栽培施設は大型生産施設を中心に増加しているが、一方ではいちごにおける高設栽培システムの普及など、小規模であっても養液栽培のメリットを生かした省力・自働化生産が土耕栽培に代わって増加していると言えよう。しかしながら、日本の施設園芸の総面積に占める養液栽培の割合はまだ約3%にすぎない。
養液栽培は、本来的には大規模栽培に向いた形態であるが、小規模には小規模なりに施設園芸の近い将来に貢献できる技術の一つである。特に都市近郊での栽培にはマッチしている。しかも環境負荷を最小限に押さえることも可能な技術であり、より安全な生産物を消費者に届けられるという有利な点も持ち合わせている。したがって、養液栽培の健全な発展は、規模にかかわらずわが国の施設園芸にとって不可欠であるとさえ思われるのである。
「養液栽培は化学肥料のみによって栽培されるから、生産される野菜は毒である」などという非常識な言葉はさすがに聞かれないが、「有機栽培野菜はより安全で栄養価も高く、おいしい」という意見はマスコミも含め頻繁に聞かれる言葉である。わが国においても、持続型農業、減農薬・減化学肥料栽培が推奨されている。有機栽培に対しては、そのプラスイメージを強調したいがためか、その環境負荷の問題はさほど重視されていない。逆に水や化学肥料をふんだんに使っている(本当は典型的な節水・節肥料栽培なのだが)というマイナスイメージの強い養液栽培は、異端者扱いされているきらいすら見られる。アレルギー体質の人は有機栽培の野菜しか食べてはいけないなど、全く根拠のない話であって、無農薬の野菜であれば、養液栽培も有機栽培も何ら差は見られない。土づくり・物質循環と環境負荷の問題は別次元の問題として明確に認識してもらいたいものである。環境負荷軽減技術は、有機栽培・無機栽培共通の責務であり、その達成に向けて相携えて進むべきものである。その芽を摘むような感情的な動きに対しては、科学的な根拠をもとに議論すべきであると強く主張したい。
5.おわりに
以上、施設園芸に関しての私見を述べさせていただいたが、現在様々な取り組みが開始されており、輸入野菜に対抗する方策は着々と進んできているとも言える。ただし、待っていては取り残されるばかりである。まず考えられるキーワードを考えつく限り挙げ、はっきりとした具体的な数値目標を立てて、それを具現できる方策を考え、その実現へ向かって実行していく姿勢が大切である。
図2 養液栽培の方式別栽培実面積の年次推移