 今月の話題
今月の話題
中国からの輸入増大と国内産地のあり方
東京農業大学 国際食料情報学部
教授 日暮 賢司
はじめに
20世紀の終わりごろから、中国からの輸入野菜量が増加している。ナゼそのころから輸入が増大したのであろうか。中国の多くの対日輸出産地は、日本へ野菜を輸出することによってプラスの影響を受けているのであろうか。その一方で、日本の輸入野菜増大は、日本の野菜産地へマイナスの影響をおよぼしている。ただ、その影響の程度は一様でない。どのような場合に問題になり、どのような場合に問題にならないのであろうか。このように思いをめぐらすと、輸入野菜の増加=国内産地へのダメージ=国内産地の衰退と考えるのは、短絡的であることがわかる。おもに国内問題すなわち野菜生産の担い手の減少に対応して必要とされる省力・大規模営農体系の不十分さ等の課題に直面している中で輸入増大によるマイナスの影響をことさら強調するのは、いかがなものであろうか。野菜の輸出国、輸入国ともに、生産者、流通業者、消費者がおり、その中でそれぞれの担い手がどのようなニーズといかなる取引が行われ、どこに問題があるのかというフードシステム的な現状の捉え方が有効であると考えられる。本稿は、そのような捉え方から主題にアプローチするものである。
1.対日輸出の背景と増加のメカニズム
日本の野菜輸入数量全体に占める中国産野菜の割合は、2003年次現在52.2%であって、第2位のアメリカ19.3%を大きく上回っている。そこで中国野菜産地の対日輸出を中心にその現状をみることにする。
中国は、1978年に文化大革命から改革・解放路線への転換をはかると同時に日中平和友好条約の締結、1993年に経済発展を重要視した社会主義市場経済への転換についての憲法改正が行われる。その後中国は、沿岸地域に集中して道路、港湾、工場団地などのインフラ投資が急速にすすむ。一方、日本の商社は、世界的規模で支店網を形成しつつあって、中国におけるビジネス機会を伺っていた。そして、塩蔵野菜、冷凍野菜、生鮮野菜の順で日本の開発輸入による野菜輸入量が増加していく1)。
さらに細かくみれば、中国において対日漬物用の原料用野菜(塩蔵野菜)の輸出は、図1のように1996年をピークとしてそれ以降伸び悩んでいる。それは、日本における減塩という健康志向と平成不況による本漬需要の低迷がおもな要因である。その結果、契約価格の伸び悩みと優良品質一次加工品のウエイトを高めた日本の野菜加工業者による引取りの影響が中国の漬物一次加工業者と原料用野菜供給農場を苦境に立たせる。
冷凍野菜については以下のようである。中国の冷凍野菜加工業者は、沿岸地域を中心に立地している。それは、日本の開発輸入の影響を受けて1980年代から1990年代にかけて増加した。日本の冷凍野菜輸入量は、図1のように21世紀にはいって増加から減少に転ずる。それとともに中国の冷凍野菜業者間の競争が激しくなる。冷凍野菜業者は、大型冷蔵庫などの多額の施設投資及び電気代などの多額の運転資金を必要とする装置型産業である。これは、日本のみならず中国においても同じである。中国の冷凍野菜加工業者は、業者間の競争のほかに原料用野菜と製品の残留農薬にかかる安全性を確保するための費用増加が加わって、経営的に良好な状態にはない2)。特に、自己資本の少ない冷凍野菜業者ほどその影響が大きい。
図1 中国からの野菜輸入数量
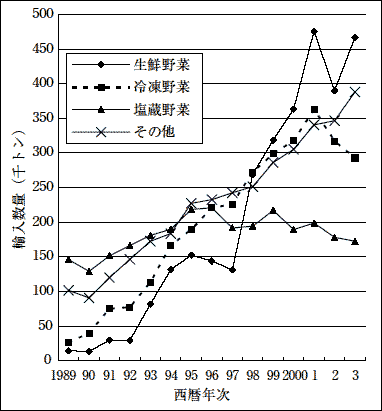
注:農畜産業振興機構『野菜輸入の動向』により作成。
生鮮野菜については、対日輸出量が増加の傾向にあるけれども、2001年12月に中国の国家品質安全局が自国産野菜について調査を行った結果、残留農薬が検出されたことが判明した3)。その結果、生鮮野菜の輸出量は、図1のように翌2002年に一時的に減少している。
2.中国産地における野菜の安全対策について
対日野菜輸出の主要な地域である中国沿岸地域においては、日本へ野菜を輸出する場合、残留農薬の検査体制が整備されている。これは、生鮮野菜だけではなく、塩蔵野菜、冷凍野菜についても同じである。対日輸出向けの原料用野菜、生鮮野菜は、農場、食品加工場、そして輸出時点の中国食品安全局において残留農薬の検査が実施されており、さらに日本側の輸入時点と量販店においてもチェックされている。それは、栽培農場名、農薬散布日、散布農薬名、散布面積と散布農薬数量、残留農薬量の検査結果についてである。それに要する中国側のおもな費用は、農場、加工場における検査員の人件費、検査機械(ガスクロマトグラフィ)の減価償却費である。後者の購入価格は、日本価格で700万円程する高価なものである。野菜の買い手である日本企業の平成不況下における低価格・高品質・高安全性というニーズと中国における野菜の輸出企業間の競争もあって、特に自己資本の少ない食品加工企業は、この新たな費用負担が経営を圧迫している。そのしわ寄せは、原料用野菜を食品加工企業に供給している農場におよぶ。
対日輸出向け生鮮野菜、原料用野菜を生産する農場は、安全性をはかるために、検査員を雇用できる規模の大きな農場に限定されるようになる。中国沿岸地域は、周知のように経済発展が続いている。この地域における農民の多くは、拡大し続ける労働市場の中で、とくに土木・建設業という農外部門で働く。その結果、耕作放棄地が増加する。市町村は、それを借り受けて20ha以上の団地として取りまとめて農場経営者へ貸し付けている。中国の農業政策は、農業経営の法人化を積極的に進めている。これは、日本のような農家出資による農業生産法人だけでなく、企業出資による農業生産法人も含まれている。後者は、食品企業が原料用野菜を調達するための大規模に農地を集積した農業生産法人(子会社)が多いけれども、そのほかに、国営企業の民営化という流れの中で、国営農場の株式会社への切り替えによる農業生産法人も増加している。このような農業生産法人が生鮮野菜を生産して日本へ輸出したり、原料用野菜を生産して、それを親会社の食品加工企業へ供給している。
日本における食品の安全性のニーズが高まれば高まるほど、中国の食品企業・農場は、その対応のための費用負担が増加する。そして、その費用負担に耐えられる食品企業・農場のみの対日野菜輸出が可能になる。そうではない食品企業・農場は、付加価値を得やすい高次加工へ切り替えて輸出を促すことと食品市場拡大の中国国内向けへ販売先を変更しつつある4)。
3.日本の産地におよぼす影響と今後の産地のあり方
中国からの輸入野菜の増加による日本国内産地におよぼす影響は一様ではなく、図2のように、(1)産地の生産額に占める割合の大きな品目(以下「主力野菜」という。)である場合と(2)産地においてそれほど大きな割合を占めていない品目(以下「マイナーな野菜」という。)である場合とで異なる。さらに産地において、その影響は、主力野菜であっても輸入数量ではなく、輸入数量割合の低い場合と高い場合とでは異なる。これらの中で最も影響をうけるのは、図2のA、Bゾーンの主力野菜であって、かつ高い輸入数量割合のケースである。ただこの場合であっても、Aゾーンの同一品種の場合とBゾーンの異なる品種の場合とがある。同一品種の方がより強い影響を受けるのはいうまでもない。
たとえば、青森県にんにくのケースでは、図2のBゾーンに該当し、中国産にんにくの輸入数量割合急拡大の影響を受けたが、品種が異なっていた。このため産地は、高級品化(高質品を市場出荷、低質品を加工用へ廻す)によって差別化に成功する。一方、香川県産にんにくは、端境期をねらって産地化された。その中で、にんにくの種は、気象条件等もあって中国からの輸入品を使用している。香川県産にんにくは、図2のCゾーンに該当し、ポストハーベストの選別・箱詰め作業において共同利用施設を用いて生産者の労働力不足を補完している主力のレタス等と比して、どのような対策を講じるかが課題となっている。
図2 輸入野菜の国内産地への影響
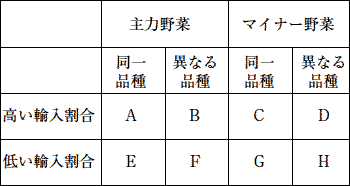
ばれいしょは、北海道などが主要産地である。そしてばれいしょは、主にアメリカから冷凍野菜として輸入され、その量も他の輸入野菜品目と比較して多い5)。一方、農林水産省の食料需給表による2003年のばれいしょの数量ベースの自給率は80%と高い。また米国からの輸入ばれいしょは、とくにアイダホ州産の長円形のものであって、男爵を中心とする日本のばれいしょと品種が異なっている。主要産地のばれいしょは、図2のFゾーンに該当する。このため産地は、本格的な輸入対策を講じていない。以上のように輸入野菜の増加傾向の中で、現在、日本の野菜産地は、Cゾーンに該当する場合において野菜品目の調整過程にあるといえる。
野菜産地の国内の問題としては、担い手の減少・高齢化があげられる。この問題は、1970年代から指摘されてきたものであって、目新しいものではない。担い手数が減少したならば、残存する農業者が作地面積の規模拡大を図っていけるように、労働集約的営農体系から労働粗放的なそれへの変更を必要とするが、その広範な実現・展望がみえない。それに加えて、すでにふれた輸入野菜の増加問題がある。特に主力野菜、高い輸入割合、同一品種の野菜産地の影響は大きい。国・地方自治体は、図2のAゾーンに該当する野菜産地に対して、共同利用施設を用いたポストハーベスト対策、量販店・外食業者・加工業者との契約取引の推進、法人などの担い手育成、労働粗放的営農体系の作成・普及などで個別的な農業経営努力に限界がみられれば、それを補うための支援が必要である。
安全性を高めている中国生鮮野菜とその加工品が日本へ輸出されているけれども、日本の消費者の多くは、中国産野菜に関して、なお「日本国内産野菜に比べて安価・低安全性」というイメージをもっている。今後、そのような中国産野菜のイメージは、時間的経緯とともに払拭されていくものと考えられる。低価格で安全性の高い中国からの輸入野菜がさらに増加すれば、日本の野菜産地はさらに強いマイナスの影響を受けるであろう。食料・農業・農村基本法第17条に明記されている食品産業と農業との連携は、今、大切な局面にある。これからの対策は、流通過程の見直しから生産過程の見直しに入っていくということが大切であろう。それは、流通の見直しによって取引方法が変化し、そのもとで生産構造を見直していくことが必要である。
これまでの野菜流通は、鮮度重視で大量の野菜を短時間に販売するために卸売市場が適してきた。今後、従来のような多額の流通費用をかけてもそれを上回るような高鮮度・高品質な野菜を供給することによって高い価格を実現するというモデルは、国内外の要因から通用しなくなる。1990年代に直売所と規模の大きな農家を中心とした消費者への宅配が全国的に増加した。これらは、野菜価格低迷の中で付加価値を維持しようとする販売方法の見直しである。
これからの産地は、農家の手取収入の最大化のための野菜規格と価格との関係、加工向けの場合の歩留まりを意識した直売、契約取引、市場出荷という販売方法の最適な組合せを検討することが重要である。先進的産地は、野菜の契約取引にともなって生じる可能性のあるリスクについて「信頼関係醸成の中で、リスクはビジネスにつきもの」という意識へ変化しつつある。勝ち組みの産地は、リスクのとり方、いいかえれば食品産業とのつきあい方についての学習効果が高まってきたといえる。これは、食品産業と農業との連携(前掲法第17条)において大変重要なことである。
注:
1)開発輸入とは、既存産地または中国では消費がほとんどない品目について、日本から最適品種、栽培技術などを提供し、産地を開発すること。有力な一説によれば、中国からの野菜輸入の9割は開発輸入であるともいわれている。
2)日本の厚生労働省が2002年3月から冷凍野菜の残留農薬の検査を開始し、中国産冷凍ほうれんそうから未加工品の基準値を超えるクロルピリホス等の残留農薬が継続して検出された。その後、中国側から残留農薬対策を提案したことから、日本の輸入禁止措置の発動が見送られる。
3)その47.5%からメタミドホス(有機リン系殺虫剤)等の中国政府の安全基準を超える残留農薬の検出であった。
4)国民の記憶にある日本の農薬問題としては、2002年7月30日に山形県において無登録農薬(ダイホルタン、プリクトラン)を販売した2業者が逮捕され、同年8月9日に山形の業者に販売していた東京の業者も逮捕されたことである。
5)独立行政法人農畜産振興機構『野菜輸入の動向』によれば、ばれいしょは2003年現在冷凍野菜として約24万トン輸入されている。これは輸入冷凍野菜全体の34%を占める。