 今月の話題
今月の話題
変化する外食産業の野菜利用
宮城大学 食産業学部
フードビジネス学科 教授 小田 勝己
はじめに
平成年代に入り外食産業を巡る経営環境は大きく変貌した、それまでの右肩上がりの成長基調が終焉し、多様化したニーズを的確に捉え、それに応える仕組みを構築した企業とそうでない企業との間で企業間格差も拡大した。外食産業内部では差別化、事業多角化などの戦略転換を図る動きも活発化し、消費者の健康志向に対応した商品政策だけでなく新たなビジネスモデルを構築する動きがみられる。
本稿では、外食産業の経営環境を業績、産業構造への影響を概観した上で、最近、公開された「食品流通構造調査(青果物調査)」から外食産業の野菜仕入動向を整理し、大手外食チェーンを中心に多様化ニーズに対応した事業多角化と、その一環として注目される野菜食材の利用を重視した「ビュッフェスタイル」レストランについて見ていくこととする。
1.外食産業の経営環境と産業構造
(1) 経営環境
外食産業の市場規模は、平成9年(1998)に29.1兆円を記録したが、その翌年から連続してマイナス成長に陥り、平成16年には24.5兆円にまで縮小を続けている1)。このような状況を生み出す要因としては、国内経済の低迷に伴う循環要因と、消費需要そのものが外食率36%、食の外部化率44%といったように量的に一定水準に達して成熟したこと、消費者ニーズがそれまでの一定品質のサービスを低価格で求める社会から多様なサービスを求める社会に転換したことに外食産業側が機動的に対応できなかったことが大きい。
その結果、需要が拡大する時代に構築した「統一メニュー」、「同一価格」、「統一サービス」を基本としたチェーン展開と、それを支える「調理の外部化(メーカー機能などを活用した同一品質製品の大量生産・安定調達システム)」の有効性が薄れ、外食企業の競争力が総合的に平準化した。そのためにいずれの企業ともに、図1が示しているように既存店(営業を開始してから1年以上を経過した店舗)の売上高が平成4年以降、客数の低迷、客単価の落ち込みにより13年連続してマイナス成長を続け、平成ピーク時の70%水準の売上高しか確保できない状況に陥っている(図1参照)2)。
このような状況の中にあっても、企業として株主への経営責任、株価対策として企業全体の売上高および収益の確保に努めなければならないことから、既存店の売上低迷を新規出店により補う動きが続いている。
図2は、大手外食企業の売上高と店舗数の増減率を示したものであるが、平成3年までは売上高の増加率が店舗数の増加率を上回っていたが、平成4年頃から売上高の落込みを店舗数の増加により下支えしようとしてきた。ところが、平成13年以降になると、既存の店舗数を単に増やすだけでは売上高の伸びを引き上げることが難しくなっている。
また、このような外食産業の全般的な市場環境の変化による、経営体質の脆弱な生業的個人店の経営悪化に加え、平成13年の国内初のBSE感染牛の発見による消費者の牛肉離れによる客数の減少、平成15年における米国でのBSE牛感染牛の発見と米国産牛肉の輸入禁止措置などによる牛肉価格の高騰なども、平成3年の輸入牛肉の自由化措置以降に、急速な拡大を続けてきた焼肉店などの、外食産業の中心部門である飲食店の業種構造に大きな変化をもたらした。
図1 既存店の売上高、客数、客単価の推移
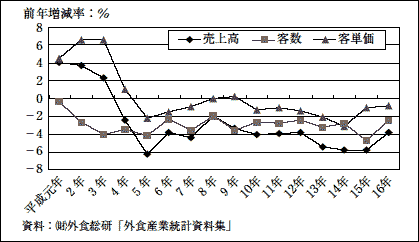
図2 外食企業の売上高、店舗数の前年増減率の推移
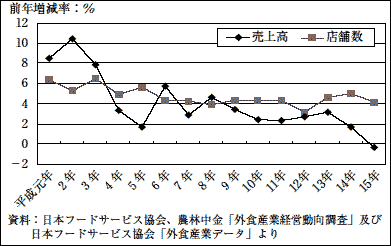
図3 飲食店の店舗数と法人店舗比率の推移
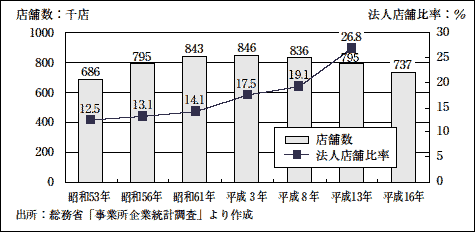
(2) 産業構造
図3は、総務省「事業所・企業統計調査」でみた飲食店の店舗数の推移と、その中に占める法人店舗比率の推移を示したものである。
飲食店の店舗数は、昭和53年の68.6万店からバブル経済がピークを迎えた平成3年には84.6万店にまで増加したが、その後は上述のような経営環境の中で、経営体質が脆弱な生業的個人店を中心に転廃業する店舗が増加し、平成13年には80万店を割り込み16年には73.9万店にまで減少(平成3年比で12.9%減)している。
その一方で、大手外食企業による売上高確保のための積極的な出店政策も影響し、店舗当たりの事業規模が大きく、また、チェーンオペレーションによる効率的な経営を実現している店舗(法人店舗)の占める比率が、平成13年には全体の26.8%と急速に高まっている。
外食市場が拡大する時代には、市場拡大に伴う経済効果(市場スラック効果)3)により生産性の低い店舗であっても存続が可能であったが、市場そのものが縮小する状況では、ブランドを確立しているオーナーシェフレストランを除けば、非効率的で競争力の乏しい生業店の転廃業が増加し、平成16年には全体1/3以上の店舗が法人経営による店舗となる可能性を示唆している。首都圏近郊の多くの商店街では、これを裏付けるようにほとんどがいずれかのチェーンに属した店舗により構成されているケースが少なくない。
このように、厳しい経営環境が続く中で、産業構造も大きく変貌を遂げようとしており、大手外食チェーンにおいても事業戦略を再編せざるをえない状況となっている。
2.外食産業における野菜の活用
一般的に外食産業の売上高に占める食材費の比率については、これまで各種の調査レポートで報告されており、売上高の30~35%、そのうちの10~20%が野菜ないしはその加工品と言われてきた。しかし、外食産業における野菜の総需要量を数量ベースでとらえたデータはこれまでになかった。
平成15年に農林水産省統計情報部は、産地生産段階以降の各産業部門について、品目、形態を限定し仕入れの水際を調査(各産業部門の仕入・販売の相互関係は考慮していない)し、「食品流通構造調査(青果物調査)」を取りまとめた。この調査結果に基づいて、外食産業(対象としているのは喫茶店を除く一般飲食店だけであり、学校給食や社員食堂などの給食部門やホテル・旅館などは含まれない)の生鮮野菜需要動向を数量ベースでみていくこととする。
(1) 生鮮野菜
この調査結果(生鮮野菜24品目)では、外食産業の野菜仕入量は129.3万トンと見込まれている。総務省「事業所・企業統計調査」によれば、平成13年の店舗数(喫茶店を除く一般飲食店)は、353,959店となっており、1店舗当たりの年間仕入量は3,652kgと推計される。また、国産と輸入の内訳では、127.0万トン(全仕入量に占める比率98.2%)を国産、残りの2.3万トン(同1.8%)を輸入が占めている。
店舗規模の大きな法人店舗の占める比率が増しているとはいえ、全体的には年間販売額が3,000万円にも満たない生業的な個人店が大勢を占めているため、国産野菜の仕入先としては、青果店やスーパーなどの小売店の納めや店頭買いによる仕入れが67.6万トン(同53.2%)を占め、次いで卸売市場の仲卸業者からが25.9万トン(同20.4%)、卸売業者からが13.6万トン(同10.7%)となっている。平成5~6年頃から大手外食企業を中心に国内の特定産地、生産者などと直接的な取引関係を構築する動きが盛んとなったが、これに該当するのは6.3万トン(同5.0%)にとどまっている(なお、図中の食料品製造業からの仕入れはあくまで生鮮野菜(前処理、一次加工程度の加工品の実重量)での仕入れで、加工度が高い製品は対象としていない)。
また、たまねぎ、かぼちゃ、ブロッコリー、アスパラ、キャベツなどの生鮮輸入野菜は、通関統計によれば80.8万トン(平成14年)となっており、これと比較すると年間2.3万トンの仕入量は少ない印象を持つが、調査対象に給食部門やホテル・旅館関係が含まれないためと思われる。これら輸入野菜も、国産と同様に小売から全体の35.3%を、市場仲卸業者から同18.4%を仕入れられている。
図4 外食産業における生鮮野菜の仕入状況
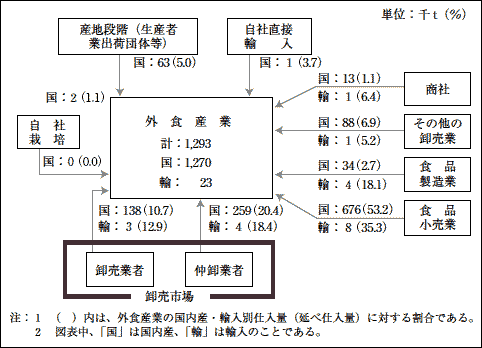
このように、外食産業の野菜調達システムは、売上上位100社にランクされるような大手チェーンを除けば、マーチャンダイジングシステム(インテグレーションを含めた垂直的な計画的調達システム)を外食主導で構築しているところは少なく、多くの店舗がビジネスサイズ、与信などの問題から社会的供給システムに依存している実態を垣間見ることができる。
さらに、この調査によれば、外食産業が仕入れている国産野菜(127.0万トン)のうち、2.2%(実重量で原料換算していない数量2.8万トン)がカット野菜での仕入れとなっており、全体店舗の6.4%(推定2.3万店)が使用している。輸入野菜(同2.3万トン)については8.7%(0.2万トン)が同様にカット野菜での仕入れで、これを全体の6.0%(推定2.1万)に相当する店舗が使用しているとの結果を示している。
(2) 輸入一次加工原料野菜
輸入一次加工原料野菜(にんじん、トマト、ばれいしょ、カボチャなどの冷凍、塩蔵、乾燥、ピューレ、缶詰などのその他)の仕入量(実重量)をみると生鮮での仕入量とは別に14.1万トンが仕入れられている。生鮮と同様に、通関統計の冷凍、乾燥、塩蔵、その他の野菜の輸入量(実重量160.1万トン)と比較すると8.7%水準にしか過ぎない。この点については、外食産業とは別に漬物、缶詰・瓶詰、調味料、冷凍調理品、飲料などの食料品製造業の仕入れが46.3万トンと報告されていること、本調査で結果が取りまとめられていないが、小売部門においても同様の仕入れが想定されること、輸入冷凍野菜で最も多いのは、ばれいしょ、枝豆、さといも、スイートコーンになるが、このうち枝豆の需要部門と考えられる酒場・ビアホール、さといもの需要部門と考えられる惣菜製造業、全般的に一次加工原料への依存度が高い給食部門が調査対象外であることなどの理由により、通関統計での実績に比較してここでの調査結果が小さく現れているものと思われる。
次に、これら輸入一次加工原料野菜の仕入先をみると、自社直接輸入が71.7%と多く、次いで商社からが11.5%となっている。このことから想定されることは、輸入一次加工原料野菜への依存度が高いのは、チェーンオペレーションを基本に店舗調理作業を標準化、マニュアル化している大手チェーンが多いものと思われる。
また、輸入一次加工原料の業種別の仕入構成比を図6でみると、ハンバーガー店での仕入量が全体の72.8%、次いで一般食堂が14.5%、西洋料理店が6.5%となっている。
以上のように、この調査結果により品目、生鮮野菜、輸入一次加工野菜に限定した仕入量とはいえ、その実態が明らかになった。しかし、フードシステムが複雑化している中で、実態としてはこの調査に含まれてない部分があることも留意しておく必要がある。
図5 外食産業における輸入一次加工原料野菜の仕入先
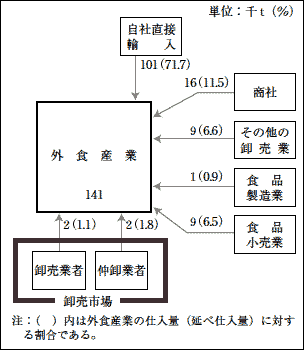
図6 輸入一次加工原料の業種別仕入構成比
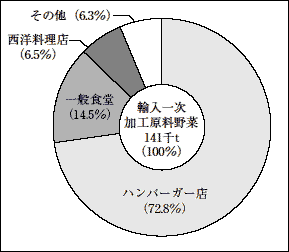
3.事業戦略の転換と野菜利用
厳しい経営環境の中で、外食の産業構造は効率的な大手チェーンに集約する傾向を見せ始めているが、大手チェーンが全て良好な業績というわけではない。
店頭公開・上場企業59社のうち、平成12~15年の間に欠損となった企業が12社認められ、残り47社について必ずしも増収・増益となっているわけではない。図7が示すように、二桁増収であっても減益となった企業が2社、一桁増収の19社では11社が減益となっている。さらに、減収している12社では7社が減益であり、このうち4社では二桁の減益に陥っている。つまり、新規出店だけでは増収しても増益はならないことを示している。
このような状況の中で、最近活発化した動きが事業の多角化である。このうち外食産業でみられるのが水平的多角化(多業態化)である。一般的に事業多角化の誘因は市場環境や技術環境が変化し企業業績に問題が生じた場合、企業内部に未利用資源が存在している場合、長期的な視点に立った時の将来有望な分野への進出の場合などに分けられるが4)、外食の場合には第1のケースが多いように思われる。
図7 売上高と営業利益率の増減率の相互関係(平成13~15年平均)
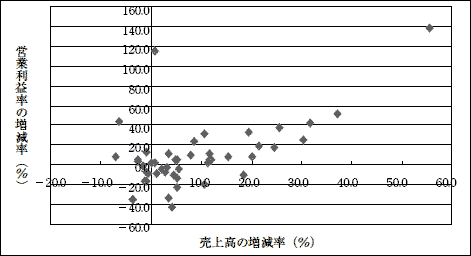
図8 多角化係数と売上高増減率
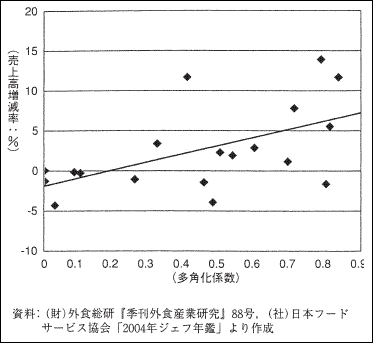
図9 多角化係数と営業利益率
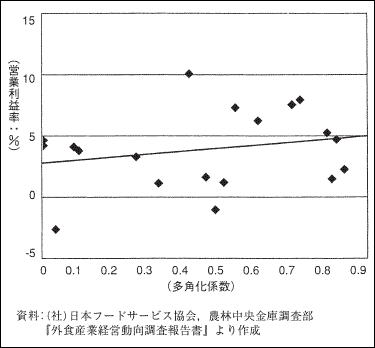
外食企業の多角化をドラスチックに実施した代表的なケースが、「すかいらーく(すかいらーくをガスト、ガーデンズ、グリルに転換)」になるが、企業業績の悪化が顕著となった平成10年以降には、多くの外食企業が同様の動きを活発化させている。
それでは、このような事業多角化が企業業績の改善に結びついているかであるが、図8と9は店頭公開・上場し、直営による店舗展開を実現している企業(ファストフードを除く)19社の多角化度合(係数が大きいほど多角化)と売上高の年率増減率(平成10~14年平均)、営業利益率の関係を示したものである。傾向線が示しているように、多角化係数が大きくなるに従って、売上高の増減率、営業利益率ともに高まる傾向を示している。
もう1点、大手外食企業を中心にみられるようになった動きは、野菜を使ったメニューを積極的に活用し、消費者の健康志向に対応することにより、競合他社との差別化を実現しようとする動きである。このような商品戦略は、平成5~6年頃から見られるようになり、そのために有機・特別栽培野菜を中心に、特定産地や生産者との間で事前協議による独自の調達システムを構築する動きが広がっている。しかし、その後は、ワタミフードサービス、サイゼリヤなどのように生産段階により踏み込んだ取り組みを行っているケースがある。多くの外食企業の場合、産地、品種、品質、価格条件などを事前に協議する意味では同じであるが、市場内外の流通機能を活用した方式に切り替えたことから、各外食企業の独自性が薄れるとともに生鮮野菜を多様化する商品政策も一般化した感がある。チェーンオペレーションの根幹をなす統一メニューを前提とする店舗オペレーションと、それを実現する調達システムの難しさを物語っているともいえる。
ところが、最近、事業多角化と生産野菜(メニューの70~80%が野菜メニュー)を積極的に活用する商品政策を同時に解決するビジネスモデルが登場し、注目されるようになっている。それが「ビュッフェスタイル」レストランである。ビュッフェスタイルは、事業所給食やホテル業界が社員や宿泊者、パーティ参加者といった特定多数の顧客を対象に、ランチタイムあるいはパーティ時間帯といった限られた時間帯に大量供給する仕組みとして生み出された手法であるが、これまでは、フロアー人件費が不要といったメリットがあったとしても、人気メニューから品切れになる、温かい状態で食するメニューが冷たくなっている、といった品質面や、フロアーの接客サービスを基本とする一般レストラン業からみたサービス面の問題から、広く採用されることはなかった。
リンガーハットグループのとんかつチェーン「浜勝」の社長であった元岡氏が、地元で栽培された有機・特別栽培の食材にこだわったビュッフェスタイルレストラン「ティア」(旬の有機・無農薬野菜を使った家庭料理の店、ランチ、ディナーとも1,400円で40種類のフードメニューと10種類以上のドリンクを自由選択)を、平成10年に熊本市内に開業している5)。
「ティア」がビュッフェスタイルを採用したのは、社員食堂やホテルのバイキングのような需要への対応ではなく、地元で栽培された旬の有機野菜を重視した営業スタイルを模索し、地元の農家グループとの連携を確立した結果といえる。
一般的なレストランでは、外食需要の特性からメニューのフルライン化は難しく、ある範囲の売れ筋メニューを定番化し、そのメニューに使用する食材の調達を行っている。しかし、地元の旬の食材を重視する「地産地消」の場合には、メニューの特定化、量的な安定性を確立することが難しくなる。そのために調達できた食材をメニュー化していくスタイルにたどり着いたものと考えられる。
外食の店舗は、食材の調理、調理品の販売、空間利用、接客サービス機能を備えた複合体であり、それぞれの質や水準が店舗の価値を決定しているといってよい。その意味で、「ティア」は農村・農家レストランや有機・自然食レストランの「地産地消」のコンセプトを採用しながら、大消費地の外食市場で競争力のある業態を提示したともいえる。
そのことを裏付けるように、表1が示すように平成10年以降になると、同様のコンセプトを採用した店舗が数多く出店することとなった。
表1 ビュッフェレストラン業態
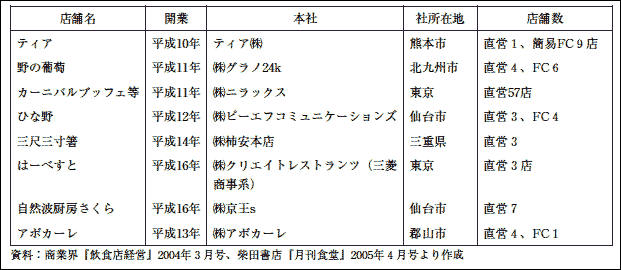
まとめ
平成に入り、外食市場は、それまでと様相を変え、画一的な需要から多様化することとなり、外食企業もそれまでの統一メニューによる単一チェーンでの全国的チェーン展開では、新規出店による増収効果を、既存店の売上げ低迷が逓減することとなった。このため、多様化した需要のなかの健康志向需要に積極的に応えることで、競合他社と差別化を図ろうとする動きが活発化した。
これらの先駆的な取り組みとして、平成5~6年頃に一部の大手チェーンが、生鮮野菜を積極的に活用した商品政策を推し進め、それを実現するための独自の調達システムを構築する動きが見られたが、市場内外でこれらに対応する供給システム作りが進み、外食企業が独自に調達システムを構築しなくても、産地や品質を指定した調達が可能となり同様の取り組みが一般化した。
平成10年以降になると、企業業績を商品政策だけで維持することが難しくなり、新たな業態開発により横断的な事業多角化(多業態化)に取り組むところが見られるようになった。その一環として「メニュー前提の食材調達」から地場の野菜を中心に「その時々に入手可能な食材をメニュー化」するビジネスモデルが登場している。それが「ビュッフェスタイル」レストランである。このモデルは、立地のベースとなる商圏が広いことから、ファストフードやコンビニエンスチェーンのような密度の高い出店が難しく、数百規模のチェーンが登場するとは思われないが、外食産業の1部門を構築することが期待される。
参考文献
1.(財)外食総研編『外食産業統計資料集』各年版
2.(財)外食総研『月次売上動向調査』
3.田村馨著『日本型経営革新の経済分析』九州大学出版会1998年 p.187~212
4.青山昌彦、伊丹敬之著『企業の経済学』岩波書店1986年 p.63
5.商業界編『飲食店経営』2004年3月 p.51~53