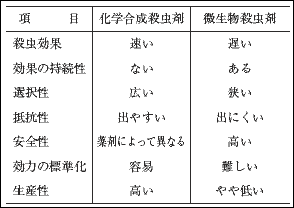今月の話題
今月の話題
生物農薬の現状と未来について
東京農業大学 応用生物科学部
教授 大澤 貫寿
あらゆる生物には、限りなく繁殖しないように抑制する作用が自然環境内に働いている。その最も重要な要素が生物的因子である。自然界では、多くの生物が互いに干渉し合って生きている。ヒトを病気にする病原微生物があるように、害虫や雑草にもそれぞれ固有の病原微生物がおり、病気を引き起こしている。また、作物害虫や雑草の死亡原因となる生物的因子は、天敵にあることが多い。このような病原微生物や天敵昆虫を利用したり、害虫の雌が放出する臭い物質であるフェロモンを利用したり、生物の代謝産物を活用したりして、病害虫、雑草を防除しようとすることを生物的防除法と呼び、こうした生物素材は生物農薬と呼ばれている。
絹を作り出すカイコが卒倒病を起こして死んでしまうことは、養蚕農家では古くから知られていた現象である。その原因は細菌による感染で、バチルス・チューリンゲンシス(Bacillus thuringiensis)(以下「BT」という。)によって引き起こされる現象であることが判明し、その細菌はカイコと同じ属の害虫にも効果的な殺虫作用を示すことが分った。この細菌を大量に培養して散布することが、キャベツやレタスなどの化学合成農薬が効かなくなっている害虫の防除に利用され、大きな成果を上げている。
昆虫は配偶者を見つけるために、言葉の代わりにフェロモンという化学物質を介したコミュニケーションを図り、相手をおびき寄せて交尾する。フェロモンは害虫をおびき寄せて捕獲する誘引剤、あるいは大量散布により雄雌間のコミュニケーションを妨害する交信かく乱剤として利用されている。このほか、害虫を捕食する昆虫やクモ、害虫の幼虫や卵に寄生する捕食寄生者の寄生蜂などの天敵を工場で大量に増殖して利用する方法がある。そして、微生物や植物の代謝産物で殺虫性や抗菌性を持つ成分を用いて作る微生物源や植物源農薬もある。
2.微生物の利用
微生物の生産する物質をそのまま用いた農薬の数は少ない。その理由としては一般に、活性が不十分なこと、天然からの単離精製が困難で収量が少ないこと、構造が複雑で合成による大量生産が困難なことなどが挙げられる。しかし、合成農薬とされているものの中にも微生物や植物などの天然物の構造を基にして開発されたものは多い。
微生物を素材とした生物農薬BT剤とは、BT細菌の産生する殺虫性タンパク質の芽胞を有効成分とした殺虫剤である。BT剤は1930年にアメリカ、ヨーロッパで市販され、世界各地の野菜や果樹の害虫に使用されてきている。日本では、1981年に農薬登録され現在では、約200トンのBT剤が使用されている。BT剤は、蝶や蛾の幼虫に対して効果的に作用し、キャベツなどのアブラナ科植物のコナガ、ヨトウガ、オオタバコガなどや、チャノコカクモンハマキに有効である。BT剤の特徴は好気性菌であるため、哺乳類の腸内のような嫌気的条件下では繁殖できない。従って、人畜に対する安全性が高い。また、生態系に与える影響が少ないことや害虫での抵抗性の発達がないなどの利点が挙げられる。BT剤は、農薬としては、普通物の分類に入り、マウスやラットに対する急性経口毒性は極めて低いことが確認されている。BT剤の殺虫活性は、菌体内に生産される結晶性蛋白質毒素が昆虫の中腸の上皮細胞を破壊して、昆虫の餌の摂取や消化吸収を妨げることによる。食毒として作用するBT剤は、天敵などへの影響が少ないことから、生態系への影響は殆どないと思われる。BT剤の今後の問題としては、殺虫活性の増大、殺虫対象害虫の拡大、抵抗性の対策などがある。
糸状菌フザリウム(Fusarium oxysporum)は、殺菌剤バイオキパ-として、サツマイモの蔓割れ病の制御に利用されている。この糸状菌の胞子は安定性が高く、ゼオライトと混和して水和剤として利用されている。バイオキパ-水和剤は、野菜類の白菜、ジャガイモ、大根、キャベツなどの軟腐病に対しての防除効果が認められている。ナス、トマトなどの灰色カビ病の予防に用いられるのは、バチルス・ズブチルス(Bacillus subtilis)で、これは芽胞という耐久性のある胞子を形成するため温度、乾燥、紫外線に強く、安定性の高い水和剤として利用されている。
微生物除草剤は、微生物の分生子の懸濁液を用いた製品が用いられ、本格的な微生物除草剤としては、大豆に寄生するネナシカズラを防除するのに炭疽病菌が1963年に中国で用いられた。その後、発酵法により大量培養が行われ、液剤として散布された。我が国では、水田の難防除雑草クログワイを防除するために糸状菌(Epicoccosorus nematosporus)を用いたのが最初である。しかし、この菌は、保存性が悪く病原性が失われてしまうとの欠点があった。その後のヒエ防除のために糸状菌(Exserohilum monoceras)を用いた微生物除草剤が開発された。微生物源除草剤の代表的なものとしては放線菌(Streptomyces hygroscopicus)の成分としてランダムスクリーニング(無作為試験)の中から見つけられた非選択性除草剤ビアラホスが挙げられる。植物のグルタミン合成酵素の活性を阻害して植物体内にアンモニアを蓄積し、その毒性で殺草活性を現す。
自然界では、膨大な種類の微生物が、寄生、共生、競合などそれぞれの様式で他の生物とかかわり合って生存している。微生物が他の生物に活性のある物質を作り出す能力は、このような他の生物とのかかわりの中で生き抜いてきたことにあると思われる。
3.フェロモンの利用
昆虫は、昆虫同士、植物との関係においていろいろな場面で化学物質による情報を利用している。
餌や産卵場所を見つけ出すため、密度を調整するため、配偶相手を見つけて繁殖するために、化学物質を介して発信、受信し、その行動を制御する。このような情報化学物質のうち、情報の出し手と受け手が同種内で使われるものをフェロモンと言う。
フェロモンとは、個体の体外に放出される物質を指す。それらは、種の個体間では極微量(10-8~10-10g)で働く。その機能から、異性を誘引し、交尾行動を引き起こす性フェロモンや交尾フェロモン、雌雄に関わらず仲間を呼びよせる集合フェロモン、重複産卵を回避するために雌が産卵場所に印をつける産卵目印フェロモン、社会性昆虫がコロニーに対して外敵などの危険を知らせる警報フェロモンや道しるべフェロモンなどさまざまなものがある。
フェロモンという情報化学物質によって、特定の種の行動をコントロールできる。なかでも、雄成虫に対して誘引、交尾行動を引き起こす雌性フェロモンは、鱗翅目・甲虫目を中心とした主要害虫において化学構造の解明が進み、大量合成法や製剤技術の進展に伴い、実際の害虫防除での応用も進みつつある。最近では、室内で繁殖し防除が困難なチャバネゴキブリの性フェロモン構造が明らかになり、今後その利用が期待される。
性フェロモンには、放出源に虫を引き寄せる誘引剤としての利用法と、生息周辺環境を広く覆うことによってコミュニケーションを妨害する交信かく乱剤としての利用法がある。
誘引剤としては、誘殺除去によって密度低下効果を狙う大量誘殺と、化学農薬との組み合わせての害虫防除に必要な発生情報を得るための発生予察とに分けられる。性フェロモン剤の利用上の利点は、種特異性が高いため標的以外の害虫に対する影響が少ないこと、極微量で生理活性を示すため、処理量も極少なく、周辺環境への影響がなく、化学構造上分解しやすく、取り扱いが簡単であること、対象害虫の種の維持に直接関わる情報化学物質であるため、効きにくくなることがない、といった利用上のメリットがある。
雌の性フェロモンに対する雄の反応の特徴は、フェロモン源に強く誘引される。そこで、性フェロモンを仕込んだトラップによって雄を一網打尽にし、雌との交尾回数を減少させる大量誘殺という誘引防除が実施されているが昆虫の発育と加害活動ステ-ジよって、その効果には大きな差異がある。コガネムシのように成虫が加害ステージである害虫では、大量誘殺により成虫による食害を減らす効果が期待できるものの、アワヨトウムシのような鱗翅目の害虫では、幼虫が加害ステージであり、成虫の除去のみではすぐには防除効果に結びつかない。また、雄は通常複数回交尾できるため、取り残し雄の複数回交尾によって雌の交尾率が維持されうる。すなわち、雄を80~90%除去しないと雌交尾率は維持され、次世代での密度低下にはつながらない。従って、雌の性フェロモンによる大量誘殺が有効となるためには、圃場の雌に対してトラップの設置が十分確保されているかが重要である。一方、ゴキブリなど集合フェロモンのような雌成虫を捕獲できる誘引剤の利用は、次世代の密度低下への効果が期待できる。また、害虫の発生時期や数、場所などの発生状況を把握することは、薬剤散布を無駄なく実施するうえで、有効な手段である。
交信かく乱は、大量の放出源を配置して害虫の生息環境を性フェロモンで覆うことにより効果が得られる。その正確なメカニズムは判明していないが、放出源(雌)を覆い隠すこと、交信かく乱剤へ誤って定位させて雌を見失わせること、継続的なフェロモンへの暴露により雄の受容体の反応の馴化を起こすことが示されている。交信かく乱の結果、雌交尾率が低下し、次世代の発生が抑えられる。
4.天敵の利用
「天敵昆虫」とは、一般にはアブラムシを捕食するテントウムシ、イセリヤカイガラムシに対するベダリアテントウ、ヤノネカイガラムシに対するヤノネツヤコバチなどを指し、外国から導入したりして古くから防除に利用されている。これらは、人間にとって有害な生物を退治してくれるという実用的な視点から、いわゆる「益虫」の意味合いを込めて用いられる。昆虫では、小鳥やクモ、テントウムシ類などの捕食者とコマユバチやヤドリバエなど寄生蜂や寄生蠅のような捕食寄生者および糸状菌や細菌、ウイルスなど昆虫に病原性を示す病原微生物に大別される。いずれも、最終的には餌や栄養源となる昆虫を殺したり、繁殖に重大な影響を及ぼしたりして増殖を抑えている。
天敵を農業害虫の防除に用いられたのは、19世紀後半にカリフォルニアのオレンジ園に侵入して壊滅的な打撃を与えたイセリヤカイガラムシに対して、原産地のオーストラリアからベダリアテントウを導入して制圧に成功した例が最初である。
この成果を受けて、我が国でも、特に侵入害虫に対して原産地からさまざまな天敵の導入が試みられ、成功を収めたものもあるが、失敗例の方が多い。このような、侵入害虫に対して天敵を導入・定着させ、永続的に利用する方法を生物的防除法として、土着の天敵の密度を高めるために天敵誘引剤を用いたり、天敵のかくれ場所や越冬場所、代替餌などを確保・提供して天敵の効果を高める工夫がなされた。また、人工的に大量飼育した天敵を継続的に放飼する方法などを開発し、広く利用されるようにもなった。天敵を継続的に放飼する方法は、天敵利用技術の確立により、施設内での生物農薬的利用として定着してきている。最近は、こうした天敵が国内外の天敵産業による製品として盛んに生産・販売されるようになった。
日本においては農薬として登録し、一般に「天敵農薬」と称され、施設園芸で広がりつつあるが、温暖で湿潤な日本の多様な作物栽培においては、害虫相が複雑なこともあり、天敵農薬の普及はヨーロッパに比べて遅れている。我が国で登録された害虫用の「生物農薬」は、ハダニに対するチリカブリダニ、コナジラミ類に対してのオンシツツヤコバチ、などがあり、主として園芸施設内で効果を上げている。しかし、日本における生物的防除は、生物的防除資材の利用と併せて、複雑な害虫相と裏腹の関係にある多様な土着の天敵相を生かすことが重要である。現在では、ミナミキイロアザミウマに対するアリガタシマアザミウマが、生物農薬として登録されている。こうした地域の土着天敵の利用の場を広げる手法の開発にも力を注ぐ必要がある。
5.植物源農薬の利用
世界で50万種類と言われている植物のうち、生理活性資源として利用されているのは、そのごく一部でしかない。それらの多くは、生薬として利用されてきているが、病害虫防除への利用は、その内のほんの一部の植物にすぎない。
近年では、化学合成農薬の環境への負のインパクトや健康への影響を考慮して新規の植物源農薬(Botanical pesticides)の探索と開発が強く求められている。
除虫菊の乾燥花の利用に始まり、デリス属植物ハイトバの根の水抽出物、タバコ葉の殺虫成分が代表的な植物源農薬として利用されてきた。除虫菊の殺虫成分はピレトリンであり、その構造から関連化合物が合成され、ピレスロイド剤として重要な殺虫剤群を形成している。最近、タバコの殺虫成分ニコチンも、その構造関連化合物が合成され、非常に強力な殺虫剤として開発されてきている。化学農薬による生物と生態環境への悪影響が絶えず危惧されているなか、自然・農業生態系で容易に分解し環境への悪影響のない植物源農薬の探索が求められている。センダン科の植物インドセンダン(Azadirachta
indica)は、インドなど南アジアで古くから害虫防除や医薬として利用されてきている。また、中国やタイ国などでもMelia azedarachなどのセンダン科の植物の抽出物が、農業用害虫防除に利用され始めている。その昆虫に対する活性は、摂食阻害作用、脱皮変態の阻害および殺虫性である。これらの製品としては有効成分アザディラクチンを0.3%含有したMargosan-OTM(R)が1990年に米国で製品化されたのを始めとして、5%含有物のNeem
Azal TM(R)がドイツで、その後、オーストラリア、インド、タイで順次商品化されている。
タイではタイニーム(Azadirachtica siamensis, A.excelsa)を原料として0.5%有効成分(azadirachtin)含有のSADAO-TM(R)や0.1%含有のNEEMPLUS(R)とNEEM-AG(R)を商品化し、野菜の重要害虫、スリップス、アブラムシやコナガの防除に利用し始めている。最近のタイなど東南アジアから日本への輸出野菜について、アスパラガスやオクラなど輸出用野菜栽培では、NEEM抽出物製剤とBT剤の組合わせのみによる防除が奨励され、無化学合成農薬による栽培野菜として輸出している。
6.生物農薬の今後
微生物には、人畜に有害なものが少なくないことも事実であり、生物農薬として利用しようとする微生物には、いささかもそのような問題があってはならない。動物試験で安全性を確認するとともに、近縁種も含めて、綿密な調査も不可欠であり、問題があれば、直ちに開発を中止すべきである。
いずれの方法にしても、生物農薬は安全性の高い作物生産に欠かせない技術の1つとして、21世紀の農業では、ますます需要が高まり、さらに多くの生物農薬が発見されていくことだろう。
(参考)
化学合成殺虫剤と微生物殺虫剤の比較