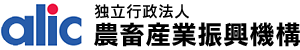ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 白ねぎのトータルビジネスに挑む 産地の労働力不足の課題解決にも積極対応 ~株式会社TFY ~
新潟食料農業大学 食料産業学部 食料産業学科 准教授 青山 浩子
【要約】
埼玉県深谷市の株式会社TFY(以下「TFY」という)は、全国の契約産地から白ねぎを集荷し、小売店や外食企業など実需者に販売する流通業者である。同社は、分社前のあらきグループの時代から産地開拓を行ってきた板橋勇二社長が率いており、現在契約農家は150軒を超える。農家の経営の安定を最優先に考えた固定価格による買い取り、専門指導者による技術支援など、生産者との濃密な関係を築いてきた。近年では、規模拡大を阻んでいる生産現場の労働力不足を解消するため、外国人材の派遣事業にも注力している。また、ねぎの機能性に着目し、研究開発に乗り出すなど、ねぎに関わるトータルビジネスを展開している。
生産費の高騰により、収益悪化を懸念する生産現場を支えるため、連携関係にある資材業者に働き掛け、価格引き下げに向けた取り組みを行う一方、物流拠点を再編するなどフードチェーン全体での効率化に果敢に挑んでいる。
生産費の高騰により、収益悪化を懸念する生産現場を支えるため、連携関係にある資材業者に働き掛け、価格引き下げに向けた取り組みを行う一方、物流拠点を再編するなどフードチェーン全体での効率化に果敢に挑んでいる。
1 40を超える契約産地から安定調達
TFYは、全国各地の40を超える産地、約150軒の生産者から白ねぎを調達し、小売店を中心に納めている。現在は白ねぎの仕入れおよびカット事業をメインに行っているあらきグループから分社化する形で、2018年4月に誕生した企業である。
まず、あらきグループの概略を述べる。同グループは、1953年創業、1979年に法人化し、青果物流通業者として長らく青果物全般を取り扱ってきた。国内に出回る青果向けの白ねぎが、中国産から国産へとシフトが進んでいた2000年前後、同グループもアイテムを白ねぎに集中させ、単品管理による収益向上を目指すようになった。自社で産地開拓を行い、生産者との契約取引を本格化させたのもこの頃である。
主に小売店向けの青果用白ねぎの取扱量を増やしていく中で、取引先の一部から、「ねぎをカットして納品してほしい」という要望が増えてきたため、カット事業にも着手した。さらに、契約産地の端境期にあたる期間の調達を目的に、生産部門を立ち上げた。これが TOSI FARM(設立当初の株式会社マッシュから社名変更)である。現在の経営規模は約40ヘクタールで、主にカット向けの原料のねぎを栽培している。
カットねぎの取引量が増えていく一方、小売店からの青果向けのねぎの注文も増えてきた。そこで、カットを行わない青果用ねぎを専門に扱う組織として、TFYが設立された。TFYは、あらきグループ時代からねぎの産地開拓を率先して進めてきた板橋社長が率いることになった(写真1)。

現在、TFYが扱う白ねぎの取扱量は、繁忙期の12月~翌2月は337.5トン/月ほど、繁忙期以外は200~225トン/月ほどである。主な契約産地は北海道、秋田、宮城、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、静岡、熊本、鹿児島などである。これだけの産地を抱えていてもなお、入荷量が一時的に足りなくなる端境期がある。そこで、同じあらきグループのTOSI FARMとは別に、TFYの生産部門を担う農業生産法人として株式会社ファーマーズトラストを2019年に設立した。埼玉県のねぎの代表産地である深谷市や熊谷市を中心とし、生食用ねぎを約9ヘクタール作付けている。TFYのねぎの納品先の8割は、食品スーパーなどの小売店、残りが外食・中食など業務向けである。日本国内で生産されるすべての白ねぎのうち、同社のシェアは1.23パーセントを占める。
まず、あらきグループの概略を述べる。同グループは、1953年創業、1979年に法人化し、青果物流通業者として長らく青果物全般を取り扱ってきた。国内に出回る青果向けの白ねぎが、中国産から国産へとシフトが進んでいた2000年前後、同グループもアイテムを白ねぎに集中させ、単品管理による収益向上を目指すようになった。自社で産地開拓を行い、生産者との契約取引を本格化させたのもこの頃である。
主に小売店向けの青果用白ねぎの取扱量を増やしていく中で、取引先の一部から、「ねぎをカットして納品してほしい」という要望が増えてきたため、カット事業にも着手した。さらに、契約産地の端境期にあたる期間の調達を目的に、生産部門を立ち上げた。これが TOSI FARM(設立当初の株式会社マッシュから社名変更)である。現在の経営規模は約40ヘクタールで、主にカット向けの原料のねぎを栽培している。
カットねぎの取引量が増えていく一方、小売店からの青果向けのねぎの注文も増えてきた。そこで、カットを行わない青果用ねぎを専門に扱う組織として、TFYが設立された。TFYは、あらきグループ時代からねぎの産地開拓を率先して進めてきた板橋社長が率いることになった(写真1)。

現在、TFYが扱う白ねぎの取扱量は、繁忙期の12月~翌2月は337.5トン/月ほど、繁忙期以外は200~225トン/月ほどである。主な契約産地は北海道、秋田、宮城、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、静岡、熊本、鹿児島などである。これだけの産地を抱えていてもなお、入荷量が一時的に足りなくなる端境期がある。そこで、同じあらきグループのTOSI FARMとは別に、TFYの生産部門を担う農業生産法人として株式会社ファーマーズトラストを2019年に設立した。埼玉県のねぎの代表産地である深谷市や熊谷市を中心とし、生食用ねぎを約9ヘクタール作付けている。TFYのねぎの納品先の8割は、食品スーパーなどの小売店、残りが外食・中食など業務向けである。日本国内で生産されるすべての白ねぎのうち、同社のシェアは1.23パーセントを占める。
2 生産者との信頼関係を最も重視
TFY設立後も、引き続きトップセールスを行う板橋社長は、現在も1年の半分以上を産地訪問に充てている。「直接産地に出向き、生産者と腹を割って話し合うことで信頼関係を築くことができる」という信条によるものだ。
ねぎは、シーズンごとに決める固定価格で、生産者から買い取っている。「単価を決めておくことで、農家の手取りが安定する。それが、優先的に当社に出荷しようという動機付けにもなる」という。買取価格の算定基準は、同社の取引先への納入価格や過去の相場を参考としながら、生産者のコストなどにも配慮し、最終的に設定する。豊作などが続き、相場が安くなったとしても、いったん決めた数量と価格は、変更することはない。豊作などにより、計画数量を超える買い取りの相談を受けた場合は、通常の契約単価を維持した上で、小売店に特売を持ち掛けるなどして、買い取り量を増やすなどの工夫をしている。
白ねぎは、収穫適期が限定される野菜とは異なり、一定期間は圃場に植えておくことが可能な“在庫性”の高い野菜だ。この特性を活かし、既存の作物や他の産業と並行した栽培が可能であるなど、“組み合わせしやすい点”を強調する。実際、同社の契約産地には、稲作メインで経営する親を持つ息子世代で形成されているケースもあれば、漁業をメインにしながら、副業でねぎ生産に取り組む産地もあるという。
商談が具体化していくと、単位面積当たりの売り上げや経費などデータを示しながら、収支シミュレーションを提示する。「栽培経験がない生産者には、発芽率や秀品率などあえて抑えめに計算し、手堅い数字を示すようにしている」と板橋社長は語る。背伸びをした数字を示し、過剰な期待を持たせるのではなく、栽培技術の向上とともに生産性や収益性が上がるという本音の話をすることでむしろ信頼関係を深められるからだ。
ねぎは、シーズンごとに決める固定価格で、生産者から買い取っている。「単価を決めておくことで、農家の手取りが安定する。それが、優先的に当社に出荷しようという動機付けにもなる」という。買取価格の算定基準は、同社の取引先への納入価格や過去の相場を参考としながら、生産者のコストなどにも配慮し、最終的に設定する。豊作などが続き、相場が安くなったとしても、いったん決めた数量と価格は、変更することはない。豊作などにより、計画数量を超える買い取りの相談を受けた場合は、通常の契約単価を維持した上で、小売店に特売を持ち掛けるなどして、買い取り量を増やすなどの工夫をしている。
白ねぎは、収穫適期が限定される野菜とは異なり、一定期間は圃場に植えておくことが可能な“在庫性”の高い野菜だ。この特性を活かし、既存の作物や他の産業と並行した栽培が可能であるなど、“組み合わせしやすい点”を強調する。実際、同社の契約産地には、稲作メインで経営する親を持つ息子世代で形成されているケースもあれば、漁業をメインにしながら、副業でねぎ生産に取り組む産地もあるという。
商談が具体化していくと、単位面積当たりの売り上げや経費などデータを示しながら、収支シミュレーションを提示する。「栽培経験がない生産者には、発芽率や秀品率などあえて抑えめに計算し、手堅い数字を示すようにしている」と板橋社長は語る。背伸びをした数字を示し、過剰な期待を持たせるのではなく、栽培技術の向上とともに生産性や収益性が上がるという本音の話をすることでむしろ信頼関係を深められるからだ。
3 生産者自身も産地形成に協力
実際に取引が始まると、産地に入って技術指導に当たるのは、農業改良普及指導員としての経歴を持つアドバイザーだ。契約産地の生産者が求める情報は多岐にわたる。とりわけ、品種、病虫害に関する情報、防除方法、他産地の作付け状況、相場に関する情報などへのニーズが高い。こうした要望に対応するため、園芸の栽培指導経験が長いプロをアドバイザーに起用し、全国の契約産地に出向いてもらっている。契約産地が北海道から九州と全国にわたっていることもあり、「遠隔地の情報を求めている生産者には大変重宝がられている」(板橋社長)。トップセールスによる産地開拓と専門的な技術指導というコンビネーションにより、順調に産地を拡大してきた点が同社の特徴といえる。
契約産地の多くが、比較的若い年代の生産者によって構成されている点も大きな特徴だ。30歳代の生産者を中心とする産地もあるという。産地から同社の物流センターまでの配送の効率性を考えると、一産地の作付面積が5ヘクタール程度まとまっているかどうかが目安となる。仮に、新規に作付けを始める生産者だけではこの目安に届かない場合、生産者自らが近隣農家にねぎ栽培または増産を働き掛け、ロットをまとめる工夫をすることもある。さらに、生産者が中心となって管内のJAと交渉し、JAの保有する配送ルートでねぎを運ぶことができないか持ち掛けることもある。現在、同社が取り扱うねぎの6割がJAの配送ルートからの調達であるが、これは若手生産者の軽いフットワークに起因している部分も少なくないという。
契約産地の多くが、比較的若い年代の生産者によって構成されている点も大きな特徴だ。30歳代の生産者を中心とする産地もあるという。産地から同社の物流センターまでの配送の効率性を考えると、一産地の作付面積が5ヘクタール程度まとまっているかどうかが目安となる。仮に、新規に作付けを始める生産者だけではこの目安に届かない場合、生産者自らが近隣農家にねぎ栽培または増産を働き掛け、ロットをまとめる工夫をすることもある。さらに、生産者が中心となって管内のJAと交渉し、JAの保有する配送ルートでねぎを運ぶことができないか持ち掛けることもある。現在、同社が取り扱うねぎの6割がJAの配送ルートからの調達であるが、これは若手生産者の軽いフットワークに起因している部分も少なくないという。
4 労働力不足解消のための外国人材紹介事業
白ねぎの需要は安定していることもあり、契約生産者はいずれも規模拡大志向を強く持っている。ところが、これを阻んでいるものが労働力不足である。この課題を避けて通ることはできないと板橋社長は決心し、着手した事業が外国人材の受け入れおよび農家への紹介事業だ。
本事業を本格的に始めたのは2019年で、当初は技能実習生を受け入れていたが、一定の専門性や技能を有する外国人の就労が認められる“特定技能”という在留資格が認められてから、同社も特定技能にシフトした。
同社が受け入れる外国人材は全員インドネシア人である。同社は、彼らの受け入れを全面的にサポートし、出入国在留管理庁などへの各種届出も行う「登録支援機関」としても登録されている。インドネシア人に特化している理由は、インドネシアとのネットワークを持ち、同国から長年、技能実習生を受け入れ、生産者に紹介する事業を行ってきた野菜生産法人の幹部をスカウトしたことが背景にある。2021年には、労働力を必要とする生産者に特定技能を保有する人材を紹介する専門組織である株式会社JMD(以下「JMD」という)を設立した。
2022年10月時点で、JMDが紹介した特定技能を保有する人材は46人である。コロナ禍で、来日が決まっていながらも、しばらく足止めされていたが、2022年春から徐々に外国人の訪日に関する規制が緩和され、順次来日できるようになった。同社と契約を結ぶねぎ生産者を優先的に紹介しているが、全国の契約産地以外の生産者も対象としている。当面100人を目指し、2025年までに300人まで増やす目標だという。
外国人材が日本での生活に定着できるよう、JMDのスタッフが全面的なケアを行っている。インドネシア語に長けた3名のスタッフがおり、入国に必要な書類の準備はもちろん、紹介先が決まれば、住居探し、生活必需品をそろえるためのサポート、オンラインでの日本語教育プログラムの紹介と、きめ細かいケアを実施している。
本事業を本格的に始めたのは2019年で、当初は技能実習生を受け入れていたが、一定の専門性や技能を有する外国人の就労が認められる“特定技能”という在留資格が認められてから、同社も特定技能にシフトした。
同社が受け入れる外国人材は全員インドネシア人である。同社は、彼らの受け入れを全面的にサポートし、出入国在留管理庁などへの各種届出も行う「登録支援機関」としても登録されている。インドネシア人に特化している理由は、インドネシアとのネットワークを持ち、同国から長年、技能実習生を受け入れ、生産者に紹介する事業を行ってきた野菜生産法人の幹部をスカウトしたことが背景にある。2021年には、労働力を必要とする生産者に特定技能を保有する人材を紹介する専門組織である株式会社JMD(以下「JMD」という)を設立した。
2022年10月時点で、JMDが紹介した特定技能を保有する人材は46人である。コロナ禍で、来日が決まっていながらも、しばらく足止めされていたが、2022年春から徐々に外国人の訪日に関する規制が緩和され、順次来日できるようになった。同社と契約を結ぶねぎ生産者を優先的に紹介しているが、全国の契約産地以外の生産者も対象としている。当面100人を目指し、2025年までに300人まで増やす目標だという。
外国人材が日本での生活に定着できるよう、JMDのスタッフが全面的なケアを行っている。インドネシア語に長けた3名のスタッフがおり、入国に必要な書類の準備はもちろん、紹介先が決まれば、住居探し、生活必需品をそろえるためのサポート、オンラインでの日本語教育プログラムの紹介と、きめ細かいケアを実施している。
5 帰国後の連携事業も構想
自ら登録支援機関となって、外国人材を受け入れ始めた経緯について、板橋社長は「契約産地の生産者は、私たちにとって貴重な資産。いわば、BS(貸借対照表)には計上されない資産です。生産者がいてこそ、われわれのビジネスが成り立ちます。その生産者が労働力の確保を最大の課題にしている以上、見過ごすことはできない」と語る。
現在、農業分野で就労する外国人材は、専門的な技術力や知識を有して永住ビザを持っている一部の人材を除き、通算在留期間が限られている「特定技能1号」に属する者、ないしは技能実習生である。同社が現在受け入れているインドネシア人も通算で5年雇用となっている。板橋社長は「遠い先の話かもしれない」と前置きした上で、卒業生たちが帰国した後、現地でねぎを生産してもらう計画を温めている。同社の取引先である大手小売店や大手外食業者の中には、すでにインドネシアを含むアジア諸国への出店を果たしているところもある。「日本で習得した技術を活かし、現地でねぎを生産し、これらの店舗に納入する仕組みができれば、インドネシアの雇用創出につながり、農業の活性化にもつながる」と話す(写真2)。

現在、農業分野で就労する外国人材は、専門的な技術力や知識を有して永住ビザを持っている一部の人材を除き、通算在留期間が限られている「特定技能1号」に属する者、ないしは技能実習生である。同社が現在受け入れているインドネシア人も通算で5年雇用となっている。板橋社長は「遠い先の話かもしれない」と前置きした上で、卒業生たちが帰国した後、現地でねぎを生産してもらう計画を温めている。同社の取引先である大手小売店や大手外食業者の中には、すでにインドネシアを含むアジア諸国への出店を果たしているところもある。「日本で習得した技術を活かし、現地でねぎを生産し、これらの店舗に納入する仕組みができれば、インドネシアの雇用創出につながり、農業の活性化にもつながる」と話す(写真2)。

6 コロナ後、調達先を見直す外食業者
2020年に始まったコロナ禍の混乱を経て、ようやくウィズコロナ社会へのシフトが図られようという時期に差し掛かった。コロナ禍に突入した当時、同社の取引にもさまざまな変化が起きた。同社の取り扱うねぎは、小売店で販売する青果向けが8割を占め、コロナ禍で甚大な影響を受けた外食向けの比率が低いこともあり、注文量の減少は免れたという。むしろ、巣ごもり需要により小売店での販売量が増えたほか、ミールキットなどを取り扱うネット通販企業からの注文が増えた。そのため、8:2だった青果向けと外食向けの比率が、一時的とはいえ、9.5:0.5となる時期もあった。
こうした中、外食企業の一部から、輸入ねぎから国産ねぎに切り替える動きがみられるようになった。2022年の春、中国の上海市で、新型コロナウィルスの感染者が急増した。中国政府は、まん延阻止のため一時的に上海市でのロックダウンを実施した。この余波を受け、同国から日本向けの農産物輸入が途絶えた時期があり、予定していた中国産ねぎを調達できず、困り果てた外食業者から同社に引き合いが来たという。その後、ロックダウンが解除され、事態が収まった後も、一部の外食業者から「同じような事態が再び起こり得ることを考え、国産ねぎの調達ルートも確保しておきたい」という問い合わせがあり、実際に同社との取引を始めたケースもある。同社としては今後も小売店向けの青果用ねぎを中心とする方針に変化はないが、価格面で折り合えば、業務用ねぎの取り扱いも増やしていくつもりだ。
こうした中、外食企業の一部から、輸入ねぎから国産ねぎに切り替える動きがみられるようになった。2022年の春、中国の上海市で、新型コロナウィルスの感染者が急増した。中国政府は、まん延阻止のため一時的に上海市でのロックダウンを実施した。この余波を受け、同国から日本向けの農産物輸入が途絶えた時期があり、予定していた中国産ねぎを調達できず、困り果てた外食業者から同社に引き合いが来たという。その後、ロックダウンが解除され、事態が収まった後も、一部の外食業者から「同じような事態が再び起こり得ることを考え、国産ねぎの調達ルートも確保しておきたい」という問い合わせがあり、実際に同社との取引を始めたケースもある。同社としては今後も小売店向けの青果用ねぎを中心とする方針に変化はないが、価格面で折り合えば、業務用ねぎの取り扱いも増やしていくつもりだ。
7 業界全体で取り組むべき生産費問題
生産現場では、目下、資材費や燃料費の高騰による生産コストの負担増が経営の足かせとなっている。契約産地の生産者から、「資材費や肥料代などの値上がりで生産コストがそれまでの1.5倍に上がった」という悲鳴が届いている。流通業者である同社にとっても燃料代や物流コストの増加は深刻な課題となっている。
契約産地を支える策の一つとして、日頃からパートナーシップを組んでいる農業資材関連企業と話し合い、生産者から資材や肥料の注文を取りまとめ、ボリュームに応じたディスカウントができないか働き掛けている。すでに関東地域の農家には割引が適用されているという。板橋社長はもともと、契約産地を拡大する際、生産現場に明るい種苗メーカーや肥料メーカーと共に産地を訪ねて、生産者に契約を持ち掛けた。生産現場に詳しい企業と、販売先という「出口」を持つ同社がタッグを組み、産地を拡大してきたわけだ。
ただ、「こうした努力が抜本的な解決策になっているとは言い難い」と板橋社長は話す。同社が契約産地から買い取る価格は、卸売市場の相場が基準となっている。相場は需給関係により決まるものであり、必ずしも生産原価が反映されるわけではない。つまり、いくら生産費が値上がりしても、農産物の小売価格に転嫁できるわけではないという背景がある。
この問題はねぎに限った問題ではない。日本農業法人協会が2022年5月、会員である農業法人向けに行った調査によると、回答者の約96.1パーセントが「コスト高騰に伴う農産物の価格転嫁ができていない」と回答した。農水省では、化学肥料の低減に取り組んだり、堆肥など有機質資源を活用したりする生産者を対象に、肥料代上昇分の一部を補てんするなどの案を打ち出している。板橋社長は「農業界全体がまとまって、消費者に価格転嫁を含め、理解を得られるよう働き掛ける必要があるのではないか」と述べる。
契約産地を支える策の一つとして、日頃からパートナーシップを組んでいる農業資材関連企業と話し合い、生産者から資材や肥料の注文を取りまとめ、ボリュームに応じたディスカウントができないか働き掛けている。すでに関東地域の農家には割引が適用されているという。板橋社長はもともと、契約産地を拡大する際、生産現場に明るい種苗メーカーや肥料メーカーと共に産地を訪ねて、生産者に契約を持ち掛けた。生産現場に詳しい企業と、販売先という「出口」を持つ同社がタッグを組み、産地を拡大してきたわけだ。
ただ、「こうした努力が抜本的な解決策になっているとは言い難い」と板橋社長は話す。同社が契約産地から買い取る価格は、卸売市場の相場が基準となっている。相場は需給関係により決まるものであり、必ずしも生産原価が反映されるわけではない。つまり、いくら生産費が値上がりしても、農産物の小売価格に転嫁できるわけではないという背景がある。
この問題はねぎに限った問題ではない。日本農業法人協会が2022年5月、会員である農業法人向けに行った調査によると、回答者の約96.1パーセントが「コスト高騰に伴う農産物の価格転嫁ができていない」と回答した。農水省では、化学肥料の低減に取り組んだり、堆肥など有機質資源を活用したりする生産者を対象に、肥料代上昇分の一部を補てんするなどの案を打ち出している。板橋社長は「農業界全体がまとまって、消費者に価格転嫁を含め、理解を得られるよう働き掛ける必要があるのではないか」と述べる。
8 白ねぎのシェア10%をめざす
コスト増加は同社にも新たな動きを加速させるきっかけとなった。一つが、物流の効率化である。同社の物流拠点は、本社がある埼玉県深谷市、宮城県仙台市、福岡県八女市の全3カ所にある(写真3)。近年、九州で白ねぎの生産を拡大する産地が増えており、同社も調達力を強化しようとしており、調達量の拡大に備えるべく、物流施設を増設した。また、輸入果物の加工・流通を全国規模で手掛ける企業とも連携し、同社のねぎを混載してもらう契約も取り交わした。白ねぎの需要は安定的に伸びており、同社も契約産地をさらに拡大する戦略を持っている。産地が広がっていく中で、産地と実需者をつなぐ効率的なフードチェーンを構築できるか。これが同社の最大の課題だという。10年後を見据えて、自社内で物流会社を設立する計画を立てている。こうしたインフラ整備により、国内で生産される白ねぎの10%のシェアを持つことが同社の長期目標だ。

このほど、川下分野における新規ビジネスにも着手した。白ねぎの機能性成分に着目した新商品の開発である。東京農工大学と連携し、白ねぎに含まれる有効成分の研究を数年間にわたって行ってきた。その結果、2022年9月、白ねぎに肌やひざ関節に多く含まれるヒアルロン酸の量を増やす成分が含まれることを明らかにし、この研究結果に関する特許を出願中だという。機能性食品をはじめ、食品分野以外での活用でも検討していくという。

このほど、川下分野における新規ビジネスにも着手した。白ねぎの機能性成分に着目した新商品の開発である。東京農工大学と連携し、白ねぎに含まれる有効成分の研究を数年間にわたって行ってきた。その結果、2022年9月、白ねぎに肌やひざ関節に多く含まれるヒアルロン酸の量を増やす成分が含まれることを明らかにし、この研究結果に関する特許を出願中だという。機能性食品をはじめ、食品分野以外での活用でも検討していくという。
9 継続的な事業のために
TFYでは、SDGsの観点から6次産業化にも取り組んでいる。出荷・調整の段階で除去される大量の葉の部分や、出荷に向かないねぎをパウダー状にした各種スパイスの商品化に着手した。板橋社長は「食べられるのに捨てられていた部分を活用するという点で、SDGsにマッチしている。大豊作の時など、あらゆる企業努力をしてもさばけない時の対応策にもなる」と期待する。現在ブームとなっているキャンプ用などに、ポケットに入れられるような持ち運び可能な調味料として販売することを踏まえ、商品名は「POKENEGI(ポケねぎ)」とした。また、介護食としての商品化なども検討し、販路開拓を行っていくという。
若手生産者を含む契約産地との関係構築により、産地を育成しながら白ねぎの取扱量を拡大してきたTFY。固定価格による買い取りを強みにすることで、いわゆる市場外流通で成長してきた企業だ。一方、物流や決済機能を持つJAとも連携するなど、市場内流通の機能も有効に利用している。コロナ禍での需要変化、さらにはサプライチェーン全体を襲うコスト高騰の波に立ち向かうには、市場外流通、市場内流通を問わず、そのインフラや機能をフル活用することで、事業の継続性を追求していくことになるだろう。同社が実践している農業資材関係者との連携、物流インフラの構築、川下マーケットへの進出などの製販一体の取り組みは、今後の園芸産地にも大いにヒントになるだろう。
参考文献
公益社団法人日本農業法人協会「農業におけるコスト高騰緊急アンケート」(2022年5月)
一般社団法人全国農業会議所「農業分野における特定技能外国人受入れ優良事例集 令和3年度版」(2022年3月)
若手生産者を含む契約産地との関係構築により、産地を育成しながら白ねぎの取扱量を拡大してきたTFY。固定価格による買い取りを強みにすることで、いわゆる市場外流通で成長してきた企業だ。一方、物流や決済機能を持つJAとも連携するなど、市場内流通の機能も有効に利用している。コロナ禍での需要変化、さらにはサプライチェーン全体を襲うコスト高騰の波に立ち向かうには、市場外流通、市場内流通を問わず、そのインフラや機能をフル活用することで、事業の継続性を追求していくことになるだろう。同社が実践している農業資材関係者との連携、物流インフラの構築、川下マーケットへの進出などの製販一体の取り組みは、今後の園芸産地にも大いにヒントになるだろう。
参考文献
公益社団法人日本農業法人協会「農業におけるコスト高騰緊急アンケート」(2022年5月)
一般社団法人全国農業会議所「農業分野における特定技能外国人受入れ優良事例集 令和3年度版」(2022年3月)