 調査・報告 学術調査(野菜情報 2017年7月号)
調査・報告 学術調査(野菜情報 2017年7月号)
新規就農タイプ別の経営確立支援方策と地域社会受容条件の解明
東北大学大学院 農学研究科 教授 盛田 清秀
【要約】
新規就農者および農業法人雇用による新規農業従事者について、香川県の2事例、石川県の1事例、静岡県の2事例、ならびに関係機関・指導農家の調査を通して次のことが明らかとなった。①国や県の経営確立支援方策は、青年就農給付金をはじめとする資金・金融支援において極めて有効に機能しており、また技術習得に関する相談・支援対策も有効に機能している。しかし、農地の確保については地域の信頼確保が重要であり支援策が十分に機能を発揮している例は多くない。②地域への受容条件としては、農業法人による社員教育を通じた地域社会との円滑な関係構築支援が有効であること、就農者本人に加えて家族の生活基盤の充実、不安解消が重要な要因であることが示唆された。
1 研究の背景と位置付け
近年の野菜に対する消費者ニーズは、新鮮でおいしい副菜の素材、食卓の彩り、ビタミン・ミネラル補給源としての役割に加え、健康志向の強まりとともに野菜の有する健康増進・維持機能にも関心が高まりつつある。このため全体として野菜需要は漸減しているものの、将来的にも底堅い需要が予想され、国民の食生活面で野菜の果たす役割は大きい。しかし、生産者の高齢化とともに生産減少が続き、若い担い手の確保が喫緊の課題である。今後は、既存農家の後継者確保が重要であるとともに、農外からの新規就農者の確保・育成を図る必要がある。
実際に新規就農者が農業を始める場合、初期投資が比較的少なくてすむ野菜作が多い。新規就農者の営農部門がわかる全国統計は平成19(2007)年公表の農林水産省大臣官房統計部「平成19年新規就農者就業状態調査」が最後であり、この調査によれば露地および施設野菜が主な経営部門である割合は52%となっている。全国統計ではないが、最近の動向に関しては北海道農政部の調査(27(2015)年)がある。これによって北海道の場合をみると、新規就農者の経営形態では野菜作が56%とやはり高い割合である。北海道では比較的広い農地を確保しやすいが、それでも米麦作などに比べてそれほど広い農地を必要としない野菜を選択する経営が圧倒的に多い。農地の確保が北海道よりは難しい都府県の場合、その傾向が一層強いと考えられる。それゆえ、新規就農者の経営定着条件を解明することは、日本農業全体としてはむろんのこと、野菜生産の将来を考えるうえでも重要な意義を有する。
2 新規就農者の動向
新規就農者数に関して、前記の新規就農者調査が平成18(2006)年以降毎年公表されている(表1)。それによれば新規就農者数は18(2006)年に8万1030人であったものが漸減し、25(2013)年には5万810人へと37%も減少する。その後回復傾向に転じ、27(2015)年には6万5030人となっている。この減少から回復への変化の主な要因は、「新規自営農業就農者」(既存農家での就農)の動向で、新規就農者の8割から9割を占めるこのタイプの動きが全体の増減を左右している。

しかし、「新規雇用就農者」(法人などに雇用されて農業を新たに始める者)と非農家出身者による新規就農である「新規参入者」の動向をみると、少し違った傾向が見て取れる。新規雇用就農者数は18(2006)年の6510人を起点に、26(2014)年までは増減を繰り返しながら漸増傾向にあったものが、27(2015)年に1万430人へと急増を示す。また、新規参入者については18(2006)年の2180人から22(2010)年の1730人へと停滞ないし減少傾向で推移していたところ、24(2012)年に3010人へと顕著に増加し、27(2015)年には3570人へとさらに数が増えている。この背景にあるのは、青年就農給付金の支給が24(2012)年度から開始されたことである。この制度は、調査結果でもふれるが、新規参入を大いに促進した政策として高く評価できる。新規参入者の増加はこうした制度的支援によって支えられている。
そのことは、表2の新規雇用就農者と新規参入者の年齢別人数をみるとより明確に理解できる。青年就農給付金の対象者は45歳未満であり、統計ではこの制度が開始された24(2012)年以降でしか当該年齢層の数を把握することができない。そこで、制度開始以前と比較するため、同表の49歳以下の人数で近似的に見ておこう。すると新規参入者については、24(2012)年に前年の1180人から2170人へと一挙に2倍近くなっている。このことから、制度・政策的支援の効果は、新規参入促進に関して極めて大きかったことがわかる。全国的な統計数値を変動させるだけのインパクトを、この政策は有していたのである。

ところで、新規就農者の詳しい属性や営農内容などに関する全国統計は存在しないが、全国農業会議所による710人の新規参入者に関する調査報告書(全国農業会議所『新規就農者の就農実態に関する調査結果―平成25年度―』平成26(2014)年3月)があり、それをもとに新規就農者の特徴を見ておこう。
まず就農前居住地と就農地の関係では、同一都道府県である割合が63.3%、同一ブロック(東北とか九州など)である割合は77.1%となっていて、土地勘のある近隣で就農する傾向がある。就農時年齢は30歳代が45.6%と最も多く、次いで40歳代22.9%、29歳以下19.0%、50歳代7.1%、60歳以上5.4%となっている。配偶者がいる割合は73.2%で、うち配偶者が多少とも農業に従事する割合は76.3%である。一定の社会経験を経て就農するので30歳代、40歳代が多くなることは理解できるし、配偶者がいてともに農業に従事するケースが多いことがわかる。
最終学歴をみると、大学・大学院を合わせると48.9%、短大・専門学校が17.3%で、いわゆる「高学歴」者が多く、これはわれわれが調査した事例でも見られた特徴である。就農理由は、「経営の采配が自由に振れる」45.8%、「農業が好き」37.7%、「やり方次第でもうかる」32.3%、「時間が自由」27.4%など、積極的な動機に基づくものが多く、経営者として自らの創意工夫で利益を確保できること、農業のやりがいや自由度の高さに魅力を感じての参入であることがわかる。家族とともに生計を営めさえすれば、農業は十分に人を引き付ける産業だといえる。
参入にあたって苦労したことは、「農地確保」69.8%、「資金確保」64.3%、「技術習得」55.5%で、農地・資金・技術面の課題、いわゆる「御三家」が群を抜いて高い。これに続くのは、「住宅確保」25.7%、「地域の選択」20.3%などである。これらについては、都道府県、市町村の支援措置を受けており、「農地あっせん」40.8%、「助成金等交付」46.4%、「研修支援」46.2%となっており、地方公共団体の支援が果たす役割は極めて大きい。
以上に関わって、就農1年目に確保した農地面積は、全国平均で160アール、都府県だけでは83アールとなっている。1ヘクタール未満の農地では、経営的視点からいえば、土地生産性が高く収穫まで時間のかからない野菜が中心となることは当然であろう。また、資金面では、平均して営農面で658万円(機械施設500万円+営農158万円)、生活面で227万円、合計で885万円必要という回答である。これに対し、農産物の売上262万円、自己資金227万円なので、差引396万円の資金が不足する。これを補うことが必要となり、青年就農給付金、制度資金の融資による補てん、資金調達が絶対的に必要となる。
農産物の販売先では、農協が58.2%、消費者への直接販売45.1%、小売業30.5%、飲食店21.0%などとなっており、複数ルートでの販売が追求されている。また、ごく一部で加工、観光農業、レストランなどの取り組みもあるが、6次産業化を展開するだけの資金的、労力的な余裕はないというのが実態であろう。
直面する課題として、低所得59.6%、技術力の低さ47.6%、設備投資資金不足34.5%、運転資金不足26.7%、労働力不足22.9%などであり、経営財務面での課題がもっとも大きい。またそれとも関わって、生活面での課題として「休暇がとれない」43.5%、「健康不安・重労働」36.9%、「生活の不便(交通・医療等)」19.0%、「集落との人間関係」18.6%、「地域の友人がいない」16.7%、「集落の慣行」15.0%などとなっており、思ったほど自由な時間の裁量がないこと、労働のきつさ、地域との関係などに悩むケースがあることが見て取れる。今後の課題として第1に挙げることは、規模拡大25.7%、技術向上21.4%、販路拡大11.8%などで、いずれも収益性の改善、所得拡大を経営目標としていることがわかる。
以上が、全国農業会議所・全国新規就農センター(2014)の調査による新規就農者の現状と課題の概況である。それではわれわれの調査した事例ではどのような状況となっているのであろうか。以下それを報告する。
3 調査結果
(1)香川県の事例
香川県高松市の株式会社荒川農園(以下「荒川農園」という)は、代表者荒川鉱章氏(44歳)自らが新規参入者である上に、雇用就農の受け皿としての役割を果たす法人である。平成25(2013)年の年間販売額は8826万円、農業所得は1673万円である(表3に香川県と石川県での調査経営の概要を示す)。法人化したのは26(2014)年で、荒川氏は新規就農前の10年間にわたる他農業法人での勤務を経験し、技術に熟練し、経営のノウハウを学び、一定の資金蓄積も果たしての就農であった。その意味で、支援機関による支援にあまり依存しないで独自に道を切り開いてきた事例である。常勤従業員は12名、その内訳は社員が3名、通年雇用のパート5人、外国人研修生4人であり、経営面積9.2ヘクタール(28(2016)年)においてブロッコリーを中心に、ねぎ、レタスを組み合わせた露地野菜作経営を営んでいる。

荒川氏は他県の出身ということもあり、とくに地域とのつながりを大切に考えてきている。販売はJAに任せ、生産に集中して品質確保と高収量を追求している。とはいえ当初は農地の確保に苦労し、地域との信頼関係ができるまで農地拡大は難しかったという。しかし、地元住民(農業者)雇用を通じて共感をはぐくみ、それを通して農地確保が進展していき、現在は地域の農地の2割を耕作するまでになった。おそらく、農地の場合はこのような信頼関係がなくては、たとえ各種の事業、たとえば近年の農地中間管理事業などを通しても農地拡大はスムースに進まないと思われる。技術も資金も重要なのであるが、それらは「関係性」、すなわち人と人との信頼関係を抜きにしても獲得は可能であろうが、農地はそうはいかない。そのことを就農希望者だけでなく関係者もきちんと理解しておくべきである。
また、香川県観音寺市の株式会社中大(代表者は大西規夫氏(45歳)、以下「中大」という)も、社員教育を重視し、農業における個々の作業の意味の理解が重要であることを強調している。この事例も荒川農園同様、人材育成を極めて重視する。その結果でもあり、前提でもあるが、高い経営収益と雇用者の給与水準を実現している。中大は28(2016)年の経営面積は19ヘクタールで、レタスを中心にねぎ、ブロッコリー、たまねぎなどの露地野菜作を基幹に、省力的な水稲作を組み合わせた経営を行っている(写真1)。前年の農産物販売額は約2億円に達している。常勤の従業員は16人で、うち外国人研修生は7人である。中大も販売はほぼすべてをJAに依存しており、生産に特化した経営戦略である。
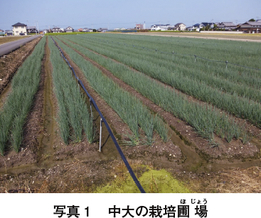
雇用を通じた就農においては、まず農業の特性を十分に理解することが重要と思われる。つまり農業技術の特徴の理解である。現在、技術のマニュアル化、「見える化」、ICT技術導入が進められており、誰でも農産物生産ができるようにするための技術開発やシステム化が進められている。これは今後も一定の発展が期待できるであろう。
しかし、米作りのような比較的マニュアル化が容易な作物がある一方で、そうではない作目、作物、品目も多い。これらは、生産工程の段階ごとに作業者の判断が求められる。気象や農地の質も異なることは、それに輪をかけて複雑性を増大させる。それゆえ、OJT教育は農業において極めて重要で、かつ思考しながらの作業、意味を理解しながらの作業を要請する。そうした人材育成を目指し、実現するためにはどうすればよいのか、この2つの事例はまさに優れた取り組みを実践し、参考とすべきモデルである。特に中大の従業員への手厚い処遇(部門責任者への他産業を上回る賃金支給)は、農業における人材確保、地域に受け入れられる人材育成という、農業産業化の重要な条件を示すものであろう。
(2)石川県の事例
石川県白山市の株式会社六星(代表者は軽部英俊氏(49歳)、以下「六星」という)の現在の主力部門は、もちを中心とした加工、ならびに金沢駅構内を含む3店舗を擁する販売部門に移ってきている(写真2)。いわゆる6次産業化で全国的に見てもトップを走る最先進事例である。平成27(2015)年度の総売上高は11億2862万円、役員を含めた常勤職員数は41人である。六星の現社長は先代社長の娘婿であり、水稲栽培に関しては昭和54(1979)年以来の前史がある。現法人は平成19(2007)年に設立、同時に軽部氏が社長に就任している。しかし経営農地面積が151ヘクタール(24(2012)年)にも達することに見られるように、加工原料の自社生産という重要な役割を果たしている農業部門は、六星にとって単なるルーツ以上の意味を持っている。農業部門を有しているからこそ、六星の強みである地域の農業に根差し(「六星は農家であり、会社です」)、食文化を担い、地域とともに歩む(「地元の土地で育った農産物、土地に根付いた食文化にこだわる」)というコンセプトが、地元の消費者、取引先に認知されるのである。

また、六星の農業部門は、土地利用型農業の水稲作が主幹である。このことは地域との関わりを特に重要なものとする。農地という農家にとって最も重要な財産を預かるのであるから、農地管理に手抜きはできないし、地主や地域社会との信頼関係を傷つけるわけにはいかない。農地貸借を媒介とした地域社会のネットワークに一定程度は組み込まれざるをえないし、その中で期待される行動と役割を果たしていかなければならない。そもそも、地域社会や農家との信頼関係なしに、土地利用型農業の規模拡大は不可能である。一般の会社なら友人はいなくても大丈夫だが、農業はそうはいかない、友人作りが必要だという代表者の言葉が端的にそのことを言い表している。なお、この六星においても、加工や販売部門のウエイトが高まるにつれて、店舗での品揃えや加工施設の稼働率確保などの理由から、野菜生産の重要性が増しつつある。
一方、社員インタビューにおいて、地域との適度な距離感の大切さについて聞くことができた。いままでそういう捉え方に接したことがなかったので、目から鱗の落ちる思いであった。共同体的で濃密な旧来の社会関係とは異なる、またビジネスのみの関係性とも異なる、新たな社会関係の構築が現場で進行中なのかもしれない。「農家」、自営農業者として地域に活動・存在する主体に加えて、農業法人に勤務する社員という新たなタイプの農村社会のプレーヤーとは一体どういう存在なのであり、農村社会とどのような関係を構築していく存在なのであろうか。その独特の「距離感」の実体を明らかにしていくことが新たな課題となっている。
(3)静岡県の事例―伊豆の国農業協同組合における取り組み―
静岡県の事例は、県の多様な新規就農支援事業の効果を示すとともに、高所得を上げうる営農モデルを提示し、それを確実に実現できる栽培技術指導体制と販売体制を構築することが成功要因であることを示している。
また、そうした実績ゆえに、同県伊豆の国市には技術指導を受け入れ、自分のものにできる就農候補者が集まってきている。調査した2人の新規参入者についてみれば、ともに1年間の研修期間を経てミニトマトの施設栽培専業経営に従事している(表4に経営概要を示す)。42歳のNY氏は平成24(2012)年に就農し、本人と5名のパートで26アールの施設から農業所得720万円を上げている。また33歳のKN氏は27(2015)年に就農し、17.55アールで就農初年目にして800万円の農業所得を実現している。労働力は夫婦に加え、2名のパートを雇用している。

この2名はともに農学・生物学系の博士号をもつ「高学歴者」であるが、新規就農開始時の不安は、事前の技術指導体制とそれまでの新規就農者の経営成果を実際に確認して解消できたようである。また、高額の設備投資の資金を調達するための国や農協などの支援措置、生活費と営農運転資金を支援する青年就農給付金がそうした取り組みを下支えし、就農支援を実効性あるものにしている。さらに、本人以上に家族(配偶者)が所得、生活面で不安を抱えていたようであるが、事前の説明や見学、既存の新規参入者の営農、生活実態を知ることで不安が和らげられたことも新規就農を決意させる重要な要素であったようである。
伊豆の国市における事例は、特に研修受入れ農家の力量に負うところが大きい。指導農家の資質、その経営管理・技術体系の合理性と早期かつ確実な習得をいかに達成するかが極めて重要であることを示している。それによってはじめて、就農初期に「生活できる」所得が確保できている。とはいえ、この伊豆の国市のように、生産者としての実績を持ち、新規就農者の営農モデルを構築して科学的な管理について指導できるような「カリスマ」指導者がどこでも確保できるわけではない。そういう場合、それに代わる体系的な指導システムと情報提供の仕組みをどのように構築するかが問われよう。
4 新規就農タイプ別の経営確立支援方策と地域社会受容条件の解明
(1)経営確立支援方策についての評価
国や県、関係機関の支援策は、新規就農者定着に大きな効果を上げていることを確認できた。国の青年就農給付金は、効果の大きさからいえばその筆頭にある。これは初期の資金上の困難を克服するうえで、格段の成果を上げている。給付対象者の評価もそれを裏付ける。また、青年等就農資金も初期の設備投資のための資金を調達するうえで格別の効果を有している。これがなければ、設備投資が多額に及ぶ施設園芸などの部門への新規就農は不可能といってもよい。この両者に加え、県や市町村、農協が重層的に資金準備に対する手当てを行っていることも効果的である。これらの措置によって、資金問題は大いに軽減され、クリアする条件は整っていると評価できる。あとは、経営収益がどれだけ確保できるか、作目・作物・品目選択が的確かどうか、販売見通しが確実かどうかが重要である。
また、全国の就農相談窓口に加え、県レベルで実施されている就農相談窓口、就農支援研修制度は、技術習得面で十分な体制が組まれていることが確認できた。入門編から基礎的知識の獲得、実地での技術研修、経営シミュレーションとしての「模擬経営」の運営など、体系的な技術および経営知識の習得システムが構築されている。今回調査した県ではいずれも技術習得支援は高いレベルで実施されていた。加えて、それを新規就農者が身につけることができる指導者・指導農家が実際に指導に当たっているかどうかが決め手となる。いかにシステムが形式的に整っていても、高い技術をもち、指導技術・教育技術をもった指導者がいなければ、決して技術習得において十分な成果は上げえない。技術の重みは十分に関係者の間で共通理解をもつべきである。農業生産を同じように行った場合でも、高品質なもの、一定の品質基準を満たすものをより多く収穫できれば、その場合の利益の大きさは格別なものとなる。技術習得の成功は、新規就農の成功の大きなカギである。
最後に、農地の確保であるが、これはなかなか難しく、決め手のない要素である。施設園芸の場合も農地が必要であるとはいえ、比較的それをクリアすることは難しくない。しかし、広い面積を確保しなければならない土地利用型農業の場合(もしくは露地野菜作のようにそれに準ずる経営面積が必要な場合)、問題のフェーズが全く異なる。その場合どうするのか。農地の確保では、まだまだ取り組みが十分なレベルに到達したとはいえない。
以上から、新規就農に関する現在の支援体制に関して言えば、資金確保、技術習得については相当程度支援策が整備されてきたといえる。農地への手当をどう進めるかが現時点で最も重要な要素であると結論付けたい。
なお、法人への就職による新規就農については、体系的に支援策が整備されているとは言えない。法人経営それ自体に対する支援メニューは準備されているが、農業法人への入職者に対して特段の支援があるわけではない。これは、研修支援を主旨とする農の雇用事業を考慮に入れても同様である。農業法人への入職者(「新規雇用就農者」)に対し、給与の上乗せといった方法は難しいであろうが、住宅支援や就学支援などの生活支援策、もしくは家族を支援する何らかの方策をメニューに加えることを考えてもよいのではないか。
(2)地域社会受容条件
土地利用型農業経営(ここでは露地野菜作経営を含めて考える)においては、つまるところ、地域社会、既存農家との信頼関係に帰着する。というのは、このタイプの経営では、ある程度の農地面積が確保されていないと経営そのものが成り立たない。経営が成り立たないところに新規就農の定着などあるはずもない。しかし、信頼関係の構築には時間がかかる。むしろ一定の時間を共に過ごすことが必要条件である。それゆえ、土地利用型農業においては、六星のケースでみたように、「法人での就業を通じた地域への溶け込み」が有効な方法の一つと考えられる。また香川県の荒川農園のケースのように、「妻の実家」、「義父」というのもキーワードの一つかもしれない。
地域社会の受容という場合、新規就農者本人よりも、むしろ家族の問題が大きいこと、家族員(パートナーや子供)の就学、近所づきあい、友人関係、医療環境といった生活、教育、健康などに不安を感じ、その解決が重要であることが調査を通して示唆された。今回は家族員への調査を行っていないが、「そこに住み生活する」という意味で、職業空間以上に重要とも言える「生活空間」のあり方、そこでの家族の満足度、幸せといった要素が決定的なものであるような印象を受けた。農業という職業活動を通じた地域社会への受容のあり方に加え、生活すること(通学する、消費行動をする、文化・学習活動をする、健康を維持するなど)を通じた地域社会への受容のあり方、という両面で考えていくことが新規就農問題を考えていくうえで重要ではないか。
(3)調査を通じて得られた新たな知見のうちの特記事項
営農面では、生産への集中ということの重要性である。もちろん6次産業化などの経営複合化・多角化を否定しているのではない。そうではなくて、新規就農の場合、資金、技術、人材、農地、情報のいずれをとっても基盤が十分な状況にはない。それをベースに考えると、まずは生産に集中し、「よいものをできるだけ多く取る」ことが経営成功のカギではないか。それができれば収益は大きく改善される。生産にまずは集中すべきではないかというのが、今回確認できた知見の一つである。
生活面では、前項で書いたように、新規就農者の地域社会への受容というよりは、家族の、しかも生活の視点に立った地域社会の受容をどのように促進するか、円滑に進めるか、不安を解消するにはどうしたらよいか、という問題、課題の解決が重要といえる。