 調査報告(専門調査)
調査報告(専門調査)
農業後継者をいかに確保するか
~静岡県内における新規就農支援策~
農業ジャーナリスト
青山 浩子
農家人口が減少している中、若手を中心とする新規就農者を増やしたいという思いはいずれの産地も共通だ。折しも不況により失業率は高まっており、農業は雇用の受け皿としても注目されている。
野菜産地、静岡県では、全国に先駆けて新規就農支援に力を入れてきた。伊豆の国農業協同組合管内では、就農の研修を受けた若者のほぼ100パーセントが新規就農者として定着している。また、浜松市の農家が出資して設立した株式会社ゆめ市では、新規就農者が定着できるよう独自の工夫を凝らしている。
本稿では、この両者の取り組みを通じ、いかにして新規就農者を確保し、増やしているのかについて探った。
◆1.研修生の大半が就農
伊豆の国農業協同組合(以下、「JA伊豆の国」と記載)は、伊豆半島の北部から中部に位置し、温暖な気候を利用して管内では、いちご、トマト、ミニトマト、きゅうりなどの野菜のほか、しいたけ、わさび、花卉、柑橘類と多種多様な農産物が生産されている。
そのJA伊豆の国管内在住でミニトマト生産農家の中村克彦さん(47)は、2004年に脱サラして新規に就農した生産者の一人である。「若い頃から農業をやりたかった」という中村さんは、15年勤めた会社を辞め、JA伊豆の国が県などと連携して新規就農を支援する制度を活用し、03年11月から2年近く、受け入れ先のミニトマト農家のもとで研修を受け、独立した。
現在は、4人のパートを雇い、夫人とともに30アールのハウスでミニトマトづくりに精を出す。ハウスは、同じように新規就農者ばかりでつくるミニトマトの団地の一角にあり、ほかの新規就農者と頻繁に情報交換もできる環境にある。
また、同JA管内でトマト、ミニトマト、きゅうりを生産する農家でつくる果菜委員会は、現在36戸の農家で構成されている。このうち21戸が中村さんのような新規就農者である。新規就農で、ミニトマトを生産している農家の平均的な経営規模は20~30アールで、中には、年間2000~3000万円の売上げを確保している農家もいる。
同委員会の販売額は、2000年度の2.2億円から09年度には5.4億円へと大幅にアップした。増加分のうち、およそ2.3億円は新規就農者によるものだ。販売高の伸びに新規就農者が大きく貢献しているというケースは全国でも珍しいだろう。
同JA管内では、ミニトマト以外にもいちご(4人)、バラ(2人)、ワサビ(2人)、トマト(1人)を合わせた25人が就農している。年齢構成は30~50代。すべて県の制度や、伊豆の国市独自の「伊豆の国市新規就農者受入支援対策事業」を活用して研修を受け、就農した人たちだ。
「自分の思う通りの農業がやりたい」と研修半ばにリタイアした1人、JAに就職した1人を除き、研修生のすべてが研修を受けた地域に定着している。09年末には現在研修中の人が就農し、トータルで32人になる予定だ。
この定着率の高さは偶然によるものではない。その背景には、
① 行政やJAなどの関係機関や受け入れ農家が、研修時から独立後までトータルで支援している
② 研修希望者をシビアに面接し、選考している
などの要因がある。


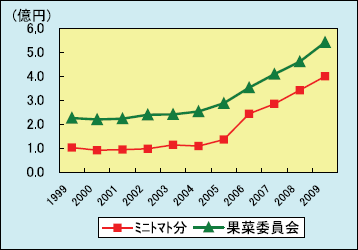
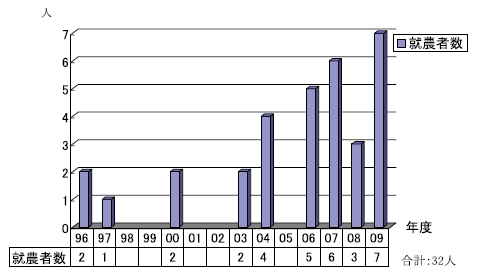


◆2.定着率向上を目指し制度を改善
静岡県が、新規就農者への支援制度「ニューファーマー養成制度」を立ち上げたのは1993年。今では静岡県以外の県でも同様の制度を実施しているが、同制度は、県内外の他産業に就いている若者が静岡県内で就農を希望する場合、研修農家の斡旋や経費の一部負担、独立後の資金融資などを行うというものだ。同県は全国に先駆けてこの制度を実施してきた。
しかし、2002年頃までの就農者の定着率はそれほど高くはなかった。静岡県産業部農業振興室の勝地孝則主査によると「特に県外からやってきた研修生は、地元に知り合いもおらず、農地の確保に苦労していた。このため、独立したとしても師匠である研修先農家から離れた場所で就農することも多かった。病虫害が発生して困った時も適切なアドバイスを受けられず、収量が上がらないため収益を確保できず、結果的に挫折していくケースもあった」という。今のように農業が注目されておらず、研修生の人数自体も少なかったが、定着率が50パーセント以下という年もあった。
定着率を上げるため、同県は04年から制度の改善に乗り出した。就農に際して最大のネックだった農地の確保は、研修受け入れ農家が仲介役となって地主やJAと折衝をすることになった。さらに独立した後も、引き続きサポートができるように、受け入れ農家の近くで就農させることにした。
受け入れ農家の責任は重くなったが、農地の確保や就農までの流れはこの時からスムーズになった。また、就農を決心してから早く所得を上げられるように、研修期間を2年から1年に短縮。制度の名称も2004年度から「ニューファーマー養成制度」から「がんばる新農業人支援事業」へと変わった。
制度が始まってから、研修を最後まで終えた人は88名。このうち自ら土地を確保して就農した人が62名、法人などに就職した人が15名。計77名が就農した。04年の制度改善後は、中途でリタイアする者はほとんどなくなり、県全体でも定着率は大幅に高まった。
◆3.欠かせない受け入れ農家の協力
JA伊豆の国が、東部農林事務所などの県の関連機関、伊豆の国市、伊豆市の両市などと「ニューファーマー養成制度」を活用し、研修生の受け入れを始めたのは96年から。しかし県内のほかの地域同様、農地の確保がネックになっていた。
この状況をなんとかしようと、関係機関が集まって「ニューファーマー地域連絡会」を立ち上げた。2002年のことだ。
連絡会の発足を提案したのは、中村さんを研修生として受け入れたミニトマト生産農家の鈴木幸雄さん(65)だった。鈴木さんは、JAの理事、農業委員、県のリーダー的農家が認定される農業経営士を歴任する過程で、地域を守るためには、後継者の育成が重要であると考え、96年からは自らが研修生受け入れ農家となった。
鈴木さんは、新規就農希望者が、研修後の農地の確保で苦心している現状を知り、同JAや伊豆の国市、東部農林事務所などに働きかけ連絡会を立ち上げた。連絡会ができてからは、研修生および新規就農者が現実に抱えているさまざまな問題点を聞き出し、それぞれの立場で提案やアドバイスを与えながら、一緒に解決策を探っていくようになった。現在も年に1、2回開催されている。
このような支援体制の中でもっとも重要な役割を果たしているのが、鈴木さんをはじめとする受け入れ農家だ。鈴木さんは、これまで20人近くの研修生を受け入れ、独立させてきた。県内には、鈴木さんのほか6名の受け入れ農家がいる。
中村さんによると、「鈴木さんは自分の決算書類も見せてくれるなど情報を公開してくれ、研修生の立場からすると、不安で先の見えない将来に明確な目標を立てることができた」と話す。
栽培技術のみならず、雇用者との接し方や地域との関わりについても助言してくれた。中村さんは、企業で15年勤めた経験があったが、「農業を営むことは経営者になること。組織の構成員として働くのでは事情がちがう」と教わった。鈴木さんは「パートさんを育てるのは息の長い仕事。作業能率だけ見てパートをコロコロ変えるようではダメ。とはいえ雇用者と被雇用者の関係だということも理解してもらう必要がある」と助言し、中村さんは「これが独立後に非常に役立った」と振り返る。勝地主査も「定着率が上がったのは、受け入れ農家の尽力によるところが大きい」と話す。
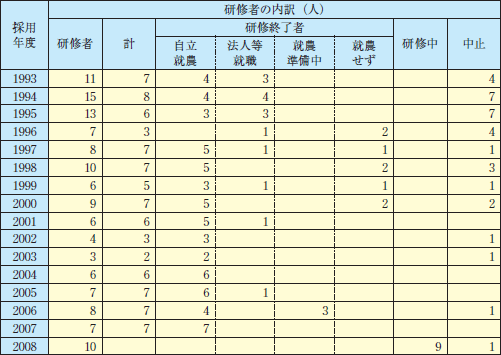
「がんばる新農業人支援事業」による就農者の内訳(1993年度~2009年7月)
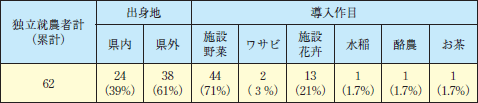
資料:静岡県農林業局農業振興室作成資料をもとに作成
表3
JA伊豆の国管内における新規就農者に対する支援策
① 就農計画作成支援
② 就農支援資金計画支援と県との対応
③ 栽培農地の確保・斡旋
④ 農地保有合理化事業による借地契約の締結
⑤ 労働力確保のための無料職業紹介所による農作業パート者の紹介
⑥ 営農指導および経営指導
⑦ 出荷資材の供給
⑧ 出荷物の販売
⑨ 「ニューファーマー地域連絡会」(※)の開催
⑩ 「伊豆の国市新規就農者受入支援対策事業」(がんばる農業人支援事業の枠にもれたが、就農意欲があると認められた人をこの事業で支援)〔伊豆の国市単独の事業〕
※「ニューファーマー地域連絡会」の構成
○ ニューファーマー(研修中も含む)
○ 受け入れ農家
○ 県農業振興室
○ 県青年農業者等育成センター
○ 東部農林事務所
○ 伊豆の国市、伊豆市
○ JA伊豆の国(常務理事、営農事業部)
資料:JA伊豆の国の資料から作成
◆4.応募者に対する厳格な選考
一方、研修募集者を厳格に選考していることも、高い定着率につながっているようだ。
県が「ニューファーマー養成制度」をスタートさせた頃、作物の選定は研修生自身が県などと相談した上で決めていた。しかし今では、研修生を募集する地区と作物をセットで提示している。地区が決まれば、必然的に作物も決まることになる。
JA伊豆の国の場合、ミニトマト、いちごに限定して募集している。同JAの営農事業部の渡辺良修部長によると、「就農して確実に利益を上げられるかどうかが、最重要課題。儲かる作物を作ってもらう、という明確な方針を打ち出している」という。
同JAでは、ミニトマトの場合、10アール当たりの平均売上げを約850万円、所得率を30~40パーセントと試算している。一家族が農業で生計を立てるには、最低でも500万円の所得が必要と考え、ミニトマトであれば経営規模20~30アールというモデルをつくり上げている。
これらのモデルを就農希望者にも提示し、承知した上で研修、就農とステップを踏んでもらう。「実際にやってみたが、こんなに儲からないとは思わなかった」というギャップが生じないようにするための措置だ。
一方、募集する人材も選考の段階から絞り込む。渡辺部長は「人とお金をシビアに判断する」と話す。本人の意欲はいうまでもないが、奥さんも一緒に農業をするつもりかどうかを聞く。単に農業がブームだからと軽い気持ちでやってくる人は最初から選抜しない。施設でミニトマトの生産を始める場合、10アール当たり1,000万円ほどの初期投資が必要となる。これらの施設整備には、就農支援資金を活用できるが、当座の運転資金は別途必要だ。このため就農希望者には「1,000万円ほどの貯蓄があるか」を聞き、蓄えが少ない場合は「資金を貯めてから再度考えてはどうか」という提案もする。受け入れ農家、作物、家族の理解、初期投資資金および当面の生活費の有無と、ここまで徹底的に絞り込めば、就農希望者も受入側も「こんなはずではなかった」という事態は避けられる。
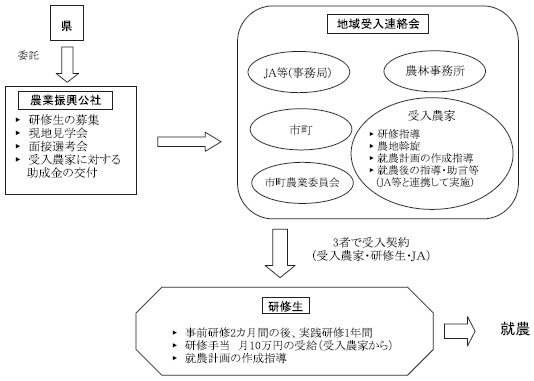
◆5.地域活性化にも貢献
研修希望者の募集は毎年5月~7月末に行い、就農したい地域や作物の希望を出してもらった上で、8月に現地視察を実施、最終的には9月の面接で合否を決める。その後、2カ月間の事前研修を経て、1年間の研修に入る。
渡辺部長によると、やる気のある人は、8月の現地視察の後、受け入れ農家と頻繁に連絡を取りあい、面接に備えるという。受け入れ農家も、積極的な希望者には惜しまずにアドバイスする。これらは募集要項には書かれておらず、あくまで希望者が任意で行うことだ。しかし、何もアプローチしない希望者に比べれば意欲があることはアピールできる。受け入れ農家によっては、学歴や職歴を重要視する人もいる。
静岡県は大消費地からも近く、就農希望者が多いからこそ、こういう選抜方法が可能なのかもしれない。研修希望者の定員確保に苦労する過疎地では別の方法が求められるだろう。
中村さんを含め、ミニトマトの新規就農者は、収穫したミニトマトの全量をJAに出荷する。これはJAの販売事業に大きく貢献している。JAに出荷することについて中村さんは、「新規就農者は、生産技術が未熟であることから収量も安定せず、販売に時間と手間を割く余裕がないので、生産に専念するためにJAに出荷した方がよいのではないか」という。
同JAの農産物全体の販売高は、2000年度が約43億円で、08年度もほぼ同じである。面積や農家数の減少があったにも関わらず、販売高は落ちていない。渡辺部長は、「新規就農者たちの貢献度は高い」という。新規就農者が2000~3000万円の売上げを上げていることを知って、既存の農家も「自分たちも負けてはいられない」と規模拡大への意欲を見せるなど、新規就農者が地域全体にも刺激を与えている。
もっともこの数字は、ミニトマトの市況がいいことにも支えられている。同JA管内ではミニトマトの市況はここ7、8年、順調に推移しているという。
だが需要が減ったり、相場が下がったりすると、たちまち就農者の経営も不安定になり、JAの販売高、求心力も下がることもあり得る。つまり、新規就農者に引き続きJAに全量出荷してもらうには、JAが販売力を維持するかアップさせるしかない。このことから、新規就農者への支援は農産物の販売と連動させ考えていく必要があるといえる。

東部農林事務所の出雲主幹(中)、就農した中村さん(左)
◆6.研修生の後見人としてのサポーター
販売と結びつけて雇用を考えている法人がすでに同県内にある。
浜松市内の認定農業者18人(法人を含む)が出資して設立した株式会社ゆめ市(森島恵介社長 以下、「ゆめ市」と記載)は、就農希望者を受け入れると同時に、09年から彼らと研修受け入れ農家の間を結ぶ「サポーター」をつけることにした。研修生と受け入れ農家の考えが同じであれば問題はないが、ひとたび意見が対立すると折り合いがつかず、研修生がリタイアするというケースが起こりやすい。
ゆめ市の徳井厚夫専務は、ゆめ市設立前の自らの苦い経験を踏まえ、「研修生と受け入れ農家の間にサポーターに入ってもらうことで、行き違いをなくそうと思った」と話す。
ゆめ市が発足したのは2007年。農産物価格の低迷が続く中、「低収益構造から抜け出すには、農家自ら生産から販売まで関わるしかない」(徳井専務)と、認定農業者による横断的組織「ゆめ市会」を発足するとともに、ゆめ市会のメンバーの作る農産物を販売するための株式会社ゆめ市を立ちあげた。
ゆめ市会のメンバーは、作物も規模もさまざまだが、「地産地消を推進したい」という共通の思いを持っていた。地元の農産物に関心の高い実需者を当たったところ、学校や企業、病院、量販店などでニーズがあることが分かった。
浜松市には、自動車メーカーのスズキ株式会社(以下、「スズキ」と記載)の本社がある。同社は、知的・精神障害者を雇用しているが、より働きやすい就労場所を障害者に提供できないものか模索していた。そこでゆめ市が名乗りをあげ、「農作業をやってもらったらどうか」と提案。障害者は農作業に当たる。そしてできあがった農産物をスズキの社員食堂などに供給することにした。障害者は収入を得られ、ゆめ市は地産地消を拡大させられる。スズキにとっても社会貢献につながる。スズキ以外にも学校や病院にも働きかけ、両者がメリットを感じられる仕組みづくりから取りかかった。
現在、新聞配達店と組んで野菜の宅配事業を始めるほか、車がなく郊外の商店に行けない高齢者のために、街中の商店街を利用して臨時の青果店を開くなど農と食を結ぶ「ゆめはまネットワーク」を構築中だ。
◆7.生産と流通の両面から助言
地域のみんながつながる「ゆめはまネットワーク」の仕組みづくりの一方で、生産体制づくりにも着手した。気候が温暖な浜松市では露地栽培で大半の農産物をつくることができるが、給食に使われる野菜のすべてを作っているわけではない。浜松市内の学校給食で使われる青果物のうち、地元産の利用率はおよそ20パーセントだという。ゆめ市では、これを70パーセントまで上げることを目標にした。
しかし、既存の農家だけでは生産量を賄えないため、新たに取り組む農家を育成することにした。徳井専務は、自らが社団法人静岡県農業振興基金協会の事業(1人当たり30万円の研修費用を助成)を活用しながら、新規就農予定者として2人の研修生を受け入れていたが、研修終了後に、1人は家族の都合で実家の家業を継ぐことになり、もう1人は「自分は別の農業を目指したい」と言いだし、徳井専務と折り合いがつかず、浜松市内での就農には至らなかった。
徳井専務が求めていた人材は、地産地消を拡大するために求められる作物を作ってくれる“即戦力”だった。ところが研修生は「荒れ地を耕すところから始めたい」と言い出した。面接の段階でも本人の希望は聞いていたのだが、その時点では当人も「ゼロから始めたい」という意志は固まっておらず、徳井専務も見抜けなかった。
このことを教訓に、ゆめ市では、新規就農者を受け入れる際、サポーターを付けることにした。同社は現在、農林水産省の「農村活性化人材育成派遣支援モデル事業(田舎で働き隊!)」を活用し、特定非営利活動法人アクション・シニア・タンク注)が事務局となり20代~40代の若者12人を受け入れている。研修期間は2010年3月末までであるが、4月以降も引き続き雇用する予定で受け入れている。12名のうち、生産現場担当の研修生が4人、残りは加工、流通、販売部門で研修を受けている。彼らの前職はサラリーマン、学校教師など多彩で、「いろんな業界の人が入ってきただけに、ゆめ市の事業の範囲も広がる」と徳井専務は大いに期待している。研修生には、同事業から研修手当として月に7万円(補助率2分の1)、ゆめ市から7万円、合わせて14万円が毎月支給される。
また、同じ事業を活用してサポーターを6人確保した。サポーターには、大企業の幹部経験者など農業関係以外の人になってもらった。「単に研修生の相談に乗るだけでなく、生産と流通の両面から助言ができ、それを実践に移すことができる人」(徳井専務)を求めていたからだ。
「たとえば研修生が独立する際、機械を入れて規模を広げたいと考えているとする。研修受け入れ農家は、『投資はリスクがある』と反対するかも知れない。だが、流通に明るいサポーターが販路を紹介し、開拓支援までしてくれれば、規模拡大しても経営が成り立つ。単なる相談相手ではなく、実質的に解決策を示してくれる人が我々の目指す農業には不可欠」と徳井専務は語る。
森島社長は、「食の市場規模は80兆円以上なのに、農業産出高はわずか8兆円。8兆円を少しでも増やさない以上、農業に未来はない。いまの農業を建て直さないまま、次の世代に渡すことなどできない」と語気を強めた。森島社長と同じことを考えている農家、法人は少なくないだろう。

語る森島社長(右)、徳井専務(左)
注)自らの課題や身近な地域の課題などについて調査、情報収集、分析、提言、行動する調査事業体で、まちづくりや商品開発、サービスの提供、政策立案などへ反映させることで、活力ある社会の実現や地域経済の活性化と、各自の意欲や能力が活かされることを目的としている特定非営利活動法人。
◆8.雇用の受け皿になるために
農業は人材が不足しており、他産業ではリストラへの勢いが強まっている。単純に考えれば、農業が雇用の受け皿になるのは両面からみても望ましい。
ここ1、2年農業界はかつてないほど注目されており、就農希望者は増えている。静岡県も研修希望者は05年まで一桁だったが、大幅に増えた。09年は10人の募集人数に対し、応募者が45人とかつてない数に達した。優秀な人材を集められる点では申し分ない。
だが、手放しでは喜ぶことはできない。ゆめ市の森島社長がいうように、農産物の価格低迷で多くの農家は経営不振に陥っている。この問題を解決せずして、若い新規就農者だけを増やしても、真の意味で農業の活性化にはつながらない。
雇用の受け皿として農業が注目されているが、農業に関心があれば、誰でもウェルカムという時代は終わった。厳選した人材への支援とバックアップ体制の整備も必要であるし、農産物の販売戦略と新規就農者の支援を一体のものとして考えていくことが欠かせない。