 調査報告
調査報告
耕畜連携事例調査
~輪作体系確立と自給飼料確保に向けたJAふらのの取り組み~
札幌事務所 所 長 角田 恵造
調査情報部 調査課 藤戸 志保
調査情報部 調査課 伴 加奈子
◆1 はじめに
資源循環による持続的農業を目指して、たい肥を利用した耕畜連携への取り組みが全国各地で見られるようになっている。また、近年の飼料原料の国際価格の高騰を受けて、畜産経営の安定化の面からは飼料自給率の向上が急がれている。
北海道にあるJAふらのでは、管内の耕種農家の生産性向上に向けた輪作体系の確立と酪農家の自給飼料確保というそれぞれの課題解決に向けて、両者を結びつけた耕畜連携体制の確立を図っている。
今回、JAふらのを訪問する機会を得たので、同JAの耕畜連携の取り組みを報告する。

(資料:JAふらのHP)
◆2 JAふらの管内の農業概要 ~青果物を中心に多岐にわたる農作物を産出する食料基地~
富良野市は、北海道のほぼ中心、十勝岳連峰や芦別岳を主峰とする夕張山地に囲まれた南北に長い富良野盆地の中央に位置する。1980年に放送されたドラマ「北の国から」の舞台となったことでも、また、ラベンダーの時期には毎年多くの観光客が訪れる場所としても有名な町である。
営農期の4~10月の積算温度は2,700度前後、年降水量は1,100ミリ程度で、7~8月の平均気温も20度以上と農業気象条件に恵まれた農業の町でもある。
JAふらのは、富良野市を中心に、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村の6農協(1市3町1村)が一つになり、平成13年2月に設立された。組合員戸数約1,665戸、作付面積約22,729ヘクタールと、北海道の中でも規模の大きい農業協同組合である。
もともと富良野市は水田地帯として発展してきたが、減反政策後、販売総額の過半(56.5%)を占めるたまねぎ、にんじんなどの青果物を中心に、米穀(水稲、麦など:18.9%)、畜産(15.6%)を含め、多岐にわたる農産物を産出する食料基地となっている(図1・2)。

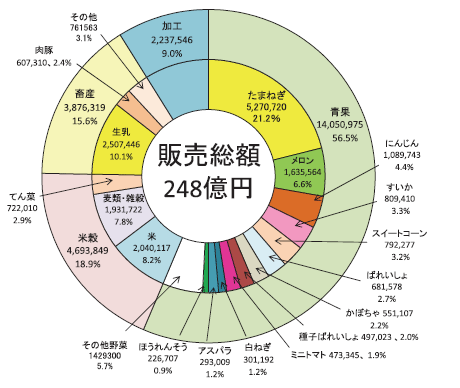
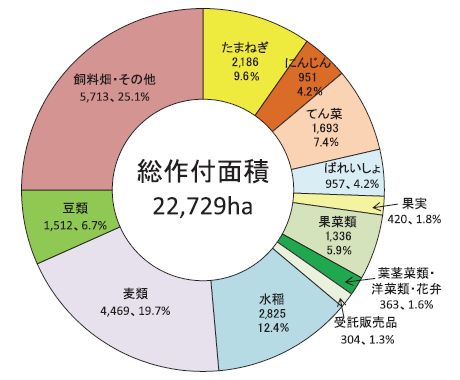
◆3 JAふらのの耕畜連携の取り組みのきっかけ
JAふらのが耕畜連携体制確立に取り組む契機となったのが、平成19年度から独自に始めた耕畜連携対策実証事業(以下「実証事業」という。)である。たまねぎを中心とする耕種農家の生産性向上に向けた輪作体系の確立と酪農家の飼料用トウモロコシ(以下「デントコーン」という。)の増産による自給飼料確保というそれぞれの課題の解決を目的とするこの事業は今年度、事業最終年の3年目を迎えた。
(1) 連作障害に悩むたまねぎ農家
たまねぎは、昭和45年頃から水田の転作作物として積極的に栽培されるようになった富良野の基幹作物である。定植機や収穫機のほかに冷蔵貯蔵施設などの設備投資を必要とする作物であるが、富良野では栽培が始まった当初から、たまねぎを主力作物として生産技術の確立を図るとともに設備投資を続けてきた。その結果、管内のたまねぎ農家戸数は430戸(平均作付面積は5~7ヘクタール/戸)、全国出荷量の6割を占める‘たまねぎ王国’北海道内でもJAきたみらいに次ぐ第2位の収穫量を誇る大産地となっている(図3・表1)。
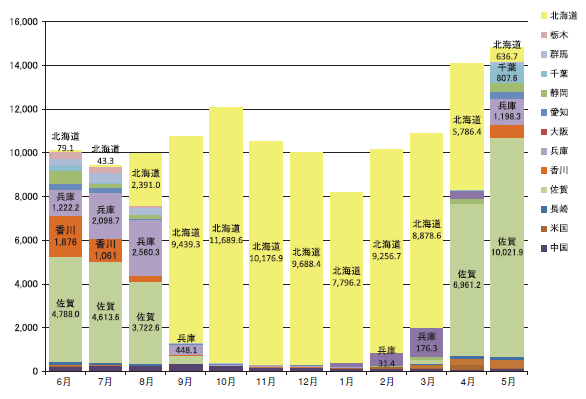
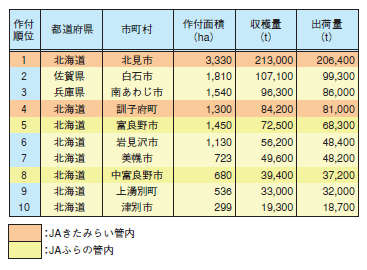
たまねぎは、連作に比較的強く、何十年も同じ畑で栽培し続ける農家が多い作物である。JAふらの管内のたまねぎ農家も例外ではなく、たまねぎの作型は、たまねぎの単作もしくはメロンやほうれんそうなどのほかの作物を組み入れるのが一般的となっている。栽培が始まった昭和45年頃からたまねぎのみを作り続けて40年近く連作している例もあるという。
しかし、さすがに最近になり、単作農家のたまねぎ畑において病虫害の発生や土壌菌の増加など、連作障害による収量の減少が見られるようになっており、たまねぎ農家を悩ませていた。
本来であれば、4年に1度程度は、休閑緑肥という形でひまわりやエン麦を組み入れてたまねぎの生産を休ませるか、たまねぎ以外の作物を導入するのが望ましい。しかし、なかなかたまねぎ並みの高収益を確保できる作物はない上に、新たな作物を輪作体系に組み入れるためには、は種機や収穫機などの設備投資が必要であることから、収量が減少する中でやむを得ずたまねぎを作り続ける状況が続いていた。
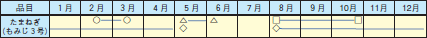
資料:本年6月聞き取り


地上部の根切り後、地干しをしたたまねぎを拾い上げ、大型コンテナに収納していく
(2) 輸入飼料原料価格の高騰に苦しむ酪農家
一方、畑作や稲作の補完として管内に導入された酪農経営は、畑酪兼業農家から酪農一本の大型専業化が進み、酪農家戸数は66戸、総飼養頭数は7,248頭(うち経産牛4,364頭)、生乳生産量は年間37,633トンとなっている。
管内の酪農家は、飼料について一般的に、牧草やデントコーンを自ら栽培し、不足分について穀物などの原料を購入して自家配合という形で補っているが、18年からの輸入飼料原料価格の高騰による生産コスト上昇が経営を圧迫し、自給飼料の確保・増産が喫緊の課題になっていた(図5)。しかし、酪農経営と並行してのデントコーンの生産は作業負担が大きい上に、農地価格の高い富良野市内では作付面積を増やしたくても増やせない状況にあった。
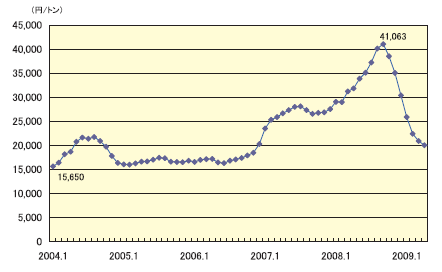
(3) たまねぎと相性抜群のデントコーン
農地に余裕のある管内のたまねぎ農家の中には、たまねぎとの相性の良さに着目し、実証事業が始まる数年前からデントコーンを作付けて、近隣の酪農家に販売する取り組みを自主的に行っている者が存在した。
上川農業改良普及センター富良野支所(以下「普及センター」という。)によるたまねぎの収量調査においても、たまねぎの輪作体系に組み入れる作物としてデントコーンが最も適していることが判明した。
図6~8・表2~3は、緑肥作物がたまねぎの収量に及ぼす影響を調査するため、普及センターが連作区、シロカラシ区、エン麦区、ヒマワリ区、デントコーン区の各試験区跡地にたまねぎを定植し、その収量を検証した結果であるが、デントコーン区が規格内収量・規格内球数率ともに多いことが分かる。
また、デントコーンは、単位面積当たりの乾物量が多いため、土壌改善効果が高い上に、ほかの休閑緑肥と違い酪農家に販売することで換金作物になる。さらに、デントコーンを栽培している酪農家がは種機や収穫機を所有しているため、耕種農家が新たに機械投資する必要がないというメリットもあった。
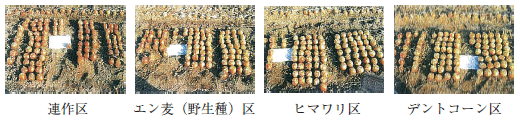
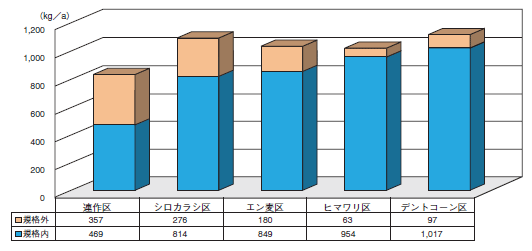
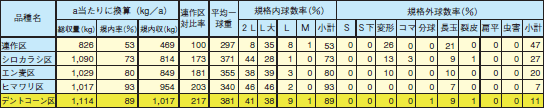
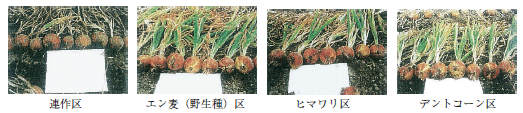
連作区は生根率が低いが、緑肥区ではしっかりとした根が見られた。また、緑肥区全般で生根に比例して青味の残った茎葉が多く見られた。茎葉の枯れ上がりが緩慢であると、肥大の良さにもつながる。(図8・表3)
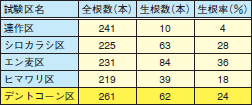
◆4 JAふらのの耕畜連携の取り組み
JAふらのとしても、地縁的なつながりから既に始まっていた耕畜連携の輪を拡大できないかという当時の営農部の提案により、耕種農家と酪農家を支援する実証事業を立ち上げた。
(1) 耕畜連携実証事業の内容
① 実証事業の概要
実証事業は、たまねぎを中心とする耕種農家が酪農家への販売用デントコーンを栽培する代わりに酪農家が耕種農家にたい肥を供給する、という取り組みに対し、JAが耕種農家と酪農家の双方にデントコーン種子代相当額(5,000円/10アール)と供給たい肥相当額(5,000円/10アール)を助成するというものである。
② 実証事業の流れ
実証事業は毎年、前年の11月下旬頃から始まる(表4)。JAは、耕種農家の飼料用デントコーン栽培希望をとりまとめ、栽培条件をJAふらの酪農部会に提示する。提示を受けた酪農部会は酪農家の飼料用デントコーン購入希望をとりまとめ、JAに購入条件を提示する。その後、JAと酪農部会が、距離や栽培条件などを勘案しながら、個々の酪農家と耕種農家の結び付けを行い、3月上旬にはデントコーン販売契約が締結されるという流れで進められる。
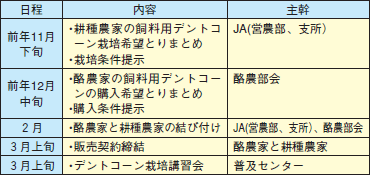
③ 耕種農家と酪農家の作業分担
契約締結後、たまねぎ農家は、自分の畑で耕起・整地を行い、酪農家が指定した品種のデントコーンをは種し、除草までの作業を分担する。一方、酪農家はデントコーンの収穫・調製作業とともに、たい肥の供給(10アール当たり5トン、搬送を含む)を分担する(図9)。
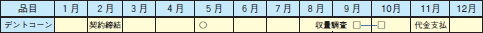
資料:本年6月聞き取り
④ デントコーン代金の支払い
酪農家から耕種農家へのデントコーン代金は、収穫を終えた11月上旬頃に、耕種農家の請求により、JAが酪農家からキログラム当たり6.3円(税込)を徴収し、あっせん手数料(デントコーン代金の3%)を差し引いて耕種農家へ支払われる。ただし、収穫量の把握が難しい場合は、双方の合意のもと、収量調査を基に面積支払いが行われる(表5)。
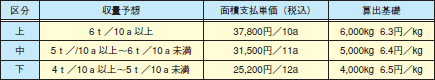
また、JAはデントコーン代金の精算とたい肥供給の確認が取れた後、たまねぎ農家へ10アール当たり5,000円(デントコーン種子代相当額)、酪農家に対しても10アール当たり5,000円(たい肥5トン相当額)を助成する仕組みになっている(図10)。
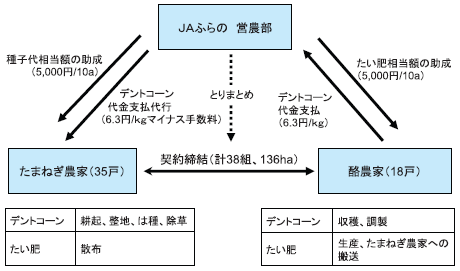
(2) 実証事業に参加する酪農家の声
今回、実証事業に参加する2戸の酪農家にお話を伺うことができたので、経営概要とともに耕畜連携の取り組みを紹介したい。
① 「磯江牧場」
~経営概要~
JAふらのの酪農部会長を務める磯江氏は、調査時点で、飼養頭数計480頭(経産牛245頭(うち搾乳牛210頭)、育成牛235頭)、年間生乳生産量2,480トンの大規模酪農経営を行っており、現在も増頭を進めている。また、1頭当たりの乳量は年間約10,500キログラム(平成19年度)と、全国平均7,988キログラム(平成19年度)を約3割上回っており、増頭に加え乳量の増加を目標に掲げた戦略的経営を行っている。
145ヘクタール(所有地76ヘクタール、借地20ヘクタール、実証事業を含む作業委託面積49ヘクタール)の飼料畑でデントコーンおよび牧草を生産しており、飼料自給率は55%、残り45%は輸入穀類を購入している。
磯江氏は、良質な自給飼料の確保により乳量を高める飼料設計が戦略的に行えると、自給飼料の生産意欲が非常に高い。また、一昨年来の飼料価格の高騰を受け、量だけではなく、でんぷん含量やたんぱく含量など栄養収量の高い良質な飼料を自給していくことが、今後の酪農経営においてより重要になると感じているという。中でも昭和41年の就農当時から生産しているデントコーンは、TMR原料としてでんぷん含量が高い粗飼料となる上、単収が10アール当たり7トンと高いことから、最優先で生産したいと語る。
~耕畜連携の取り組み~
磯江氏は、事業が始まる以前から、知り合いの耕種農家と連携してデントコーンの生産に取り組んでいた。飼料生産の拡大意向があっても、前述のとおり、富良野市内は農地価格が周辺地域と比較して高く、酪農家が農地を取得するのは容易ではない。
地縁的なつながりで始まった、限られた面積の中での取り組みが、JAの実証事業によってPRされることにより、飛躍的に面積を伸ばすこととなり、現在、同事業を通じて10戸の耕種農家と合計約46ヘクタールのデントコーンの栽培契約を結んでいる。
収穫期には、近隣の酪農家4戸で運営する営農組合のメンバーと臨時雇用により、同組合が共同所有する自走式ハーベスタでの刈り取りを行っている。大型ハーベスタ(刈り取り能力:13ヘクタール/日)で効率的に作業を進めるため、飛び地の小規模農地などでは購入条件の折り合いがつかないこともあるという。
個人的に感じている実証事業のデメリットとしては、参加要件である10アール当たり5トンのたい肥の供給を挙げている。通常であれば、生産したたい肥全量を自ら利用することは困難であることから、連携により、たい肥の循環体系が確立できることはメリットになるが、磯江氏の経営では、生産するたい肥の大部分を自家使用しているため、21年度事業で年間2,300トン(46ヘクタール分)のたい肥を耕種農家に供給しなければならないことからむしろたい肥の不足感があるという。一方で、デントコーンの増産による自給飼料の確保が可能となったことは、そのようなデメリットを相殺すると言い、実証事業によるJAの助成が無くなってもこの取り組みを続けたいと語る。
また、磯江氏は、耕畜連携による耕種農家側のメリットについても充分認識している。以前、デントコーンを10年連作し、連作障害を起こした畑に小麦を植えたところ、翌年の春小麦は10アール当たり8俵、翌々年の秋小麦は10俵と、地域でもトップクラスの収量を上げた。その経験から、デントコーンとの輪作による土壌改善の効果を実証事業に参加した耕種農家にもぜひ実感して欲しいという。また、その結果が、実証事業終了後の農家の取り組みにどう結びつくか期待しているとのことであった。


② 「及川牧場」
~経営概要~
及川氏は、前述の磯江氏と同じ営農組合のメンバーである。飼養頭数計160頭(経産牛85頭、育成牛75頭)、年間生乳生産量970トンの大規模酪農経営を行っている。また、20年度の1頭当たり乳量は、11,000キログラムと高泌乳酪農経営を営んでいる。前述の磯江氏と同じく、及川氏も乳量を上げる基本となるのはやはり粗飼料と語る。でんぷん含量の高い良質なデントコーンおよびたんぱく含量の高い牧草を確保することで、輸入穀類の配合量を低く抑えることができ、さらに牛の食い込みも良くなるという。
60ヘクタール余りの飼料畑に、牧草(40ヘクタール)、デントコーン(20ヘクタール)のほか、小麦などを栽培している。大型ハーベスタを利用した共同作業により、9ヘクタール分(バンカーサイロ1基分)のデントコーンの収穫・密封までを1日で終えることができ、良質なサイレージの生産が可能となっている。


~耕畜連携の取り組み~
及川氏は、JAふらのの実証事業を通じて2戸の耕種農家と約8ヘクタールのデントコーン栽培契約を締結している。
たい肥は、自家使用、実証事業による供給(5トン/10アール)に加え、従前より、麦作農家とのたい肥と麦かんの交換や野菜農家への販売も行っている(図11)。
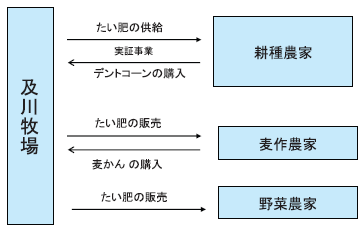
富良野地域では近年湿害や干ばつなどに見舞われ、たい肥を継続的に散布している畑とそうでない畑の差が極端に現れてきており、たまねぎ、にんじんなどの耕種農家のたい肥需要は、肥料価格が急騰した2008年以前から増加しているという。及川氏自身も、実証事業による耕種農家への年間400トン(8ヘクタール分)のたい肥供給に加え、規模拡大により最近取得した農地に多めに投入したい意向があるため、昨年あたりからたい肥の不足感を感じているとのことであった。
また、20年度の同事業で生産したデントコーンは、耕種農家が後作の麦を植えるため、予定より1週間早く収穫しなければならず、水分含量が高いものとなってしまったことから、今年は事前の打ち合わせを綿密に行い、栽培計画に適した品種を選定したいと語る。
前述の磯江氏と同様、デントコーンの購入とたい肥の供給という新たな耕畜連携の取り組みを、実証事業が終わる21年度以降も続けていきたいと意欲的だ。


(左)。麦かんは十分に手に入るため、ルーズバーン方式の乾乳牛舎には麦かんが全面に敷き詰められている(右)。


◆5 おわりに
19年度から始まり事業最終年の3年目を迎えたJAふらのの実証事業の契約数は、13組→29組→38組と年々増加している。それに伴い、事業によるデントコーンの作付面積も72ヘクタール→103ヘクタール→136ヘクタールと年々拡大している(表6)。
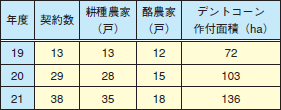
事業に参加してデントコーンを作付けた耕種農家が、たまねぎの栽培に戻したときの事業効果の確認ができるのは事業参加の翌々年となる。そのため、事業効果の測定はこれからの段階であるが、耕種農家の輪作体系の確立と酪農家の自給飼料の確保というそれぞれの課題解決に向けた取り組みは、着実に地域に浸透しつつある。
JAふらのでは、この実証事業以外にも野菜残さの処理と土作りを兼ねた独自の有機物供給センターを有するなど、たい肥を活用した地力の向上に向けた取り組みを行っている。来年度には現在年間11,836トンのたい肥製造量を倍増させるため、新たな有機物供給センターを建設中とのことである。
地域密着型のJAが、管内の農家が抱える課題や要望をいち早く把握し、まずは事業という形で支援することで、取り組みが地域に浸透するきっかけを数多く作っているように感じられた。
実証事業の参加者からは、事業が終了する21年度以降もこの取り組みを続けたいと意欲的な意見が数多く寄せられており、地縁的なつながりから始まっていた耕畜連携の取り組みをヒントに始まった実証事業がきっかけとなって、今後ますます持続的農業を目指した取り組みの輪が広がる手応えを感じた。
最後になったが、本調査を実施するに当たり、ご多忙中にもかかわらず多大なご協力をいただいたJAふらの営農販売事業本部の小河 健伸係長、酪農部会長の磯江 敏昭氏、及川 栄樹氏にこの場を借りて厚くお礼を申し上げる次第である。




たまねぎ、にんじんなどの野菜残さは、分解・発酵しやすいように破砕機で前処理がなされる。幅7メートルにもなる発酵槽では、菌が死滅する70度以上に保ちながら、自動運転による攪拌機で1日1回の切り返しを20日間行うことにより、一次発酵・二次発酵まで含めて3カ月でたい肥化される。