 調査報告
調査報告
順調に輸出を伸ばす「十勝川西長いも」
~JA帯広かわにしの取り組み~
調査情報部 審査役 武居 正和
調査情報部調査課 課長 瀬島 浩子
わが国の農林水産物の輸出額は、世界的な日本食ブーム、アジア諸国を中心とした富裕層の増加などを背景として近年増加傾向で推移しており、平成19年には前年を16.0%上回る4,337億円となった。農林水産省では、平成25年までに輸出額を1兆円規模に拡大するという目標の下、官民挙げての総合的な輸出戦略を推進している。
こうした中、わが国から輸出されている野菜の一つであるながいもについて、平成18年に地域団体として「十勝川西長いも」の商標登録を取得し、台湾への輸出を順調に伸ばしている帯広市川西農業協同組合(JA帯広かわにし)を取材する機会を得たので、十勝川西長いもの生産の概況、輸出に至るまでの経緯や今後の動向などについて報告する。
◆国内生産量約20万トン、北海道は3割のシェア
わが国のながいもの生産量(収穫量)は、ここ数年20万トン程度で推移しており、平成19年産では、19万400トンとなった。都道府県別に見ると、青森県が38%を占め、次いで北海道が34%となっており、この2道県で全国の約7割を占めている。
道内では、函館から北見に至る広い地域で生産されており、中でも、帯広を含む十勝管内は、道内の8割の生産量を誇る一大産地となっている。
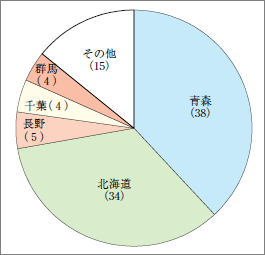
注:データはいずれも「やまのいも」の収穫量である。
◆JA帯広かわにしの選択:輪作体系の中で模索した高収益作物
帯広市は、北海道の東部、十勝平野のほぼ中央に位置し、輪作体系に基づく、小麦、豆類、てん菜、ばれいしょを基幹作物とした畑作、酪農・畜産など、大規模で機械化された土地利用型農業が展開されている。
JA帯広かわにし(帯広川西農協と帯広市農協の合併により平成15年4月に設立)によるながいもの導入は、昭和30年代後半に始まる食料輸入増に伴う農産物価格の低迷が契機であった。30戸前後の生産者の自主的な取り組みとして、収益性の高い野菜を模索した結果、ながいもについては、寒暖の差が激しい気象条件と水はけの良い土壌を有する当地に適合し、品質の良いものの継続的な収穫が可能となったことから、これを輪作体系に組み込むこととした。
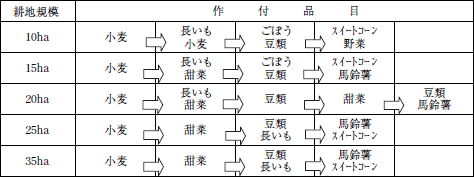
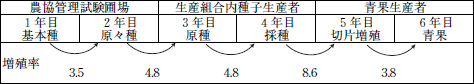
◆種いもの栽培体系の確立と機械化による産地形成
ながいもの本格的な生産に当たって取り組んだのが、種いもの栽培体系の確立と作業の機械化である。まず、種子体系については、生産者みずからの手で、当時道内で最大の生産地であった夕張から導入した種いもをベースに個体選抜を繰り返し、昭和55年には1系統の優れた種いもを普及できるまでに確立した。現在は、徳利型をした均一で形質の優れた無病種いも確保のため、基本種をJAが管理する試験ほ場で栽培するなど6年の歳月をかけて増殖するとともに、罹病株の共同抜き取り実施などを通じ、ウィルス病の撲滅に全力を挙げている。
また、機械化については、昭和40年代中頃以降、トレンチャー(作付け前に畑を耕す作業機。ながいもは地中深く根をはるため、幅20センチ、深さ1メートルの土を柔らかくする)やバックホー(収穫時に作業者が入るための溝を掘る重機。もともとは建設機械)などの大型機械を導入し、畑の造成から収穫までの作業の効率化を図った。
◆広域共販体制の下での通年出荷
このような取り組みにより、昭和54年には管内の生産者に加えて近隣の芽室町がともに生産を始めるなど、作付面積は徐々に拡大し、昭和50年代後半には生産量が100トンを超えるようになった。このため、産地形成に当たっては、JA・町村の枠を超えた広域的な集荷販売体制による通年出荷が不可欠と判断し、昭和60年にJA中札内村を加えた3JAによる「川西長いも運営協議会」が発足した。現在は、芽室および中札内のほか、足寄、浦幌、新得および十勝清水の6JAが原料生産に参画し、JA帯広かわにしによる一元集荷、多元販売として通年出荷体制が可能となっている。
以上述べたようなさまざまな取り組みが奏功し、生産量はほぼ一貫して増加傾向で推移している。
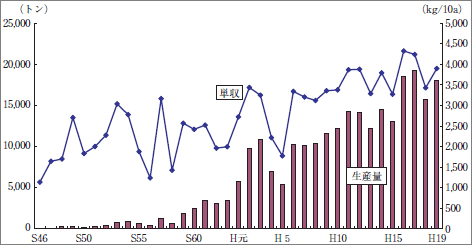
◆輸出の契機は台湾の薬膳ブーム
生産量が増加し、主要産地として年間を通じて市場に出荷する中、豊作時の価格の暴落や太物(4L規格:1,400グラム)は、カット販売されるため規格外品並みの価格でしか販売できないなどの課題に直面するようになった。中でも平成11年は、豊作による太物の比率増加と市況の下落懸念もあり、国内市場の価格維持と太物の販路拡大を目指して、台湾への輸出を開始した。
台湾では14~15年前、医学界がながいもを漢方薬と位置付けたことなどから、ながいもが健康食品として珍重されるようになり、「山薬(シャンヤオ)」と呼ばれて薬膳料理のスープ食材として根強い人気を誇っていた。こうした台湾での健康志向、薬膳ブームに着目した関西の仲卸業者が、十勝川西長いもを試験的に輸出したのである。


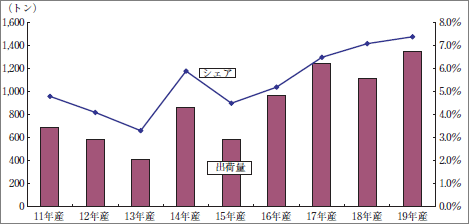
注1:出荷量は11月から翌年10月である。
2:シェアは、出荷量に占める台湾向け輸出量の割合である。
◆太物志向が奏功し輸出は着実に増加
日本では大きすぎてカット販売されるなど持て余されていた太物が台湾では逆に好まれる上、地場産のものより色が白く、美味であることなどから、十勝川西長いもは、健康志向の強い富裕層を中心に、現地で高い評価を得ることとなった。このほか、JAサイドの取り組みとして、野菜の貿易実績がある取引業者を介するとともに、代金決済についても専門の商社を利用したこと、国内市場を経由したう回輸出品との差別化を図るため、専用箱を導入したことなども、台湾輸出成功の要因として挙げられる。
こうした努力の結果、十勝川西長いもの台湾向け輸出は、スタートした平成11年(11月~翌年10月)の684トンから平成19年には1,350トンとほぼ倍増し、生産量の7.4%を占めるまでになった。
◆4Lの有利販売で生産者の収入が増加
4L規格の場合、国内市場向け販売価格が1箱(10キログラム)当たり2,700円程度であるのに対し、台湾向けは100~200円程度上乗せして出荷されるため、輸出により、国内向けの主流である2L規格(900グラム)の販売価格(1箱当たり3,000円程度)と遜色ない水準を達成できるようになった。さらに、台湾という太物の需要先を確保したことで、国内においても4Lサイズの供給量が調整できるようになり、国内価格の維持を図ることが可能となった。
十勝川西長いもの単位当たり粗収入を見ると、広域共販体制が始まった昭和60年から輸出開始直前の平成10年までの平均が10アール当たり56万2千円であるのに対し、輸出開始後(平成11年から平成19年の平均)では同72万4千円と、輸出前に比べて3割程度増加している。粗収入の増加は、栽培技術の向上など輸出以外によるところもあるとは思われるものの、台湾への輸出が大きく貢献していると考えられる。
◆担い手による安定・継続的な生産を実現
十勝川西長いもの生産現況は、作付面積450ヘクタール、農家戸数250戸、1戸当たりの作付面積は1.8ヘクタールとなっている。輪作体系の中で仮に2ヘクタールのながいもを作付けるためには、最低8ヘクタールを耕作する必要があり、JA帯広かわにし管内の専業農家の場合、平均耕地面積は25.5ヘクタールと、30ヘクタール規模の生産者も少なくない。生産者の平均年齢は40代半ば、入植後4代目から5代目の、まさしく壮年層が経営を担う状況となっている。
ながいもの生産には、大型機械、種いも貯蔵用低温庫、収穫用コンテナ容器などの各種資材の調達コストなど、1ヘクタール当たり1千万円の初期投資が必要であり、再生産の確保には10アール当たり60万円の粗収入が必要となるという。このような中、後継者不足とは無縁の状況となっているのは、ながいもという高収益作物の生産、輸出を通じて満足のいく所得水準が確保された結果であるといえよう。



◆目標はバランスのとれた輸出
以上見てきたように、生産が着実に増加する中で、台湾向け輸出がここ3年は1,000トン台で推移するなど、台湾での十勝川西長いもの評価は定着したといえる。しかし、台湾向け輸出は、その市場規模などからして、今後飛躍的に拡大するとは考えにくく、今後は、現地での健康志向や高品質志向がどの程度継続するかなどを注視しつつ、複数産地間の低価格競争に陥らないよう、需給バランスを調整することが重要となってくる。
こうした中、台湾以外の輸出を新たに開拓する取り組みも始まっている。米国向けに年間200トン前後輸出しているのを始め、シンガポール、タイなどの東南アジアや、ドバイといった中東地域、さらにはヨーロッパ諸国へも試行的に出荷している。例えばシンガポールでは、暑い国のため加熱調理が好まれず、ながいも特有の粘りも受け入れられないことから、ミキサーにかけて牛乳と糖分を加えた「ながいもジュース」を提案し、消化吸収に優れ、滋養強壮になるといった機能面を訴求するなど、現地の需要にあった販売に腐心しているという。
このように輸出先の開拓に取り組んではいるが、ながいも生産については、輪作体系の中に高収益作物を取り入れるというのが基本的な方針である。JA帯広かわにしとしては、特別な生産体制をとるなどして輸出を重点的に伸ばしていくのではなく、あくまで国内市場への通年安定出荷に軸足を置き、過剰生産に陥って値崩れしやすい国内市場の需給バランスを維持して価格の安定を図るとともに、生産の過程で必然的に収穫される4L規格(収穫量の8%程度)を有利に販売するための手段の一つとして輸出を位置付けるとしている。
◆継続的な農業生産を目指して
今回の取材で最も印象に残ったのが、「息子や孫の代までこの地で農業を続けるために何をすべきかということを常に考えている」という、JA帯広かわにし別府事業所の常田所長の言葉であった。今から40年以上前に、生産者の自主的な取り組みとしてながいもの生産が始まって以来、広域化による産地形成、優良無病種いも確保のための厳格管理、ブランド化の取り組み、輸出を含めた戦略的な販売、産地間競争の中でのブランド維持など、JA組織としてさまざまな取り組みを行ってきたが、これらは、ひとえに「子や孫の代まで」という強い思いに支えられてきたのだと思われる。この言葉どおり、再生産を可能とする所得水準の達成、日本有数の産地という生産者の自負、輸出も手がけているという自信と励みが相まって、担い手による継続的・安定的な農業生産が現実のものとなっており、いったんは家を離れて就職しても、その後Uターンするケースも多いという。このような順調な状況があるからか、訪れた収穫現場では、とても明るい雰囲気の中で作業が行われていた。

JA帯広かわにしは平成20年3月、別府事業所内のながいも洗浄選別施設において、食品衛生管理の国際規格「HACCP」の認証を取得した。農産物の選果場による認証取得は、世界でも珍しいものであるが、こうした先駆的な取り組みも、消費者の安全・安心への関心は内外を問わず今後一層増していくと判断し、「自分たちの子孫がここ帯広で農業を続けていく」ための先行投資であるとみられる。
ながいもの栽培には、深さ1.5メートルまでの表土に「れき」がない状態が必要であるが、帯広一帯は、地表残留水の排除や地下水位の低下のための暗きょ管が深さ1メートル前後の地中に整備されているのが一般的であり、作付けできる農地が限られているのが現状である。今後、輪作体系の中で広域的にながいも生産を拡大していくためには、基盤整備事業の活用などにより、深暗きょを整備していくことが必須となってくる。
また、JA帯広かわにしでは、新たに枝豆について、JA中札内村との広域体制の連携を検討中であるという。JA中札内村は、ながいもの広域共選体制を通じて長年密接な関係にあり、枝豆の生産・加工で市場の評価が高まっていることから、枝豆を通じた同JAとの連携により、生産者の収益性の向上を図るとともに、ばれいしょなど根もの作物への依存度が高い現在の輪作体系を改善したいとしている。JA帯広かわにしの今後の動向について、輸出も含めて注目していきたい。