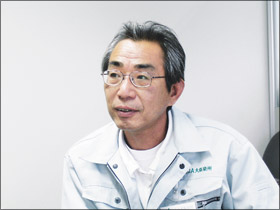調査報告
調査報告
キャベツの供給を通じた産地と仲卸業者の関係強化
農業ジャーナリスト 青山 浩子
大阪府の大阪泉州農業協同組合(以下「JA大阪泉州」又は「同JA」)は、仲卸業者である大阪市の株式会社丸促(以下「丸促」)とキャベツの取引を通じて信頼関係を深めている。キャベツの品質の良さに加え、産地をとりまとめる同JAの役割が丸促から評価され、同JAはキャベツの有力な販売先を確保できた。産地の対応力と仲卸業者の販売力、提案力がうまく組み合わさった事例と言える。
■土地に適した品種が高い評価
(産地の概要)
大阪府の南部(4市2町)を管内とするJA大阪泉州は、かつては農業が盛んであったが、関西空港が誕生して以来、農地は減少し、都市化が進んでいった地域だ。約21,000名の組合員のうち、農業生産者は約1,700名。農産物の販売金額は約28億円だ(数字はすべて2008年3月時点)。
農産物全体において最大の販売金額を占めるのがキャベツである。なかでも「松波」(有限会社石井育種場)という品種は高い評価を受けている。同JA営農経済部の南口義彦部長は、「生食用では一番甘いと言われている。関西の食文化に欠かせないお好み焼きに向いた品種で、『火を通すとさらに甘みが増す』と好んで使われている」と話す。
この品種は同JA管内の土地によく適しており、糖度がのりやすい。大阪以外にも愛知県、島根県、九州一帯でも栽培されたようだが、大阪で作る場合と同じようにはいかないという。同JAの販売課の北野幾久課長によると、「寒さに弱く、新しい畑で作ると肥大しすぎるなど土地を選ぶ品種なのだろう」と話す。冬キャベツの大産地といえば、愛知県産のキャベツだ。数量では圧倒的に少ない大阪産のキャベツが、愛知県産とほぼ同じ価格で販売されているのは、品質面で高い評価を受けているということだと言える。
同JAが「松波」を生産するようになったのは20年以上前。「市場関係者から、松波の評判が良いことを聞き、農家からのキャベツを受け取る際に、品種によって価格差をつけるようにした。すると高値のつく松波の生産量が増えていった」(北野課長)。ピーク時にはキャベツ全体の90%を「松波」が占めていたが、連作障害などで徐々に減少し、現在は栽培面積全体(約170ヘクタール)の60%程度だという。「松波」以外の品種としては、「彩音(アヤネ)」、(タキイ種苗株式会社)、「冬のぼり」(株式会社野崎採種場)などを主に栽培している。キャベツ農家は約500人で、1人当たりの平均栽培面積は50アールほど。大半の農家が表作で米をつくり、裏作としてキャベツ、あるいはたまねぎの栽培を組み合わせている。

■両者の利害が一致
(丸促の概要)
この「松波」にほれ込んで、JA大阪泉州からキャベツを仕入れているのが丸促だ。同社は1963年に創業した仲卸業者で、当初はししとうがらし、オクラといった促成栽培の小物の扱いからスタートし、国産および輸入青果物を取り扱ってきたが、5年ほど前からあらゆる青果物を取り扱うようになった。輸入青果物に対する消費者の信頼度の低下に伴って、徐々に国産にシフトしており、現在輸入ものの取扱いは全体の10%にも満たないという。取り扱う青果物の60%が量販店向け、残りの40%が専門店、納入業者、加工業者向けだ。青果用と加工・業務用で分けると8:2の比率。調達する青果物の過半は、荷受けからの仕入れだが、全国の農業法人、農家グループなどとの契約栽培により直接調達するケースも多い。売上げは約65億円である。
(両者の出会い)
同社がJA大阪泉州のキャベツを調達するようになったのは2005年から。蔬菜部の小泉智弘部長は「松波という品種も魅力だったが、品質の面からも関西圏内ではトップレベル。何としても扱いたいと思っていた」と話す。同社は自ら入場している大阪市中央卸売市場内の荷受けである大果大阪青果株式会社を通じ、同JAのキャベツを調達してきたが、複雑な流通経路を経ていたため、同JAと荷受けの了承をとりつけて直接取引を始めた。
この直接取引の話は、JA大阪泉州サイドも望んでいたことだった。丸促と直接取引をすることで、荷受けに渡していた委託手数料をそのままカットできる。「JAの経済事業改革が進行中だが、肥料・農薬代、重油代が上がっているなかで、組合員からの手数料を上げることはままならない。それに手をつけず経済事業を採算に乗せる方法を考えてきた」という南口部長。利益確保のためのひとつの方法として直接取引をとらえていた同JAと、同JAのキャベツがほしかった丸促の利害が一致し、取引が始まった形だ。

■仲卸の提案力と産地の組織力が信頼構築
(丸促に寄せる信頼)
JA大阪泉州が12月から翌年4月にかけて出荷するキャベツは約80万ケース。このうち丸促は約6万ケースを取り扱っている。出荷量全体からみれば少量だが、同JAからキャベツを調達している業者別に見ると、4番目に多い数量だ。しかも丸促以外はすべて卸売市場である。つきあいをはじめてわずか3年の仲卸業者1社が、卸売市場に負けず劣らずの数量を調達していることになる。南口部長も「丸促さんには優先的に分荷している」と話す。それだけ丸促が販売力を持っており、同JAから信頼されている証拠であろう。
(販売における工夫)
丸促が量販店などへの販売面で力を入れているのが、単に青果物を納めるだけではなく、「どうすれば消費者が買ってくれるか」を考えて小売側に提案する、いわゆる「売り場提案」だ。
量販店の仕入れは「青果担当」、「水産担当」、「デリカ(惣菜)担当」など縦割りになっており、部門を越えた連携は薄い場合が多い。だが消費者に買ってもらうためには、青果でよく売れるばれいしょをコロッケの材料として使うとか、サンマとすだちをセットで販売するといったマーチャンダイズミックスが不可欠だ。このような量販店の弱みを丸促は指摘するとともに、売り場づくりまで提案するのだという。丸促の営業販売促進部の近藤春彦統括部長は「そういった提案までできない限り、我々中間業者は生き残っていけない」という。
また、青果物の家庭用需要が50%を下回り、さらに減少が予想される中、近藤部長は「景気の後退もあって外食マーケットが縮小している現状を考えると、外食が伸びるというのは考えにくい。しかし家庭で使うカット野菜の需要は伸びている」と話す。
同社は今年から、複数のカット野菜をセットにした簡便野菜を商品化し、コンビニエンスチェーンに提案し、販売に結びつけている。代表的な例が、キャベツとにんじんなどを組み合わせたものにタレをつけた「炒め物セット」、「カレーセット」、「豚汁セット」などだ。「主婦にも独身者にもニーズがある。青果をあまり扱ってこなかったコンビニも店舗が飽和状態で、差別化を迫られている。差別化策のひとつが青果品の扱いだったようです。まだ始めたばかりですが、右肩上がり。アイデア次第でこの市場はまだ伸びると思います」(近藤部長)。
(JA大阪泉州に寄せる信頼)
一方、JA大阪泉州に対する丸促の信頼も厚い。実需者が産地と直接取引する際、難しいのは組織をまとめることだという。農産物を必要数量分調達するには、産地側にまとめ役がいることが欠かせない。「その点、JA大阪泉州は組織をきっちりとりまとめてくれる」と近藤部長。JAが産地をまとめる役割をしっかり果たしていることが、両者の取引を円滑に運んでいるのだろう。
■品質が価格に反映されない農産物流通
(販売実績と市場相場を考慮した取引)
丸促はJA大阪泉州から仕入れたキャベツの80%を青果向けに大手量販店、コンビニエンスストアなどに販売し、20%を加工・業務用としてお好み焼きチェーン店、カット野菜業者に販売する。青果向けには段ボール箱1ケース当たり8、9、10玉というサイズを向け、加工・業務用には歩留まりのいい4、5玉を向ける。青果向けが多いこともあり、加工・業務用についても、青果向け同様段ボール詰めをしている。
両者間の取引は、あらかじめ数量や価格を固定させる契約取引とは少し異なる。JA大阪泉州は農家からの入荷量全体をまとめ、どの業者に何ケース分荷するかを決めている。その際に参考となる指標はこれまでの販売実績だという。販売実績の多い取引先ほど優先的に調達することができる。価格についても市場相場を参考に、JA大阪泉州と丸促の間の話し合いで決まっていく。
契約栽培では価格をあらかじめ固定させるというのが一般的だが、両者ともに固定させるより流動的にしておきたいという思いが現段階ではあるようだ。丸促の近藤部長は「数、価格、規格などを決めた上で取引できればこちらも安定するのは確か。しかしキャベツの相場は600円~2000円と変動幅が大きいため、固定させてしまうとリスクがある。当社としては相場と連動させるほうがリスクは少ない」と話す。一方、JA大阪泉州の南口部長も「価格を固定させ、それが市場価格よりも高くなった場合、売れなくなる恐れがある。量販店などはあらゆる産地のものを扱っており、価格も敏感。すべてを売り切るという使命を持っているため、市場価格に連動させ臨機応変な対応ができるようにしておくほうがリスクは少ない」と話す。
(青果物の流通への思い)
JA大阪泉州は実需者から評価の高い松波という品種を持っており、さらに、その品質の良さから産地が取引先にどれだけの数量を分荷するかという決定権を持っている。つまりキャベツについて同JAは「売り手市場」にあるといっていい。それでいながらキャベツの価格は市場の相場と変わらない。南口部長は「2008年は肥料・農薬代が値上がりしていながら、キャベツの価格は低迷が続いた。価格が回復しなければキャベツの作付面積は今後減る可能性がある」と懸念さえする。北野課長も「数年前までは米の後、キャベツかたまねぎを必ず作っていた。それが『米は作っても野菜はできない』という農家がでてきて、今では『米もあきらめた』という農家が増えた」という。今までは「自分では作れない」という農家から土地を借りて作ってきた農家もいたが、その当人も「もう作れない」と(地主に)返すケースも出ている。品質の良さが価格に反映されないという点が、現在の青果物流通の最大の課題といえよう。
■信頼関係の先にある契約栽培
(加工・業務用への転換の課題)
こういった状況にありながら、JA大阪泉州ではキャベツの産地維持のために、現在10%に満たない直接取引の比率を今後増やしていくつもりだという。「農家の高齢化を考え、あまり手間をかけず、大玉にして出荷する加工・業務向けを増やすことも考えている」と南口部長。ただ、具体的に加工・業務にあった専用品種を作付けしたり、直接取引できるような加工業者を自ら開拓するという段階まではまだいっていない。「業務用をひとつの軸に据えると、そのための担当者を1人確保しなければいけないし、『段ボールではなくコンテナで納めて欲しい』など要望にも応えていかなければならない。加工・業務用といっても生産者の顔を出したいというところが増えている。これまでは部会で一本化してきたが、行き先によって生産者を分けるとなると部会の了解も必要」(南口部長)と、解決しなければならない課題が少なからずあるからだ。
(産地と流通業者との信頼関係の重要性)
こういった課題を抱えつつも、「量では大産地にかなわないが、品質や中身で産地を売り込んでいくという方針は変わらない」(南口部長)という。その点で、丸促は大きな力となっている。丸促の演出によって、JA大阪泉州の特産のキャベツや水なすは関西に基盤を置くデパートで販売され、定期的に「泉州フェア」も開催される。その際、同JAの生産者も売り場に立って、商品の特徴や食べ方を説明する。「生産者自身が参加することでPR力が高まる。大阪に農業地帯が残っていること自体、関西の消費者には知られていない。それを知らせることはチャンスになる」と南口部長は期待している。産地の生き残りには、販売力、提案力に長けた流通業者とパートナーシップを組むことは欠かせない条件といえる。
一方、丸促側も産地と実需者との間に立って仲介機能を果たすことで、生き残りを図ろうとしている。「最近は量販店が農業生産を始めるなど小売業者が川上産業に近づくといった動きも出ているが、産地と実需者の間に立って調整する機能は欠かせない。それを荷受けが担うか、仲卸業者が担うかという問題が今後整理されるだろう」と丸促の近藤部長はいう。
契約栽培は農家の経営安定につながり、産地の維持にもつながるのは確かだ。しかし、JA大阪泉州と丸促の関係を見ると、契約栽培という形に至るまでに両者が互いの事情を理解しながら、信頼関係を築いていくことが大前提となることがわかる。
契約栽培は取引のひとつの形態だ。形態そのものにこだわるのではなく、産地として販売力を持つパートナーといかに組んでいくか、彼らと連携してどう需要拡大をめざしていくか具体的な方策を探っていくことが出発点となろう。契約栽培はその先にあるととらえたほうがいいかもしれない。