 専門調査報告
専門調査報告
~外食業者、サプライヤー、産地間の連携事例から~
契約取引において、今、産地が求められているもの
農業ジャーナリスト
青山 浩子
1997年の市場規模29兆円をピークに、2005年には24兆円にまで落ち込んだ外食産業。しかし最近、大手外食企業を中心に根本的な改革に乗りだしている。それとともに外食企業が求める野菜へのニーズそのものも変化しつつある。
外食産業は、契約取引によって食材を調達するケースが多い。外食業者に青果物を供給しようという産地にとって、まずその変化をとらえることが実需者の期待に応える第一歩となる。
外食産業の戦略がどう変化したのか。それにともない産地にはどういった対応が求められるのか。新たに企業戦略を打ち出した外食大手のロイヤルグループ、同社向けの野菜を調達しているサプライヤーおよび産地を訪ねた。
◆1 ファミリーレストランが「地産地消」に乗りだす
2006年8月22日、テレビ東京系列で放映された「ガイアの夜明け」は農業関係者に強烈な印象を残す番組だった。この日のテーマは「食の安心とは?~情報公開をめぐる知られざる裏側~」。食に関わる企業数社が紹介されたが、そのうちの一社、ロイヤル株式会社(以下「ロイヤル」)(本社:福岡県福岡市)が「地産地消」に取り組んでいる様子が紹介されたからだ。
ファミリーレストランといえば統一されたメニュー、マニュアル化されたサービスが売り物だ。「地産地消」とは対極に位置するというイメージが強い。
ロイヤルは外食産業大手でロイヤルホスト、シズラーを始めとするレストラン事業(ロイヤルホスト約320店舗、その他約380店舗)、ホテル業などを展開、グループで1000億円を売り上げる企業である。
番組の中で、持株会社であるロイヤルホールディングス株式会社の梅谷羊次執行役員は「低価格競争のもと、材料費や人件費を切り詰めた結果、ファミリーレストランが“ハレの場”でなくなった」、「ファミリーレストランからファミリーが遠ざかってしまった」と語っていた。その上で、ファミリーが再び訪れたくなるような店にすべくさまざまな改革に取り組んでいる様子が紹介された。
地産地消への取り組みはその一端であり、同社はレストラン事業の方向性そのものを大きく転換させようとしているように見受けられた。同社を訪ね、方向性の大転換について梅谷執行役員に聞いてみた。「方向性を決めるのに参考になるのは社会現象です。一つには少子高齢化社会。人口が減り始めたいま、空腹を満たすニーズは後退せざるを得ない。しかしもう一つの社会現象は団塊の世代の大量リタイア。彼らはライフスタイルを充実させたいと思う。さらに自分たちと子ども、さらに孫という3世代が一緒に食事を楽しむというニーズが高まっていくと見た」。こういう人々が求める食のキーワードは「健康」、そして「長寿」。これらから連想するものには、安全、産地表示、質がよく味のいい野菜、地元でとれた旬の野菜などがあるという。「こういったものを提供することで、ファミリーレストランをふたたび“ハレの場”にできるのではないか。そうなればマーケットのさらなる拡大が期待できるという考えに至った」と話す。
団塊の世代、あるいは3世代が楽しめる食事・・・を軸に、マーケティング戦略を考えた結果、でてきた答えの一つが「地産地消」だった。現在、地産地消を実施しているのはロイヤルホスト4店舗、シズラーで3店舗。導入している店舗の大半はサラダがビュッフェ形式で食べられる「サラダバー」を設置している店だ。生産者や食材が頻繁に変わることを考え、臨機応変に食材を使うことのできるサラダバーがもっとも導入しやすいようだ。ロイヤルホールディングス株式会社の城島孝寿広報室長は「本格的な取り組みはこれからです。課題は物流。地元の生産者と店舗をどうネットワークしていくか検討しなければならない」と話す。
◆2 物流体制を刷新、産地表示も本格化
ロイヤルでは新たな戦略に沿って、食材の調達方法、物流システム全体を大きく変えつつある。
同社では、食材や備品など社内で使う物品の物流システムについて、3年に一度見直しをしている。3年前までは、野菜以外の食材、物品は同社の物流センターから各店舗へ配送しており、鮮度が求められる野菜だけは20数社の仲卸に委託し、各店舗に配送してもらっていた。
しかし「健康」、「安心」を軸に、新たな顧客・マーケットを創出していくために、自ら産地を確保し、生産情報を詳細に把握している業者と取引する必要性が高まってきた。また、同社としてもトレーサビリティ体制を確立し、顧客に対し産地情報を伝えていきたいという計画を持っていた。そこで、社内で検討を重ねた結果、少数のサプライヤーに野菜を調達してもらい、野菜は物流センターに集め、そこから各店舗に配送するという体制にした。東京地区にある170店ほどのロイヤルホストについては、後述するデリカフーズ株式会社(以下「デリカフーズ」)と全国農業協同組合連合会茨城県本部(以下「JA全農いばらき」)がサプライヤーとなっている。
ロイヤルホストがもっとも多くの量を使う野菜はレタス、トマト、きゅうりである。なかでもレタスの使用量は多く、年間370トンほど使う。種類別では結球レタス(60%)、グリーンリーフ(20%)、ロメイン(20%)という割合だ。ロイヤルの購買部食材調達課の坂本憲彦課長は「サプライヤーとの値決めは、基本的には月ごとの固定価格で、前月に決める。量販店のように、1店舗あたりの使用量が多くないため、1ケースあたり○円というやり方ではなく、1kgあたり○円という決め方。アイテムによっては1個○円という決め方もある。レタスの場合、サイズは問わない」と話す。価格はいったん決めれば、原則的には変えないが、異常気象などで市場相場と乖離した場合は、若干の調整をすることもあるという。
ロイヤルホストでは2005年10月から全店舗で、使用する食材の産地表示をスタートさせた。ホームページ上では野菜、肉を含む主な22品目について生産県段階まで表示している。同年12月からは店頭にパネルでの表示もスタートさせ、さらに一部の店舗で、お客さんが生産情報を自由に検索できる画面も設置した。「顧客・生産者・サプライヤー・従業員との信頼関係作りを実現するために生産者表示をめざしたい。」と城島広報室長は話す。


◆3 産地との直接取引が過半
多店舗展開する外食業者の場合、自らが産地と直接契約して食材を仕入れるケースはまれで、ロイヤルのようにサプライヤー、あるいは仲卸を仲介させ、産地との調整はサプライヤーに一任されるケースが多い。サプライヤーは実需者のオーダーをとりまとめ、納品をする。産地が不作であってもオーダーを受けた以上、数量と価格に責任を持っている。従って、産地が契約取引に取り組みたいと思えば、まずサプライヤーと関係を持ち、彼らの期待に応えていくことが第一歩となる。ロイヤルに納めているサプライヤーのうちの一社、デリカフーズとある産地との関係を探った。
デリカフーズ(本社:東京都足立区)は、1979年の創業以来、外食・加工業者などに青果を卸している企業である。扱っているアイテムは350品目ほど。同社の特徴は主に3点ある。一つは顧客の80%近くをファミリーレストランチェーンが占めており、外食中心の中間業者であるという点。2つめは自社でカット野菜の工場も運営しているという点。3点目が卸業務だけではなく、産地と顧客を結ぶコーディネート役もしていることである。つまり、顧客にはメニューの提案、生産者には売れ筋野菜や野菜の成分分析に関する情報を提供する。さらに、大学などの研究機関と野菜に関する研究開発も行っている。卸業務は地域によって東京デリカフーズ株式会社、名古屋デリカフーズ株式会社、大阪デリカフーズ株式会社に分社化されている。2005年の売り上げは約200億円で、2005年12月には東証2部に上場した。
同社が扱う野菜は卸売市場からの仕入れが大半だったが、約2年前から契約による直接取引が過半となった。いまでは産直が60%、市場からの仕入れは40%という。
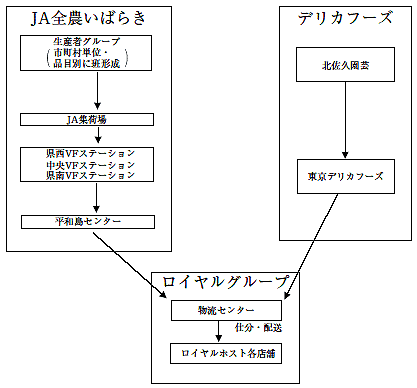
◆4 相場制の限界から産直取引にシフト
仕入れ先が市場から産直にシフトした大きな要因は、相場の乱高下というリスクを抱える市場からの仕入れでは、外食業者の求める定量定価での調達が困難だったためだ。
外食産業はメニューどおりの料理の提供が不可欠である。従って、市場相場がいくら高騰しても表示の価格で提供せざるを得ない。当然ながらサプライヤーにはオーダーどおりの数量を求め、相場に左右されない一定の範囲内の価格での調達を求める。そこで、相場に左右されない量を確保しようと、デリカフーズ自らが産地に入りこんで、大規模農家や農業法人などから直接調達できるルートを開拓していったのだ。
さらに2年ほど前から、外食産業が原料の産地表示の取り組みを強めたことが、産直へのシフトを後押しした。東京デリカフーズ仕入部担当者によると、「外食の世界では、代表生産者の情報開示だけでは満足してもらえない。完璧なトレーサビリティが可能な産地を探していったら直接取引にいきついた」という。
ただし、産直の比率が増えれば増えるほど、天候変動などによる不作時に予定通り荷が集まらないというリスクも大きくなる。そのため、同社は産直で仕入れる60%のうち、アイテムによっては伝票上、卸売市場を通す替わりに、不作時に荷を集めてもらうというリスクヘッジ策をとっている。入荷量の変動が激しいレタスなどをそのような仕組みにしている。
産直の場合、産地との値決めは月ごとの前決め。市場仕入れが多かった頃、同社は市場の値動きをアイテムごとに長年にわたって蓄積し、分析してきた。その結果、サプライヤーと産地の両方が納得できる価格をはじき出すことができるようになったという。ただし、天候など予知できない理由で過不足が生じた場合は、ロイヤル同様、後に若干調整することもあるという。
産直で仕入れる青果については、シーズン前に必要量をあらかじめ算出し、各産地に分散して作付けをしてもらう。産地は予定通りの数量を納めるために契約数量の20%増しで作付けするのが通常だという。仮に計画どおり収穫ができ、そのまま20%が過剰となった場合、デリカフーズの3社(東京、名古屋、大阪)間で調整をする、それでも過剰な場合は、カット野菜部門に回す。カット野菜用に契約した野菜が過剰となった場合はホール部門に回すこともある。収穫量が天候に左右されるのが農産物の常だが、調整する機能を社内で持つことは、同社にとっても強みであり、産地にもメリットになっている。
かつて業務・加工用需要への対応に消極的だった卸売市場が、一部ではあるが積極的に取り組むようになった。これは業務・加工用需要の流通が市場外で形成されつつあることへの危機感の表れだといえよう。
◆5 統一した肥料で特色ある野菜づくりめざす
デリカフーズが取引している産地の一つに北佐久園芸株式会社(以下「北佐久園芸」)がある。
同社(長野県北佐久郡)は1970年に北佐久園芸集荷センターという名称で産地卸の事業をスタート、1989年に法人化した。現在、取扱品目はレタス類、キャベツ、はくさい、だいこん、エリンギなどで、契約している県内の生産者組織は39組織(個人、出荷組合、グループを含む)。主な販路は外食・中食企業への直販(全体の40%)、スーパー・量販店への直販(同40%)、卸売市場(同20%)となっている。ただし、直販のうち約半分は卸売市場を間に入れ、過不足時の調整役をしてもらっている。売り上げは年々増加し、約6億5千万円である。
創業当時から実需者との直接取引をすすめてきた同社は、特色ある野菜づくりをめざしてきた。その一環として契約農家には、統一した肥料による肥培管理を指導している。肥料メーカーと共同で開発した有機肥料主体の肥料、さらに微量要素主体の特殊肥料の使用を推奨し、質の高い野菜には「収穫の朝」というブランドをつけて販売している。生産者からの買い取り価格にも品質評価を加えており、レタスの場合だと1ケースあたり400~500円の差がついてしまう。特に高値の場合1000円を超えるという。これに同社のマージンと流通経費などを上乗せして取引先に販売する。


◆6 実需者、サプライヤーとの信頼関係で販路拡大
同社とデリカフーズとの取引が始まったのは2年前。長年、取引関係にある地方市場大手、長野県連合青果株式会社(以下、「連合青果」)からの紹介だった。当時、連合青果は自ら帳合に入り、県内の野菜をデリカフーズに卸していた。しかし外食産業の産地表示への取り組み強化により、デリカフーズとしても生産者段階までトレーサビリティがつながる産地をさがしていた。その情報をつかんだ連合青果は、北佐久園芸の山本富士雄社長を伴って、デリカフーズを訪問した。
北佐久園芸はすでに別の外食企業との取引経験も豊富で、相場に左右されない固定価格での取引に理解を示したこと、自ら真空予令庫、冷蔵庫を持ち、鮮度管理をしていること、そして生産履歴が詳細に至るまでトレースできることが評価され、連合青果に帳合いをとらせる形で取引がスタートした。
現在、デリカフーズに出荷しているアイテムはレタス、サニーレタス、ロメインレタス、グリーンリーフレタス、キャベツ、はくさいの6アイテム。5月から10月にかけて約8トンを出荷している。
一方、長野県がシーズンオフになる11月~5月についても県外の契約産地から野菜を調達している。契約している産地は、九州、中国、近畿、東海、関東、東北とかなり広範囲にわたっている。長野県のシーズンに比べると出荷量は1/3ほどになるものの、この点はデリカフーズにとって大きなメリットとなっている。デリカフーズの仕入れ担当者は「従来、産地が変わると品質も変わるため、均一化するのに苦労したが、北佐久園芸さんのように産地リレーしていただけると栽培管理も統一され、品質のブレも少なくなる」と話す。
山本社長はデリカフーズとの取引に対し「高値で買ってもらうわけではないが、毎日決まった量が出て行くという点では安定した取引先」と話す。「また、市場で高値がつく中玉(レタスなら2L)ばかりが出荷できると限らない。デリカフーズは大玉でも小玉でもカット用に引き取ってくれる。カット用はホールに比べて価格は安いが、反収全体でみればアップするので生産者にはありがたい」(山本社長)
山本社長は、「自分から営業をしかけて取引先を増やした経験は一度もない。すべて紹介によるものだ」と語る。社長自ら実需者や市場関係者と頻繁にコミュニケーションをとることに力を注いでおり、信頼関係を築いたことが販路の拡大につながったのであろう。業界の動向が刻々と変わりやすい業務・加工需要に対応するには、最新の情報をいかに早く、正確に入手していくかということも契約産地には求められる。
◆7 JAがサプライヤー事業に進出
一方、東京地区のロイヤルホストが取引しているもう一社のサプライヤーはJA全農いばらきである。実需者と契約を結んで特定の品目を供給するJAは多いが、外食向けにサプライヤー事業を展開するのは、他に例がないといわれている。
サプライヤー事業は、同JA園芸部が1996年に発足させたVFステーション(直販を担当する集出荷施設。VEGETABLE &FRUITSステーションの略)が担っている。VFステーションを立ち上げた目的は多元化する流通に対応していくためだ。VF課の野崎和美課長は「当時、大型量販店の出店が加速化し、産地パッケージへの要望が高まってきた。また外食やコンビニの発展にともない、産地との直接取引が増えてきた。しかし高齢化した農家、小規模な兼業農家にとって、産地パッケージや直接取引に個別で対応するということは難しい。そこでVF事業を立ち上げ、選果選別・包装、および実需者への直販を専門的に行うVFステーションを立ち上げた」と話す。VF課では売り先によって青果の買い取りと委託販売を併用している。
VF事業は順調に売り上げを伸ばし、2005年の販売高は103億円。園芸部全体の販売高(約780億円)の1/8以上を占めるまでになった。現在の主な販路は生協向け(30%)、量販店向け(30%)、業務・加工向け(30%)、その他(10%)となっている。ステーションは県内4カ所、東京に1カ所あり、合計19人の営業マンが実需者向けの営業活動を行っている。
VF課では5,6年前からロイヤルに野菜などを供給していたが、あくまで当時のサプライヤーに納める一産地であり、供給品目も限られていた。そうした関係が変わったのは、前述したようにロイヤルが3年前に行った物流システムの見直しがきっかけとなった。
ロイヤルが同JAをサプライヤーとして選んだ理由について、前述のロイヤル食材調達課の坂本課長は「サプライヤー事業にたいへん意欲的だった。また仕分け作業については生協ですでに実績を積んでいた。全農のもつ全国的ネットワークへの期待も大きかった」と話す。
同JAは2003年より、生協の委託で共同購入商品の仕分け事業を実施しており、後には生協の店舗向けの仕分け事業も加わった。そうした実績も認められたようだ。
◆8 安定供給には小グループ制が有効
「しかし選ばれたからといってどこでも始められるものではない。まず、仕分けする施設を消費地におくことは絶対条件だった」と野崎課長。受注から納品までの時間が限られているからだ。このため同JAは東京・平和島に新たなセンターを設けた。
サプライヤー事業が始まったのは2005年10月。東京地区にある170店舗のうち、同JAが食材調達を任されている店舗は70店舗強。店舗から同JAにオーダーが入るのは毎日18:00。即座に店舗ごとに仕分けをした上で、24:00までに千葉県にあるロイヤルの物流センターに届ける。6時間という短い時間で業務を完了させなければならないうえ、注文に応じるには茨城県産の野菜だけでは間に合わず、どうしても各地から荷を集めやすい消費地に拠点を置く必要がある。さらに作業の効率化のために、曜日ごとのおおよその必要量を見込みで準備しておくという。
東京の拠点づくりとともにサプライヤーに求められる機能は、なんといってもオーダー通りに安定供給することだ。このことを産地や個々の生産者にいかに理解してもらうかが、サプライヤーとしての評価につながる。
VF課では、10年間にわたる契約取引の経験から、安定供給していく体制を作り上げたという。それが“小グループ制”だ。野崎課長によると「大規模なグループだと市場が高値の時に市場に出してしまうケースも起こりやすい。最初から気心が知れ、信頼関係で成り立つ小グループをつくった方がいい」という方針のもと、単協とともに生産者を募集し、5~20人までの小グループをつくった。JA青年部、集落、旧単協単位、農業生産法人などが母体になっている。契約取引にこれから乗りだそうという産地にとっては参考になる手法だろう。
レタスを例にあげると、外食産業向けには結球、サニー、グリーンリーフ、フリル、ロメインを供給しており、小グループは品種、地域によって15に分かれている。このグループで春と秋のレタスを供給する。ロイヤルとの値決めは月ごとだが、生産者とはシーズンごと、つまり2ヶ月で一本の価格だという。
VFステーション全体ではレタスを日量約5000ケース扱っており、そのうちロイヤルにいくのは30~100ケース。一方、茨城県産がシーズンオフになる夏は岩手県産、冬は九州産をVF課が調達して納める。
◆9 川中産業進出によるメリット
野崎課長は「数量と価格に対する責任を負っている以上決して楽な業務ではないが、それを上回るメリットがある」という。野崎課長が指摘するサプライヤーとしてのメリットは次の3点。
まず、川上産業から川中産業に入ったことで情報の量と質が大きく変化した点だという。「実需者がなにを求めているか、生の情報が入るだけでなく、競合産地の状況もわかる」(野崎課長)。
次に、そうした情報をスピーディに産地に落とし込み、生産に反映させることができる。場合によっては競合産地でつくっていたものを自県産に切り替える可能性もある。「そうすれば、シーズンによって10~20%という自県産比率をさらに高められるだろう」と野崎課長は期待している。
3点目が、実需者と密接な関係を構築できたことで、いままで知り得なかったノウハウが蓄積されたことだという。「ロイヤルの担当者と会議や商談を重ねるうちに、営業担当者の資質が向上したように思う。そのほか、平和島のステーションを運営するなかで、品質管理の手法、効率的な仕分けの方法、マーケティング手法も身についてきた」と野崎課長。
一方、今後の課題は、予定通りの数量が集まらないといったリスクをどう回避するかだそうだ。これは同JAに限らずすべてのサプライヤーに共通のテーマだろう。しかし、野崎課長は「全国組織であるJAの強みを生かし、他県のJA全農の直販事業部門と情報交換をするなど連携を深めることで打開策を見いだしていきたい」と話す。
実はこの点に対し、ロイヤルの期待も高く、前述のロイヤルの坂本憲彦食材調達課課長は「いちごは年間安定して調達するのが難しいアイテムだが、JA全農いばらきと他産地との連携で安定的に調達できた。こうしたネットワークをさらに活用してほしい」と話している。
ロイヤルがすすめようとしている「地産地消」の導入についても「JAが各地で運営する直売所と連携を組み、供給体制を作っていくこともできる。JAが持っている有形無形の財産を活かしてビジネスチャンスを広げていきたい」と野崎課長は期待を込めて話す。
産地情報の公開、質の高い野菜の調達、「地産地消」の取り組み、という新たな戦略に対応していくには、自ら産地を確保し、生産情報を把握している業者と取引する必要性が生まれてきた。「いい食材を使えばそれなりのコストがかかるのは当然。だが物流と情報の仕組みを変えれば、質のいい材料が低コストで手に入る。品質とコストはトレードオフではない」─梅谷執行役員のこの考えにもとづき、ロイヤルは生産者やサプライヤーとの更なるパートナーシップの強化に乗り出している。
◆ まとめ
契約栽培を通じて外食業者向けに食材を供給するにあたり、産地に求められる要素をまとめるとすれば次の4点になるだろう。
①安定供給していくための体制作り
②トレーサビリティの仕組み作りと有効な運営
③実需側の関係者とのコミュニケーション④過不足の際のリスクヘッジ策
このなかで懸案となるのは①と④が背中合わせの関係にあるという点だろう。安定供給に応えていくということは、産地は必ず過不足のリスクを抱えることになる。北佐久園芸は多様な販路を持ち、卸売市場も活用することでそういった問題を解消している。
食の外部化比率は高まっており、産地として業務・加工需要への対応は欠かせないとはよくいわれることだ。しかし、産地の立場から見ると「足らなければどうするか」、「過剰になればどうするか」という課題にすぐに直面することになる。
外食向けのサプライヤー事業という新たな分野への進出で注目されるJA全農いばらきだが、「実需者の要望に沿った産地作りと、従来の卸売市場を重視した産地づくりの2つの軸をもとにした販売戦略は今後も変わりはない」と野崎課長は断言する。おそらく、契約栽培に取り組もうという産地であれば、リスクを最小限にとどめるという点からも、“直接取引”と“卸売市場出荷”という2本の軸を持たざるを得ないだろう。一方、野崎課長が「サプライヤー事業を通じて得られたさまざまな情報やノウハウを、卸売市場重視の産地づくりにも活かしていけると思う」と指摘するように、2つの機能を相互に活かすことで、産地の底上げにつながるだろう。
「卸売市場にさえ出荷していればお金に替わる」という時代ではなくなった。実需者の期待に応えつつ、販売全体のバランスをとっていかにリスクを減らすかが、これからの産地にとって重要な戦略の一つになっていくだろう。