 専門調査報告
専門調査報告
パプリカ生産における国内・外の生産・流通の変化
愛媛大学農学部 資源・環境管理研究室 教授(前農林水産政策研究所 地域振興政策部) 香 月 敏 孝
農林水産政策研究所 地域振興政策部 柳 京 熙
野菜の輸入量が増加している中、一部の品目においては価格競争などにより、国内生産の縮小も余儀なくされている。
パプリカの場合も、韓国産、オランダ産といった外国産パプリカの輸入量が総消費量の9割を占めている。しかし他の野菜生産とは違い、むしろ外国産パプリカによって新しい需要が創設され、その市場に日本の産地が参入しているような形態である。したがって他の野菜生産・流通とは違う様相をみせているが、まだその現状については明らかにされていない。
本稿では、統計データや事例分析を行い、パプリカ生産・流通・輸入を取り巻く国内・外の現状について検討し、今後の国内パプリカの生産拡大・可能性を探る。
1.パプリカの生産・流通の概況
(1) パプリカの区分について
未熟な緑色のピーマン以外の赤色、黄色、橙色等のカラフルな完熟型のベル型ピーマンをカラーピーマンといい、そのなかでも肉厚の甘い品種がパプリカであり、ジャンボピーマンとも呼ばれる(農村漁村文化協会『農業技術体系野菜編5』、追録第30号・2005年)。
しかし、第1表に示したように、カラーピーマンの形状をベル型以外も含め、かつパプリカとジャンボピーマンとを区別した分類が行われる場合もある。厳密には、こうした分類になると考えられるが、国内でのカラーピーマンの生産が僅少であることもあり、生産、流通上の統計では、しばしば、パプリカとジャンボピーマンとは同一の品目群として掲上されることが多い。例えば、農畜産業振興機構編『野菜輸入の動向』での輸入品目区分では「ジャンボピーマン」としているが、そのほとんどは「パプリカ」である。また、農林水産省野菜課「地域特産野菜の生産状況」の区分「パプリカ」は、「ジャンボピーマン等をいう」としている。
本稿の記述については、一応、第1表に示した分類を基礎にしながらも、統計上の扱いについては、それぞれの区分にしたがっている。

文化協会『農業技術体系野菜編5』、追録・2004年)から作
成。
(2) 国内生産の概況
パプリカは、近年消費量が増加しているものの、需要の大部分に対応しているのは輸入品であり、国内生産は僅少である。このため、パプリカの国内生産について、その実態を示す資料は、多くはない。まず、既存のデータにより、おおよその国内生産規模を把握すれば、以下のようになる。
農林水産省野菜振興課「地域特産野菜の生産状況」の平成10(1998)年産調査において、パプリカは初めて調査品目となり、その後の平成12(2000)年産、14(2002)年産とあわせてこの3年分については、総体としての国内生産規模を把握することができる(同調査は、隔年で実施、平成12年産からは野菜課から刊行)。その結果を示したのが第2表である。
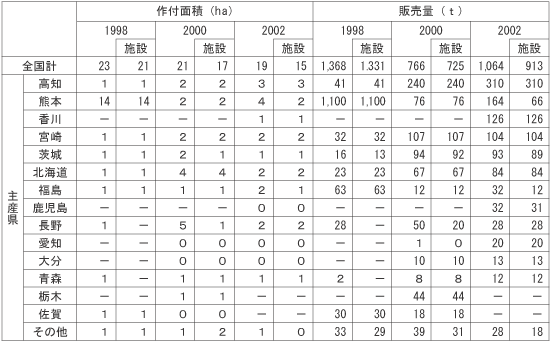
1998年産の作付面積は、23ha(うち施設栽培21ha)、販売量は1,368トン、2000年産は、21ha(同17ha)、766トン、2002年産は19ha(同15ha)、1,046トンとなっている。つまり、この間の国内生産は、作付面積が20ha程度、販売量が1,000トン程度とみることができる。なお、先に指摘したように、この数値にはジャンボピーマンを含むほか、1998年産の熊本県産には、パプリカ、ジャンボピーマン以外の第1表の「小型ピーマン」を含んでいるとみられる。いずれにしても、後にみるように、2万トンを超えるパプリカの輸入量と比較し、その国内生産が極めて少ないことがわかる。県別にみれば高知、宮崎、茨城、熊本といった県での生産が多いが、2002年産の場合で、最大の高知でも生産面積3ha、販売量310トンの規模である。またそれぞれの県で生産を担っている市町村を第3表に示したが、年次による入れ替わり変動が大きく、いわゆる主産地の形成が、順調に進展していない状況をあわせて見て取ることができる。
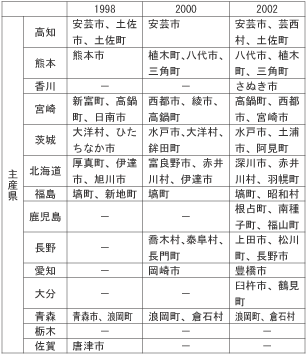
次に、部分的ではあるが、主要な卸売市場での出回り量からジャンボピーマンの生産動向を窺い知ることができる。第4表には、東京都中央卸売市場と大阪府内の中央卸売市場(大阪市および大阪府中央卸売市場)におけるジャンボピーマン(この場合もパプリカを含む)の2000年から2004年にかけての出荷県別の入荷量の推移を示した。

これでわかるように、この間の国産入荷量は、それぞれ東京都中央卸売市場では、1,005トンから1,270トンへ、大阪市・大阪府中央卸売市場では227トンから374トンに増加しており、国産シェアはそれぞれ、30%台と20%台で伸び悩んでいるものの、両市場出荷に向けての国内生産は拡大基調にあることといえる(両市場合計のジャンボピーマン入荷量は、1,200トン程度から1,600トン程度に増加)。県別の入荷量からみれば、両市場とも高知県が最大であり、次いで東京都中央卸売市場では、茨城県、千葉県が、大阪市・大阪府中央卸売市場では、広島県、宮崎県がこれに続く。
ところで、両市場合計の年別の入荷量と前掲第2表に示した販売量とを比較すれば、2000年、2002年とも入荷量が販売量を上回っている。これは、卸売市場流通については東京、大阪以外の卸売市場での入荷量があること、また市場外流通量も相当程度あると見込まれる中で、卸売市場の流通量が生産サイドの販売量を上回るという不整合な数値となっている。この点については、卸売市場統計の方が、集計の範囲を広くとっている、あるいは地域特産野菜調査の補足率が低いといった可能性が考えられるが、その詳細は把握できない。なお、この点に関連して、2001年のパプリカ生産量が2,000~3,000トンとの推計もあり、地域特産野菜調査の2~3倍の数量となっている(資料:橋本文博「パプリカの売り方・育て方」、『農薬ガイド』No.101、2002.4、アリスタライフサイエンス株式会社)。
しかし、こうした数量での差異はあるものの、やはり、国産パプリカの生産量は、圧倒的な輸入量と比較して、僅少であることには違いがない。
(3) 輸入パプリカの動向
パプリカは、オランダからの生鮮品輸入が解禁された1993年以降に急速に輸入が増加したといわれている。貿易統計上でピーマンのうち「肉厚大果のもの」(一般に1個当たり重量が100g超)が区分されたのは2000年からであり、それ以降についてのパプリカの輸入動向は把握することができる。
それ以前には、生鮮とうがらし等を含む「ピーマン等」の区分に一括されており(正確には「とうがらし属又はピメンタ属の果実」という)、詳細は明らかではないが「ピーマン等」の輸入量は、1994年の1,365トンから一貫して増加し、1998年、1999年にはそれぞれ8,807トン(対前年増2,984トン)、11,185トン(同2,378トン)となっている。98年、99年の伸びが特に大きくなっているが、この増加のほとんどをパプリカが占めていると考えられる。
2000年以降のパプリカ輸入の動きについては、第5表に示したとおりである。2000年には、10,326トンの輸入のうち、オランダが60%、韓国およびニュージーランドそれぞれが20%程度の割合であった。それが2001年には、前年のほぼ倍の19,655トンに増加しており、その増加分のほとんどは韓国によるものである。すなわち、韓国からの輸入は2000年には、2,000トン程度であったものが、2001年には、11,000トン程度にまで増加し、輸入量の56%と過半を占めるに至る。
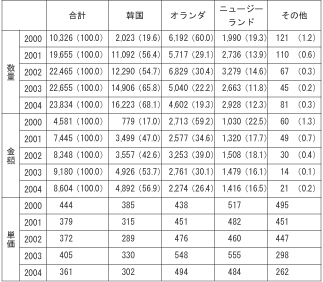
資料:財務省『貿易統計』
2001年に韓国の対日輸出攻勢が本格化したことになるが、その後も、輸入総量が22,000~23,000トン程度で推移する中にあって、韓国からの輸入は2002年12,290トン2004年16,223トンと着実に増加している。一方で、オランダは、2002年の6,829トンをピークに2004年には4,602トンまで減少、同じくニュージーランドも2002年の3,279トンをピークにしてその後3,000トンを割り込んでいる。こうして2004年の国別割合は、韓国68%、オランダ19%、ニュージーランド12%となり、韓国1国で7割近くを占めるところとなっている。なお、オランダ、ニュージーランドからは、航空機、韓国からは船舶コンテナによる輸送が中心となっている。
次いで、輸入量の月別の変化みたのが、第1図である。まず、2000年の国別の輸入量については、1月から3月まではニュージーランド、6月から11月はオランダが過半をしめ、4月、5月には、韓国、オランダ、ニュージーランドがシェアを分け合っている。つまり、冬期はニュージーランドが、夏秋期はオランダがそれぞれ中心となり、韓国はこの両国からの輸入の狭間となる春期を主体に輸出していたことになる。
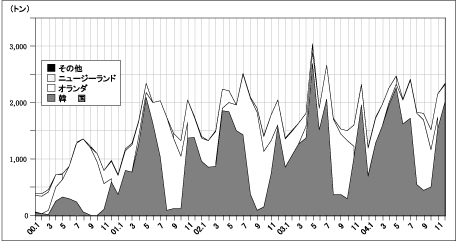
ところが、2000年の12月には、韓国の割合が61%と過半を占めている。それ以降、韓国の輸出が目立った増加を示し、2001年の7月まで引き続き過半を占めている。こうした傾向が最近まで継続しており、韓国の輸出時期と重なるニュージーランドは1月については韓国に次ぐシェアがある(2004年には40%)ものの、2,3月には2割程度に落ち込んでいる。一方、オランダについても、韓国が輸出期間を延長していることから、過半を占める月は、はぼ7~9月の3ヵ月に限られるに至っている。さらに、韓国では、2003年から周年出荷体制を整え夏期の輸出にも力を入れるようになり、2004年には7~9月のシェアを3割程度占めるまでになっている。
ところで、これら3国の輸出品目としてのパプリカの生産をめぐる状況は、以下のようになる。
まず、オランダでは、パプリカはガラス温室による施設園芸のメジャー品目であり、国内生産の大半が輸出向けとなっている。年間20万トンを超える輸出のごく一部5,000トン程度が日本向けとなっている。オランダからの輸出は4月から10月が中心であるが、日本向けは高価格が期待できる夏期に集中していることは既述のとおりである。
また、オランダ統計庁のWEB MAGAZINE(2005年10月25日)によれば、オランダでは、過去25年(1980~2004年)でパプリカの収穫量は10倍に増加した。これは、栽培面積および単収の増加によるもので、この期間に栽培面積は200haから1,200haに、同じく10a当たりの単収は15トンから26トンに増加した。収穫量は、1990年代での増加が大きいが、色別にみれば赤色と黄色の増加が著しい(かつて多かった緑色は1990年代前半に頭打ちとなり、それ以降は漸減)。また、2004年のパプリカ生産者数は559戸であり、1戸当たりの面積は2.1haである。生産者のうち、単一色の生産者が90%(赤色が最も多く42%、次いで緑色22%、黄色18%)であるが、赤色+黄色、赤色+緑色+黄色といった複数色の生産者の平均栽培規模は4haを超えて大きい。
韓国の場合、1990年代の施設野菜作の伸長は著しく、パプリカもその拡大の一環をなしている。しかし、ほとんどの施設野菜作が韓国国内需要向けである中で、パプリカについては、唯一輸出に特化し、しかもそのほとんどが日本向けである点で、極めて特異な性格をもっている。韓国農産物流通公社のパプリカ国内情報(2005年8月5日)によれば、パプリカの2004年の生産量20.6千トンのうち日本への輸出はその85%に当たる17.4万トンに達している。パプリカは1995年に輸出用として本格的な栽培が開始された(面積は1.1ha)。その後、施設野菜の中でも最も所得が高いとの認識が高まり、作目転換を中心に拡大し2004年には260haにまで増加している。また、10a当たりの単収は15トン程度であり、後述する日本と比較して高水準となっている。これは韓国のパプリカ作の一部がオランダ式ガラス温室によるものであり、ビニールハウスの場合でもガラス温室同様に軒高の高い施設による生産が多く、総じて日本よりも施設設備が高度であるためと考えられる。
また、ニュージーランドの場合は、輸出農産物の大宗を占めるのは畜産物であり、園芸品目の割合は14%(2004年)にとどまっている。園芸品目の中でもキーウィ、リンゴ、たまねぎ、かぼちゃといったところが主要品目で、パプリカは主要輸出品目とはいえない状況である。このため、生産実態が把握できる情報は少ないが、ニュージーランド産パプリカを輸入している日本国内の貿易会社のホームページによれば、同国でのパプリカ生産は軒高が5mもあるガラス温室で行われており、コンピューターによる環境制御も導入されているとしている。
以上のように、これらの輸出国におけるパプリカ生産は、オランダ、ニュージーランドの場合は、施設規模の大きな企業経営によって担われていることになる。韓国の場合も一部は雇用を多数かかえた企業的経営が展開している一方、日本同様に家族労働力を主体とした小規模な経営もあわせて存在している。
いずれにしても、この3国とも日本と比較して生産性が高いパプリカ生産を行っており、これらの国からの輸入増加によって日本国内での需要が拡大されたといえる。こうした中、国内生産の拡大の可能性も広がっていると考えられるので、次に我が国のより具体的な実態について見ていくことにしよう。
2.国内生産の実態─茨城、高知の事例─
ここでは、前掲第2表に示した主産県のうちから、対照的な生産形態をとっている茨城と高知の事例について、実態調査に基づき紹介していく。
両者の特徴については、第6表に示したとおりであるが、茨城の事例は、水戸市においてガラス温室で雇用労働を入れ、企業的な生産を行っている有限会社A社であり、JA高知春野(春野町)のそれは高知県園芸連と連携し従来型の家族労働による施設野菜作の一環として取り組んでいるB生産者グループの事例である。
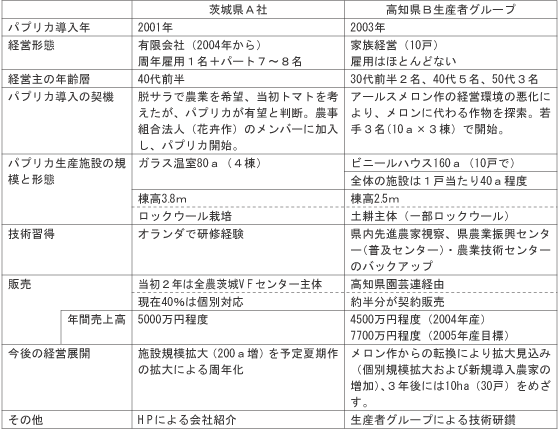
両者はパプリカ生産の拡大を模索している点では共通している。パプリカの主産国オランダや対日輸出を戦略的に展開している韓国と比較して、日本での生産条件は必ずしも良好ではないと考えられる中で、そのハンディをいかに克服しようとしているのだろうか。
まず、パプリカの栽培技術の特徴を整理しておこう。パプリカは果実を主枝に結果させて収穫するため、施設の軒高が高い方が有利である。加えて、パプリカの栽培適温帯は狭く(茨城県A社によれば最低気温18℃に対して最高気温25℃)、温度管理が重要となる。このため、高度な施設の整備が必要となり、ガラス温室等の大型の施設が有利性をもつ。つまり、スケールメリットを生かした規模の大きな、したがって投資額も大きい施設園芸作としてのパプリカ生産が求められるということになる。オランダはまさにこうした生産方式によっており、韓国の場合もかなりの部分はそうした条件を満たしていることになる。
また、日本の場合、─韓国も同様であるが─施設栽培では夏期の温度が高すぎるために、この時期の生産は難しい。一方、オランダではむしろ夏期の生産量が多く、春から秋にかけて長期間の生産を実現している。
このような条件下で、施設規模の大きな経営を目指しているのがA社であり、既存のビニールハウスを利用し単収を上げる技術の確立をめざしているのがB生産者グループといえる。以下、2つの事例ついて詳しくみていく。
(1) 茨城県A社の取組
A社の代表取締役H氏は、元農業団体職員である。在職中から農業生産に強い関心を抱き、退職後、2000年に新規就農した。当初トマト生産も考えたが、輸入が急増しているパプリカが有望と判断した。同氏は経営不振に陥っていた農事組合法人(バラ生産)のガラス温室施設を継承し、2001年にパプリカの生産を開始した。栽培技術の習得のため短期ではあるがオランダに技術研修にも行った。経営は2年目までは赤字であったが、3年目からは黒字に転じ、5年目には過去の累積赤字も清算することができた。そうした過程で、2004年には組織形態を有限会社に変更した。同年産の販売額は5,000万円程度である。
当初は土耕で栽培していたが、土壌病害(青枯病)の連作障害が生じてきたこと、生協の取引条件として土壌消毒が不可である点を考慮して、有機培地を使用した養液栽培に転換した。また、天敵を利用した防除にも努め、化学農薬の施用量を1/3にまで減らした。こうした取組を経て、A社は2004年に県からエコファーマーの認定を受けた。
A社の施設規模は80a(20a×4棟)で、もともとバラ栽培用の施設であるため棟高が通常より高く3.8mである。3棟で赤色、1棟で黄色のパプリカを生産している。赤色を生産している棟では一部橙色も生産しているが、橙色は全体出荷量の5%程度である。温室棟の中央に、選果施設が設置されている。
労働力は、H氏夫妻と20歳代の常用雇用1名のほか、パートが7~8名である。常用雇用者がほぼ作業全般をこなすことが出来るまでになったので、H氏は主に販売を担当している。
販売については、当初の2年間は、全農いばらき県本部の直売部門であるVF(ベジタブル・フルーツ)ステーションに依存していたが、価格の変動が大きいこともあり、現在では6割をVFステーション向けとし、4割を独自に販売している。独自販売のうち量販店が3~4割、生協が1割、残りが外食などの業務筋である。量販店の中には高級食材を扱うスーパーも含まれており、今後も国産品として高めの価格設定をしてくれる販路を開拓したいとしている。
A社は4kg箱で出荷しているが、輸入品と比較した相場感として、国産品の安全、安心という優位性から、輸入品の5Kg箱と同程度の価格であれば良いと考えている。
さて、A社では今後の経営展開について、施設規模を2ha増設する大幅な規模拡大を検討している。その背景としては、現在、地元スーパーと取引しているが、同チェーン120店舗中わずか5店舗で販売されているに過ぎず取引数量増加を要請されているという実情がある。また、2004年から開始した学校給食向けは、数量的にはまだまだ少なく全体の数%であるが、地産地消、食の安全、安心の観点から、今後伸びる可能性が強いとみている。このため、小学生の見学を受け入れるなどの取組も実施している。こうしたことから、現在の年間販売量80~100トンでは需要に十分に応えきれていないと判断している。
また、施設規模の拡大とあわせて販売の周年化をも目指したい。現在の出荷期間は、11月下旬から7月上旬までであり、夏季の出荷を行なっていないが、パプリカの価格はサラダ需要が多い夏季が高い。
こうした規模拡大をめざす理由には、オランダで開発された生産方式はスケールメリットが大きいということもある。自動環境制御のための設備を装備するには、施設面積3haは欲しいとしている。
これと関連し、A社の経営理念として、敬遠されがちな農業に対するイメージを払拭し生産性の高いビジネスとしての農業をめざしているとのことである。同社のHPによれば、「これまで、日本の温室野菜生産の多くは、生産性・労働・収穫量などから『家内制手工業』の域を脱することができませんでした。しかし、マニュファクチュア化されたオランダの温室農業技術を導入すれば、生産性の高いビジネスとして構築することができます。」としている。
以上のように、きめ細かい国産パプリカ需要への対応を図りながら、あわせて高い収益性の確保を目指しているのがA社であるといえる。
(2) 高知県での取組─JA高知春野B生産者グループを中心に─
1)高知県園芸連における取組
高知県園芸農業協同組合連合会(以下、高知県園芸連)は、高知県園芸品目(青果物、花き)の農協系統共同販売の中核となっている組織である。まず、高知県園芸連におけるパプリカ生産・販売の実態をみておく。
同園芸連を通じたパプリカの販売は2000年に始まり、その生産量は第7表に示すように、2003年度(前年9月~8月)の出荷量が、242トンであった。翌2004年度には255トンに増加したが、その後は2005年度の255トンまでほとんど増加していない。

資料:高知県園芸連
2005年度の栽培面積は407a、販売額1億円程度である。これが、2006年度(2005年9月からの出荷)計画では栽培面積が538aとなり、前年より130aほど増加、栽培戸数も前年の28戸に対して、38戸となり、ごく最近になって、パプリカ生産増加の兆しがみえるものとなっている。
また、2003~2005年度のパプリカ販売を月別にみたのが第2図である。主に12月から7月での出荷販売となっており、この時期は施設の加温生産が主体である。その他、夏秋期の出荷も若干あるが、これは、高冷地での雨よけ生産も一部実施しているからである。
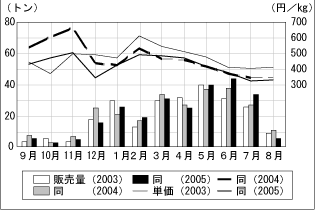
資料:高知県園芸連
なお、高知県園芸連では、パプリカに先行して、通常ピーマンを完熟させた赤ピーマン、パプリカよりは小振りで果肉が薄いジャンボピーマンの販売を行ってきたが、これらの品目は需要が伸び悩んでいる。この点で、パプリカは輸入が主導して国内市場を開拓し、引き続き需要増加が見込まれると判断している。高知県では施設野菜作が全般的に落ち込んでおり、生産縮小品目に代わって、振興すべき園芸品目の1つとしてパプリカが位置づけられるところとなっている。
2006年出荷に向けて、生産拡大に意欲的なのが次にみるJA高知春野である。
2)JA高知春野での取組
JA高知春野は吾川郡春野町を管内とする農協である。高知県の施設野菜作は、1960年代までは、きゅうりが中心であったが、70年代以降にはそれぞれの地域において様々な新規品目の導入による品目分化が進行し、県全体として著しい多品目生産へ移行してきた。そうした中で、春野町の中心品目は一貫してきゅうりであり、それに次ぐ品目がメロン(アールス)である。
現状での農協管内の園芸用施設面積は172ha、農家数585戸(品目別生産戸数の延べ合計)である。このうち、きゅうりが62ha(246戸、1戸当たり23a)、メロンが46ha(89戸、1戸当たり53a)であるから、この2品目で施設面積の62%を占めている。これに続くのが、トマト14ha(29戸)、春鈴なす13ha(53戸)となっている。
きゅうりは1990年の98ha(350戸強)、メロンは1991年の80ha(150戸程度)が、それぞれ生産のピークであり、その後減少傾向にある。このうち、きゅうりの減少は、施設作からの完全撤退がほとんどであるのに対して、メロンの場合には比較的大規模農家が多いこともあって、メロン作に代わる品目の探索が行われている。
メロンは近年、需要減退が大きいうえ、冬期の最低設定温度が20~23℃と高いために加温重油のコストが嵩む品目である。特に2005年には重油高となるとともに例年にない冬の低温に見舞われて、一層のコスト高とならざるを得なかった。このため、設定温度がより低く、比較的広い施設面積を活かせる品目が求められた。
パプリカへの転換は、若手農家3名のチャレンジによって開始された。高知県農業技術センターでパプリカ圃場を見学し、これらなら出来ると判断したという。さらに、農協では彼らを連れて県内で先行してパプリカを導入している農家(安芸地域)を訪問し話を聞く機会を設けた。こうして、2003年(高知県園芸連の年度では2004年度の生産・販売)に3戸の農家は、それぞれ1棟10aづつをメロン作を転換してパプリカを導入した。パプリカ栽培が3年目になる2005年には10戸、1.6ha程度にまで拡大した。全員がメロン農家であり、施設の一部をパプリカに転換している。経営主の年齢は、30歳代前半が2名、40歳代が5名、50歳代が3名であり、青壮年層が中心となっている。前年2005年度(2004年9月~2005年8月)のパプリカ販売実績は、赤色86トン(3500万円)、黄色25トン(1000万円)であったが、2006年度にはその1.7倍を見込んでいる。
また、農協によればパプリカを導入していないメロン作農家についても、特に若い生産者はパプリカ作への関心が強く、先行作農家の経営成果が順調にあがっていけば、3年後には30戸、10ha規模の産地となることも考えられるとしている。
ところで、同JA管内の施設野菜作農家は、全体として家族労働力のみの農家が80%程度を占め、残りも1~2人の臨時雇用程度となっている。また、施設の軒高は2.5m程度である。
パプリカ導入農家も、家族労働力を主体とした生産である。また、既存のメロン作用のビニールハウスを利用しており、必ずしもパプリカに良好な施設環境とはいえない。販売は農協系統組織に依存しており、パプリカ生産農家はもっぱら反収向上に力をいれている。
現状では、10a当たりの収量は、一般的な土耕栽培で10トン程度、一部導入されているロックウール(養液)栽培で12トン程度であるが、これをそれぞれ12トン、14トンに引き上げる取組みが行われている。10a当たりの収量が10トンの場合、農家の販売手取り額は330~350万円(所得率は46~48%)になるが、12トンを達成すれば400万円程度が期待できることになる。
同地区では、生産者間での栽培技術に関する情報交換のほか、定期的に県農業技術センターや農業振興センターの指導を仰いでいる。こうした背景には、県農業技術センターによる多収技術の開発の成果がある。同センターニュース(37号、2004年10月)によれば、「当センターでは、パプリカの養液栽培において、軒高の低いハウスでも、主枝を摘心しないつる下げ誘引仕立てと、密植(370株/a)により、スペシャル(赤色品種)で16t/10a、フェエスタ(黄色品種)では20t/10aの収量が得られる技術を開発しました。(中略)土耕栽培においても、つる下げ誘引仕立てでは、慣行の摘心仕立てより上位収量が45%も多くなります。」としている。こうした技術の積極的な導入に向けて、生産者組織と県が一体となった取組が行われていることになる。
既に、当地区でも養液栽培で単収14トンをあげた生産者がおり、こうした生産者の場合にはさらなる反収向上をめざしている。
次にこの産地の販売対応についてみてみよう。販売は全量が農協高知県園芸連を通じた系統販売となっているが、このうち、約半分が名古屋、東京市場を中心とする卸売市場向けであり、約半分が契約による出荷販売となっている。契約販売は、2つのルートがあり、いずれも京浜地域の量販店向けの販売である。1つは仲卸を通じ、もう1つは納め業者を通じている。後者の場合は、個包装(高知県園芸連の集配施設で対応)で、色別割合を赤色6、黄色3、橙色1とする出荷であり、個人番号を添えた生産履歴を送付するなどのきめ細かい対応を行っている。こうした契約販売を実施するため、2006年度からは橙色のパプリカを充実させる予定となっている。
以上のようにパプリカの生産、販売の体制が整いつつある中で、産地の拡大意欲は高いものがある。仲卸経由の契約販売では対応できる量の倍の引き合いがあり、名古屋市場向けでは学校給食用の引き合いも強いといった国産需要の高まりがあることも、その背景にある。
また、パプリカ国内流通量の90%以上は輸入であり、オランダは市場価格が下がれば輸出量を減らして価格復元を図るという価格調整を行っている。このため、国内産地としては当面、出荷量の増加による値崩れを心配することはないと判断している。いずれにしても、同農協では、現状の卸売価格400円/kgというパプリカ市況が継続すれば、パプリカへの転換は進むと見込んでいる(価格の推移は前掲第7表、第2図参照、なお、当産地の出荷期間は12月上旬~翌7月上旬)。
ただし、前提となる価格水準が今後どのようになるかは、オランダよりもむしろ大きなシェアをもっている韓国の出方が問題となるといえよう。
おわりに
以上、日本のパプリカ生産・流通の概況をはじめ、韓国を中心とした対日輸出国におけるパプリカ生産・流通をめぐる状況について検討した。
日本におけるパプリカの消費は、本来輸入によって促進・定着してきた経緯があり、国内生産は、輸入によって創られた市場に遅れながら参入した格好となっている。そのうえで、国産との希少性と商品特性によって輸入品より有利な価格形成を行っている。
これに対し、輸入パプリカはいまや韓国産が総輸入量の7割近くを占めるまでに拡大している。韓国は国内にほとんど需要がなく、その生産は日本の消費動向に強く影響されている。
その韓国の動きをみると、これからも日本の需要は増加すると見込んでいるのか、韓国国内のパプリカ生産に対する投資は依然として活発である。したがって韓国からの輸出攻勢はしばらく続くと思われる。しかし一方、韓国の先進産地においては、対日輸出の経験を生かし、台湾、アメリカをはじめとする、輸出先の多角化を図る動きがある。同時に、国内向けの供給も本格的に展開しようと模索中である。
ただし、最近起きた残留農薬の問題から見て取れるように、生産の拡大に見合う産地体制の構築はかならずしも十分ではないと考えられる。
これらの状況を踏まえてみると、今後、日本国内の戦略と体制如何によっては、生産の拡大の可能性も十分にあるようにみえる