 専門調査報告
専門調査報告
かぼちゃ輸入の今日的状況と 国内産地の動向
東京農業大学 国際食料情報学部
教授 藤島 廣二
本稿では、かぼちゃを対象に、以下の点の究明を試みることにしたい。
第1にかぼちゃの輸入がこれまでどのように推移し、今後どうなる可能性が高いか、換言すれば輸入動向の変化とその要因の解明である。
第2に国内産地の生産・出荷量がどのように変化したか、またどのような輸入対策が実施されたか、産地の輸入対策に関する特徴点の解明である。
はじめに
野菜の輸入量は最近では生鮮品と加工品(生鮮換算数量)の合計で400万t近くにのぼり、国内の野菜総消費量の約20%を占めている。しかも、輸入は特定の品目に片寄る傾向が依然として強いために、ごく少数の品目でとりわけ輸入量が多く、消費量に占める比率も高い。そうした品目の一つがかぼちゃである。
例えば2003年のかぼちゃの輸入量は14万tで、これはたまねぎに次いで第2位、生鮮野菜総輸入量の15%に相当した。しかも、同年のかぼちゃの国内収穫量が23万t、出荷量が17万tであったことから、輸入物が消費量に占める比率を推計すると、40%前後に達していたとみられる。
なお、これらの解明にあたっては、統計データの分析を行うと同時に、関係者からの聴取調査を行った。調査にご協力いただいた方々に衷心より感謝申し上げたい。
1.かぼちゃ輸入の変容とその要因
(1) 伸び悩み状態の輸入量と輸入額
かぼちゃの輸入動向を把握するため、まず初めに年々の輸入量と輸入額の推移をみたのが図1である。輸入量は1994年まで大幅に増加し、同年に157千tと、最大の数量を記録したものの、その後は横這い傾向に、特に2000年代に入ってからは減少傾向に陥った。また、輸入額(CIF)は既に1991年から横這い傾向に変わり、1998年からは減少傾向に転じた。このことは、野菜全体の輸入量が残留農薬問題が発生する前年の2001年までほぼ一貫して増加し続け、輸入額も1998年まで増加傾向であったのと大きく異なっている。
図1 かぼちゃの年間輸入量・輸入額の推移
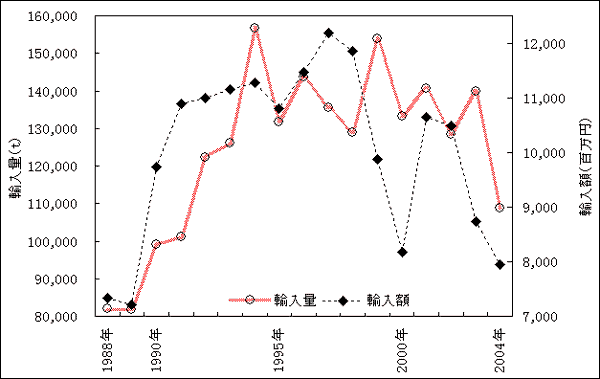
図2 東京都中央卸売市場におけるかぼちゃの国産・輸入別・月別取扱い状況(1989年-1999年-2003年)
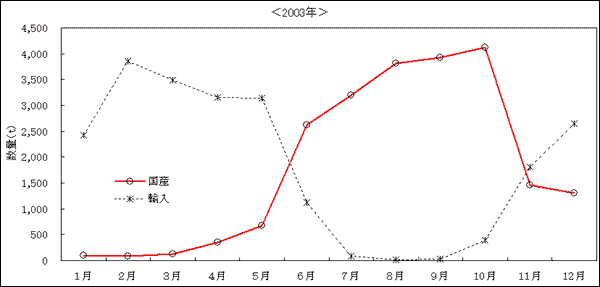
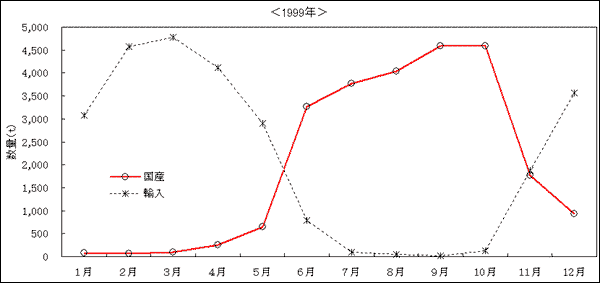
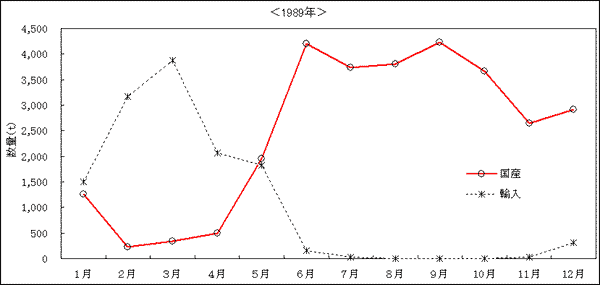
かぼちゃの年間輸入量および年間輸入額がこのように横這い・減少傾向に転じた理由を探るために、図2において東京都中央卸売市場(9市場)における国産かぼちゃと輸入かぼちゃの月別取扱量を示した。ちなみに、本来ならば、月別輸入量と国産物の月別出荷量をみるべきであるが、この両者の古いデータまたはごく最近のデータについて同年時のものを一緒に入手することができないため、ここでは東京都中央卸売市場の取扱量とした。ただし、同市場の輸入かぼちゃ取扱量が輸入かぼちゃ全体の15%超と高い比率になっていることもあって、比較可能な年次でみる限り、同市場の輸入物と国産物の月別取扱量は月別輸入量および国産物の月別出荷量と極めて類似した動きを示しており、十分に代替データとしての役割を果たしうると考えられる。
同図から2003年、1999年、1989年の3カ年の輸入物と国産物の月別取扱量を比較すると、1989年から1999年にかけて国産物の取扱量が減少する中、輸入物の取扱量が1月、4月~6月、11月~12月において著しく増加し、その結果、輸入物の周年化が顕著に進展したことが明らかである。ところが、1999年から2003年にかけては輸入量が最も多い月であった2月~4月の取扱量が減少し、1989年から1999年にかけてみられたようなポジティブな意味での周年化はほとんど影をひそめてしまった。
すなわち、かぼちゃの輸入は国産の端境期を埋めるものとして始まり、年間輸入量の大幅な増加と輸入の周年化が実現したものの、1990年代中期以降はそうした輸入の周年化が止まったために年間輸入量も横這い・微減傾向に転じたといえる。しかも、こうした年間輸入量の横這い・微減傾向は、1991年以降に現れた輸入単価の低下傾向(1991年が過去最高で108円/kg、2003年は62円/kg)と相まって、年間輸入額の横這い傾向、さらには1998年からの減少傾向をも引き起こしたといえよう。
(2) 過半を占めるニュージーランド産
次に、かぼちゃの主な輸入先相手国とそれぞれからの輸入量の変化を明らかにする。
かぼちゃの主な輸入先相手国は一部順位の交代はあったものの、1990年以降に限るならば、第1位のシェアを有するのがニュージーランド、第2位がメキシコ、第3位がトンガ、といった順位で変わらず推移している(図3)。しかも、ニュージーランドのシェアはきわめて高く、特に1990年以降は上昇傾向が明白で、2位以下との格差が拡大傾向にある。例えば1991年はニュージーランドが48%で、メキシコ25%、トンガ21%であったが、1998年以降はニュージーランドが常に60%以上にのぼり、2004年にはニュージーランド64%、メキシコ19%、トンガ12%に変わった。かぼちゃ輸入におけるニュージーランドの重要性がますます高まっているといえる。
しかし、ニュージーランドからの輸入量も2000年代に入ってから明らかな減少傾向が認められる(図4)。
図3 がぼちゃの輸入先相手国別シェアの推移
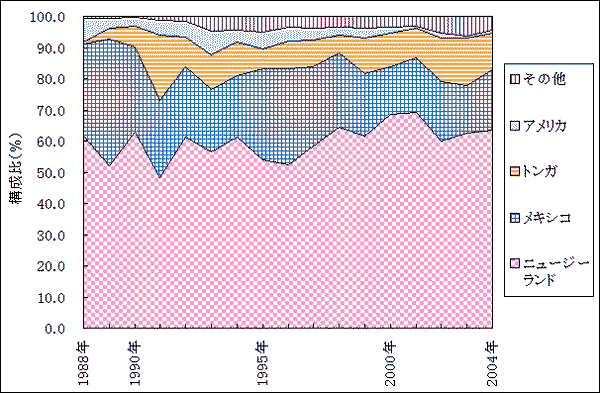
図4 かぼちゃの輸入先相手国別輸入量の推移
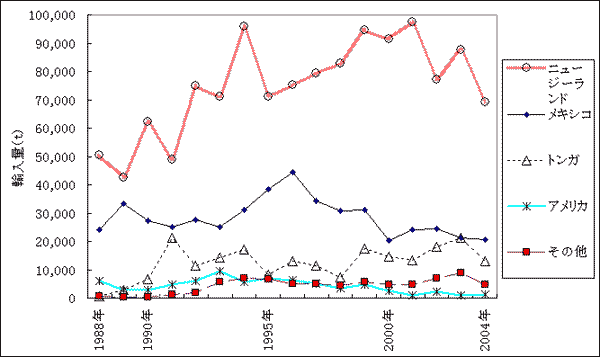
このようなニュージーランドからの輸入量の減少がどのように生起したかを把握するために、図5において2002年から2004年までの3カ年の各年の月別輸入量の変化を示した。同図をみると明らかなように、輸入量が多いのは1月から5月までであるが、興味深い点は2月から4月までの各年の輸入量の傾向と異なることである。どのような違いかというと、2月から4月までの月間輸入量は2002年から2004年にかけて年々減少するということがないのに対し、1月と5月の場合は2002年から2004年にかけて月間輸入量が年々減少しているのである。このような変化は前節でかぼちゃ全体の輸入動向との関連で指摘したのと同様、輸入の周年化とは逆の方向であるといえよう。
図5 ニュージーランド産かぼちゃの年別・月別輸入量
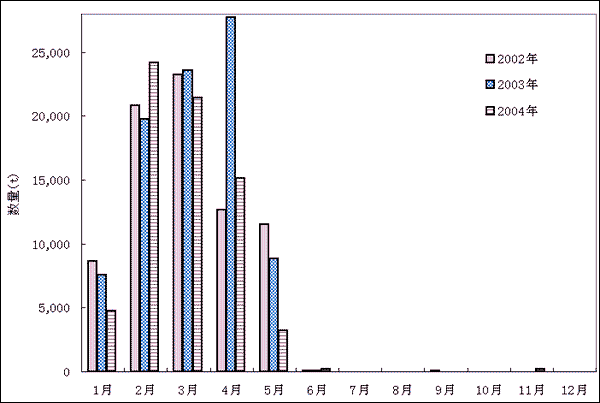
図6 ニュージーランド産かぼちゃとメキシコ産かぼちゃの月平均輸入単価の比較
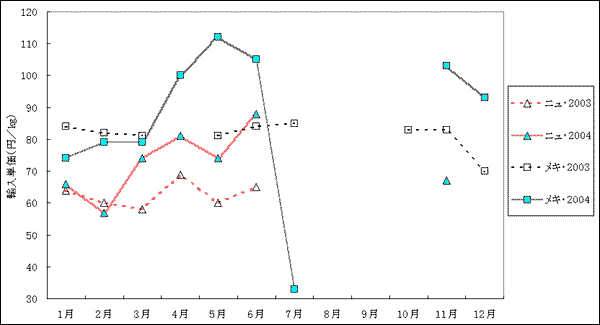
すなわち、わが国のかぼちゃ輸入ではニュージーランド産が過半を占め、輸入の中でのその重要度はますます高まっているといえるものの、同国産の主要輸入期間が短縮化の傾向を強め、その結果、輸入量の減少が起きているのである。
(3) CIF価格を変えた為替レートの変動
かぼちゃの輸入はニュージーランド産が過半を占め、また最近は輸入量が減少傾向にあるが、これらの理由を明らかにするために、過日、都内のA商社において聴取調査を行った。同商社はニュージーランドの親会社が全額出資している子会社であり、親会社からの日本向け輸出分の一部を取り扱っている。年間取扱高は約8億円、そのうちかぼちゃが2億円強(このうちほぼ1割が冷凍かぼちゃ)で、残りはレトルトコーン(3億円)、生鮮にんじん(2.5億円)、たまねぎ(0.3億円)等である。
A社の親会社は日本向けのかぼちゃを生産するために、日本から種を輸入し、その種を契約農場(15農場)に供給する方法でかぼちゃの集荷を行っている。輸出する際の荷の単位は500kg(ビンと呼ばれる木箱)である。収穫がほ場ごとに一斉に行われることもあって、この500kgの箱の中に入っているかぼちゃのサイズは様々である(1玉当たり1kg程度のものから3kg近くまでのものが混じっている)。ただし、販売先を考慮して時にはS、M、Lのサイズ別に荷をまとめることもある。
日本国内での販売先比率は量販店向けがほぼ6割、卸売市場向けが4割である。A社は他のかぼちゃ輸入商社に比べると量販店向けが多い。他の商社は少なくとも6~7割が卸売市場向けである。卸売市場向けが多くなるのは大量に販売できることに加え、取引数量の調整に気をもむ必要がないからである。したがって、A社も卸売市場向けをこれ以上低くするつもりはない。
販売価格は「CIF+40円/kg」程度が普通で、これは量販店向け、卸売市場向けで大きく変わることはない。というのは、輸入物が日本に着いてから、通関手数料が約10円/kg、ブラッシングとリパックが箱代込みで15~20円/kg、商社マージンが5~10円/kg、その他(関税等)が3~5円/kgと、合計でほぼ40円/kgほどかかるというのは業界の常識であるため引き上げるのが難しいからである。ちなみに、ニュージーランドから日本までの船運賃は専用船で25~30円/kgであるが、これはCIFに含まれる。
かくして、「CIF+40円/kg」ということから、輸入物の価格競争力はCIF単価(輸入時点での価格)次第ということになる。ニュージーランド産かぼちゃの場合、その単価が国産物より安いのはもちろんのこと、メキシコ産に比べても2~3割も安い(図6)。このことが1995年までの輸入量の増加、またニュージーランド産の高シェア、あるいは同シェアの一層の上昇となって現れたと考えられる。
しかし、こうした価格競争力も円安およびニュージーランド・ドル高によって、ここのところ徐々に弱まりつつあるとのことである。周知のように1995年以降は次第に円安傾向が強まっており、USドルに対する最近の円の価値は1995年当時に比べ15~20%ほど低下した状態にある。そして、この影響を受け、2000年以前には1ニュージーランド・ドルがおおよそ50円であったにもかかわらず、最近は80円台にまで上昇した。こうした変化がニュージーランド産かぼちゃの価格の有利性を薄れさせ、主に1月と5月における輸入量の減少につながったとみて間違いないであろう。
なお、ニュージーランドにあるA社の親会社は日本向け輸出を増やすために、12月からの輸出を目指し、現在、施設栽培を奨励する等の努力をしている。
2.国内産地の輸入対策と販売戦略
(1) 減少傾向の中での底打ちの兆し
次に日本国内のかぼちゃの生産・出荷状況の最近の特徴や輸入対策等についてもみることにしたい。まずは、作付面積、収穫量、出荷量のこれまでの動きを概観すると、図7のとおりである。
図7 かぼちゃの作付面積・収穫量・出荷量の推移
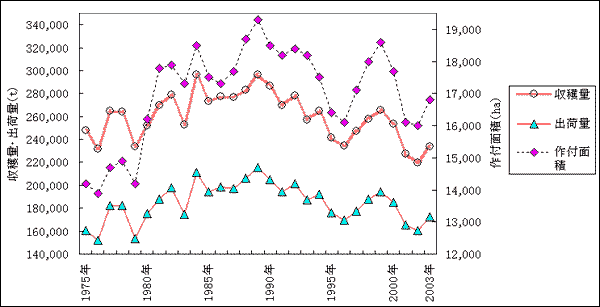
これから明らかなように、かぼちゃの作付面積、収穫量、出荷量とも1980年代末まで増加傾向であった。作付面積は1975年の14千haから89年の19千haへ、5千haも増加し、収穫量と出荷量も同期間に247千tから297千t、および160千tから215千tへと、それぞれ50千tないしそれ以上も増加した。1980年代後半には輸入量が既に増加傾向であったと思われることから、健康志向による緑黄色野菜消費量の増加がかぼちゃの国内生産量と輸入量の両方の同時的増加を可能にしたのであろう。
1990年代に入ると、国産かぼちゃの作付面積、収穫量、出荷量のいずれも減少傾向に転じた。
しかし、最近、そうした国産かぼちゃ生産の減少傾向が底を打ったような兆候が認められるようになった。国産かぼちゃの地域別生産動向において興味深い質的変化が現れたのである。1990年から90年代後半にかけての国産かぼちゃの減少期にはその生産が大産地に、特に北海道に集中する傾向がはっきりと存在していたのに対し、同年代末以降においては各都道府県産地の作付面積、収穫量、出荷量の構成比が安定してきたことである(表1)。
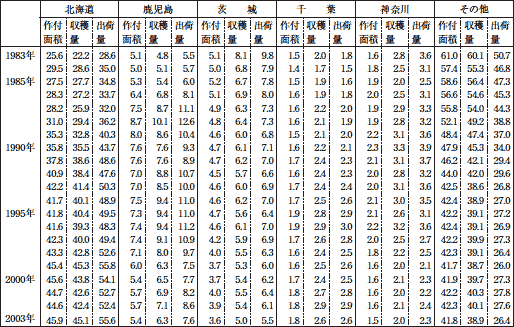
出所:農林水産省「野菜生産出荷統計」
これは、先に指摘したような円安やニュージーランド・ドル高等によって輸入物の競争力が低下するなど、国内各地の産地が地力を回復しうる環境ができあがりつつある中、多くの産地がかぼちゃの生産・出荷活動を強化しようと努めているのであろう。
(2) 食味の向上を目指した品質へのこだわり
それでは、国内産地は輸入物に対抗し、生産力を回復するためにどのような活動をしているのであろうか。その具体的な内容を把握するべく、神奈川県と鹿児島県の両産地において聴取調査を行った。その調査によって明らかになった主な点は、輸入物との区別が可能になるような食味を実現するために品質に徹底してこだわっているということであった。


このこだわりのために両産地が共通して取り組んでいる方法のひとつは、粉質系の品種を採用するである。それは神奈川県産地の場合、「みやこ」であり、鹿児島県産地の場合は「くりゆたか」であった。これらはニュージーランド産の主要品種である「えびす」に比べ水分含有率が低いため、完熟栽培を行うことによって食べた時に「ホクホクした美味しさ」が強く感じられるとのことである。ちなみに、「えびす」の10a当たり収量は2t程度であるが、粉質系の場合は約1.5tと少なめである。
第2の取り組みは、高品質化を実現するために完熟栽培を徹底していることである。「みやこ」も「くりゆたか」も早取りが可能な品種であるが、早取りをすると「ホクホク感」のある品質にならないため、収穫時期を早取り物よりも2週間ほど遅らせるかたちで完熟栽培を実行している。神奈川県では「花が咲いてから40日後」に収穫するように徹底しているし、鹿児島県では目安として「受粉後60~65日、積算温度1100度-1200度」で収穫することにしている。なお、完熟栽培を実行する際に十分な堆肥が必要なことは指摘するまでもない。
第3の取り組みは、収穫後、即座に販売するのではなく、若干の日にちをおいてから販売するようにしていることである。というのは、収穫後2週間ほど追熟することによって「ホクホク感」が出るからである。ただし、3週間も4週間も経ってしまうと、追熟のしすぎで逆に「ホクホク感」が出ずらくなるといわれている。それゆえ、仮に輸入物の品種が変わり、完熟栽培を行ったとしても、現在のように日本に到着するまでに3週間以上もかかる限り、「ホクホク感」が出るような高品質なかぼちゃになることはないとのことである。
これらの方法を採用したことによって両産地のかぼちゃは食味が向上し、それは価格の高さとしても現れている(図8)。すなわち、鹿児島県産かぼちゃの単価は2~4月と8~9月において国産平均価格を著しく上回るほど高く、神奈川県産かぼちゃの単価は、その主要な出荷時期である6~7月において国産物の平均単価を大きく上回っている。
図8 東京都中央卸売市場における産地別・月別単価(2003年)
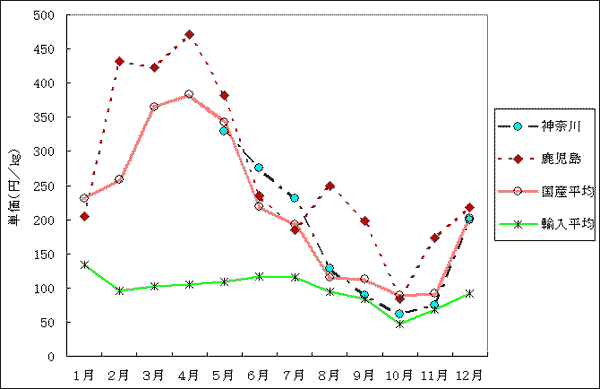
(3) 差異化のためのブランド化の推進
両産地では食味の良さを土台に、輸入品等との違いを容易に区別できるようにブランド化も進めている。ブランド名は神奈川県産地の場合「こだわりみやこ」で、鹿児島県産地の場合「加世田のかぼちゃ」である。
両産地がブランド化のために共通して採用している方法を整理する。
(1)高共販率を維持し、量的まとまりを確保
両産地とも上記のブランド名で出荷する産地に限れば、共販率はほぼ100%に達している。これによって特定のブランド名と「ホクホク感」とが結びつく状況を創り出しているのである。また、全県単位の出荷組織が形成されていない神奈川県産地では、2農協で特産・三浦野菜生産販売連合を設立することによって農協出荷としての量的まとまりを実現し、当該ブランドのかぼちゃだけで大手小売業者の仕入量を満たすことができるようにしているのである。
(2)出荷先の絞り込み
神奈川県産地の場合、かつては野菜の出荷先卸売市場は100市場以上(最大時は116市場)にのぼっていたが、現在では52市場に絞り込んでおり、「こだわりみやこ」の出荷先に限れば数市場にすぎない。また、鹿児島県産地の場合も「加世田のかぼちゃ」の固定的出荷先卸売市場は現在では関東と関西の7市場だけである。出荷先の絞り込みは輸送コストを削減するためだけでなく、当該卸売市場でのシェアを高め、知名度と希少性を高めることによってブランド化を推進するのである。
(3)小売店頭での積極的な販売促進
両産地とも生産者と農協職員が自産地品を仕入れている小売店に出向き、その店頭でマネキンとして試食販売をおこなっている。これはもちろん、単に売上を伸ばすためだけではない。最も適切な時期と調理方法を伝え、消費者に当該産地のかぼちゃの美味しさを知ってもらうことが大きな目的である。ブランド化は最終消費者にまで当該ブランド名が知れ渡ることによって初めて達成される。小売店頭での販売促進はそのための主要な方法の一つなのである。
3.おわりに
以上、かぼちゃの輸入動向と産地の輸入対策について述べた。最後に、今後の動向について触れておくならば、3~4年程度の近い将来においては輸入量は減ることはあっても、輸入が引き続き国内産地に打ち勝って大幅に伸びるという可能性は極めて低いとみられる。というのは、現在の国内産地は今日に至るまで輸入物との厳しい競争の中で生き残ってきただけに、栽培方法の改善に積極的に取り組むなど、筆者の目にも力強さが感じられるからである。
ただし、産地の方々も危惧しているように、現在の生産者と生産方法に依存せざるを得ない状況が続く限り、いずれ生産者の高齢化と後継者不足による生産力の低下を避けることができず、結果として国内産地がさらに後退し、輸入がさらに増加することにならざるを得ないであろう。そうならないためには、従来とは異なる新たな生産方法を構築する必要があろう。その方法とは、これまでのように多数の生産者がそれぞれに10~50a程度の小規模生産を行うのではなく、鹿児島県で推進しようと考えている「10~20haの生産規模」あるいはそれを上回る生産規模を実現し、少数の生産者(経営者)が機械等を利用して大規模に生産するというものである。もちろん、大規模生産だけにしなければならないということではない。大規模生産と小規模生産が併存することによって、多様なニーズに対応しやすくなるというメリットが強まることを考えるならば、併存する方が望ましいといえよう。