1.長野県におけるレタスの生産・出荷動向
レタスが長野県を代表する作物であることは言うまでもない。同県で生産される野菜のうち、レタスによる売上げが1/4を占め、夏場は全国の流通量の80%のシェアを持っている。
農家の高齢化、生産基盤の脆弱化という問題を抱えながらも、レタス・白菜は農家の生産意欲も高く、年間出荷量は1400万ケース(1ケース10kg入り)前後と、安定的に推移している(表参照)。
表 レタスの出荷量と単価
(全農長野県本部取り扱い)
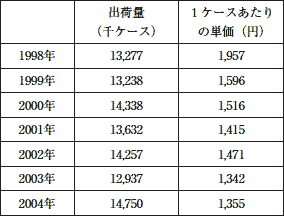
同県は、野菜の生産振興のために、農協組織が全国に先駆けてさまざまな仕組みを構築してきたことでもよく知られている。計画生産・計画出荷を目的として、1966年からJAと長野県で策定した「長野県野菜基本計画」にもとづいた生産をしている。流通面では、1971年に県下初の予冷施設を建設、70年代半ばにはほぼすべての産地で導入されるなどコールドチェーンへの取組みも早かった。また、市況情報をオンラインで単協まで伝える販売市況情報システム、どの卸売市場にどれだけ出荷するかを決定する分荷情報システムを1970年代半ばに相次いで整備した。
価格安定制度への取組みも早く、「野菜生産出荷安定法」ができる前の1960年から、県独自の価格安定事業をスタートさせた。こうした体制を構築してきたから系統利用率も高く、特にレタスの場合は85~90%と、他の野菜と比べても高い。
現在、出荷先は直販課で取り扱う市場外流通分を除き、90%以上が卸売市場に出荷される。だがそこから先の販路については時代とともに変化してきた。
レタスといえば、かつては家庭で食べるサラダとしての需要が圧倒的に多く、卸売市場を経由し、大手量販店を始めとする小売店に出荷される比率が高かった。だが業務および・加工需要の拡大にともない、契約取引が増加してきた。現在、契約を交わしているエンドユーザーは、カット野菜業者、外食業者、小売店などである。ただし、全農長野県本部が実際に契約を結んでいるのは、エンドユーザーに納める卸売業者が多く、卸売市場を何らかの形で経由しているという。卸売市場を通るレタスのうち、20%~30%が契約栽培によるものである。価格設定はシーズンごとの交渉による取引先もあれば、一週間、1ヵ月、4ヶ月ごとなど短い期間で決める取引先もあるという。今後は、安定供給が見込める業務需要を増やしていく計画で、歩留まりを重視する加工・外食業者向けには、市場出荷用とは区別し、大きめのサイズのレタスを専用に栽培するなどの対応もすでに始めている。
2.産地が抱える課題と今後の方向性
レタスを含む野菜事業における課題は大きく2つある。一つは産地価格の低迷、そしてもう一つは流通コストの増加である。
全農長野県本部が扱う野菜の出荷額は、1950年の発足(当時は、長野県経済連)以来、おおむね右肩上がりで伸びてきたが、1993年の1034億円をピークに下がり始め、2004年は697億円にとどまっている。
こうした落ち込みに対し、全農長野県本部は3つの要因があるのではと見ている。一つは、大手量販店の発展により、価格競争の激化、それにともなう産地への仕入値の引き下げ要求などが強まり、産地の出荷価格が低迷したことである。二つ目が、加工需要が増え、相場に左右されない契約栽培が増えてきたことである。三つめが、需要そのものの落ち込みである。これについては、(1)水菜、パプリカなどサラダ用野菜の多様化が進んだこと、(2)国民全体の野菜の消費量の減少、(3)少子高齢化・核家族化の進展で必要な量しか買わなくなったこと、(4)不景気による食費の切り詰めなどさまざまな要因が絡まっているのではないかと分析している。
もう一つの流通コストの増加の理由としては、トレーサビリティへの対応に伴うコストアップ、環境への配慮から従来商品より割高なクギのない段ボール使用としたこと、コールドチェーンの普及とともに冷蔵車つきのトラックの装備を取引先から求められていることなどである。一方、生産コストは、肥料・農薬の代金が値下がりしたことと、使用量そのものが減ってきたためにコストダウンが進んでいる。
2005年度の「長野県野菜基本計画」では、レタス1ケースあたりの推進価格(産地価格)を10kgあたり1500円と設定している。だが、上記のようなさまざまな要因から、2000年以降の単価をみる限り、1300円台~1400円台にとどまっている。また、平均的な農業所得は10アール(400ケース分)あたり約17万円というところである。10キロあたりにすると425円(一玉あたり約27円)にとどまる。しかもこの中に人件費も含まれており、それを差し引けばもっと低くなる。
こうした厳しい現実を打開していくため、全農長野県本部では今後、レタスの生産・販売事業について以下の方向性を検討していくこととしている。
(1)特徴ある商品の開発および提供を図る。
(2)従来は同じ規格の農産物を、一ヶ所に集め、大量出荷することで有利販売をめざしてきたが、ユーザーのニーズが多様化している以上、供給側もさまざまな供給方法をとっていくというスタンスに転換しつつあるが、これをさらに明確(多元集荷多元販売)にしていく。
(3)レタスをひとつのアイテムとして一括りで出荷するのではなく、品種・栽培方法などを通じて味で差別化を図る。例えば「甘くておいしい」といわれながら、姿を消しつつある品種『オリンピア』の生産振興も検討する。
3.独自の産直スタイルを確立した専業農家
一方、こうした環境にあって、需要サイドとうまく連携をとり、生産者が安定した収益をあげている事例がある。レタスや白菜をスーパーに直接販売している(株)信州がんこ村(長野県佐久穂村)という生産者組織である。
代表をつとめるのは横森正樹氏(64歳)である。横森氏は家族経営(自身と奥さん、長男夫婦)でレタス、白菜などを作る専業農家である。経営規模は約10ヘクタール、約20年前からサンヨネ(愛知県豊橋市)というスーパーと産直を始め、以来、東京都、群馬県などのスーパーとも取引を広げている。
横森氏がスーパーとどういった取引をしているのか、サンヨネとの連携を事例にあげてみよう。

「農業はやり方次第でおもしろくなる」
と話す横森正樹氏
産直の場合、農産物をスーパー(あるいはスーパーが指定する物流センター)まで持っていく物流費は生産者側が負担するのが普通であるが、横森氏の場合、スーパー側が自らトラックを仕立て、集荷を行っている。全国的にも珍しい「畑渡し」である。
個人の生産者がスーパーと直接取引する場合、ネックになるのはロットとデリバリーである。スーパーが求めるだけのロットがそろうのか、仮にそろっても個人でトラックを仕立てるには多額の費用がかかることとなる。横森氏は、最初に直接取引を始めたスーパーサンヨネ(愛知県豊橋市)に相談を持ちかけたところ、サンヨネは、自らが懇意にしている仲卸業者が横森氏の畑までレタスを取りに行くこととなった。費用はサンヨネの負担である。
トラックを自費で仕立ててまで取りにいくにはそれなりの理由があった。サンヨネの三浦和雄営業本部長はこう話す。「食べればわかりますが、横森さんのレタスは甘くておいしい。それに人柄によるところも大きい。常に前向きで、思ったことは何でもやってしまう。人生の師と仰いでいるんですよ」。もっともレタスだけでは4トントラックが満載にはならないため、横森氏が紹介した地元の野菜、乳製品を混載し、物流費の負担を軽くしている。
横森氏は就農当時から、「国家公務員なみの年収」、「生産者と流通業者が共存できる関係」をめざしてきた。サンヨネとの取引スタイルはまさにこの目標に叶ったものだった。産直によって中間手数料や物流費がゼロになり、大幅なコストダウンに成功した。一方、費用・労力を削減することにより、流通業者(その背後にいる消費者)が喜ぶレタス作りに専念できることとなった。現在、レタスは5月~10月の毎日、サンヨネが経営する6つの店舗に届けられる。これは、横森農場で作られるレタスの約60%に相当する。

横森氏のレタスを販売しているコーナー
(譁サンヨネ蒲郡店)
4.生産者組織を結成、出荷農家に最低価格を保証
そんな横森氏が、信州がんこ村を設立したのは2000年である。年収で毎年、5000万円台を確保できるようになった横森氏は「周囲を見渡すと営農意欲がありながら、思うように収益をあげられていない生産者が多いことがわかった。還暦を境に、農場経営は長男夫婦に任せ、地域の生産者のサポートと地域農業活性化に専念したい」と決断した。
信州がんこ村の事業内容は、生産者への技術指導、農業資材の販売、農産物の集荷・予冷・販売などである。設立にあわせて自宅近くに予冷および冷蔵庫を備えた物流センターも建てた。
生産者メンバーは現在約20名、売り先は横森氏が取引をしてきたスーパー、新たに開拓したスーパーである。スーパーとの取引を長く続けてきた横森氏は「スーパーがどんな農産物を求めているか」に注意を払ってきた。そして導き出した答えは「スーパーは特徴のある商品を求めている」だった。横森氏は長年、土壌改良材として、常緑広葉樹の樹皮を原料とする炭の粉末に木酢液を吸着させた「サンネッカE」という農業資材を使い続けてきたが、信州がんこ村でも、同資材を共通資材として使うことにした。また、有機質堆肥で肥沃な土づくりをし、化学農薬や化学肥料は極力抑える栽培方法を推奨している。生産された野菜は「がんこ村」ブランド名で販売されている。

コンテナ出荷に取り組み、 コストダウンを図る
ただし、生産された農産物を付加価値販売するための資材と考えていない。「いまの時代は、『いいものを高く』ではなく、『いいものを安く』が求められる。サンネッカEは、木材の皮を有効利用したものであり、木を炭にして土に戻し、新たな植物を育てる循環型農業に叶ったものという特徴が相手側に伝われば、それだけで大きな特徴になる」というのが横森氏の持論である。
モノの流れは、スーパーからあらかじめ注文をとり、それぞれのスーパーに納入する生産者、数量をある程度振り分け、作付けをするという受注生産である。
機能としては農協と同じであるが、価格の決め方は、農協や卸売市場とはまったく異なる。まず、生産者が再生産できる最低価格(手取り)を決める。レタスであれば10kg入り1箱(通常16玉)で900円(1玉あたり約57円)である。これに信州がんこ村の取扱手数料として5%、予冷費(1箱あたり50円)を乗せた上で、スーパーと価格交渉をする。基本的には、卸売市場の相場に連動させるが、市場が高騰、あるいは暴落しても1玉あたり70円台から160円台でおさまるように取り決めしている。こうすることで生産者もスーパーも相場の乱高下の影響を軽減することができる。
最低価格が保証されているため、生産者は安心して農業に取り組むことができる。金銭的および精神的な余裕があるから、土づくりや栽培によりエネルギーを注ぐことができる。その結果、品質はアップし、消費者の満足度もアップする。まさに農産物流通の望ましい循環といえるが、すべて横森氏自身がサンヨネなどとの取引を経験として、作り上げた仕組みである。
5.欠かせないコントロール機能と多元化販売
だが、こうした仕組みだけを作っても思うようにいかないのが農産物流通である。そこで横森氏は、仕組みを支える2つの壁を越えてきた。
一つは、供給側とユーザー側とにあるギャップであった。横森氏はこう話す。「流通は消費者相手の商売。店は一日も休めないので安定供給を求める。一方、一般的な生産者は、農協や卸売市場に出せば終わりだ。両者のギャップを埋めなければ両者がメリットを得ることはできない。特に、生産者にはなぜ一度決めた契約、出荷量を守らなければならないのかということを理解してもらうのに苦労した。」
例えば、台風で農家が収穫を休んだ場合、信州がんこ村の社員がその農家の畑に出向き、代わりに収穫をするということもあったという。すると、農家も家の中にじっとしてはおられずに一緒に収穫作業をするようになった。ユーザーにとって安定供給がどれほど大切かということを、横森氏は身をもって生産者に示し、理解を得たという。
もう一つは、農家のグループ分けである。当初、信州がんこ村には30名以上の生産者がいたが、栽培技術、野菜の品質、営農意欲にバラつきがでてきた。横森氏は、設立当初に「5年間で栽培技術を高めてほしい」と農家に頼んだというが、全員の足並みがそろうわけではなかった。そこで苦渋の決断をし、2005年から20名は「がんこ村」というブランドで販売を継続し、残りの生産者ついては本人の意思を確認した上で、ブランドをはずすことにし、ノーブランド商品を求める売り先とマッチングさせることとした。
6.産直ビジネスのモデルに
こうした取組みによって、信州がんこ村は年間35万ケースの野菜を出荷、野菜の取扱高は約3億5000万円、営業利益では約1000万円をあげている(いずれも2004年度)。もっとも、同社に出荷することで20名の生産者の所得が安定したということが、信州がんこ村の最大の成果かもしれない。
2005年度の「長野県野菜基本計画」では、生産者が農協にレタスを出荷する場合の、1ケースあたり425円の生産者の平均農業所得は、生産コスト、流通コスト、安定事業に係る負担金などすべてを差し引いたうえでの手取りである。
信州がんこ村へ出荷する生産者の最低保証の900円には、生産コストが含まれており、種代、農薬代、肥料代などの生産コストは、多くても400円程度であるということから、農家の収入は500円となる。
信州がんこ村の取組みは以下の3点に整理することができる。
(1)ユーザーの要望に沿った特徴のある商品づくり
(2)生産者とユーザーの間のギャップを埋める機能
(3)多元集荷多元販売
信州がんこ村の取組みは、これまでの農産物流通を大胆かつ果敢に改革したものであり、全農長野県本部、あるいは他の産地がすぐにそのまま導入するというのは難しいと考える。しかし、よく見ると信州がんこ村がやっていることは、全農長野県本部がめざそうとしている方向性と重なっている。上記の(1)~(3)と「2.産地が抱える課題と今後の方向性」で全農長野県本部が示した3つの方向性との共通点がおわかりいただけるだろう。
また、横森氏は、「農協がその気になれば改革の方法はいくらでもある」と話す。「例えば、長野県で特徴ある商品づくりをするとしよう。長野県は森林資源に恵まれていることを考えると、木材から炭を作り、それを土づくりの資材にするという方法がある。環境問題、資源の有効利用は、消費者にとっても関心の高い分野である。身の回りの資源を生かすだけで差別化は可能である」と話す。
また、「多元集荷をするなら、消費者ニーズの多様化を考えて『有機・特別栽培野菜』、『ブランド野菜』、『一般野菜』というカテゴリーは持っておくべきだろう。生産者の努力が報われるような売り方をすれば、質のいい作物が必然的に農協に集まるはず」と提案する。
家庭での野菜の消費減少、小売店の激しい価格競争、乱高下する相場…。どれをとっても現状のやり方を維持していては、価格低迷から抜け出すことは難しい。株式会社である信州がんこ村のスタイルを、協同組合である農協組織がそっくりそのまま実行するには無理があるかもしれない。農協にとっての最大の目的は、生産者の手取りを増やすことにほかならない。それを、身をもって示している信州がんこ村の事例は、経済事業の建てなおしを図ろうとしている全国の農協、農村地域にとって、一つのビジネスモデルとなりえるだろう。