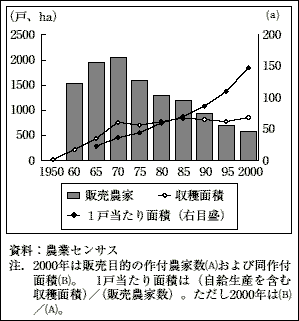専門調査報告
専門調査報告
はくさいの生産・輸入等の動向に係る実態調査
農林水産省 農林水産政策研究所 地域振興政策部長 香月 敏孝
(1) 国内生産の推移
1)全国の動向
はくさいの作付面積は、昭和41年の50.6千ha、出荷量は昭和52年の1,293千トンがそれぞれピークとなっている。それ以降、はくさいの生産は年を追って減少しており、図1に示したようにその傾向は近年に至るまで継続している。
作付面積は平成に入って30千haを下回り、平成15年には20.7千haとなってピーク年次の4割程度の水準にまで減少している。また、出荷量は作付面積ほどの減少ではないが、昭和63年に1,000千トンを下回り、平成15年には728千トンとなりピーク年次の56%にまで減少している。
特に、出荷最盛期の秋冬(10月~翌3月出荷)はくさいについては、出荷量のピークとなった昭和46年の1,057千トンに対して、直近の平成15年のそれは457千トン(ピーク年次の43%)の水準にまで落ち込んでいる。このように、はくさいは野菜の中でも生産後退が著しい品目と位置づけられる。
図1 はくさいの作付面積・出荷量の推移
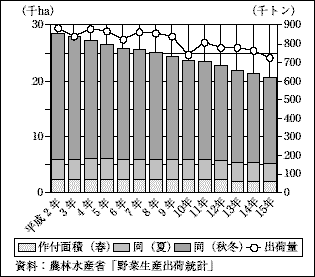
2)県別の動向
県別および作型別のはくさいの生産動向を表1に示した。生産実態の指標として平成12~14年の3カ年平均の作付面積と出荷量を掲げ、併せて10年前(平成2~4年の3カ年の平均値)と比較した増減率を表示することで、この間の変化をみたものである。それぞれの作型に表記した都道府県は、生産の多い順に、全国に占める割合がおおむね8割になるまでを示した。
表1 県別・作型別にみたはくさい生産の動向
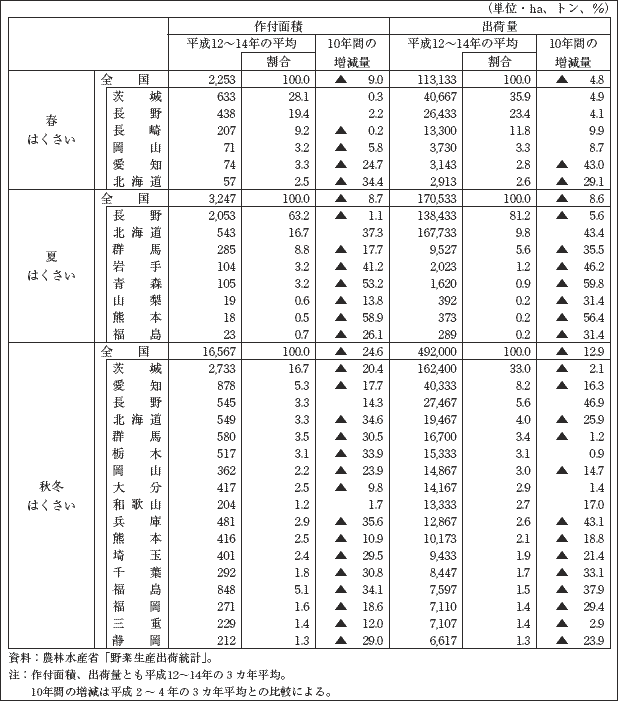
まず、作型別の産地集中の程度は、次のようになる。
春はくさい(4~6月出荷)は、茨城、長野の2県に生産が集中している。平成12~14年に作付面積、出荷量の割合(対全国シェア)は48%、59%である。表に示していないが、10年前の割合は、それぞれ、43%、54%であったから、この間に両県への集中が進んだことが分かる。
夏はくさい(7~9月出荷)は、長野1県で作付面積の63%、出荷量の81%を占めており、これに続くのが北海道であり、この2道県で作付面積の80%、出荷量の91%とほとんどを占めている。10年前には、両者でそれぞれ70%、85%であったから、夏はくさいも一層の産地集中が進展している。
秋冬はくさいについては、上の2つの作型に比べて生産は分散しているが、茨城、愛知、長野、北海道の4道県で作付面積の29%、出荷量の50%を占めている。10年前のそれは、それぞれ27%、46%であったから、秋冬はくさいの場合も上位4道県で出荷量の半分を占める集中となっている。
なお、この間の茨城の秋冬はくさいの作付面積は20%も減少している(平成2~4年の3,483haから12~14年の2,773haに710haの減少)が、出荷量はわずかに2%の減少に止まっている点が注目される。この間の10a当たりの出荷量の増加によるところが大きいといえる。
以上のように、各作型とも、主産県への集中が確認できることになる。これに付帯して次のような動きも併せて確認することができる。茨城、長野の両2大産地は、茨城では秋冬はくさい、長野では夏はくさいの生産を中心としているが、この10年間の動きとして、中心となる出荷時期の出荷量を減少させ、茨城では春はくさい、長野は春はくさいと秋冬はくさいの出荷量を増加させている。いずれも、出荷時期の延長を図る取り組みがなされていることが見て取れる。
また、その他の産地の動きとしては、ごくわずかな地域ではあるが、生産を拡大する動きが確認できる。出荷量が増加した県を挙げれば、春はくさいは、長崎を中心に宮崎を除く九州6県と高知、夏はくさいは北海道(増加率が43%と高い)、秋冬はくさいは、和歌山、長崎、鹿児島、といったところである。
(2) 用途別需要量の変化
はくさいは、従来から漬け物消費が多いことなどから業務用の需要がかなりのウエイトを占めている。こうした用途別の需要量の変化をみてみよう。
図2 はくさいの用途別需要量の変化
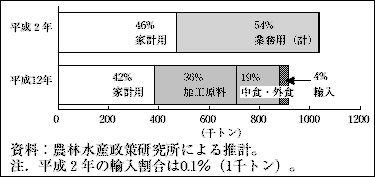
ここでは、はくさいの用途別需要を、国産について(1)家計用(調理用素材などとして家計が購入して消費)、(2)業務用(加工原料、中食・外食)に分け、これに(3)輸入を加えた区分とした。平成2年と12年について、用途別需要量を推計すれば、図2のようになる(なお、この推計は減耗量を控除した粗食料ベースであり、農家自給分を含む)。
これで分かるように、平成2年には家計用と業務用とが、それぞれ473千トン(46%)、564千トン(54%)であり、既にこの段階で業務用需要が家計需要を上回っていた。またこの時点での輸入は1千トン(0.1%)に過ぎない。
これが12年には家計用が398千トン(42%)、業務用が518千トン(55%)、輸入が36千トン(4%)となっている。業務需要について、これを加工原料と中食・外食に分ければ、それぞれ36%、19%となっている。
この間の需要量は家計、業務用とも減少しており、それぞれの減少率は16%、8%である。
家計用途ばかりでなく業務用の需要量も減少しているが、この点が他の品目と比較した場合のはくさいの特徴的な動きとなっている(例えば、レタス、たまねぎといった品目は、家計用需要は減少しているが、業務用需要は増加している)。
はくさいの全体需要量は1,038千トンから916千トンへと10年間で9%も減少しているが、以上のような用途別の需要動向がその背景となっていると考えられる。しかし、こうした状況の中にあって、はくさいの輸入は増加していることになる。なお、平成12年のはくさいの輸入のうち、半分近くは漬け物製品(キムチ)として、家計で消費されていると推計される。
用途別需要のうち、業務用需要の最近の動向については、加工(漬け物)会社および外食会社の事例を後に2で紹介する。
(3) 価格動向
これまでみてきたように、はくさいは消費量の減少に伴って生産の縮小傾向が強い。こうした状況を反映した価格の動きはどのようになっているのだろうか。
図3 はくさいの卸売市場価格の推移(作型別)
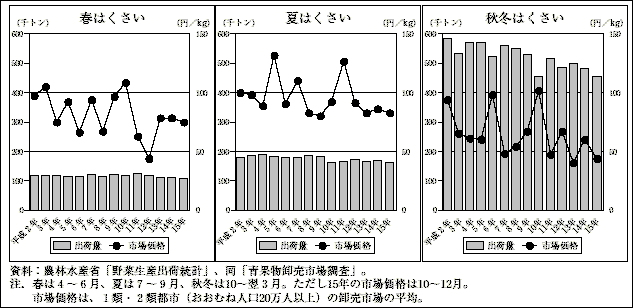
はくさいは、先にみたように大きく3つの作型に分けられることから、それぞれの価格(卸売市場価格)の動きに注目した。図3は作型(出荷時期)別の価格の推移とそれに対応する出荷量を併せて示したものである。
平成2年から15年の14年間の1kg当たり平均単価(単純平均)は、作型別に春が82円、夏が97円、秋冬が66円である。高冷地栽培が主体の夏はくさいが最も高く、平場での露地普通栽培が主体となる秋冬はくさいが最も低く、平場での促成栽培(一部トンネル栽培)や準高冷地での生産が多い春はくさいがその中間という、序列になっている。
次いで、このような価格水準の差はあるものの、いずれの作型も、年次別の振れを含みながらも、近年、価格は低下傾向にある。直近の平成13~15年の3年間の平均は、春が78円、夏が84円、秋冬が49円となっており、いずれも14年間の平均を下回っている。
特に、こうした傾向は、秋冬はくさいで強い。秋冬はくさいの場合は、平成元年から10年までの間に50円を下回ったのは7年(49円)のみであった。しかし、10年の不作による価格高騰を経た後には、11年(48円)、13年(41円)、15年(44円、ただし10~12月)と、隔年で50円を下回っている。
秋冬はくさいの出荷量が減少する傾向にありながらも、このような弱含みの価格趨勢となっているところに、近年のはくさい需給環境をめぐる問題が象徴的に現れていると捉えることができる。
2 事例からみたはくさいの業務用需要の動向
先にみたように、はくさいの需要は業務用が多い。ここでは業務需要のうち、加工(漬け物)製造業と外食産業から、それぞれ業界を代表する会社の輸入を含むはくさいの仕入れ実態などを調査した。
(1) 漬物製造業A社
1)仕入れの実態
A社は浅漬けを中心とした漬物製造業社である。同社では平成12年の原料の原産国表示義務化に伴って、原料調達を全面的に国産とすることにした。はくさいはここ数年にわたり年間4,000トン程度の仕入れを行っている。野菜単品では、はくさいの仕入れが最大であり、これにだいこんの2,500トン程度が続く(野菜全体では平成15年度で9,200トン程度)。
平成15年度のはくさいの仕入れは、4,100トンであるが、そのうち86%が契約による仕入れである。ただし、契約仕入れのうちの4割近くは農協との契約で、商流は卸売市場を経由するが、物流は工場への直搬入となっている形態であり、代金決済の機能は卸売市場に依存している。その他の契約仕入れは、生産者、生産者グループ、農協系統、産地業者などを対象としたものである。また、契約取引以外は卸売市場(卸、仲卸)などからの仕入れとなっている。
はくさいの季節別の契約産地は、おおよそ以下のようになる。春(4~6月)は茨城県で生産者、農協など、夏(7~10月)は長野県で農協など、秋冬(10~2月)は茨城で農協および全農県本部などである。契約仕入れ量の54%が茨城県、31%が長野県で、ほとんどがこの2県で占められている。
このほかの産地としては、春と夏の繋ぎとして群馬県(農協)、秋冬期の補完産地として静岡県(農家)、鹿児島(産地業者)、長崎県(産地業者)が挙げられる(茨城からの仕入れが無い3月は、静岡、鹿児島、長崎の3県からの調達となっている)。
こうした契約生産を担っている農家は、例えば、茨城県ではくさいの生産面積が10ha規模であるなど、かなり大規模な生産農家が含まれている。
また、契約に際しては、シーズン初めに価格を決定し、月間を通じた固定的な価格で取引されている。契約栽培は、最低3年はやってみてその後の対応を考えていくとしているが、産地との信頼関係が欠かせないとの判断から、1ヵ所で長い契約を結ぶことを基本としている。
A社は、以上のような契約栽培を25年前頃から実施しており、16~17年前に本格化させている。こうした契約栽培を全面的に展開するようになった背景は次のとおりである。
小売業態としてスーパーが台頭し、冷蔵陳列が一般化するにつれ、漬物は従来の古漬けから浅漬けに消費がシフトしていった。こうした動向を捉えてA社も、浅漬け生産の拡大を図ったのである。その際に、古漬けと比較して外観がより重視される浅漬けは、品質の良い原料を確保する必要が強まった。さらに、それ以上に考慮しなければならなかったのが、日量ベースの安定的な原料の確保であった。こうして浅漬け生産拡大と契約栽培の拡大が軌を一にして進展していったのである。
2)キムチ製造をめぐって
さて、このようにして調達されたはくさい原料は、現時点では、浅漬けとキムチでほぼ半々となっている。キムチは、近年の消費ブームによって生産が拡大された。
A社では、早くから本場のキムチに注目し、自社製品の開発を行い、国内工場のほかに韓国に現地企業との合弁会社を設立し、日本、韓国の両国に生産の拠点を確保している。
国内工場でははくさいなどの主原料は国産を、薬味などの一部の副原料は韓国産を用いている(ただし、台風の影響を受けてはくさい価格が高騰した平成16年11月には、一部韓国、中国からの輸入も考えざるを得なかった)。一方、韓国工場では、現地の原料を用い、A社の仕様による生産を行い、現地パックした後A社に送り出している。
キムチ製造量の割合は、国内7~8割で残りが製品輸入となっている。現時点では、国内産はくさいを原料とした国内製造が多いことになるが、今後の見通しについて、次のようなコメントがあった。
キムチの出回り量が多くなるに伴って、かつて例えば、400g詰めで598円といった小売価格が、現在では298円の物が現れるなど、近年、価格競争が激化している。こうした状況が深まっていくとすれば、国産原料に依存したキムチ製造は、必ずしも有利とはいえない。
(2) 外食産業B社
B社は、定食や丼物を中心とするファストフードのチェーン店を全国展開している外食業である。食材の提供は一括してセントラル・キッチンで行っている。店舗からの食材の発注は15時締めとなっており、カット野菜などの食材は翌日2回の配送となっている。
野菜の仕入れの多い物として、日量でキャベツ10トン、たまねぎ7~8トン、レタス5トンである。だいこん、きゅうり、にんじんはそれぞれ1~2トン程度である。以上のうち、たまねぎの半分近くが中国からの輸入(時期は1~5月が中心)であるほかは、全量国産を使用している。ただし、平成16年産のキャベツについては、価格高騰を受け、やむなく一部中国、韓国産を使用した。たまねぎの輸入は平成13年からであり、15年から本格化している。
はくさいは、大半が漬物食材として提供されており、漬物のうちキムチが7~8割、新香が2~3割の構成となっている。はくさいは、上記の他の品目と比べて、日量の振れが大きい。週間で60トンを超えることもあれば、10トンを下回ることもある。キムチは豚肉とよく合う食材ではあるが、定番メニューが少ないからである。
サラダや付け合わせで出されるキャベツ、レタスの仕入れは、8割が農協系統で2割が商系からである。前者については、一部契約栽培による仕入れとなっているが、その場合でも決済は卸売市場を経由したものとなっている。はくさいの場合は、6割が市場経由の仕入れとなっている。
その他の野菜品目も含め仕入れに当たって、卸売市場を介在させるのは、店舗からの連絡を受け、日々変動する仕入れ量を過不足なくこなすためには、バッファーとしての卸売市場の機能に依存しなければならないからである。不足分は卸売市場から仕入れ、契約で過剰となった分も卸売市場が捌いてくれる。
契約栽培は、安定的な仕入れをめざしたものであり、併せて生産履歴が分かるトレーサビリティの構築も視野に置かれている。契約は、定植前に産地に納品日、数量および価格を呈示して行われる。B社は歩留まりの良い大玉の仕入れを希望している。
契約栽培の代表事例として全農茨城県本部が挙げられ、はくさいおよびキャベツは生産者指定であるが、レタスは固定されていない。
以上のように、B社は野菜の仕入れに当たり、国産を重視している。鮮度はやはり国産となるからである。しかし、加工品となると、そうもいかない事情がある。
上述したように、はくさいの場合は、キムチなどの漬物がメニューの中心となり、かつて、B社では漬物を自社生産していた。しかし、冷夏による平成15年産米価格の上昇、さらには15年末に発生したアメリカでのBSE牛の発生に伴う同国からの牛肉輸入停止措置によって、廉価な牛肉の調達が困難となった。こうした状況の下で、食材コストの削減を図る一環として、キムチは中国からの製品輸入へとシフトしている。中国に自社工場を設置する構想もあったが、それは止めて、レシピはB社が指示して行う委託生産となった。こうして、現在では、キムチの仕入れの9割は輸入物に置き換わっている。
こうならざるを得なかったのは、以下のようなコスト差があったからである。すなわち、キムチ製品1kg当たりコストは、国産が600~700円であるのに対して、輸入製品は100円程度に過ぎない。
ところで、コストのうち、はくさいの原料費は国産が50~60円であるのに対して、中国では30~40円であり、大きな差とはなっていない。主なコストはキムチ製造にかかる人件費である。人件費を考えれば、とても国内生産では太刀打ちできないことになる。より端的にいえば、国内製造の場合には、たとえはくさい原料がタダだとしても、中国からの輸入製品よりも、コスト高となってしまうのである。
こうして、はくさい需要をめぐって、急速に輸入製品が、外食産業に浸透している実態の一端をみることができる。
3 はくさい生産の動向
─茨城県八千代町の事例─
前掲表1で示したように、茨城県は春および秋冬はくさいの生産が最も多い県である。茨城県の中で市町村別にみた最大産地が(結城郡)八千代町である。八千代町は県西部に位置し首都圏からは60km圏内にあり、農業は平坦な地理的条件の下に展開している。ここでは、同町のはくさい生産の動向を統計分析および農協実態調査(常総ひかり農協)に基づき紹介していく。
(1) 八千代町の農業概況
1)農業の特徴
農業センサス結果(平成12年、販売農家)からみた八千代町の農業の特徴は以下のようになる。
八千代町の耕地面積のうち普通畑が占める割合は47%とほぼ半分を占めている。県平均は29%、県西地域は30%であるから、八千代町は茨城県の中でも畑地が卓越していることが確認できる。なお、県西地域は、真壁、結城、猿島郡および結城、下妻、岩井、下館、古河市からなる地域で、県下でも野菜生産の比重が高い地域であり、八千代町は県西地域のほぼ中央に位置している。
また、八千代町の1戸当たりの耕地面積は、169aであり、県平均の132a、県西地域の138aより大きい。同じく、1戸当たりの普通地面積は、それぞれ、80a、39a、41aである。
以上のように、八千代町の農家は畑地比重が高く、かつ耕地面積規模の大きな経営基盤を持っていることが分かる。図4に示したように、八千代町では2ha以上の農家割合が高く、特に5ha以上農家は、県全体および県西地域の倍近い密度で存在している。5ha以上農家の実数は60戸であり、このうち10ha以上では20戸、15ha以上も10戸となっている。
八千代町の畑面積1,491haのうちその44%に当たる662haが借入地となっており、こうした高い畑地流動化によって、大規模農家が形成されていることになる。
図4 耕地規模面積別の農家数割合
(平成12年、茨城県)
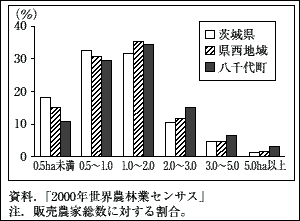
2)野菜作の展開─はくさい作を中心に─
こうした農業生産の基盤の上で、八千代町は野菜作に特化した農業が営まれている。表2に示したように、昭和55~平成2年(1980~90年)の間、農産物販売農家のうち過半が露地野菜販売を行っており、平成12年(2000年)でも43%を占めている。
表2 八千代町における野菜作の展開
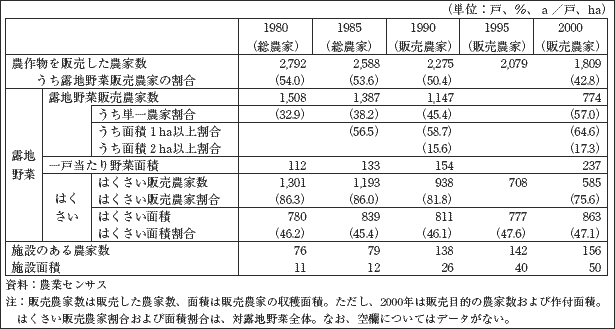
この間の野菜販売農家数をみれば、1,508戸から774戸へ半減に近い減少となっている。しかし、残った農家は、野菜作の比重を高めつつ(農産物の販売額の8割以上が野菜である単一経営の割合が昭和55年の33%から平成12年の57%まで増加)、1戸当たりの野菜作付面積規模を拡大している(同じく、112aから237aへ拡大)。特に、こうした動きは、農家数が減少の傾向を高めた平成2年以降に、顕著となっている。
そうした中で、八千代町の野菜作農家に占めるはくさい作農家の割合は、昭和55年の86%から平成12年の76%となっている。漸減の傾向はあるものの、一貫して野菜作農家の大半がはくさい作を行っている。また、この間の野菜面積のうち、はくさいが占める割合も、45~47%と半分弱を維持している。全体として野菜作農家の「はくさい離れ」ともいうべき傾向が、徐々に現れつつあるが、今もって八千代町の露地野菜作が、はくさい作を中心に展開していることが分かる。
また、併せて従来の露地野菜を中心とした経営から、施設園芸作への転換も徐々に進展していることが指摘できる。施設園芸作農家数および施設面積は、昭和55年の76戸、11haから平成12年の156戸、50haまで増加している。
次いで、八千代町の農業生産額の推移をみたのが表3である。平成9~14年における同町の農業生産額のうち野菜が占める割合は65~73%であり、同町が野菜作に特化していることがより鮮明に示されている(平成14年の比較で八千代町の71%に対して、県全体が37%、県西地域が49%である)。
表3 野菜およびはくさいの生産額の推移(八千代町)
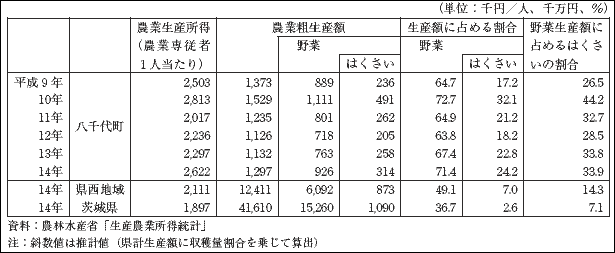
そして、はくさい単品が農業生産額に占める割合を推計すれば、17~32%(野菜全体に対しては、27~44%)に達する。この割合は、はくさいが高騰した平成10年に最大となっている。この年の農業専従者1人当たりの農業生産所得も2,813千円と最大を記録している。価格を含めたはくさい生産の如何が町農業全体に与える影響が大きいことが分かる。また、同表に示したように、はくさいの生産額は極めて振れが大きいことが、併せて指摘できる。
最後に、近年における八千代町のはくさい生産の推移を表4に沿って確認しておこう。
表4 はくさい生産の動向(八千代町)
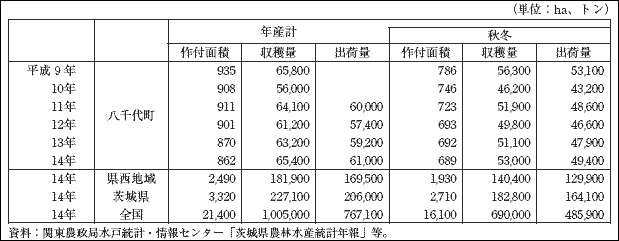
作付面積は平成9年の935haから14年の862haへ、うち秋冬はくさいは786haから689haへ、それぞれ7.8%、12.3%の減少となっている。秋冬はくさいの作付面積が年産計のそれに占める割合は、この間84%から80%に低下しており、その分は春はくさいへのシフトとなっている。
こうした作付面積の減少と比較して、この間の収穫量は平成10年の不作といった状況はあるものの、平成9年と14年は共に65千トン台であり、おおむね維持されているといえる。単収の増加によるものである。
八千代町のはくさい出荷量は平成14年に61千トンであるが、これは県西地域の36%、県全体の30%、全国の8%を占めている。秋冬はくさい49.4千トンについては、それぞれ、38%、30%、10%である。すなわち、八千代町は秋冬はくさいの全国シェアの1割を占める主産地であることが確認できる。
(2) 八千代町におけるはくさい産地の形成─昭和60年前後の産地最盛期までの状況─
八千代町におけるはくさい産地の形成の過程についてさかのぼってみてみよう。
茨城県西南地域は、かつて麦、陸稲を主体とした普通畑作地帯であったが、高度経済成長期以降の首都圏の人口拡大に伴う野菜需要の増加によって、都市近郊野菜産地へと転換していった。
こうした中で、八千代町でははくさい作が近郊野菜作の展開を牽引した。まず、はくさい作をめぐって次のような栽培技術の発展があった。昭和30年代後半には練床育苗、移植栽培法などの普及に伴って、従来の直播栽培に比べ、幼苗期の栽培管理、潅水、病虫害防除作業が精緻化、省力化され、本圃での活着率も100%近く確保されて、間引き労働も省力化された。
こうした技術の導入と並行して、同地域に多くみられる平地林の開墾による畑地の造成、さらには栽培期間が短く換金が早いという作物上の特徴も手伝って、急速な産地形成をみるのである。
同町のはくさい作付面積は、昭和41年の660haから、45年の988haまで増大し、全県では45年前後に6,000ha程でピークに達するのに対し、その後も、50年に1,100ha、55年1,400haへと増加し、昭和50年代後半に至り増大傾向が鈍化する。
同町の1戸当たりはくさい作付規模も、昭和45年の70aから55年の98aへと増大しているが40年代後半において、300aにおよぶ大規模農家が現れている。いずれにしても、先にみたようなはくさい作を基幹とする大規模露地野菜作の展開に特徴づけられる八千代町の農業は、既にこの段階にその動きをみることができる。
しかし、はくさいなど露地重量野菜は、作り易い一方、価格は安くしかも不安定であった。はくさいは、東京市場で昭和30年代の後半にこそ、大きく入荷量が増大するものの、食生活の米離れの進展と相まって、需要の減少が著しい品目であった。1人当たりの購入量は家計調査結果によれば、昭和35年の8.8kgから、55年の4.3kgpへと50%以上も減少している。
こうした商品としての性格もあって、関東農政局茨城統計情報事務所『茨城の白菜』(1973)によれば、「はくさいの価格(名目)は、昭和27年から45年までの20年間に、短期的には変動しているが、長期的には全く上昇することなく、むしろ、わずか下がっているということができる」というほど野菜一般と比較すれば、特異な動きをみせている。
このため、はくさい作のみでは経営としての安定性を欠くことから、当初は表作として、すいかがとり入れられ、後にはプリンスメロン(トンネル作)が経営を安定化させる基幹作物として導入されている。秋冬期のはくさいと夏期のすいか、メロンなどの果菜類とを組み合わせた野菜複合経営の展開である。なお、すいかの継続的な生産が可能となったのは、接木栽培の普及によるところが大きいが、この技術の導入は、はくさいの練床育苗技術の導入とほぼ並行して行われている。すいかの大幅な作付増加は昭和40年代であるが、すいかに代わってプリンスメロンの作付が増加したのは、昭和40年代後半のことである。
こうした作付方式をとることによって、はくさい産地が維持されていくことになる。なお、近郊および中間地域の露地野菜生産は、このような野菜複合経営に担われていることが多いという共通の特徴を持っている。こうした中で、昭和44年に八千代町内の5農協が合併して八千代町農協が発足し、48年8月には八千代町農協メロン・スイカ・はくさい部会が結成され、後にはくさい部会となった。
昭和50年代後半は八千代町においてはくさい生産が最も盛んであった。当時は、部会員600~700人、共販率は7割程度となっていた(農水省野菜計画課「野菜指定産地一覧」によれば昭和54年産の秋冬はくさいの共同出荷量割合は69%)。
しかし、出荷最盛期の12月のはくさい市場価格は、1kg当たり10円程度の安値に甘んじなければならない年が、昭和52年の11円、53年の9円、57年の10円(いずれも東京都中央卸売市場)と続いた。これに対処するために、この時点では、次のような物流コストを切りつめる努力がなされている。
荷姿は、1kg当たり7~8円もかかるダンボール箱(15kg詰、110~125円)を用いず、8kg束(はくさい2~4株)を紙にまいてゴムテープで結わえる独自な簡易包装(kg当たり0.8~1.0円)をとっている。
また、市場までの輸送を委託すれば東京まで1kg当たり4円はかかり、加えて出荷最盛期には、農協の集荷・配車能力も物理的に不十分であるために、作付規模の大きい農家を中心に、トラック(2トンないし3トン車)を買い入れ、自ら市場に搬入するという出荷対応が一般化していた。この場合でも農協の集荷計画に基づく共販体制下の対応となっている。いずれにせよ、はくさいの生産拡大に伴って系統共販が伸びたのであるが、この背景には、価格下落時に一定の補償が受けられる価格安定制度に組み込まれたことによる効果もあった。
ついで、当時の茨城県産はくさいの出荷市場別対応をみてみよう。基本的に一貫して京浜市場を中心として対応をしているが、昭和50年代後半から、北関東、東海、東山への分散出荷傾向や、冬場の地域内生産が不足する、北海道、東北に向けた出荷が拡大する動きがみられる。ただし、この地方都市市場への対応は、農協系統出荷ではなく産地市場が主にその機能を担っていた。
こうした動きはあるものの、秋冬はくさいは作り易く立地を選ばないため、それぞれの市場の周辺に産地が形成され、単価の安さが輸送コスト負担力を極めて小さくして、遠隔産地からの入荷を阻止する性格をもっていることから、中京・京阪神市場では、愛知産のシェアが高く、中国、四国、九州に至ってはそれぞれの地域自給率が極めて高いという地域需給圏が形成されている。
なお、八千代町を中心に近郊はくさい産地が維持された背景の1つには、高い土地生産力、すなわち高単収(重量)の維持、実現という実態を見逃してはならないだろう。昭和58年、全国平均秋冬はくさいの10a当たり収穫量が4,099kgであったのに対し、八千代町では連作障害の発生が言われながらも6,630kg(茨城県平均は6,316kg)を実現していた。
(3) 常総ひかり農協(八千代地区)管内におけるはくさい生産の動向
1)はくさい販売状況
八千代町を管内に含む常総ひかり農協は、平成6年2月に、八千代町のほか、下妻、千代川、石下、水海道の5農協が合併した広域農協である。各旧農協単位に野菜集荷場があって、旧農協単位による野菜出荷対応を色濃く残している。ここでは、同農協の八千代地区のはくさい生産・販売対応の最近の動向をみていく。
同地区での平成15年度(農協会計年度:2月から翌1月)のはくさいの取扱実績は、販売量が18,794トン、販売金額が1,073百万円となっている(1kg当たり販売単価は57円)。はくさい部会員数は180戸であるから、1戸当たりの販売額は596万円となる。
秋冬はくさい(10月~翌3月)の出荷実績のここ数年の変化は表5に示したとおりである。総出荷のうち7~8割が卸売市場向けであり、市場向けの9割程度が関東市場であり、京阪神と東北がそれぞれ5%程度である。出荷時期別にみれば、およそ11~12月の出荷最盛期で6割、1~3月が3割、10月が1割の構成となっている。
表5 秋冬はくさい出荷実績(常総ひかり農協八千代地区)
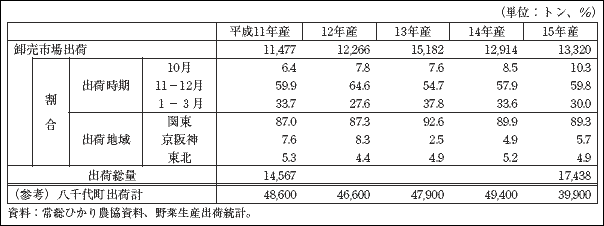
一方で、2~3割弱が市場外出荷、そのほとんどが全農茨城県本部の産直組織であるVFSとの契約となっている。契約生産を主に担っているのは、規模の大きなはくさい生産者であり、生産者側からみてはくさい生産のうち契約が占める割合は30%程度(最大で50%程度)となっている。
平成14年産および15年産の常総ひかり農協出荷のはくさい月別市場価格は表6に示した(同表は八千代地区以外も含む常総ひかり農協全体のものであるが、八千代地区が農協出荷の7割近くを占めている)。年産平均で1kg当たりそれぞれ、49円、41円と低迷しており、秋冬のみでは47円、33円とさらに低い。既に、はくさいの全国卸売市場での価格の動向は、前掲図3でみたところであるが、この農協出荷についても同様な状況であることが確認できる。
表6 はくさい市場価格(常総ひかり農協)
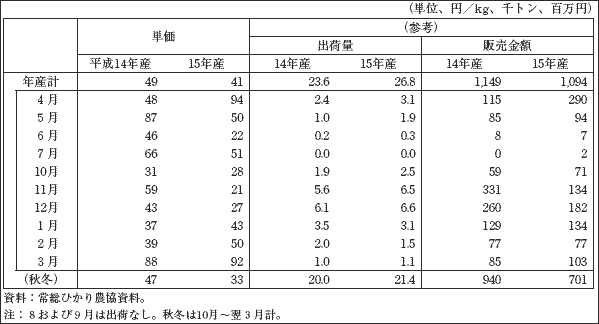
一方で契約価格については、価格高騰時の平成10年産が89円と高かったが、以降11年から15年産にかけては、ほぼ30円台で推移している(平成14年産は40円、15年産は31円)。
こうした価格低迷の状況にあって期待されるのが、価格安定制度に基づく交付金の交付である。平成11年度以降の交付実績は表7に示したとおりである。この間に程度の差はあれ、いずれの年度も交付されており、一貫して価格が低迷していることになる。中でも隔年置きに11年、13年、15年の価格低下年での交付額が多い。なお、交付金は市場価格が過去の平均価格を基に算定された保証基準価格を下回った旬に対して交付される。
図5 農業就業人口の変化
(八千代町、男子・年齢別)
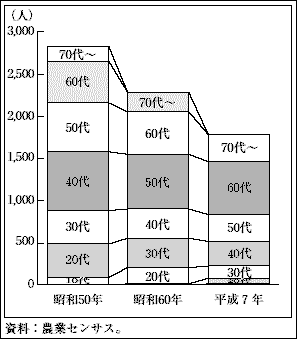
表7 秋冬はくさいの交付金交付実績(常総ひかり八千代地区)
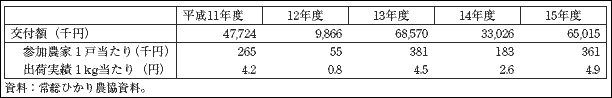
15年度の場合で、交付額は6,500万円であり、参加農家(180戸)1戸当たりでは36万円、出荷量1kg当たりで4.9円の補てんがなされたことになる。農協の担当者によれば保証価格が再生産価格を下回っているとして、必ずしも十分な保証を受けているとは考えてはいない。農協で想定している再生産価格は60円であるが、ちなみに関東市場出荷の場合の保証価格は、10月で46.5円、11~12月が30.0円、1~3月が55.0円となっている。
2)はくさい作経営の展開
八千代町の農業は、はくさい作を中心に野菜作に特化している。一般に野菜作は労働集約的な営農形態をとることが多い。八千代町の農業労働力のあり方に注目してみよう。図5は、同町の男子農業就業人口の動きを年代別に示したものである。八千代町の場合、はくさい生産が最も盛んであった昭和50~60年には、男子の担い手が各年齢層で比較的バランスがとれた形で存在していたことが特徴的である。
特に、昭和50年段階では、壮年層の経営主(40歳代)とその父親(60歳代)と後継者(20歳代)の三世代にわたる担い手を確保した農家も少なからず存在していたことが推測される。この時点で経営の中核を担っていた40歳代層が、昭和一桁生まれである。
平成7年には、昭和一桁生まれ層が60歳代となった。この段階では高齢者の多くがリタイヤし、若年層の就農は少ない。このため同層が担い手としての比重を高めざるを得ない状況となっている(平成7年には農業就業人口全体の35%、昭和50年には24%)。
しかしながら、その後継者層である40歳代の担い手層は比較的確保できており、はくさいの経営主も40歳代が中心となっている。同地域の農業普及センターの資料によれば、平成8年に八千代はくさい部会の198戸のうち、98戸(48%)が40歳代経営主となっている。この時点では、親世代との二世代経営が中心ということになる。
さて、それからほぼ10年を経た現時点では50歳代が経営主となり、昭和一桁世代は70歳代で多くはリタイヤせざるを得ない状況となっている。後継者層もかなり薄くなっている。このため、はくさい作も50歳代夫婦による一世代型経営といった経営も少なからずあることになる。
こうした労働力状況にある中で、はくさい作は一方で労働節約的な技術の導入を図りながら、他方では雇用型の経営が増加するという変化をみせている。
労働節約的技術の導入としては、移植機の導入と段ボール出荷への移行が挙げられる。移植機は県単補助事業により平成7~9年に24台、10年に9台、11年に8台が導入されている。
移植機の効果について、普及センター資料によれば以下のように述べられている。全自動移植機の導入によって、育苗日数17~18日の苗を用いて、10a当たり90分程度で植え付けることが可能となった。導入前は、労働力5人総出でも1日35~50aしか植え付けができなかったにの比べて、作業は非常に軽減されている。移植機の操作は妻が行い、経営主は定植のための圃場づくり(耕起、畦づくりなど)や苗運搬を行う。残りの3人は抑制アールスメロンの管理作業などの他の作業に従事するというように、作業分担ができるようになった。
また、出荷荷姿は昭和35年頃から長らく紙巻き結束方式が続いていたが、昭和60年代に入って段ボール箱へ置き換わっていき、平成8年頃には定着するところとなっている。従前は、はくさいを持ち帰って家での作業となっていたが、段ボール出荷の場合は、圃場での作業が可能となったことで省力化となった。
なお、農林水産省農業経営統計調査の「野菜・果樹品目別統計」によれば、平成15年産の茨城県の秋冬はくさいの10a当たりの労働時間は92時間となっている。これに対して平成2年産のそれは(野菜生産費調査)、115時間となっており、この間の省力化の経過を窺うことができる。
一方で、雇用労働力の導入については、はくさい作以外の農家を含む町全体ではあるが、表8に示したようになる。常雇(年間7ヶ月以上の雇用)、臨時雇用とも平成に入ってから増加し、特に7~12年にかけての増加が著しい。平成12年の常雇数201人は、市町村別にみて茨城県で最も多い実績となっている。こうして、近年、はくさい作は雇用に依存した経営が少なからず展開している。
最後に、はくさいの収益性について検討しておこう。同じく「野菜・果樹品目別統計」によれば平成15年産の茨城県の秋冬はくさいの10a当たり所得は95千円、家族労働1時間当たりでは1,127円となっている。この場合1kg当たり卸売単価は49円程度と推計される(同統計には流通コストの計上が無いため、常総ひかり農協資料により、同コストを加算して求めた)。この1時間当たり1,100円程度の所得は、一方で農協が想定している家族労働コストの1,000円をやや上回っていることから低い水準ともいえない。
今後の価格水準の動向にもよるが、はくさい作は10a当たりの所得が低いとしても、労働節約技術の導入を伴った規模拡大が一つの経営展開の方向として示されることになろう(規模拡大の経過など八千代町のはくさい作の展開については図6参照)。事実、八千代町では、秋冬はくさいで20ha規模の農家が存在しているという。
一方で、規模拡大を希望しない農家の場合には、これもはくさい作の省力化を基礎にしながら一層の複合部門の拡大が指向されている。農協では平成16年11月にモデル経営類型を策定した。その1つとしてパイプハウス30aと露地100aの経営規模で、ハウスではメロン(2作で60a)およびカブ(30a)を、露地ではメロン(30a)、秋冬はくさい(100a)というモデルを示している。この場合、想定される所得は6,145千円であり、そのうち秋冬はくさいは780千円となっている。施設園芸を主体とした経営に従前の露地作を組み込んだ営農類型ということになろう。
こうして、はくさい作は、引き続き一方では大規模経営が形成されながら、他方では経営の副次部門として性格を強めた経営とに分化しながら展開していくことが見込まれる。
表8 農業雇用の動向(八千代町)
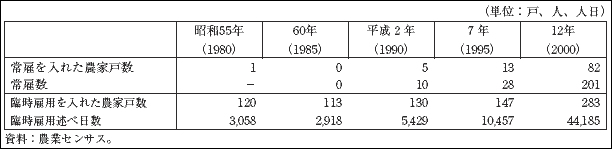
図6 はくさい生産の動向(茨城県八千代町)