 海外情報
海外情報
韓国の農業政策の転換と野菜生産・流通の新たな展開(1)
~韓国の農業政策の展開過程~
社団法人JA総合研究所 基礎研究部
主任研究員 柳 京煕
南九州大学 環境園芸学部
准教授 姜 暻求
Ⅰ.はじめに
日韓両国の農産物貿易額の推移を見ると、1995年に韓国が日本へ輸出した農産物の輸出額は、約3億2,000万ドル(日本円に換算して約291億2,000万円)、そのうち、園芸農産物は9,700万ドル(同約88億2,700万円)で、全体に占める割合は30.4%であったが、2004年には約6億2,700万ドル(同約570億5,700万円)、そのうち、園芸農産物2億4,200万ドル(同約220億2,200万円)で、同38.5%へと拡大した。
一方、日本から韓国への農産物の輸出額は、1995年の約2億3,600万ドル(同214億7,600万円)、そのうち、園芸農産物1,500万ドル(同約13億6,500万円)で、同6.2%から2004年の約1億6,800万ドル(同約152億8,800万円)へと縮小している中で、園芸農産物の輸出額は、約2,200万ドル(同約20億200万円)で、同12.8%へと拡大している。今は交渉が中断しているが、日・韓FTA(自由貿易協定)締結交渉が妥結すれば、両国間の園芸農産物の貿易は、さらに拡大していくことと予想される。
しかし、そのような現状にあるにもかかわらず、日本国内においては、韓国の園芸農産物についての情報は、必ずしも豊富とは言えない。
本稿では、韓国の園芸生産、とりわけ野菜生産を念頭に置きながら、韓国の農業政策を踏まえたうえで、園芸生産・流通分析を3回に分けて行うが、第一回目は、韓国の農業政策の展開過程について考察する。
韓国の農業に対し、輸入自由化の波が本格的に直撃し始めた1980年代以降から最近のFTA政策まで重要な政策を重点的に取り上げながら、その歴史的展開と政策の特徴について明らかにする一方で、そのような一連の農業政策のうち、園芸政策がいかに扱われ、またどのような部門に集中的に政策支援が行われてきたかについて考察する。第二回目は、1980年代末から貿易自由化への本格的な対応が求められた韓国政府が、自由化時代の農政として「守る農業から攻めて守る農業への転換」を行う際、最も重点的に生産・流通基盤整備を行った野菜部門に焦点を合わせ、その生産・流通に関わる政策の展開について概観する。そして、第三回目は、韓国園芸生産の成長を牽引してきた種子産業(育苗部門)の現況について考察を行うと同時に、近年の農業政策の目玉であった親環境農業がどのように成長してきたかについてその成立過程と現状に至るまでの展開過程について整理し、全体の総括として、韓国の園芸生産・流通の現段階と今後の方向について検討し、韓国園芸部門の成長要因の一つであった対日輸出の意義とそれに伴う日・韓の農業部門への連携・協力の可能性について述べたい。
Ⅱ.農業政策の変遷
1.経済成長に伴う農業政策の変化
工業化による経済成長を優先してきた韓国において、1970年代半ばまでの農政は食糧の増産に主眼をおいていた。その後、農家の所得向上や農工間の所得格差の是正に移り、その一環として園芸農産物の奨励も位置づけられた。その後、経済発展に伴い、食糧問題は1970年代半ばになるとほぼ改善され、畜産および園芸部門においても、複合営農および畜産の奨励、ハウス栽培技術の普及によって大幅な増産を見せたが、流通政策が遅れたため、野菜と豚肉価格が乱高下を繰り返し、農家の負債問題、流通問題が新たな問題となった。
1980年代前半は、一連の政治的不安から一時期マイナス成長を余儀なくされるが、その後、経済が回復し、1986年から高い成長率と国際収支の改善を背景に、経済政策が政府主導型市場保護から民間主導型市場開放へと大きく転換した。一方、農業政策では、米穀増産および価格支持政策が実施され、農業所得が増大し、畜産・園芸奨励により園芸、畜産業が大きく拡大した。しかし、野菜類と畜産物においては、価格の乱高下により、生産者の負債が増加したことから、農業政策に大きな批判が集まった時期でもあった。
2.貿易自由化時代の農業政策の展開
農政に大きな転機をもたらしたのは、1980年代終わりのGATT(関税および貿易に関する一般協定)特恵国からの除外、GATTウルグアイラウンド(以下、「UR」と略す)の妥結、FTAの推進など、経済のグローバル化である。政府は、グローバル化時代の農政として「新農政」を標榜し、国民のコンセンサスを後ろ盾に、農業・農村構造改善へ莫大な予算を投入し、生産基盤および物流の整備を図った。特に園芸部門は、農業の成長部門と見なされ、集中的な支援が行われた。その結果、品質の大幅な向上と収穫後の品質保持技術の普及により、良質な農産物を国内消費者へ提供するだけでなく、輸出部門として成長してきた(表1)。
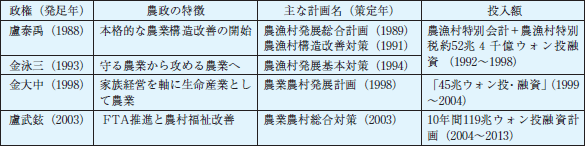
注)農漁村特別会計は本文中の「42兆計画」、農漁村特別税は「農特税」を指す。
政府は、輸入自由化を念頭に置きながら、その対応策として、国内の農産物の国際競争力を高めるために、3次にわたる農業構造転換政策を実施した。
第一次構造転換政策は、1989年にとられた「農漁村発展総合対策」である。同対策は、長期における農漁業の構造改善を狙うもので、政府は、「農漁村振興公社」と「農地管理公社」を新設し、農業の法人化を促進するための農地購入資金の融資により、営農法人および委託営農法人の育成を図った。ほかに農外所得および農村定住圏の開発、農産物加工業の育成、豚肉および園芸農産物の輸出促進を主な施策として提示した。
第二次構造転換政策は、GATT・BOP(Balance of Payment)委員会が、韓国を輸入制限国から除外したことを受けて、翌年の1991年に打ち出された「農漁村構造改善対策」である。この対策は、前回の政策をより具体化するため「農漁村構造改善特別会計」を新設し、1992~2001年にかけて農漁村構造改善に新たに42兆ウォン(日本円に換算して約3兆1,500億円)を投資するという内容である(「42兆計画」と称する)1)。
1993年2月に発足した金泳三政権は、従来の農業政策とは異なる、自由化時代の農政(「新農政」と称する)を標榜した。「新農政」が従来の農政と抜本的に異なる点は、
① 農業を産業として認識し、「生産→加工→マーケティング」という一連の過程を各インダストリー政策に盛り込んでいる点
② 大統領の諮問機関として「農漁村開発委員会」を設立し、農政にかかわる行政を、縦割り行政から横割り行政へ転換した点
③ 「守る農業から攻める農業」への転換を目指した点
が挙げられる。そのうち、「攻める農業」の核心は、農産物輸出であり、日本向け輸出であったことが大きな特徴である。
こうした「新農政」の具体的な計画(新農政5カ年計画)は、皮肉にも1993年12月に妥結したURが追い風となり、政府の想定を遥かに超える国民の支持を得て、農業部門への積極的支援が可能となった。これによって、1994年3月24日に農漁村の競争力強化、農漁村産業基盤施設の拡充および農漁村地域開発事業に必要な財源を確保することを目的とした国税である「農漁村特別税」(以下、「農特税」と略す)が導入され、農業部門への財政的な支援が具体的に施行されるようになったのである。(1992~1998年の間「42兆計画」+「農特税」=57兆ウォン投入計画)。
農業・農村への短期の集中的な投・融資(期間中の実施額52兆3,000億ウォン)は、大きなインパクトを与えた。特に「42兆計画」は、3分野(競争力強化、生活環境改善、福祉増進)のうち、全投・融資額の約60%を競争力強化分野に充てる一方、「農特税」の税収を競争力強化分野に重点配分することによって、生産施設および流通施設の抜本的な改善が実施された。以上の投・融資により、国家予算に占める農業部門予算は急上昇し、1995年には14.8%に達した。
このような中、1997年11月に訪れた外貨危機は、韓国経済にとって未曾有の出来事であった。翌年2月に発足した金大中政権は、これまでの「農業基本法」を大幅に改定し、1999年2月に「農業・農村基本法」と改める一方、「農業は生命産業であり、食料の供給と環境保全を担う産業であると認識し、グローバル化と地域化に適合する家族農業を育成する」としており、前の政権とはかなり方向性が異なる政策理念を打ち出した。
金大中政権期間(1998~2004)における投・融資についての基本的考えは、ハード事業への投・融資を抑える一方で、産地流通改善や輸出促進、親環境農業の育成、農家経営の改善に投・融資をシフトさせた。
しかし、このようなパラダイムの転換は、必ずしも農産物輸出促進政策を撤回することを示すものではない。当政権の農政のバックボーンである「農業・農村発展計画」にも盛り込まれているように、高品質農産物の生産と農産物輸出団地の造成、海外市場開拓の支援、輸出金融制度の拡充などによる輸出農業の育成は、引き続き実施された。
3.自由貿易協定(FTA)推進
金大中政権の政策理念を受け継いで発足した、盧武鉉政権の経済政策は、基本的には所得の分配とFTAの推進であった。このスタンスは農政にも反映され、農村地域の福祉増進と直接所得補償、FTAに伴う国内対策に主眼がおかれ、任期終了直前の2007年4月には、米・韓FTAが合意した。当政権は、「農業農村総合対策」(以下、「総合対策」と略す)を策定し、2004~2013年までの10年間で119兆ウォン(日本円に換算して約8兆9,250億円)の農業予算を投入することを決めた。「総合対策」の主なものは、
① 農業体質強化(投融資額の52%)
② 農業者所得安定(27%)
③ 農村福祉増進などの事業(15%)への集中投資
である。具体的な重点施策としては、親環境農業の普及、専業農業者20万世帯育成、農業規模拡大による価格競争力確保、優良品種開発、農産物流通革新、排水改善、施設改善、畑作基盤整備である。さらに、暫定的に運営している「農特税」を今後10年延長し、農業地域の福祉向上を目的とする農漁村福祉向上基金の助成などの財源を確保した。
盧政権の目玉政策は、所得政策と言える。直接支払い制度を所得政策の中軸として据えており、直接支払い制度の予算は2004年 9,300億ウォン(同697億5,000万円)(10.8%)から、2013年には3兆4,100億ウォン(同2,557億5,000万円)(22.9%)まで増やす計画を策定した。
次に、韓国のFTAの推進過程について見ると、2004年韓・チリを皮切りに、2006年韓・シンガポール、2006年韓・EU、2007年韓・米FTAに至るまで、すべてのFTAは、当政権において締結されている2)。当初から盧武鉉政権は、WTOドーハ開発アジェンダ( Doha Development Agenda)/自由貿易協定(FTA)などによる農産物市場開放に対応するため、「総合対策」に国内農業の競争力を高める施策を盛り込みつつ、他方、関税撤廃によって影響が大きいと思われる分野では、「FTA履行特別法」を制定し、「FTA履行支援基金(通称FTA基金)」3)を創設し、FTAによって被害を受ける生産者の競争力の向上や経営安定を目的として2004年6月1日より実施した。
所得政策とFTA対策、そして、もう一つ農業政策の柱としては、「親環境農業政策」の推進が挙げられる。親環境農業が具現化したのは、1997年の「環境農業育成法」の制定からである。同法は翌年98年12月から施行され、これに付随する親環境農業関連法が次々と制定・施行された。
Ⅲ.園芸生産政策
1.UR以前の園芸政策
韓国政府は、食糧問題が1970年代にある程度解決されたことにより、「第4次経済開発5カ年計画(1977~1981年)」における農業開発政策として、園芸政策を本格的に実施した(表2)。果実部門では、果樹面積の拡大と協業化を図る団地に対して貯蔵施設を助成した。野菜は、92カ所の蔬菜団地(3万7,945ha)が指定され、貯蔵・流通施設および機械化資金の支援が行われた。
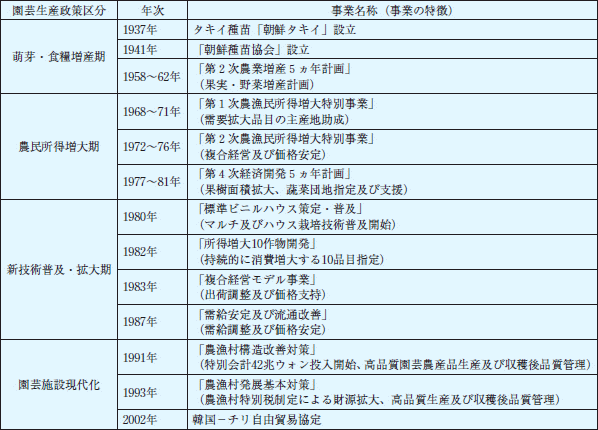
こうした背景には、国民所得の増加により、野菜・果実の消費が拡大したことがある。さらにこの時期に、新技術の導入によって生産に大きな転機がもたらされたことを指摘しておく必要がある。
政府は、1980年に4種類の標準ビニールハウス規格を策定し、ビニールハウス本体と換気施設およびかん水施設の普及を支援した。また、試験場の役割を担っている政府機関である農村振興庁は、マルチ栽培およびビニールハウス栽培技術の開発・普及事業を行った。これによってハウス面積が、1970年4,000ha、1975年7,000ha、1980年1万8,000ha、1985年2万9,000haへと急増した。その後1980年代末、園芸政策は需給安定にその対策が移った。
また、この時期はハウス栽培技術の確立によって周年生産が一般化された。
2.UR以後の園芸政策
園芸部門は、1993年のUR交渉の妥結によって、新たな転機を迎えることとなった。前述のように、政府はグローバル化時代の農政として「新農政」を標榜し、従来と全く異なる農政へと転換した。その中で園芸部門は、成長潜在力と国際競争力のある部門として見なされ、政府が「施設の近代化」「輸出支援」「物流近代化」をワンセットとして支援した。野菜の場合は、露地の灌水施設整備拡充、選別・低温倉庫建設、ガラス温室をはじめ施設の近代化に膨大な予算が投入され、品質の向上と輸出基盤が助成された。
果樹は、品種の更新や古い果樹園の廃園、流通基盤整備を中心に政策が展開された。また、この時期に新たな成長作物として切花が政策的に導入された。切花は、主にガラス温室で生産するが、「花卉系列化事業」によって、小規模生産体制から20ha以上の大規模生産へ移行し、種苗の生産から収穫・選別・輸出まで系列化が図られた。
図1は、園芸生産額の推移を示しているが、園芸生産がいかに政策によって大きく左右されたかが読み取れる。特に1980年代に入り、マルチおよびビニールハウス栽培普及、1990年代以降の高品質生産基盤整備と収穫後の品質管理によるグローバル化対応策などは、節目ごとに停滞から成長へと導いているといえよう。
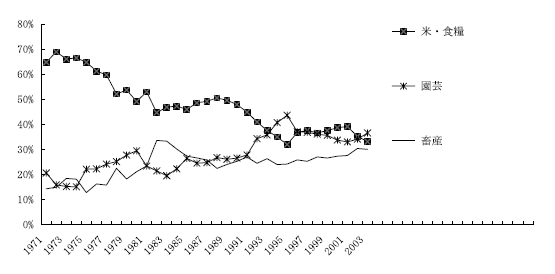
Ⅳ.園芸流通政策
1.1990年代の流通政策
1970年代半ばから、青果物の商品化率の急増、農家の市場志向的な生産、流通基盤の脆弱さによる価格の乱高下などが、大きな社会問題となった。これに対処するため、政府は1976年に「農産物流通および価格安定に関する法律、(以下、「農安法」と略す)」を制定し、卸売市場の近代化を進める転機となった。1985年に、最大消費地であるソウル市に可楽中央卸売市場(Garak Market)を皮切りに、全国の重要都市に中央卸売市場を開設した。
青果物流通を既存の私設市場経由から、公正な価格形成が可能な公営中央卸売市場へ移す転機となった4)。また、産地集荷商人の役割を大幅に減らし、農家または生産者団体が大都市および中小都市へ直接出荷することで、効率的な流通経路の確立を図ったことも大きい。しかし、このような過程で既存の産地集荷商人や私設市場委託商人を中央卸売市場の卸売業者として取り込まなければならない実態を招く一方、産地においても農協による共販場が開設された5)。これにより、当初の目標であった公正な価格形成や効率的な流通経路の確立からは、大きくかけ離れる結果となった。
他方、このような努力にも関わらず、農産物の物流コストが農業生産額の約27%を占めるに至り、物流コストの削減が社会的に要求されるようになった。とくに農産物物流コストの約50%を青果物が占めていたため、青果物流通の合理化は焦眉の問題となった。さらに、1996年の流通部門の全面的な自由化によって、外国の大型流通業者(例えば外資系のマクロMacro、カルフールCarrefour、ウォルマートWal-Mart)が国内に進出し、量販店を中心に青果物流通が急速に再編されることとなった。外国の大型小売店の参入は、国内の大型店およびディスカウントストアは言うまでもなく、産地市場や卸売市場にも大きな影響を及ぼした。国内の大型小売業者は、安い仕入れ価格による競争力アップを図るため、産地との直接取引ルートを開拓するようになった6)。
このような量販店台頭や物流合理化の必要性が浮上する中で、産地流通改善が求められるようになった。
これらの問題に対し政府は、1993年に政策の重点を流通分野に絞った「農産物物流合理化事業」を実施した。
その内容は、農産物流通施設(産地流通センターと農産物総合物流センターAgricultural Product Packing Complex:APC)を中心に、生産者団体による「出荷調整」「ブランド化」「高品質化」「規格化」を推進するものであった。引き続き政府は、1990半ばから流通改善対策として、「農漁村構造改善対策(財源:農漁村構造改善特別会計)」および「農漁村発展基本対策(財源:農漁村特別税)」の事業から多くの資金を振り分け、青果物流通施設(Agricultural Product Processing Center:APC)を建設した。
結果、事業の開始から施設が急増し、1999年までに簡易集荷場が3,290カ所、APCが141カ所、農産物加工場が1,407カ所建設された。その運営主体は、「総合農協」「専門農協」「作物班(生産部会)」「営農法人」などの生産者団体である。その後、産地流通施設の運営でさまざまな問題が顕著化し、非効率的な流通施設の廃止と流通施設への投資の抑制が行われ、2002年には簡易集荷場が3,065カ所、農産物加工場が1,097カ所へと減少した。青果物流通の主要な担い手であるAPCだけは、206カ所へ増加した(APCのうち、青果物APCは、204カ所である)。いかに青果物流通に政策を集中していたかが、確認できる。
2.2000年以降の流通政策
2000年以降の青果物流通政策は、「農産物流通改革委員会」を中心に行われた。その内容を「産地流通政策」「卸売市場政策」「物流および情報化政策」に分けて整理してみよう。
まず、「産地流通政策」を見ると、政策目標は、
- (1)構造的需給安定のよる適正価格安定の実現
- (2)生産者組織(作目班、営農組合法人、委託営農会社など)の育成による共同出荷率の向上
- (3)産地流通施設の拡充および運営活性化による産地包装・加工・ブランド化推進
となっている。
次に、「卸売市場政策」を見ると、施設面では、
- (1)地方自治体の財政負担を考慮し、卸売市場建設費を国庫で支援する
- (2)私設市場を中央卸売市場へ吸収させるか、一定の条件を満たしている私設市場を地方卸売市場として指定・管理する
- (3)中央卸売市場や大都市集配センターの低温貯蔵庫、荷役施設、駐車場などの施設を改・補修、新規建設する
としている。
そして、「物流および情報化政策」を見ると、「物流」の具体的な政策手段として、規格包装の定着のために、
- (1)農産物包装規格をユニットロードシステム(輸送しやすい単位にまとめて輸送するシステム)に併せて整備する
- (2)包装資材の支援を大幅に拡大する
- (3)中央卸売市場への非包装青果物の入荷を制限する。また、コールド・チェーンシステム確立のために、農家の低温貯蔵施設建設への補助金提供、産地低温施設への国庫補助を新規支援する
などであり、「情報化」については、
- (1)卸売市場や物流センターと生産者団体間の電子データ交換(Electric Data Interchanging)システムの導入および拡大による農産物流通業務の効率化を模索する
- (2)農協などの生産者団体に農産物電子ショッピング・モール(Shopping-Mall)を開設し、直販や統合モールの構築による電子商取引を促進するなどの政策手段を用いるとしている。これについては、次回詳しく紹介したい。
注
- 1)本稿における米国ドルおよび韓国ウォンの日本円への換算については、過去の為替レートにかかわらず、便宜上一律に、2009年9月時点の1米国ドル≒91円、1000韓国ウォン≒75円で計算した。
- 2)韓国のFTAへの取り組みについては、姜求・柳京熙「米韓FTAにおける農業保護から自由化への転換に関する研究」南九州大学研究報告第38B号、2008年4月を参照。
- 3)韓国・チリFTAの時に創設された。
- 4)公設卸売市場の開設以前には、消費地の私設市場と呼ばれた市場で実質的に野菜の収集・分配機能を担っていた。
- 5)農協共販場は農協が敷地内に敷設した簡易セリ場である。
- 6)2005年時点で4店舗以上を出店している大型販売店14社だけの出店の推移を見ると、1995年に全国にわずか17店舗にすぎなかったが、2005年12月時点では271店舗にまで増加している(韓国チェーンストアー協会「大型販売店の現況と展望」2006年を参照)。また、ソ・ソンチョン・キム・ピョンリュル「大型販売店の農産物購買形態分析と展望」韓国農村経済研究院、2006年によると、大型販売店の農産物の総売り上げ規模は3兆2,000億ウォンと推定している。