 海外情報
海外情報
韓国における身土不二運動の展開
千葉大学大学院 園芸学研究科
准教授 櫻井 清一
助 教 霜浦 森平
1.はじめに
食品をめぐるグローバリゼーションは日に日に進んでいる。どの国・地域でも、外国から入ってくる多様な食材、あるいは輸入飼料を食べて育った家畜由来の畜産物にかなり依存した食生活を送っている。しかし、こうした傾向が顕著になる一方で、地元で採れた食材や地域固有の食生活を見直す動きも世界各地にみられる。こうしたローカル・フードシステム再評価の動きはとりわけ先進国で顕著である。イタリアで始まったスローフード運動は、日本をはじめ多くの国に紹介されているし、農産物輸出国であるアメリカにもBuy Local運動がある。日本でも「地産地消」をキーワードとした取り組みが浸透しつつある。
日本のお隣の韓国は、この4半世紀の間に急速な経済発展・都市化と、それに伴う農業構造の変動を経験してきた。ライフスタイルの変化も激しく、それは野菜と唐辛子・味噌の絶妙な組み合わせにより育まれてきた韓国の伝統的食生活にも及んでいる。この韓国でも、「身土不二」という言葉を掲げた国産・地場産食品の価値を見直す運動が取り組まれている。韓国のローカル・フードシステムの動きを、自然・経済条件が似ている面も多い日本の動きと比較することは、地産地消をはじめとする地場食材見直しの取り組みを冷静かつ相対的に評価することにもつながるであろう。
そこで本稿では、韓国の身土不二運動の展開を、日本の動きとも比較しながら紹介することにする。その際、韓国の食生活において極めて重要な役割を果たしている野菜の取り扱い状況についても随時述べることにする。
2.身土不二とは?
身土不二(韓国語読みでは「シントブリ」)は、もとは仏教に由来する概念である。漢字表記のとおり、人間のよりどころとする身体とその人の生まれ育った土地・環境とは切っても切り離せない関係にあることを意味する。ここから派生して、農業や食の問題と結びつけてとらえられるようになり、「郷里の食材や地元の食文化を大切にすることが、健康上も望ましいし、自然環境の保全、さらには生活の安定・向上にもつながる」という意味に解釈されている。出典や語義の変化については諸説あり、定まった評価はない。しかしローカルな食材の優位性を強調することでは、この用語を使う論者の考えはほぼ一致している。
韓国で身土不二の概念が普及し始めたのは1980年代末である。この時期はガット・ウルグアイラウンド農業交渉が山場を迎えた時期とも重なる。当時の韓国も日本と同様に輸出国から農産物自由化の圧力を受け、国内農業の基盤も揺らいでいた。そのような中で、韓国農協中央会(以下「中央会」)が身土不二をスローガンとして掲げ、マスコミや学校教育の場を通して、韓国産農産物の積極的な購入と利用を呼びかける運動を展開した。この取り組みがある程度国民にも浸透し、その後も身土不二というスローガンが随所で用いられるようになった。
このように身土不二運動は農協主導による取り組みとしてスタートした点がユニークである。韓国の農協も日本と同じく総合農協(販売・購買・金融など様々な事業を地域の農協がまとめて行う運営方式)である。しかし、その全国組織は、事業別に組織が分かれている日本とは異なり、中央会が全ての事業や機能を一括して担当している。そのため中央会は経済的にも社会的にも巨大な存在である。この中央会が当初から主導した、全国的な運動であったことは、地域の小さな取り組みが徐々に認知され、その後自治体等の公的部門や農協も支援するようになった日本の地産地消運動と異なっている。
3.農協の店舗にみる国産・地場野菜の流通
図1は韓国と日本の1人当たり年間野菜消費量を比較したものである。韓国の消費量はアジアや世界の平均も大きく上回っており、世界有数の野菜消費国であることがわかる。韓国で食堂に入ると、まずミッパンチャンという総菜のセットが出される(写真1)。キムチをはじめ様々な野菜料理が並び、その豊富さに驚かされる。また、焼肉や刺身を食べるときも、サンチュやエゴマの葉で包んで食べることが多い。鍋や汁物にも野菜はたっぷり入っている。韓国の食卓で野菜は主役を演じていると言える。
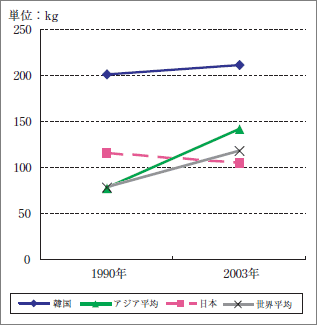

身土不二運動をリードしてきた韓国の農協は、購買部門として小売店チェーンも展開している。この農協店舗の運営方針にも身土不二の考えが反映されており、現在では「農産品は原則として国産品のみを販売する」という方針を貫いている。農協の店舗にはハナロクラブとハナロマートという二つのタイプがある。それぞれの特徴と、野菜をはじめとする食材の取扱い状況を紹介しよう。
ハナロクラブは、農協中央会またはその関連会社が運営する大型の店舗である。食料品や日配品だけでなく、家電品や衣料も扱う店舗もあり、日本の総合量販店に近い業態といえる。2005年現在で15店舗オープンしている。こうした大型量販店が韓国では急成長しており、ここ5年間では前年比10%以上の売上増を毎年達成している。ライフスタイルの都市化と自動車の普及により、特に若い世代は大型量販店でのショッピングを好むという。表1は主な大型量販店チェーンの売上額であるが、ハナロクラブも財閥系または外資系のチェーンと競合関係にある。その中でハナロクラブは、食料品を重視し、さらに国産の食材にこだわった品ぞろえをすることで顧客に安心感を与え、他社との差別化を図っている。
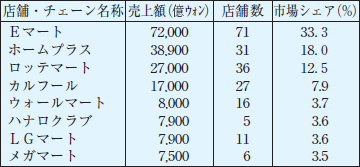
注1) カルフールは、現在、韓国市場から撤退している。
2) ハナロクラブの店舗数は上記資料では過小となっている
筆者らが調査した水原市ハナロクラブ(写真2)は、売り場面積15,000m2、駐車場1,000台分を確保する大型店舗である。店内の食料品売り場をみると、生鮮農産物については100%国産品を扱うというポリシーを貫いている。牛肉も韓国産の韓牛のみである。水産品や加工食品については一部輸入品も並んでいるが、国産重視の方針であることには変わりない。
野菜売り場では、「親環境農産物」のラベルを付した産品コーナーがかなり広くとられており、品ぞろえも充実している(写真3)。


韓国政府は、1997年に環境農業育成法を制定し、その後農家や集団への直接支払いもリンクさせた制度を用意して環境保全型農業を支援しており、取り組む農家数も急増している。野菜はその対象品目として重視されており、消費者の関心も高い。産地では日本よりも早くからGAPの導入が推奨されてきた。単に地元産・国産であればよいのではなく、品質や栽培環境保全の側面でも輸入品との差別化を図ろうとする姿勢をうかがうことができる。
ハナロクラブは、その大規模性が注目されがちだが、もう一つのユニークな特徴として、産地から仕入れを行う卸売機能を持っている点が注目される。日本の全農が運営している生鮮食品集配センターに近い機能を担っている。卸売機能を自前で持つことにより、産地・農家に対しては手取り金額のアップを、消費者に対しては小売価格の低下を図ろうとしている。卸売部門の取扱額は小売部門に比べ小さく、店舗間格差も大きいと言われている。それでも出荷する産地・農家の手取り価格が上昇したことを示す調査結果も報告されるようになり、卸売部門を内部化した成果はある程度出始めているようである。
一方、ハナロマートは、韓国全土に展開する個々の農協が運営する中小規模の小売店の総称で、2005年現在で2,588店オープンしている。日本のAコープに相当する。取り扱う商品も類似しているが、近年、全土のハナロマートでは日用品や農業資材よりも食品の販売を重視する戦略をとっており、ハナロクラブと同様に農産物は原則として100%国産品を取り扱う方針を守っている。
4.身土不二の「土」が意味するもの
このように、韓国農協は、自身の小売部門でも身土不二の名のもと、国産品を最優先して販売し、消費者に対し国産品の優位性をアピールしようとしている。
ここで一つの疑問が生ずる。身土不二の「土」が意味するのは韓国という一国なのであろうか。本来は人々が生まれ育った郷里、あるいはその人が今住んでいる地域共同体を指すはずである。しかし、農産物販売の現場では、国産品であることは強調されるが、韓国のどの産地・地域で生産されたかについてはあまり言及されることはない。店頭の野菜に付いたラベルや陳列棚の説明をチェックしても、国産との表示は随所に見られるが、具体的な産地や生産者を記してあることは稀である。そのため多くの国民は身土不二を国産品の愛用運動としては認知しているものの、地元・地場の産品を重視する取り組みという認識はあまり持っていない。この点、時に形式的だが細かな産地表示にこだわりをみせる日本の消費者、また店頭での産地表示に注意を払わざるをえない日本の流通業者とはとらえ方が異なるといえよう。
地元・地場の産品を重視できない制約条件も存在する。まず、韓国では日本以上に人口の都市集中が進んでいる。特に首都ソウル周辺への集中は著しく、韓国の人口の4割がこのエリアで生活しているという。そのため、都市近郊産地の生産力が低下しており、膨張する旺盛な需要を満たすには、国産品でも遠隔産地への依存度を高めざるを得ない。また、野菜の流通システムに注目すると、日本の都市部では卸売市場の近郷売場や産地商人の集荷活動、農産物直売所等、都市農家の少量多品目出荷を可能にする流通システムがある程度残っている。しかし韓国では、規格・等級こそあまり問われないものの、一定のロットを確保しないと出荷できないケースが多く、零細な都市農家の出荷物をまとめるフレキシブルな流通システムが日本ほど展開していない。ハナロクラブ/マートも、農家の個別出荷を形式上は拒んでいない。しかし実際には一定のロットを求められるため、能力のある農家でない限り個別出荷は難しいという。個別出荷が可能な流通経路としては、交通の要所に展開してきた定期市場が挙げられる。しかし量販店主導の小売システムが発展するにつれて、特に大都市圏では定期市場も姿を消しつつある。
しかし、韓国の人々は、決して地域に無関心であるわけではない。食に関しても、「この料理はどこが発祥の地」とか「この地方の名物はこれだ」といった話題には事欠かない。ハナロクラブ/マートでの販売においても、高級品・贈答品のコーナーでは産地にこだわった売り方をしているし、不定期ではあるが地場産品を集めたフェアは開催されている。
5.地域に根ざした運動へ
近年、韓国では身土不二とともに「農都不二」という用語も用いられている。文字通り農村と都市の共生を唱える用語である。そこには農産物への関心だけでなく、それを栽培する産地や、農民の住む地域社会への理解を深めようという意向を読み取ることができる。都市化が急速に進んだとはいえ、社会の中核をなす世代には農村部出身者も多いのが現代の韓国社会である。ミドルクラスの中には、郷里やそれを思い出させる農村部への関心を抱く人々も多い。
農都不二を具体化する取り組みとして広がっているのが「一社一村運動」である。都市部の企業がゆかりある農村部の集落と提携し、従業員のレクリエーションや農産品の販売を通じて農村との交流を図ろうとする取り組みで、約2万社が関わっているという。
農村ツーリズムがある程度普及したことも、こうした取り組みの普及に好影響を与えている。韓国の農村ツーリズムは、1980年代半ばにスタートした。しかし、当時は特定の観光農園のみが肥大化し、提供するサービスも画一的であったため、農村経済の循環や伝統文化とは接点を持てなかった。この反省を踏まえ、90年代後半から、支援事業がソフト重視のものに再編されるとともに、提供するメニューも地域の伝統や食文化を重視した内容に再編されていった。
日帰りまたは短期滞在で農村の魅力に触れるのが韓国の農村ツーリズムの典型的な形態であるが、提供される体験メニューには野菜をはじめとする農産物が重要な役割を果たしている。いも掘りなどの収穫体験やキムチなどの農産加工体験は人気メニューである(写真4)。また土産品として地元の農産物や加工食品が多く購入されている。韓国はインターネット環境が整っているので、都市住民が帰宅後にネットで農産品を発注することもよく行われている。先行研究によれば、農村ツーリズムにより得られる収入の20~30%は地場農産物ないしその加工食品の売上げにより占められているという。地場農産物は農村ツーリズムを地域に根ざしたビジネスとするための素材として貢献している。

このように、当初は国産品愛用運動と販売事業の展開に関心が集中していた身土不二運動も、徐々に取り組みが多様化しおり、産品だけでなく地域社会へ視点を拡大する傾向もみられる。
6.おわりに
日本でも近年、海外で展開するローカル・フードシステム再評価の動きを紹介し、それをもって地産地消の重要性を再確認しようとする論調がみられる。しかしスローガンや活動の表層を簡単に紹介するだけで、地産地消運動との共通点あるいは違いをきちんと理解しようとする取り組みとなっていないケースが多い。
韓国の身土不二運動も、タイトルがシンプルであることから、言葉だけは早くから紹介されてきた。だが日本の地産地消と比較すると、スローガンに込められた意図は類似していても、具体的な取り組み内容は異なる面も多いことがわかる。地産地消に比べ、身土不二運動は当初から農協が強いイニシアティブを取ってきた点、国産品の優位性や重要性を強くアピールしている反面、地元・地場の産品の評価にはなかなか結びついていない点が特徴的である。それには日本以上に急激であった都市化や、流通システムの微妙な違いが影響していると思われる。それでも近年では、農産物販売に限らない多様な取り組みが展開しているし、人々も産品だけでなくそれを生む農村・地域社会に関心を向けつつある。身土不二運動は今後もその裾野を広げていくことだろう。その中で野菜は、韓国の食生活を支える基礎的な食材であるため、国産、可能であれば地元産野菜の安定供給が期待されている。さらに栽培環境の保全や食品としての安全性など、質的な面でも地元産地のレベルアップが求められており、評価基準の整備や、実際に取り組む農家への支援策も整いつつある。
(参考資料)
朝倉敏夫 『世界の食文化1 韓国』 農文協、2005。
深川博史 「環境農業の現状と環境直接支払い」 『農業と経済』 2004年 5月号。
ヒョン・イソン 「身土不二運動の現況と課題」 『地産地消国際シンポジウム報告書』 2007。
金東煥ほか 「韓国における青果物流通の構造と特徴」 永木・茂野編 『消費行動とフードシステムの新展開』 農林統計協会、2007。
Sakurai、S.. et. al. "Development of Local Food Marketing in Korea"「農業市場研究」 16 (2)、2007。