 海外情報
海外情報
韓国の有機農業の現状
急成長遂げた韓国の親環境農業
農業ジャーナリスト 青山 浩子
有機農業の先進国といえばすぐに思い浮かぶのはヨーロッパ諸国であろう。しかし、お隣の韓国でも有機農業が勢いづいている。
韓国では有機農業、環境保全型農業を含め「親環境農業」という。最近、隣国の親環境農業に注目する日本の農業関係者は少なくない。理由の一つは、生産量、消費量ともに飛躍的に増えているからだ。ここ10年間でほぼ倍増している。
政策への関心も高い。日本では品目横断的な経営安定対策に絡み、環境保全型農業を進める地域への営農支援(環境支払い)が検討されている。しかし、韓国はすでに1999年から直接支払い制を導入している。
日本では有機農産物のマーケットがなかなか拡大しないことが課題となっている。日本と韓国は、気象条件も農業構造も似ているが、韓国でなぜ親環境農業が成長してきたのか。野菜を含む親環境農産物の生産現状と政策展開、マーケット急成長の要因、さらに最近に入って浮上してきた課題を探ってみた。
1.生産の現状と政策展開
1.割高でも消費者から支持される親環境農産物
韓国で親環境農業に取り組む農家は約53000戸ほどである。全農家の4.2%にあたる。
親環境農産物の認証制度もあり、栽培方法によって「有機農産物」、「転換期中有機農産物」、「無農薬農産物」、「減農薬農産物」の4区分に分かれる。表1は、認証を受けた農産物(穀類、野菜、果物、飼料、その他)の面積を栽培方法別に示したものである。
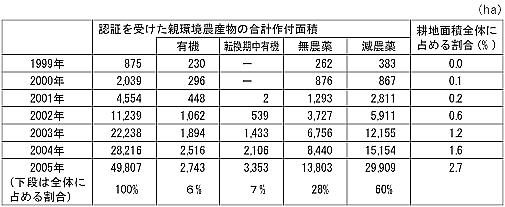
認証を受けた農産物の面積は毎年増えており、2005年では全耕地面積(約182.4万ha)の2.7%を占める。区分別に見ると、減農薬農産物が60%を占め、有機および転換期中有機農産物は13%にすぎない。つまり「有機」とつく農産物は全耕地面積の0.3%ということになる。
日本も有機JASの認証を受けた農産物は0.16%といわれている。従って、有機認証に限ってみれば、全体に占める比率は日本とあまり変わりはない。しかし、作付け面積の増え方を見ると、ここ数年の伸びには目を見張るものがある。
ソウル市内に、「ハナロクラブ」という大規模な農産物直売所がある。韓国農協中央会の子会社、株式会社農協流通が運営する店舗で、ソウル市内及び近郊に20店舗ある。98年にオープンした良材(ヤンジェ)店の野菜売り場にいくと、親環境農産物のコーナーがかなりのスペースを確保している。価格は慣行栽培の農産物に比べて30~50%ほど割高だ。それにもかかわらず、このコーナーにやってきて野菜をカートに入れていくお客さんは途切れることはない。青果担当の金慧星(キム・ヘソン)チーム長によると、同店では青果の10%が親環境農産物だという。
「店がオープンした当初は、生産量もわずかで、求めるお客さんもわずかでした。しかし3年ほど前から人気が高まってきました」と金チーム長。筆者は年に一度ぐらいはこの店を訪れるが、行くたびに親環境農産物のコーナーが広くなっていることを感じる。
韓国政府は親環境農産物の割合を2013年までに10%まで拡大するという目標を立てている。さらに2010年以降は「減農薬農産物」の認証を廃止し、無農薬栽培以上のみを親環境農産物とするよう基準を引き上げるなどかなりの熱の入れようである。日本の有機農業関係者が韓国を訪れ、「韓国の親環境農業に学ぶところは多い」と語る理由がここにあるのだろう。
2.国内農業の生き残り策のひとつと位置づけ
だが、1990年に入るまでの状況はいまとはまったく違っていた。韓国で親環境農業が発達したのは1970年代中盤からだという。生産者が増えてくるに従い、「正農会」、「有機農業研究会」、「自然農業協会」など生産者団体も生まれ、技術講習会を開いたり、団体として販路開拓に乗りだすなど活動をさかんにするようになった。
ところが、こうした取り組みに対する政府の評価はすこぶる低かった。韓国が米の完全自給を達成したのは1985年前後。このころまで農政の柱といえば“食糧増産”だった。収量の安定しない親環境農業は政策から外れたものに過ぎず、むしろ実践農家のリーダーのなかには“反体制派”として政府からにらまれていた人もいたほどだ。
政府が親環境農業に着目し、具体的な動きを見せるようになったのは90年に農林部(我が国の農林水産省に該当)内に「有機農業発展企画団」を組織化したのが最初といわれている。また、93年には現在の親環境農業を意味する「持続農業」を政策の一つとして初めて掲げた。
持続農業を実際に政策に落とし込んだのは、農林部傘下にあるシンクタンク、農村経済研究院の副院長だった崔洋夫(チェ・ヤンブ)氏である。崔氏は金泳三政権時代に「農林海洋主席」というポストにいた。80年代終盤から始まったウルグアイラウンド(UR)交渉がきっかけで、激しくなった農民デモを沈静化させ、専門家の立場から大統領の諮問にこたえるためにできたポストだ。以前、崔氏にインタビューした際、「私自身UR交渉に参加し、韓国の農業もいずれは市場開放から免れないことを実感した。その一方で親環境農業は生き残りの一つの方向になると思った」と語っていた。
3.トップダウンで法制化、直接支払いの実施も
崔氏は、親環境農業に否定的だった農林部や農村振興庁(農業技術の研究・普及・指導する政府機関)の職員を説得する一方、実践農家を対象とした補助事業を立ち上げ、94年には農林部内に「環境農業課」を新設。すぐさま、親環境農業を推進するための法案作りに乗りだした。法案づくりには時間を要したが、ついに97年「環境農業育成法」を制定した。
98年、大学教授であり、「正農会」の顧問でもある金成勲(キム・ソンフン)が農林部長官に就任後、さらに動きが加速した。98年には親環境農業育成政策を発表し、99年からは「親環境農業直接支払い」など具体的な支援策がスタートした。
直接支払いの金額は、農林部が確保する全体の予算の兼ね合いもあり実施当初から変更されているが、2006年現在では、次のようになっている。
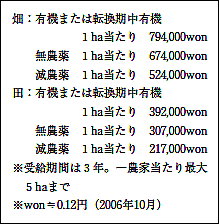
2.マーケット拡大の要因
図1は、1999年から2005年までの親環境農業に取り組む農家戸数および生産量の推移である。栽培面積と同じように飛躍的に増えている。
これほどまでに生産が拡大した要因について訪韓するたびに関係者に尋ねてみるが、おおよそ次の三点に集約できる。
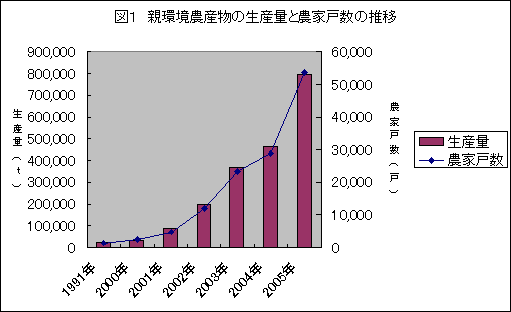
1.政策的支援と消費者の健康志向で生産が拡大
一つめは、前述したように政府が親環境農業を国内農業の施策の一つとして位置づけ、具体的な支援もしたことが後押しとなり、取り組む生産者が増えたことだ。
ソウル市から東に車で一時間ほどの廣州(クァンジュ)市。ここでイ・ヨンギ氏は各種の葉物野菜を有機栽培でつくる一方、周辺の農家とともに販売組織をつくり、ソウル市内のスーパーやデパート、有機専門の宅配業者に卸している。「単に農産物を作るだけでは経営として成り立たない。有機であればビジネスとして可能性があると思い始めた。ほとんど有機栽培だが慣行栽培よりも20~30%高く売れる」と話す。
二つめに、消費者の健康志向の高まりも一つの要因だ。韓国では2002年頃から「ウェルビーイング(well-being)」という言葉が大流行している。これは日本でいえばスローフード、ロハスに類似したもの。「健康にもよく、環境にもやさしい農産物、食品を食べましょう」という考え方が浸透し、これが親環境農産物の消費拡大に一役買った。とりわけ葉物野菜は、生で食べる機会が多く、有機や無農薬などの消費量が増えた(図2)。
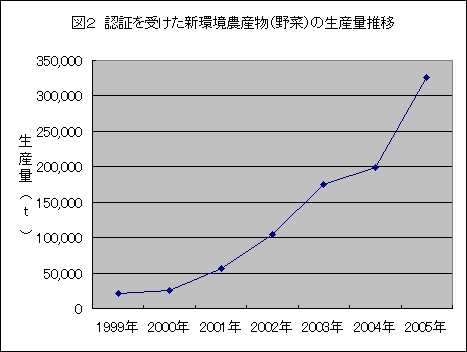
韓国はここ数年で農産物の流通形態が大きく変わった。かつて主婦たちが買い物をする場所といえば在来市場や小規模スーパーが多かった。しかし、ここ5年ぐらいの間に外資系を含む大型量販店が急速に店舗数を増やし、一カ所でまとめ買いをする「ワンストップショッピング」が定着した。そうした大型量販店はほとんどの場合、「親環境農産物コーナー」を設けており、供給量も必然的に増えた。韓国の親環境農業の研究者として第一人者である韓国農業専門学校の金鍾淑(キム・ジョンスク)教授によると、「親環境農産物の販売所の数は2000年には352カ所だったが、2005年には1,200カ所に増えた」としている。
2.都市と農村の連携の一環として発展
三つめは、親環境農産物の市場拡大の背景にはもうひとつ大きな理由がある。
ソウル市には漢江(ハンガン)という川が流れている。この川の水はソウル市および周辺の約2,000万人の飲み水となる。韓国の人口は約4,800万人。つまり人口の半分近くが漢江の水に依存していることになる。そこで、漢江の汚染を防ぐため、川の水源地域に暮らす生産者たちに親環境農業を実践してもらい、その恩恵を受けるソウル市民たちが生産者を支援するということを10年前から行っているのだ。
漢江上流にある八堂(パルタン)とよばれる地域では、約3,000人の生産者が新環境農業に取り組んでいる。ソウル市、韓国農協中央会は親環境農業生産者を対象に、1995年~2005年まで低利融資を行ってきた。内容は一戸当たり4,000万ウォンを上限する融資で12.5%の金利のうち、ソウル市と農協中央会が7.5%の金利を負担(生産者負担は5%)するというもので、総額1,000億ウォンの資金を造成した。
また、両者による販路ルート確保の支援も行われ、ソウル市内約10カ所に親環境農産物の販売拠点が設けられた。この販売拠点については運営を担当した農協中央会の販売ノウハウの不足、PR不足などによって順調とはいえず、大半が閉店となったが、前述した「ハナロクラブ」などでインショップの形で販売するようになってから、軌道に乗ってきたという。
ハナロクラブの親環境農産物コーナーで買い物をしていた主婦にインタビューした時、「パルタンのことはソウルに住む人であれば誰でも知っていることですよ」と答えており、飲料水を介した都市と農村の連携の定着ぶりを実感することができた。


「親環境農産物」と大きく表示されている
タン地域。看板には「きれいな水を大切に
しよう。環境農業21」と書かれている。
パルタン地域で96年から親環境農業に取り組む生産者の一人、崔大榮(チェ・テヨン)氏はトマト、ズッキーニ、ねぎを約40アールで栽培している。生産されたものは、崔さんを含む約100名の生産者でつくる生産者団体「パルタン生命とくらし」に全量出荷をするという。パルタン生命とくらしは、農産物をハナロクラブや生協、消費者団体などに販売しており、年間約65億ウォンの売り上げをあげている。販路が確保されていることに対し、崔さんは「ありがたいこと。ここ以外でも親環境農業に取り組む生産者は多いのに、行政の支援もあり助かる」と話していた。

れた野菜。表示認証マークもついている
パルタン生命とくらしの広報担当者によると、05年まであった低利融資制度は終了したものの、販売コーナーは拡大している。またソウル市民が負担する水道代として、パルタン地域の親環境農業を支えるために一戸当たり1,000ウォンを「水利用負担金」という項目で負担しており、それらは崔さんたち農家がたい肥などを購入する補助金に与えられているという。
3.自治体ごとの支援も活発化
日本においても、海の水質を守るために山に木を植えるなど地域を越えた連携が行われているが、大都市ソウルを舞台に、川の上流の農業を都市の消費者が支えるという仕組みが作られたことに対し、韓国を訪れる日本の農業関係者は誰もが大きな刺激を受けるようだ。また、この取り組みが親環境農業の市場拡大につながったのは確かである。
こうした大々的な取り組みは、パルタン地域とソウル市以外には今のところない。だが、親環境農業を推進していこうという流れは依然加速化しており、政府のみならず、各地方自治体レベルでも親環境農業育成政策を打ち出し、実践農家への補助事業を導入するようになった。
韓国南部にある全羅南道では、モデル地域の選定および補助金交付、販売施設の設置、親環境農産物の広報活動などのための予算を確保し、2004年に1.5%だった親環境農産物の割合を2009年までに30%までに引き上げ、農薬・化学肥料の使用量を30%削減するという計画を掲げている。
3.課題
1.生産と消費の不均衡是正が課題
韓国の農業も日本同様、安価な輸入農産物の増加、米余り、高齢化・後継者不足という課題を抱えている。しかし親環境農業についてみれば順風満帆で、マーケットもさらに伸びていきそうな勢いだ。しかし、ここにきて課題もいくつか見え始めている。
一つは生産と消費の不均衡である。国として方向性を打ち出し、支援策も講じてきたこともあり、すでに見てきたように農家数、生産量は飛躍的に増えた。しかし最近、消費の伸びが一段落し、作物によっては生産過剰が指摘されている。パルタン生命とくらしの鄭瑛棋(チョン・ヨンギ)広報チーム長によると、「野菜については依然、需要が伸びているが、アイガモ農法による米などが生産過剰気味で在庫が増えている」という。
パルタン生命とくらしは、野菜が中心で、生産過剰の影響は受けていないという。しかし、鄭チーム長は「若い消費者は手料理をしなくなっており、野菜そのものを買わなくなる傾向が強まるのではという警戒感を持っている。生産者レベルでも加工に乗りだすなり、消費者の食生活の変化に対応していく必要がある」と話している。
もう一つの課題は、農協自らが親環境農産物を扱うようになり、流通に変化が生じたことだ。消費者の「ワンストップショッピング」が定着し、大型量販店がハイスピードで新規出店を続けている。こういった大型店に農産物を供給するには、ロットをまとめ、規格を統一し、安定的に供給する体制作りが不可欠である。親環境農産物においても小さな生産者グループでは供給しきれないという危機感から、農協組織として昨年、本格的流通に乗りだすこととした。05年12月には農協が扱う親環境農産物に「アッチムマル」というブランドでの販売を始め、親環境農業の生産者らに参画を呼びかけている。しかし既存の生産者は自分たちが開発してきた固有ブランド、地域名を打ち出すことにこだわりを持っており、生産者と農協の連携はいまのところ順調とはいえない。今後どう動いていくかが注目される。
政府の支援、消費者の健康志向、環境保全の視点からの取り組みなどがうまく組み合わさって韓国の親環境農業は今日まで発展してきたといえる。筆者は、農協中央会で産直業務に携わる産地流通部の呉世(オ・セチョル)次長に「親環境農業では日本は水をあけられたようです」というと意外な言葉が返ってきた。
「韓国では親環境農業に取り組む農家だけが注目されているが、日本では生産者全体が環境保全型農業の方向に進んでいる。認証を受けていない生産者であっても農薬、化学肥料の使用はかなり削減している。全体の動きとしてはまだ日本のほうが進んでいるのではないか」とのことだった。
確かに政策面では韓国が進んでいるように見える。だが、日本でも特別栽培農産物に対する各県段階での認証、エコファーマーの認証など生産現場での取り組みは確実に前進している。こうしたり組みを消費者にどうやってPRするか、政策にどうつなげるかが日本の課題だろう。特に環境を保全する農業が結果的に消費者にメリットがあると位置づけた韓国の手法には学ぶところが多い。こうした点から韓国の事例は多いに参考になるだろう。