 海外情報
海外情報
韓国における育苗事情 ―育苗センターの事例分析を通じて―
農林水産省 農林水産政策研究所 地域振興政策部 (日本学術振興会 外国人特別研究員)
柳 京煕
南九州大学 環境造園学部
助教授
姜 求
1.はじめに
韓国の果菜類主産地である全羅南道のローカル紙は2005年4月27日の記事で、次のような旨の内容を報じた。「Z貿易社は、日本の大型ホームセンターと契約し、ナスとトマト苗を輸出することに成功した。今回の輸出は、韓国の営農法人M育苗センターとZ貿易社が1年余りの準備を経て成し遂げた。苗は、長距離輸送に耐えられないことや、低コストの船舶輸送でなければ輸出が困難であることから、韓国だけが日本に輸出できる。日本の市場潜在力は大きく、人件費が高いために韓国内より50%以上の高値で取り引きされる。韓国内の140ヶ所余りの育苗センターは、熾烈な価格競争を繰り広げており、零細な育苗センターの経営が悪化しているなかで、日本への輸出は、有望な輸出品目になり得る」。
さて、日本国内に目を転じれば、野菜・茶業試験場が2000年5月に育苗センターのアンケート調査を行い、「野菜の接ぎ木栽培の現状と課題」を2001年1月に公表した。この報告書を取りまとめた、吉岡宏氏は、「農業及び園芸」第76巻第3号に「野菜の接ぎ木栽培の現状と課題―アンケート調査の取りまとめ―」を投稿した。その内容は、概ね次のようにまとめられる。
「日本国内において栽培面積で見た果菜類の苗動向は、1990年に比べて1998年には購入苗が18.3%増加し、接ぎ木苗も25.9%増加している。これは農家の苗供給が、自家生産から相当な労力を必要とする接ぎ木苗を中心とした購入苗へ移行していることを示唆している。また、育苗センターが取りあげた今後の研究課題として、経済(コスト)と関わる項目の「簡易接ぎ木方法・低価格の接ぎ木ロボットの開発」と「小規模生産に対応した低コスト養生装置の開発」を各々12、11都道府県が挙げている」。つまり、日本国内の苗需給からみでも、果菜類の苗を輸入する要因が内在していることを示している。
以上のように、韓国の育苗センターは、過剰な国内競争から輸出圧力が生じており、一方、日本では接ぎ木苗を中心に良質で安価な苗の需要が高まっている。近年に台頭した韓国の苗輸出の背景と果菜類生産の動向を知る上で、韓国の育苗現状を把握することは欠かせない。しかし、それに関する報告は、日本においては言うまでもなく、韓国内でも皆無に等しい。次節以降では、韓国育苗センターの概要と大手育苗センターの事例調査を通して育苗センターの現況を紹介したい。
2.育苗センターの概要
韓国の大手種苗会社であるS社が、3年前に調査・推計した結果によれば、全国には380ヶ所の育苗センターがあるとされている(注1)。これは冒頭の新聞記事に比べて40ヶ所少ない。いずれにせよ、韓国の育苗センターに関する調査・報告書は現時点では存在しない。それゆえ、この節では2000年に発足し、今年度に社団法人として登録された、韓国育苗産業連合会(以下「韓国育苗連」と称す)の会員を中心に育苗事情を概観してみよう。
韓国育苗連の会員として参加している育苗センターは、現在50ヶ所で、そのほとんどがプラグ苗を生産している。会員のうち、現に資料の入手が可能な30センターについてみることにしたい(表1)。実績は2000年度であるが、ここ4~5年の間に育苗センターが大幅な規模拡大を進めていることに留意してほしい。株式会社の2ヶ所を除けば、全ての育苗センターは個人や営農法人の経営である。そもそも営農法人は、幾つかの農家が、政府支援を受けやすくするために法人化したものである。従って、営農法人も個人経営とみなして良い。つまり、韓国の育苗センターは、農協や自治体によって設置された日本のそれと違って、ほとんどが公益性を帯びない個人経営が主体である。
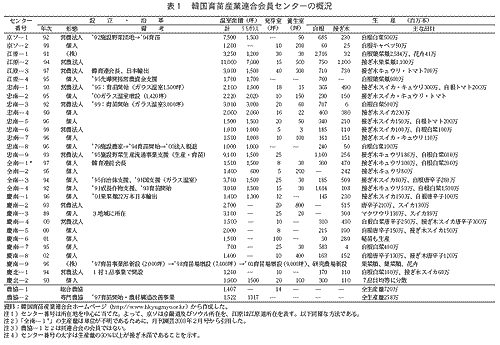
また、育苗を開始した時期は1990年代初めからであるが、30センターのうち21ヶ所が1990年代半ば以降である。これは1990年代初めから施設野菜が本格的に取り組まれたことに比べて5~6年遅れている。後述の事例のセンターも同様であるが、多くの育苗センターは、施設野菜農家からスタートし、その間の栽培経験を生かして育苗センターへ転換したと思われる。
接ぎ木苗の生産比率が30%を超える育苗センターの施設について見ると、「慶南―4,5,6,8」と「慶北―1」を除いた全ての育苗センターは、ガラス温室を有している。ガラス温室を持っていない「慶南―4,5,6,8」は2000年以降に設立されたセンターである。これは政府支援と深く関わっている。ガラス温室は1991年からの政府支援(補助と融資)によって建設され始め、1998年には野菜のガラス温室面積176haのうち161ha(92%)が政府支援を受けている。その後2000年から補助が打ち切られ、2003年には216haと伸び悩んでいる。政府支援の大きかった時期はガラス温室を中心に、近年はビニール温室を中心に育苗センターが建てられている。よって、育苗センター展開における政府支援の重みが容易に推察できよう。
いずれのセンターにおいても注文生産で、料金の前払いと輸送費の農家負担を求めている。個人や営農法人の運営の場合、出荷後のトラブルを避けるため、農家に多くの責任を課している(例えば「忠南―7」の場合、(1)輸送時に発生するトラブルの責任は、センターが負わない、(2)農家が受け取った後、24時間以内に異議申し立てがなければ、農家の責任である、としている。
これに対し、農協運営のセンターは、出荷後も事後指導や収量確認を行うなど、個人運営のセンターより遥かに公益的な役割を果たしているといえる。しかし、前述でも指摘したとおり、これら農協主体のセンターは、農協中央会の種苗開発センターを含めて10ヶ所に過ぎない(注:韓国の農協中央会は経済事業も行っている)。
次は、苗の出荷価格を個人・営農法人と農協の運営するセンターと比較してみよう(表2)。

表は「忠南―7」に「農協―2」とS農協を合わせて作成した。そのために比較できない規格もある。S農協の方が「忠南―7」より多くの規格において高い価格設定をしている。しかし、農協運営の育苗センターは、個人・営農法人が運営する育苗センターに比べて、より多くのリスクを負担し、事後サービスを提供していることを考慮すれば、必ずしも高価とは言えない。さらに、S農協は管内の農家に10%強の割引も実施しているために、農協センターの価格設定は、個人・営農法人センターと同等の価格水準にあると言えよう。
しかし、苗の出荷価格は、農業資材の価格と農村賃金が上昇傾向にあるなかで、(農業資材は107.0→111.6、農村賃金105.5→109.6)、育苗センター間の価格競争により低下傾向となっている(次節の事例であるH育苗センターにおいても、育苗価格を年々下げている)。しかし、技術向上によってコストダウンも十分に考えられることから、センター間の競争の実態については、今後、細心の調査が必要と思われる。
3.事例調査 ―H育苗センター―
1)設立および施設概況
調査事例の対象であるH育苗センターは、表1の「江原―3」に該当する。
H育苗センターの設立主体は、H営農組合法人である。H営農法人は、1997年に農業に従事する5人により立ち上げられた。当時は、政府の補助金を円滑に受給するためにも、そのような法人の参加が比較的に盛んに行われた経緯がある。Hセンターも法人を設立母体とし、政府補助金50%・融資30%・自己負担20%で10億ウォンのガラス温室を建てた。H営農法人は、果菜類生産の専門農家の集まりだったので、当初から苗供給の重要性を認識し、育苗センターへ転換を試みたのである。
その後、事業の成功に伴い、規模拡大を行うこととなり、国や自治体の支援を受けながら、2000年に1億5千万ウォン、2003年に2億ウォンの投資が行われた。その結果、2005年1月時点での施設概要は、温室6,600坪(ガラス温室1,500坪、ビニールハウス5,250坪)とその他の付帯施設250坪となっている。それに伴って、発芽室や養生室も300坪、1,300坪と拡大している。しかし、現在はガラス温室への政府補助が断ち切られたことから、規模拡大はビニールハウスだけとなっており、土地の買収や借用が円滑に行われず、施設は3ヶ所に分散している。
2)生産実績と経営
生産実績についてみることにしよう(表3)。2000年の1,440万本から2003年1,575万本と約10%増加した。接ぎ木苗の多い品目はトマト、きゅうりとズッキーニであるが、3品目間の接ぎ木率にはトレード・オフの関係がある(注2)。2004年には前年度対比147%増の2,317万本強を見込んでいるが、パプリカを中心とした品目の多様化(2003年その他1%→2004年その他5.5%)が見られ、増産と多様化による稼働率の向上を図っていると言える。
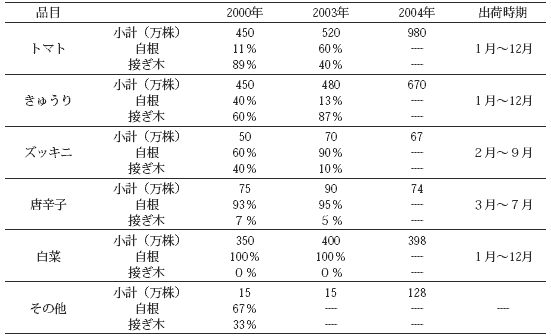
それでは、Hセンターが全国に占める育苗供給量のウェイトを簡単な方法で推定してみよう。トマトの場合、1坪(=3.306m2)当たり8~10本の苗が必要となる(トマト種子の供給会社であるS社の指導要領から参考にした)。2004年の見込み量980万本で単純推計すると、延べ面積は324~404haになる。2003年度の韓国のトマト施設栽培面積は3,971ha(露地131ha)であるので、全国のトマト面積の約8%~10%を占める。きゅうりは坪当り9~10本が必要となるので、2004年の670万本をトマトと同様な方法で推定すると、221~246haの面積となる。これは2003年の韓国きゅうり栽培面積である6,648haの3~4%に該当する。
種子費が高いのは、トマトにおける種子費が経費の主体となっていることに起因する。果菜類の2003年の経営実績について見ると、粗収入が25億ウォンであるなかで、種子費が最も高く11億6千万ウォン、続いて人件費が8億5千万ウォン、光熱費が1億2千万ウォンの順となっている。韓国では近年にトマトの需要が高まっているが、トマト種子は日本品種が多く使われている。特に、ミニトマトのほぼ100%は日本品種である。日本品種のトマト種子は、韓国産と比べて割高である。当センターのトマト苗は、日本品種を使っており、また、接ぎ木ロボットを導入せず、常勤20名とパートタイム年間延べ人員16,700名で賄っているために、人件費が多くなっている。


3)広域出荷への展開
まず、Hセンターが広域出荷できた背景と経緯を見てみよう。Hセンターの立ち上げ当時は、近隣の江原道春川地域を主な出荷先としていた。春川地域は、ソウルと近い地理的な利点を生かし、90年代の果菜生産の拡大に伴って新興産地として成長した。それによってHセンターの知名度も徐々に上がり、全国的に知れ渡るようになった。その上、Hセンターが広域出荷へ転換できたことには、韓国に特有な事情もある。前節で見たようにほとんどの育苗センターは個人・営農法人および会社経営であり、これらの経営主体は販売先を管内と限定せず、基本的に利益を求めて全国展開するという販売戦略をとっている。従って、育苗センターの生産条件と農家の需要条件さえ合えば、広域出荷を行っている。
Hセンターが、遠隔地である慶尚北道尚州地域へ広域出荷したのは、1999年である。尚州地域は、きゅうり栽培面積154haの主産地である。当地域の主な栽培型は、施設抑制型であり、8月上旬~9月中旬の定植、10月中旬~1月下旬の収穫期、12月上旬の収穫最盛期となっている。ところが、周辺の育苗センターの苗は、夏場の暑さのため、良質な苗を生産できず、農家と地元育苗センターの間に度々問題が起きていた。そのような状況の中で、以前から評判を得ていたHセンターにきゅうり苗の供給を要請した。一方、Hセンター側は、春川地域への出荷のピークが12~5月となっており、尚州地域への供給は、既存の出荷先とは時期的に重複しない利点を有している。Hセンターにとって新たに尚州地域へ出荷することは、稼働率の大幅な上昇を意味する。そこで、Hセンターは栽培指導などのサービスを付け加えながら、今まで経験したことのない遠隔出荷に踏み切ったのである。また、2003年にはビニールハウス2,000坪を増築し、2004年は尚州地域の農家100戸に供給している。尚州地域への出荷経験は、尚州地域同様の遠隔地である慶尚北道浦港地域にトマト苗を供給することに繋がった。浦港地域は主に5月から出荷しているが、2004年は年間30万本の供給を見込んでいる。
このような全国出荷への展開によって白菜に続き、きゅうりとトマトもある程度の周年出荷を実現し、施設稼働率は90%以上となっている。また、出荷の周年化は稼働率の向上のみならず、農家との取引形態にも変化をもたらした。設立当初の代金支払いは後払いであったが、今は100%契約生産で、苗代金の3分1を先払いするという形態を取っている(トマトは播種の2ヶ月前、きゅうりは1ヶ月前である)。契約形態の変更によって代金回収のリスクが減らされ、苗の管理に専念できるようになった。これによってより良い苗が生産でき、農家の信頼性が高まるという好循環を生み出している。
4)日本輸出
H育苗センターが、熊本地域にトマト苗を輸出したのは2002年からである。品目は専らトマトに限定されている。これまでの輸出実績をみると、初年度は50万本、2003年には韓国国内トマト価格の高騰によって30万本に減少したが、2004年には80万本へと再び増加した。
日本輸出が可能になったのは、価格の安さだけでなく、技術的ないくつかの要因がある。
一つ目は品種である。周知の通り、韓国のトマト種子は、ほとんどが日本から輸入された品種である。そのために、苗の品質さえ良ければ、生産後の販売に何ら支障が生じない。
二つ目は苗の品質と関わっている。熊本のトマト主産地は、ハウス加温抑制型の栽培が多い。この作型は、7月初め~8月上旬まで播種し、9月中旬まで定植する。苗作り期間において、天候によっては日照不足が起こることもある。また、この地域はトマト黄化えそ病が発生し、育苗段階から防除の徹底が求められているが、自家苗や地元の育苗センターの苗は、ウィルスフリーとは言えない。
三つ目は、輸送費用と時間距離である。H育苗センターから釜山港まで半日、釜山港から博多港まで一晩、博多港から熊本まで半日の30時間という近距離であることから、この間の苗の衰弱は回復時間の設定によって挽回可能である。最後に、H育苗センター側から見れば、韓国内出荷のピークを過ぎた7月からの輸出になるため、稼働率の向上や供給体制の周年化が一層強化できるメリットがある。
4.終わりに
韓国に育苗センターが開設されたのは、1990年代初めであるが、大半の育苗センターは1990年代半ば以降に建てられた。農協や自治体による建設は少なく、主に施設野菜栽培の経験を生かした個人農家または営農法人が建設した。近年の施設野菜の低迷によって価格競争が激化し、農業資材価格と農村賃金が上昇しているなかで、苗の価格は低下している。
このような状況において、零細な育苗センターは退出を迫られている。しかし、H育苗センターの事例で見たように、技術水準の高い大規模な育苗センターは広域な出荷体制の構築と共に、地理的利点を利用して日本輸出を始めている。彼らにとって、日本への輸出は国内の価格競争の回避と周年出荷体系の確立というメリットがある。
最後に、日本における苗輸入の展望と意義について考えてみよう。
展望を述べる際には、両国に置かれている経済状況を分けてみることが必要と思われる。
まず、韓国内で生じている輸出圧力についてみると、韓国内の施設野菜生産の動向と育苗技術水準またはセンター間の競争構造如何によって左右される。
韓国内の生産動向をみると、1990年代終わりから施設野菜の生産は停滞しており、技術水準は1997年まで開発段階の中・低位と分類されていたが(注3)、事例のH育苗センターで見たように技術向上は堅調である。さらに前述で指摘したとおり、センター間の価格競争によって年々価格の低下が顕著である。これらの諸条件を考慮すると、今後韓国の輸出圧力は高まると予測される。
他方、日本側の輸入需要は、コストダウンおよび病害虫対策によって左右されるが、熊本の例をとっても、日本国内の事情次第によって輸入が増加することは十分にあり得る。また、韓国産苗(部品)の輸入は、果菜類(完成品)の輸入とは異なる側面を持っている。果菜類の輸入増は、国内生産者にとって市場の蚕食に過ぎなかったが、苗輸入は生産費の節約と病害虫の対策に利用できる。いずれにせよ、日本国内の育苗センターにとって、韓国の育苗センターの新規参入は時間の問題と思われる。
今後、種子問題をめぐるさまざまな問題がクリアー出来れば、これまで以上に育苗の輸出・入が増加していくと思われる。過去に度々起きた農産物における近隣国との貿易摩擦問題を考えれば、今後、相互利益をもたらす貿易体制を構築する必要がある。これは日本にとっても切実な問題であろう。これについては今後の課題としたい。
(注1):調査方法及び結果は公表されていない)。さらに、プラグ苗の生産できる育苗センターはおよそ100ヶ所とみている(注:韓国ではプラグ苗を「工程苗」とも称す。これは、近代的な設備の下で一定の工程を経て生産された苗と、そうでない苗とを区別するためである)
(注2):2005年にはきゅうりとトマトの接ぎ木率を90%にする計画である)
(注3)(キム ビョンユル他『園芸及び特別作物の中長期政策方向』韓国農村経済研究院、1997年12月)