 情報コーナー
情報コーナー
加工・業務用野菜の品種及び技術研究最前線⑲
広島大学大学院 生物圏科学研究科
教授 櫻井 直樹
1.はじめに
たくあん“ポリポリ”、お茶漬け“サラサラ”、いかにも日本語らしい表現である。しかし、この表現は英語にもフランス語にも翻訳できない。彼らの文化・言葉には食べ物を食べたときの音・食感を表現する言葉が少ない。食感に関する音の表現では、英語にはCrispy(パリパリとしたさま)、Crunchy(ボリボリとしたさま)という2つの言葉があるだけである。しかし、ちょっと考えただけで日本語には10以上の音食感を表す言葉がある(表1)。これをよく見ると、いわゆる擬音語で子音がサ行・ハ行の摩擦音、カ行、パ行、バ行の破裂音に限られており、しかも同じ言葉が二度繰り返されている。二度繰り返される言葉は南方ポリネシアを起源とするという説もあり、これらの言葉の起源は南方系かもしれない。
日本語では“シャキシャキ”はレタスの新鮮さを表す言葉であり、リンゴは“サクサク”していないとおいしくないし、 “シャリ”感はスイカのおいしさを表す表現である。ポテトチップスは“パリパリ”していないと湿気ているように感じる。このように食感を表す言葉が日本に豊富にあるのは、豊かな自然と恵まれた気候により、さまざまな自然の食材を生で食べる文化が発達していることが背景にあるのであろう。ところが、サラダの起源はギリシャ時代にさかのぼると言われ、アメリカ大陸ではすでに16世紀から食されており、日本には明治時代に紹介されたそうである。それからすると、生の野菜の食感を表す言葉が外国語に少ない理由は分からなくなる。
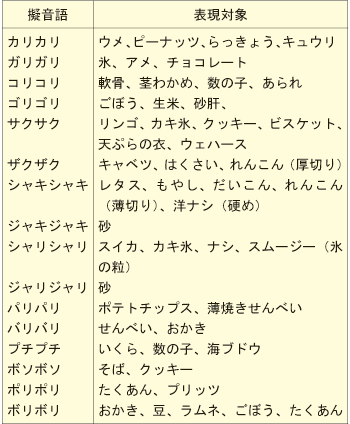
2.食感測定装置の誕生
筆者らは1994年から果実を切らずして硬さを測る研究を開始し、その後、振動を利用した非破壊による硬さの測定である「レーザードップラー法」という新しい方法を提案した(1、2)。この研究をもとに、果実の硬さから果実の食べ頃・熟度が予測できることを次々に明らかにしてきた。また、その頃山形大学のM先生から「ラ・フランスの果肉の食感をレーザードップラー法で分析できないでしょうか」という依頼を受けた。当然できると思って始めた研究は、すぐにつまずいた。あのラ・フランスのとろけるような食感になる瞬間が、「レーザードップラー法」ではとらえられないのである。果実の軟らかさは徐々に変化するのに、ラ・フランスのあのバターのような食感は突然現れる。そこで、食感を数値化する必要が出てきた。
食感を測定する装置のヒントは、意外にも筆者の歯の治療中に浮かんだ。歯の根元にある神経の代わりに、圧電素子を使用して食感を測定できないだろうかと考え、すぐに装置のイメージが頭に浮かんだ(図1左)。
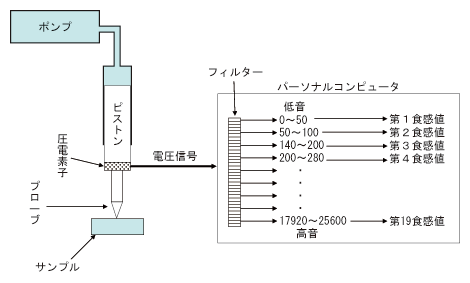
圧電素子は昔、ガスや石油ストーブに火をつけるときにカチャカチャと引き金を引いていた装置である。引き金を引いて圧電素子にぶつけると電気が生じて火花が散る。歯の治療のため抜歯した筆者の前歯を使用して、その根元に圧電素子をつけ、軟らかい桃に差し、その信号をテープレコーダに録音した。その音を聞くと、「ピシピシ、ミシミシ」と、通常は聞こえにくい高音部分の音が鮮明にとらえられていた。食感測定装置(Acoustic Measurement of Crispness、AMC)の誕生である(3、4)。
物を噛んだ時に歯で生じた音は、耳に伝わるまでに骨、関節、筋肉、頭蓋骨を通る。その間に高い音は失われ、頭蓋骨に共鳴するような低い音が強調されて耳に伝わる。初期の食感研究では、ヒトは耳に到達する音で食感を判断していると考えていた。しかし、被験者の耳にヘッドホンを装着し、大音量の音楽を聞かせながらいろいろなクッキーを食べさせて、その違いが分かるかを試験した結果、ヒトは耳を使わなくても食感を判断できることが分かった(5)。歯を真似たAMC装置は、物を噛んだときの振動をすべてとらえられる。後はこの信号を数値に変換すればよい。
ここで装置の説明をしよう。装置には、私の歯の替わりに円錐形(犬歯型)や楔形(門歯型)の金属の探り針(プローブ)を用いた(図2)。その根元に圧電素子を貼り付け、ピストンに接着し、ピストンを動かしてサンプルにプローブを差し込む。普通は上下の作動にはモーターを使うが、モーターの回転運動を上下運動に換えるにはどうしてもギアが必要となり、ギアは動くとその摩擦で音や振動が発生する。食感信号は振動として圧電素子にとらえられるので、その部分に外部の振動が伝わってはまずい。そこで、液体を使ってピストンを動かすことにした。得られた電圧の信号は、コンピュータに取り込んで分析することとした(図1右)。図3にスイカ、キャベツ、レタスを材料に圧電素子で得られた電圧の波形を示した。スイカは、果肉にプローブが突き刺さっている間ずっと信号が出ているが、キャベツやレタスのような葉物野菜ではプローブが葉を突き破った瞬間、電圧値は大きくマイナスに振れる。この波形から、食感を表す数値を取り出す必要がある。
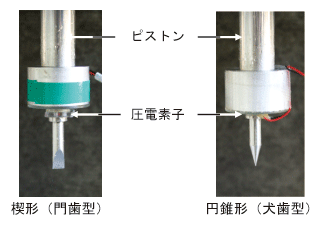
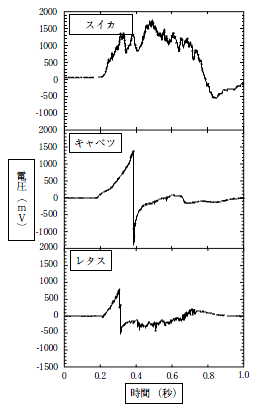
3.信号の解析方法―フィルター
音食感を表す言葉、例えば“バリバリ”と“パリパリ”を比較してみよう。その言葉は音程に違いがありそうである。“バリバリ”のほうが“パリパリ”よりも音程が低い。「パ」も「バ」も破裂音であるが、音程に違いがある。音程とは振動数(単位Hz)である。Hz(ヘルツ)とは、1秒間に何回振動するかという単位である。つまり、いろいろな食感を表す言葉には振動が関係しているらしい。これを日本語は表現しているのではないか。“ボリボリ”と“ポリポリ”も振動数に違いがありそうである。そこで、AMC装置で得られた信号には、いろいろな振動が含まれているはずなので、それらを分けて評価すれば人の食感を数値化できるかもしれないと考えた。通常、複雑な振動を分析するには、フーリエ解析という数学的手法が使われる。しかし、フーリエ解析とは「ある一定期間“持続”する振動を解析する方法」であり、物を噛んだ時に発生するような“断続的、短期的な振動”には向いていない。ものに歯が貫通するときに発生する振動は、断続的、短期的で決して連続した美しい音ではない。そこで別の方法をとることにした。
それはフィルターである(図1右)。ある特定の幅の音程だけを通す窓を電子工学的にこしらえ、そこを通ってきた音だけを評価するという方法である。例えば、テレビの「メニュー」ボタンを押すと、音設定という項目がある。これを開くと、ニュース、シネマ、ミュージック、などの項目が並んでいる。“ニュース”はヒトの声なので、通常聞き取りにくい高音を強調している。“ミュージック”ではその音楽の幅をダイナミックに伝えるために、高音だけでなく、低音も強調している。この方法はイコライザーと呼ばれる。ある特定の幅の振動(音程幅)だけを通す窓をたくさんこしらえて、低音から高音までの信号を別々に数値化すればよい。そこで、どのような音程幅(周波数帯域という)にしようかと考えた。
とりあえず、人間の耳に聞こえる振動数は20~2万Hzといわれているので、その幅を何通りに分けるかである。音楽の音程はドレミで表されるが、「シ」の次はまた「ド」である。次の「ド」は前の「ド」より1オクターブ高いという。最初のドの周波数が260Hzであれば、1オクターブ高い次の「ド」の音は520Hzである。人の耳では(つまり脳では)、2倍の振動数を一区切りと感じているようである。最初はこの原理で、0-100、100-200、200-400、400-800と分け、最後は12,800-25,600Hzとなるように、9帯域に分けた。後にこれでは少し大まか過ぎるので、2の何乗ではなく、√2の何乗(半オクターブ)というやり方で19帯域に分けた(図1右)(6)。
4.食感指標の数値化
次に得られた信号をどのように数値にするかが問題である。プローブが野菜の葉などに押し当てられるとプラスの電圧が発生する。葉を突き破るとプローブにかかっていた力が解放され、プローブが慣性で前に進むのでマイナスの電圧が発生する。つまり、プローブがサンプルを貫通している間、プラスとマイナスの電圧が両方発生している(図3)。どちらも、もしその信号(プラスとマイナス)をすべて足し合わせると、ゼロに近くなってしまい、その違いがはっきりしない。そこで、すべての信号はまず2乗することにした。それらを足し算すると、両方ともプラスの値となる。また、長い間信号を取れば合計はおのずと大きくなるので、時間やデータ数で割って補正しておく必要がある。
次に振動とエネルギーの問題がある。たとえば、拍手をするときに1秒に1回の拍手なら誰でも難なくできるが、1秒間に10回拍手するのはかなり大変である。手が同じ幅を往復する動作でも回数(振動数)が多くなると、より大きなエネルギーが必要である。つまり、同じ強さの電圧信号でも、周波数の高い信号のほうがエネルギーは高いのである。そこでこれを考慮するために、周波数を掛けることにした。掛け方は、その帯域の低い周波数と高い周波数である。こうして食感値が求められた(7)。
食感値=下限帯域周波数×上限帯域周波数 ×(∑(電圧値)2/データ数)
このようにして得られたスイカ、キャベツ、レタスのそれぞれの食感指標のグラフを図4に示した。キャベツはスイカより0から50Hzの帯域を除けば、すべての周波数帯域でスイカを上回る食感指標を示した。0から50Hzの指標は、歯応えを表すものと考えられるので、歯応えはスイカの方が高いが、食感はキャベツのほうが高いといえる。レタスは、キャベツとよく似たパターンを示しているが、どの周波数帯域でもキャベツより低く、食感値はキャベツより弱いと言える。しかし、2,240から6,400Hzに特徴的なピークがあり、このピークがレタス特有の“シャキシャキ感”を与えていると言える。逆に、スイカでは、8,920から12,800Hzに特徴的なピークがあり、このピークが“シャリシャリ感”を与えている可能性がある。
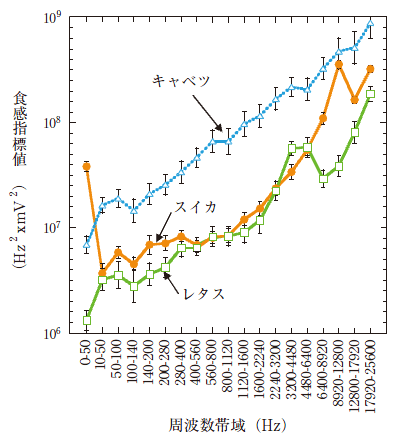
ねぎは、芯が数枚の葉で覆われている複雑な構造をしている。本当にAMC装置がこのような複雑な構造の食感信号をとらえているか調べるために、プローブを突き刺した後のねぎの断面の顕微鏡写真を撮り、得られた信号と比較してみた(図5)(8)。すると、0~50Hzの周波数のフィルターを通ってきた信号は、最初の1枚目の葉にプローブが当たって信号が上昇した後に、それを突き破ったときの急激な信号の下降が見られた(図5矢印)。次の2枚目の葉にプローブが当たると、また信号はプラスに転じ、突き破ると下降する。これらが繰り返され、芯にプローブが到達すると比較的平坦な信号が出るようになった。この結果は、ねぎの複雑な構造をこの装置が厳密に電圧信号として取り出していることを示している。また、0から50Hzの信号は、プローブがサンプルを押すときの力を示すことがこれからも言える。このAMC装置で、ねぎ(9)、キャベツ(7)、レタス、スイカ以外に、キュウリ、ラ・フランス(10)、柿(11)、ブドウ、ポテトチップスなどを測定した。キャベツでは、5品種の冬キャベツと1品種の春キャベツの食感を比較した(図6)。それぞれの品種の食感の違いが、いろいろな周波数帯域に個別に現れていることが分かった。冬キャベツの中でも品種1は特に高音の食感が優れていた。2と3はほとんど同じ食感を示した。4は1、2、3より低音の食感が低いが、高音は遜色なかった。5はかなり食感値が低かった。春キャベツは、低音の食感がしっかり出ているが、高音が極めて低く、ザクザク感が主であることが分かった。
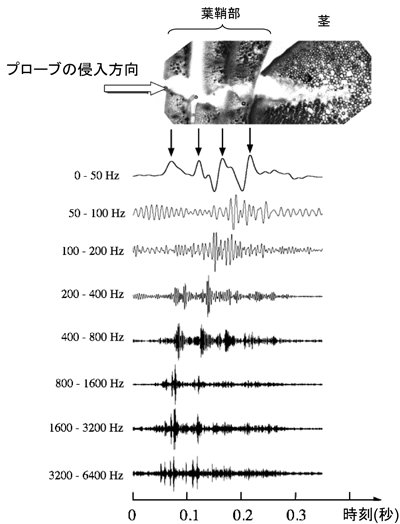
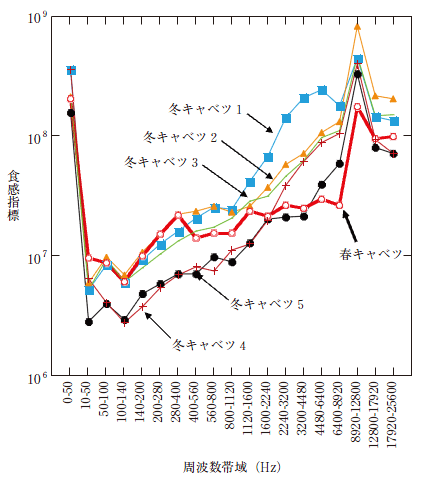
5.AMC装置の今後の課題
それでは、AMC装置は万能だろうか。まだ問題が残っている。それは人の感性とのすりあわせである。レタスの“シャキシャキ感”は、たった一つの帯域の信号に対応しているのだろうか。あるいは、複数の帯域の信号の組み合わせだろうか。あるいは複数の帯域の信号の強さの比率だろうか。これらを調べるためには、AMCで得られた信号を今度は人間に戻す(聴かせる、あるいは感じさせる)という研究が残っている。これらが完成して初めて「このレタスのシャキシャキ度は9です」などという表示が新鮮さを表す指標として使えるようになるだろう。また、センサーとして使っている圧電素子は、低い周波数の振動には鈍感である。応力センサーや、マルチシート(12)のような低い振動数に向いたセンサーとの併用も必要であろう。またさらに、野菜は前歯(門歯)や犬歯だけで食べているわけではない。奥歯でもそしゃくしている。いろいろな形のプローブによるさらなる解析が必要である。
6.AMC装置の使用目的および応用の方向性
例えば、シャキシャキ感がアップしたねぎの新品種を育成した場合、ヒトの食感により多くのねぎを食味することは不可能である。なぜならば、2、3本のねぎを食味しただけで、舌が麻痺してしまうからである。また、キュウリでさえ、長時間にわたり食味試験をすることは苦痛を伴う。このように野菜の食味試験には、ここで紹介したAMC装置は効果を発揮する。もともとヒトの知覚は、物性値の10倍を2倍と感じるようにできているといわれ、ヒトによる知覚による比較はあいまいである。人によってもその表現が異なり、スイカのシャリ感は専門家にしか判断できない。専門家もその評価は正確でも、「評価基準」を人に伝えることの難しさを知っている。さらに、専門家でさえ、昨年、一昨年の値と今年の値を比較することは困難である。このように評価がはっきりとしない比較結果に対して、装置で機械的に測定された食感値は客観的な値なので、何年も前の値とでも比較できるところに大きなメリットがある。
現在、1キログラム、1メートルのように物理的に定義された単位による食感指標を構築中である。これが完成すれば、世界中で共通の評価基準ができ、米国でも日本でも同じ基準でレタスのシャキシャキ度が比較できるようになるであろう。
文献
- 櫻井直樹(2003)レーザー・ドップラー装置による果実の非破壊的粘弾性測定、日本バイオレオロジー学会誌17:92-97.
- 櫻井直樹(2004)果実の硬さで食べ頃・取り頃を知る技術、農業および園芸79:1286-1292.
- Sakurai, N., S. Iwatani, S. Terasaki and R. Yamamoto(2005)Texture evaluation of cucumber by a new acoustic vibration method. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 74:31-35
- Sakurai, N., S. Iwatani, S. Terasaki and R. Yamamoto (2005) Evaluation of ‘Fuyu’persimmon texture by a new parameter, “Sharpness index”. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 74:150-158.
- Christensen, C.M. and Z. Vickers (1981) Relationships of chewing sounds to judgments of food crispness. J. Food Sci. 46: 574-578.
- Taniwaki, M., T. Hanada and N. Sakurai(2006)Device for acoustic measurement of food texture using a piezoelectric sensor. Food Research International 39: 1099-1105.
- Taniwaki, M. and N. Sakurai (2008) Texture measurement of cabbages using acoustical vibration method. Postharvest Biol. Technol. 50: 176-181.
- Taniwaki, M., T. Hanada and N. Sakurai(2006)Development of a methodology for quantifying food texture using blanched bunching onions. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 75: 410-414.
- Kuroki, S., T. Hanada, M. Tohro, T. Wako, A. Kojima and N. Sakurai(2008) Detection of textural difference between cultivars of bunching onion using the device for acoustic measurement of food texture. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 77:440-446.
- Taniwaki, M., T. Hanada, M. Tohro and N. Sakurai(2009)Non-destructive determination of the optimum eating ripeness of pears and their texture measurements using acoustical vibration technique. Postharvest Biology & Technology 51: 305-310
- Taniwaki, M., T. Hanada and N. Sakurai(2009)Postharvest quality evaluation of“Fuyu”and“Taishuu” persimmons using a nondestructive vibrational method and an acoustic vibration technique. Postharvest Biol. Technol. 51: 80-85.
- Dan, H., K. Okuhara and K. Kohyama (2003)Discrimination of cucumber cultivars using a multiple-point sheet sensor to measure biting force. J. Sci. Food Agric. 83: 1320-1326.