 情報コーナー
情報コーナー
夏秋どりいちごの生産の現状
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構
東北農業研究センター 夏秋どりイチゴ研究チーム長
森下 昌三
1 夏秋どりいちご栽培の背景
いちごは、我が国では年間を通して消費されている。生産の少ない夏秋期にもケーキなどに利用され、大手の洋菓子メーカーから町のケーキ屋まで、使う量に違いはあるものの、1年中欠かすことのできない品目となっている。冬春期には促成栽培のいちごが業務用として利用されるが、夏秋期はアメリカ合衆国などの海外から年間およそ4,000~5,000トンが輸入されている。いちごの価格は一般に冬から春に向けて下落し夏秋期に再び上昇するサイクルを毎年繰り返している(図1)。価格の高い夏秋期にいちごを出荷できれば大儲けできる理屈である。これが夏秋どり栽培をする動機であり、魅力となって栽培面積が徐々に増えてきた。
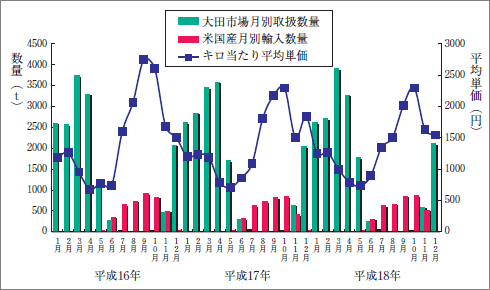
いちごの月別取扱数量とキロ平均単価の推移
我が国のいちご栽培は冬春どりと夏秋どりに大きく分けることができる。冬春どりは、いわゆる促成栽培に代表される11月頃から翌春の5月頃までに収穫・出荷するいちごを指し、作付面積はおよそ6,800ヘクタール(平成18年)で、およそ19万トンの果実が年間収穫されている。産地は主に宮城県以南の冬期温暖な地域に分布している。一方、夏秋どりは6月頃から11月頃までに収穫・出荷されるいちごであり、生産量は冬春どりに比べて少なく、作付面積で80ヘクタール程度、収穫量で1,500トン程度であろうと見られている。産地は北海道、東北および関東以西の高冷地など、夏期冷涼な地域で生産されている。栃木県が行ったアンケート調査によると、夏秋どりいちごの作付は北海道に全体の半分以上が分布し、次いで青森、宮城、徳島、長野などで多い(図2、なお、この調査における夏秋どりいちごは、四季成り性品種を使った栽培を対象としている。秋田県には一季成り性品種を使った夏秋どり栽培がおよそ20ヘクタールあるので、これを含めると秋田県は、北海道に次ぐ夏秋どりいちご産地となる)。
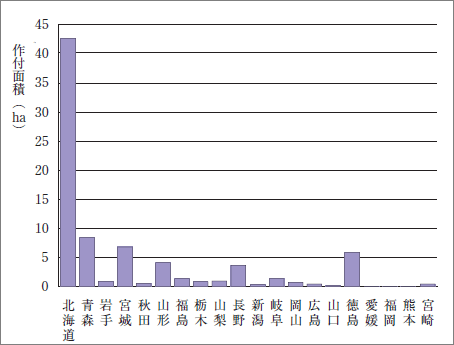
夏秋どりには2つの方法がある。1つは一季成り性品種を利用する方法、もう1つは四季成り性品種を利用する方法である。
一季成り性品種とは「とちおとめ」、「さちのか」、「北の輝」のような冬春どり用品種のことで、短日と低温条件で花芽分化する品種群である。これらの品種は夏期の高温・長日条件下で花芽分化注1)させるにはクーラー等で温度を下げて、さらに遮光資材で日長を短くして花芽を誘導しなければならないが、東北地域は冷涼であるためにクーラーを使わなくとも、日長を短くするだけで夏期に花芽分化させることができる。一季成り性品種は食味が良好で市場評価も高いことから実需者ニーズに十分応えることができる。
一方、四季成り性品種は、長日条件で花芽分化しやすい性質をもち、夏秋期に人為的操作なしで花芽分化して開花するため、夏秋どり栽培用品種として従来から使われてきた。しかし食味が一季成り性品種に比べて劣るという欠点があり、食味の優れた四季成り性品種を育成することが課題となっている。
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター(以下「東北農研」)では、これらの問題を解決して夏秋いちごの自給率向上を図るため、平成15年から5カ年間一季成り性品種の短日処理による夏秋どり栽培技術の開発と四季成り性良食味品種の育成を主要課題に、東北6県・東北大学と共同してプロジェクト研究「寒冷地におけるいちごの周年供給システムの確立」を実施したので、本稿ではその成果を紹介する。
注1) 植物は、茎の先端にある生長点で、新しい葉をどんどん作りだしているが、ある時期に葉を作らなくなって、顕微鏡で見なければ見えないような小さな花芽ができる。これを「花芽分化」といい、この小さな「花芽」は、やがて花となることから、「花芽分化」は植物が生殖の段階に入ったことを意味する。
2.一季成り性品種を利用した夏秋どり栽培技術
1)短日処理による9~11月どり栽培
相対的短日性植物注2)の一季成り性いちごは9~10月の気温と日長に感応して花芽が形成されるため、一般に夏秋期には開花できない。それゆえ、花成注3)誘導処理なしに夏秋期にいちごを収穫することは困難である。東北地域の夏期は比較的冷涼であり、最も気温が高い8月においても平均気温は23.2℃(盛岡市)と、九州(佐賀市)と比べておよそ5℃も低い。一季成り性品種「さちのか」、「女峰」、「とちおとめ」を盛岡で昼間8時間の短日処理を行ったところ、処理開始からおよそ30日で花芽分化が確認された。また、晩生品種の「北の輝」では45日で分化した。
温暖地の促成栽培地帯では温度が高すぎるためにクーラーを使って花成促進を行っているが、東北地域はクーラーを必要としない点で、夏秋どり栽培に適しているといえる。短日処理は小型ハウスを遮光フィルムで覆い、自動開閉装置により午前9時に開けて、午後5時に閉めることで昼間の時間を8時間にする(写真1)。最適な短日処理時期と処理日数を調べたところ、6月下旬~7月下旬の30日間の短日処理が最も多収であることが分かった(山崎2005)。また、これよりも早い場合には果実が小さく、反対に遅いと果実が大きくなる傾向が認められた。

2)越年苗による7~8月どり栽培
いちごは冬季休眠する。休眠は低温に遭遇することで覚醒するが、覚醒後しばらくは花芽が分化しない期間があり、それを過ぎる頃には気温が高く、日長も長いために、一季成り性品種は春に花芽を新たに分化しないのが普通である。そこで、東北地域の春の気温は低いため、日長さえ短ければ花芽分化できるであろうと考えて、前年の夏に採苗した苗(越年苗)を用いて実験した結果、5月上旬から日長8時間の短日処理を30日程度行うことで花芽が誘導され、7~8月に収穫できた(矢野ら2004、今田ら2005)。
しかし、「短日処理による9~11月どり栽培」および「越年苗による7~8月どり栽培」はいずれも短日処理によって収穫できる果房は1つであるため、収量は少ない。そこで、実用的な作型とするには他の作型と組み合わせる必要があった。以下の作型はそのような理由から開発したものである。
3)短日処理による超促成栽培
福島県・宮城県・岩手県では促成栽培が太平洋沿岸を中心にして行われている。出荷期の一層の前進はかねてよりの懸案事項であり、地域によっては既に夜冷短日装置を導入して11月上旬から出荷しているところもある。太平洋岸はやませ地帯とも重なり、夏期比較的冷涼であることから、「短日処理による9~11月どり栽培」を利用すれば夜冷短日装置を使うことなく、しかも9月下旬から収穫できる超促成栽培が可能となる。
宮城県気仙沼市は古くからのいちごの産地で、夏期冷涼冬期温暖であることから、この地域を現地試験地に選定して「短日処理による超促成作型」の開発を行った(鹿野2008)。この作型は品種は「とちおとめ」を用い、6月上旬に採苗して7月上旬から30~40日程度短日処理、8月上旬に定植、10月から収穫を開始して翌年の6月まで収穫を続ける(図3)。第2花房の連続的分化や高温対策が課題として残っているが、慣行の促成栽培を組み合わせた営農モデルによって労力の分散や所得増大効果が認められている。
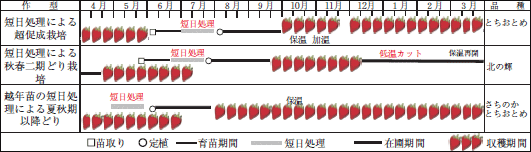
4)短日処理による秋春二期どり栽培
岩手県・山形県・秋田県には低温カット栽培という半促成栽培が今も少ないながらも行われている。これは冬期の低温遭遇量を制限することで4月下旬から7月上旬まで収穫する作型で、「北の輝」のような晩生品種が利用されている。この作型に「短日処理による9~11月どり栽培」を組み合わせて、秋と春の2回、同じ株から収穫する作型、短日処理による秋春二期どり栽培を開発した(高橋2008)。この作型は品種は「北の輝」を用い、5月中旬~6月上旬に採苗、6月中旬から40日間の短日処理、7月下旬~8月上旬に定植、9月下旬~11月下旬に収穫する。その後は低温カット栽培に準じて、低温遭遇させて3月から本格的に保温、そして4月下旬~7月上旬まで収穫する(図3)。低温カット栽培と比較して収量が増加、とくに価格の高い秋により多く出荷することで所得率の向上が期待できる。
5)越年苗短日処理による夏秋期以降どり栽培
青森県、なかでも太平洋岸は冬期の積雪が少なく施設栽培が古くから行われているいちご産地であるが、やませ常襲地帯でもあり、夏期の気候が冷涼であることから、この地域を現地試験地として「越年苗による7~8月どり栽培」を取り入れた作型「越年苗短日処理による夏秋期以降どり栽培」の開発を行った(岩瀬2008)。この作型は、品種「さちのか、とちおとめ」を用い、前年夏~秋に採苗・鉢育苗して積雪下で越冬させた苗を3月上旬から2ヶ月ほど保温して新葉を5~6枚展葉させたのち、5月に4~5週間短日処理して花芽分化させ、6月上旬に定植して8~9月に収穫する。その後しばらく収穫が中断するが、この間に新たに花芽が形成されるので保温・電照して翌年の6月まで収穫を続ける(図3)。足かけ3年に及ぶ栽培であるが、およそ8トン/10aの収量が得られる。
このほか、短日処理は行わないが、半促成栽培あるいは促成栽培を6月中下旬に終了した苗を手入れして夏以降再び収穫を開始し、冬春期は保温・電照して翌年の6月まで収穫を続ける「越年株の据え置きによる長期どり栽培」を開発した(岩瀬2008)。この作型は採苗から栽培終了までに足かけ3年をかけ、およそ10トン/10aの収量を得ることができる。青森県の特殊気象がこのような多年栽培を可能にしている。
注2) 相対的に日照時間が短くなると花をつける植物
注3) 「花成」とは、植物が栄養成長から生殖成長への切りかえをいい、「花成」の外的要因としては、光周期(一日のうちの夜の長さ)と温度は重要で、光周期条件により、短日植物と長日植物、またはどちらにも属さない中性植物とに分けられる。
3.四季成り性品種を利用した夏秋どり栽培
1)品種
四季成り性品種は、一季成り性品種のような短日処理などの花成誘導操作が必要でないことから、以前より夏秋どり栽培に利用されているが、それらの品種の多くは民間や個人によって育成・品種登録されているので、生産あるいは販売上に制約のある場合が多く、生産者自身による生産コストの削減や有利販売がしにくいといわれている。また公立試験研究機関においても四季成り性品種が開発されているが、これも他県に許諾されない場合が多いため、安く自由に使用できる独立行政法人育成品種が期待されている。
東北農研では2007年8月に「なつあかり」(写真2)「デコルージュ」(写真3)の2つの四季成り性品種を育成し、登録した。いずれの品種も苗を種苗会社から購入できて自家増殖が自由である。


「なつあかり」は、「サマーベリー」に「北の輝」を交配して育成した品種である。草姿は立性、草勢は強で、ランナー数注4)は少ない。果実は円錐形で大きく、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は中、果実の硬さは中、果肉色は淡紅、果心の色は淡赤である。食味は四季成り性品種の中で最も優れ、一季成り性品種と比較しても遜色がなく、生食に適し、業務用にも利用できる。うどんこ病抵抗性は中、萎黄病には罹病性である。
また「デコルージュ」は、「Pajaro」に「盛岡26号」を交配して育成した品種で、草姿は立性、果実は円錐形で大きさは中、光沢が強く、硬い。果皮色は濃赤、果肉色は鮮紅、果心の色は淡赤で食味は濃厚、ケーキ用途に適し、洋菓子メーカーの評価が高い。ランナー数および花房当たり花数は少で、うどんこ病に強い。
これら2品種にはそれぞれいくつかの欠点がある。「なつあかり」は四季成り性が弱く、高温期に果実が軟らかい。また果実の柄離れが悪く、収量がやや少ない。一方、「デコルージュ」は果実の種子が浮き上がること、気温の低下につれて果形が長くなること、収量はやや低いことが欠点である。既に一部地域で栽培されているが、今後これらの欠点を早急に解決して栽培面積の拡大を図る計画である。
2)作型
四季成り性品種による夏秋どり栽培には秋植え栽培と春植え栽培があり(図4)、秋植えは、夏に採苗して、10月に定植し、翌年6月~11月まで収穫する。一方、春植えは、冷蔵苗を3月上旬に出庫、50日程度ポリポットに仮植して苗を養成する。この間に発生する花房は摘除、4月下旬に定植して7月から11月まで収穫する(濱野2005)。総収量では秋植えが春植えよりも多収であるが、春植えは秋植えに比べて品薄の夏期に多くの果実が収穫できることから四季成り性品種の基本作型となっている。
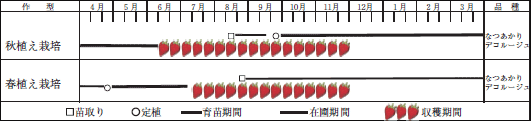
注4) ランナーは、春から秋に葉腋から発生する
4.今後の課題
本プロジェクトで開発した新作型によって収穫期間は拡大し、東北地域でいちごを周年供給することが可能であるが(図5)、夏秋いちごの市場は冬春いちごに比べて小さく、生産量が増加したときに今の価格が維持できるかどうか疑わしい。年間の需要量が5,000トン、キロ単価が2,000円と仮定すると、夏秋いちごの市場規模は100億円である。冬春いちごが1,500~2,000億円の市場であるのに比べると夏秋いちごの市場は小さい。これを産地間で取り合い、また外国産いちごとも競争しなければならない。
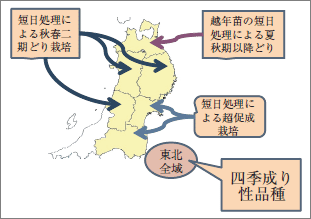
また夏秋期はいちごには不良環境であるので、高収量・高品質化は難問である。収量においては3トン/10a以上が当面の目標となるので、さらなる多収量の技術開発が望まれるところである。また可販果率の向上、高い割合で発生する小果、変形果、着色不良果などの規格外品の販売方法、管理作業の省力化、生食への用途拡大などが今後の課題である。
なお、本プロジェクトの成果は「夏秋どりいちご栽培マニュアル(改訂版)」(平成20年3月)として発行した。また東北農研のホームページ(http://tohoku.naro.affrc.go.jp/periodical/other/index.html)にも登載されているので、詳しくはマニュアルをご覧下さい。
参考文献