 情報コーナー
情報コーナー
加工・業務用野菜の品種及び技術研究最前線②
きゅうりの食味・食感を探る
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
野菜茶業研究所 野菜茶の食味食感・安全研究チーム長
堀江 秀樹
新潟医療福祉大学 健康科学部 健康栄養学科 助手
玉木 有子
1.きゅうりは食感が重要
インターネットで検索すると、きゅうりにはピラジンという青臭い香り成分が含まれ、血液をサラサラにするとか、ククルアスコルビン酸にガン予防効果があるなど、著者らも知らないような怪情報があふれている。非常に身近な野菜なので、健康によいという情報を期待したいというのは理解できるものの、科学的根拠のない情報が一人歩きすることは好ましいことではない。そもそも、栄養や食品の機能についての研究が進む以前から、きゅうりは世界中で食べられてきた野菜のひとつである。きゅうりがこれほど身近な存在なのは何故か。答えはおいしいからであり、食文化にマッチしていたからといえる。一方で果実のうちの95%が水分であるきゅうりには、現在のところ他の野菜や食材と比較して特に優れた健康維持効果は発見されていないというのが現実である。
きゅうりはおいしいから食べられるのだと書いた。それではきゅうりのおいしさとは何か、漠然としたイメージは個々の人が持っているとしても、これを科学的に解明しようという研究はほとんどなかった。トマトやいちご、メロンなどの野菜は味が濃いため、甘さや甘味と酸味のバランスがおいしさの重要な要素と考えられる。一方できゅうりについては、特段強い酸味や甘味があるわけではない。きゅうりのおいしさについては味よりも食感の占める割合が大きいものと考えられる。
2.食感評価法開発のための研究体制
農業研究においては品目毎の開発研究を縦糸とすれば、品目横断的に基盤技術を開発する横糸との関係が重視される。農林水産省委託プロジェクト研究「低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発」1系(以下「加工プロ」と略す)においても、野菜品目ごとの加工・業務を目的とした技術開発を縦糸とすれば、品目横断的に品質評価法を開発する横糸的な研究グループ(食味・食感ユニット)が配置されている。
野菜の食感(あるいはテクスチャーとも呼ばれる)については、従来は試料にプランジャーとよばれる棒を差し込む時にかかる力の大きさから「硬さ」を測定していた程度であった。このような測定結果は、消費者が野菜に求める「シャキシャキ」、「パリパリ」、「しんなり」などといった食感表現にはとても対応できるものではなく、食感を客観的に評価する手法の開発が強く望まれている。これを受けて、加工プロの食味・食感ユニットは特に食感評価法の開発に重きを置く体制になっている(図1)。前置きが長くなるが、加工プロの食味・食感ユニットの構成を紹介する。
広島大学では、音響法と呼ばれる新しい食感評価法の開発を行っている。人が咀嚼する際にはパリパリ、ボリボリといった音が発生し、食感を反映している。咀嚼音をマイクで計測することも考えられるが、唾液や口の大きさの違いが障害になる。そこで、人の歯を模したプローブと呼ばれる金属片を野菜など食品に貫入させ、得られた音響信号から食感を客観的に評価しようというものである。
食品総合研究所では、多点シートセンサーを用いた咀嚼の解析法を開発した。この圧力センサーを口に入れて野菜を噛ませた場合に、歯のどの位置にどれだけ強い力がかかっているかがリアルタイムで測定できる。さらに、同じセンサーは、機器測定での力の検出計としても利用できるため、機器測定値とヒトの咀嚼パラメータとの比較が容易になる。
■新たにきゅうりのパリパリ度の評価法を開発
野菜茶業研究所では、前号(本誌2007年11月号)に示したように食感に特徴のあるきゅうり系統を保有し、さらにその特徴を指標化するための方法を考案してきた。従来から測定されてきた「硬さ」だけでは、きゅうりの微妙な食感を表すには不十分である。そこで、従来からきゅうりの物性評価の際に得ていたデータを見直して、新たにCI(crispness index)というきゅうりのパリパリ度の評価法を開発した。CIの概念については図2に示した。また、野菜茶業研究所は野菜の呈味成分の探索や分析法の開発も担っている。
様々な方法でデータが取得されても、それらを人がどのように感じるかと結びつけないと意味がない。そこで、どうしても人の五感を用いた評価(官能評価)が重要になってくる。この部分は新潟医療福祉大学が担当している。
先にきゅうりでは食感が重要であると記載した。種苗会社が販売するきゅうりの種子の宣伝文句にも「食感が優れる」とは書かれているが、どういった物性や特徴を有するきゅうりの食感がよいのか、あるいは食感をどういう方法で数値化すればよいのか明らかにされてこなかった。そこで、加工プロでは、きゅうりの食感としてどういったものが望ましいのか、またこれを客観的に評価する手法はないかという観点から、食味・食感ユニットを中心に共同研究がなされている。
すなわち、野菜茶業研究所で食感に特徴あるきゅうり品種を栽培して各研究者に配布する。それぞれの研究者は先に紹介したそれぞれの方法で解析し、それらのデータを持ち寄ることができれば、人の評価と解析データとの相関がとれ、それぞれの方法でのきゅうりの食感評価に重要なパラメータが抽出できるはずである。
なおユニット内には大阪府立食とみどりの総合技術センター(2007年に大阪府環境農林水産総合研究所に改組)も配置されているが、きゅうりの場合と同様、キャベツでの試験においては、ここを要として食味・食感ユニットが他のユニットと協力しながら食感や物性評価法を探っているところである。
このように、これまで研究材料として取り上げられることの少なかった果菜類・葉菜類の食感を中心にしたおいしさ評価法の開発を目指し、正面から向き合うのが加工プロの食味・食感ユニットであり、野菜のおいしさに関する日本発の世界に向けた解析・評価法の開発が期待されている。
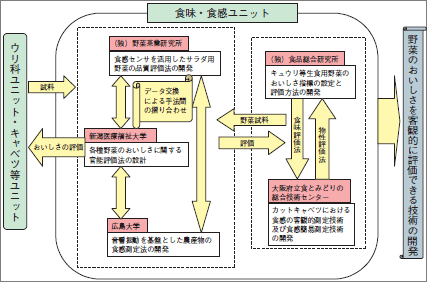
※クリックすると拡大します。
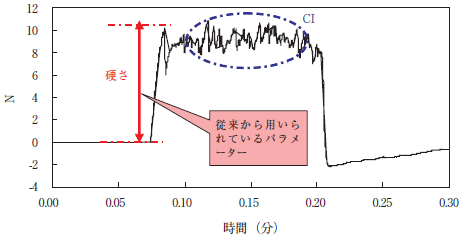
3.きゅうりの食味・食感についてわかったこと
先述のように、きゅうりの食感評価法開発のための共同研究がなされている。本研究のミソは「同じ」試料について多様な方法で解析する点にある。「同じ」きゅうりを異なる手法で評価し結果をつきあわせれば、それぞれの方法の特徴や、品種間差が明らかにできると期待できる。ところが、実際に共同研究してみると、問題点は「同じ」にひそんでいた。当然のことながら、同一品種内はできるだけ均質な材料を配布すべく栽培しているが、きゅうり果実間でバラツキがでる。外部で評価する際にはどうしても反復数が少なくなりがちであり、得られたデータが本当にその品種の特徴を表しているのか疑問が残る場合もあった。また、きゅうりの物性は収穫後も刻々と変化しているため、共同研究先への輸送に伴う時間差も問題となった。このように、実行してみて気づく意外な壁に苦しみながらも、成果は上がりつつある。現時点で、分かってきたことのエッセンスの一部を紹介する。
■きゅうりの食感は、収穫後も変化し、貯蔵によってパリパリ感が増加する
きゅうりの食感は収穫後も変化する。例えば図3に示すように、収穫直後とこれを共同研究先が受けとって評価を開始する2-3日後では明らかに物性が変わってしまい、さらに数日保存する間も同様の傾向が続いた。(「硬さ」よりも「CI」に示されるパリパリ感の増加が著しい。)このような傾向については、官能評価によっても確認されている。
このことは、もぎたてのきゅうりを主に対象として研究する園芸分野の研究者やブリーダーが食味試験する場合と、消費者が店頭で購入後、冷蔵庫に保存したきゅうりを食べる場合とでは、同じ品種のきゅうりからも食感への印象が全く異なることを示す。また、きゅうりは新鮮なものほどおいしいと考えられてきたが、食べ方次第では、貯蔵によって増すパリパリ感を楽しむことができるかもしれないという官能評価結果も得られている。
官能評価では、「硬さ」以外に、「歯切れ」、「多汁性」、「咀嚼音」などの食感関連項目も品種や貯蔵条件間で比較している。現在、多点シートセンサーや音響法で得たデータを官能評価値と比較しながら、きゅうりの食感を示すパラメータの設定を模索しているところである。
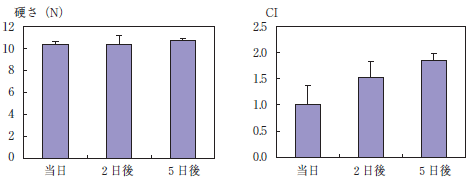
■切り方で違う渋味
食味に関しても研究は行っており、きゅうりの渋味についておもしろい知見が得られつつある。中央で2つに割って直後に割口をかじると渋味を強く感じる。しかし、同じ品種でも果皮をはいだり、輪切りにしたりして皿に盛りつけた後に試食した場合では渋味はそれほど強い評価は得られていない。これは評価する方法(喫食形態)によって渋味の印象が大きく異なることを示唆している。
また、昔からアク抜きの方法としてなされたように、ヘタを切った後に実をこすりあわせれば、同様に割って食べても明らかに渋味が低下する。この原因は、果皮のすぐ下側にある維管束に渋味成分が溜まっており、ヘタと実をこすることによって渋味成分が吸い出されるようである。
このように、必ずしも園芸研究の専門家でない者も集めた食味・食感ユニットでは、新しい視点を活かし、活発に議論しながら、野菜の食感をいかに評価するかという難題に取り組んでいる。試料間のバラツキが意外と大きく難航している部分もあるが、逆に、野菜の食味・食感についてこうした大規模な比較試験は、世界でもなかなか先例のない内容と思われる。ここで行う試みや問題への対処法などは、農産物のおいしさを評価する際の新しいパラダイムの創成につながるものと期待される。
※ 次号は、「単為結果性なす品種あいみのりと、その種なし化をめざす育種について」を掲載する予定です。