 情報コーナー
情報コーナー
高知県での輸入野菜の増加の影響と輸入野菜に対応するための産地の取り組み
高知県農林水産部 園芸流通課
主任 岡林 俊宏
高知県は冬期の恵まれた日射量と温暖な気候を生かして、多くの品目を周年化して供給する古くからの施設園芸産地である。中でもなすは、432haで栽培され、約110億円の産出額(H17年産)を誇る最も重要な品目となっている。そのメインとなるのは中卵タイプの普通なす(写真1)であるが、他にも小なす(写真2)や約350g中心の大型の米なす(写真3)などの個性派のなすも産地化されており、それぞれが日本一の流通量を誇っている。



それらのなすの9品種の中でも、最も手間をかけて作られているのが小なすだ。市場担当者らから『黒いダイヤ』とまで言わしめた小なすは、大量流通する品目ではないが、その芸術的な荷姿で、業務筋向けに高単価で取引をされていた。ところが、その小なすの平均販売単価が、平成4園芸年度をピークに毎年のように右肩下がりとなってきた(図1)。当時、市場担当者からは小なすは料亭や割烹など高級料理店の天ぷら用などでの利用が中心ということであり、一般消費向けの商材ではないので、生産量が少しでも増えれば安値となり、需要より供給が減れば高値となる傾向が一層強いと言われていた。そこで、産地では適正な生産量を維持するために栽培面積を抑えることで単価を支える方針を出し、生産者らに理解を求めて耐えてきた。しかしながら安値は止まらない。さらに、県園芸連では、市場経由で漬物会社に販売していた分をそれまでの下級品だけでなく、場合によってはA品まで柔軟な対応をして、市場への流通量をさらに減らしていくことで単価を支えていこうとした。だが、それでも価格安に歯止めはかからなかった。その結果、年々面積が減少し生産量も減ったにもかかわらず、平均単価はさらに落ち続けるという事態になってきている。
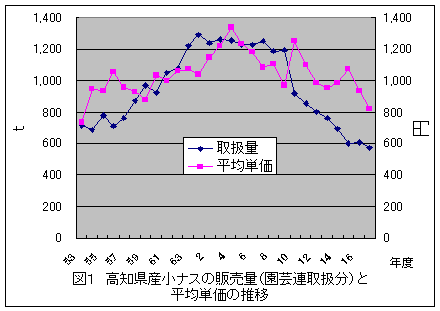
なぜ、価格安に歯止めがかからないのか。バブルがはじけて以来、高級料亭などでの会食や、結婚式などの形態なども変化し縮小傾向であり、そういった業務筋需要の商材として成長してきた小なすの需要が減ってきてしまったのであろう。ここ最近まで、私たちは小なすのこの厳しい現状をそう分析していた。
2.産地には見えない輸入の全貌
1)甘かった産地の認識
昨年の6月のことである。高知県の大阪駐在所の職員が、たいへんショッキングな情報を収集し産地に送ってきた。それは、ある大手の冷凍野菜輸入会社の取材で得た、ベトナムからの小なすの冷凍加工品の輸入実態である。日本に輸入されることになってきた多くの品目がそうであったように、この会社の輸入してくる商品も、原料となる小なすは日本人の技術指導者が現地に入って生産指導を行ったものであった。さらに日本人の嗜好に合わせた味での加工開発が徹底され、その流通は一般の市場流通経由ではない。さらにショックなことに、なんとその小なすの冷凍加工品が、地元高知県内の生協のチラシ販売にも、『本格業務用小なすのはさみ揚げ…料亭の味をそのままに…プリプリのエビを挟み揚げました』と紹介され販売がなされていたのであった(写真4)。今年のチラシでは、また別の業者の輸入品で、ベトナムからの焼きなすの冷凍加工品が紹介されている(写真5)。また、その会社のホームページによるとなんとフリーズドライ製品の焼きなすも開発され輸入されているのである。


シ販売に(2005.6)
販売に(2006.6)
今までのように単純に、市場に生鮮のなすが供給過多になって売れなくなっているのではない。市場の先にある取引先あるいはさらに一般の消費者にまで、市場を経由しないルートで、いろんななすが直接にどんどん届きだしていたのである。しかも生鮮ではなく、高度な調理加工をしたなすが冷凍やフリーズドライで輸入されてきているのだ。産地が、いくら生産調整をして市場に出荷しようが、単価が今まで通り簡単に維持できるはずがないわけである。今まで、産地と取引のあった業務筋関係のお客さんどころか、一般の消費者までもが、さらに安く、簡単で、ロスのない形態でのこれらの輸入冷凍加工製品のなすを直接買うことのできる大きな道ができてしまっているのである。
2)恐るべき輸入量
平成17年度の貿易統計によると、生鮮野菜の輸入量はついに100万トンを超え、冷凍、塩蔵などの加工も含めた輸入野菜量は250万トンに達している。平成14年のほうれんそうの農薬残留事故による影響で一時減少していた中国からの輸入量は完全に復活し、全輸入量の60%以上を占めている。
この年々増加する野菜の輸入量を、私たち国内産地や農家はどういう風に捉えたらいいのか?野菜の消費量自体が減っている中で、この輸入量がとても多いというのはわかる。しかしながら一口に250万トンと言っても漠然としていて、いったいその量がどの位多いのかというのは実感しにくい。
そこで、図2にH17年度の輸入量と高知県園芸連の出荷販売量とを比較してみた。高知県産野菜は、なす類の他にもシシトウ(全国1位)、ピーマン(全国4位)、しょうが(全国1位)、ミョウガ(全国1位)、オクラ(全国1位)、にら(全国2位)など上位のシェアを持つ品目も多数ある。しかしながらその全出荷販売量はわずかに9万トンを上回る程度にすぎない。本県の場合、軽量野菜が多く、輸入野菜の場合は、たまねぎやかぼちゃといった重量野菜も多いなど単純比較はできない。とはいえ、生鮮での輸入野菜量と比較して、本県の販売量はそのわずか1/10程度、冷凍や塩蔵など加工野菜を加えると1/25程度にすぎない。いかに輸入野菜が国内流通に浸透してきているかが想像できるのである。
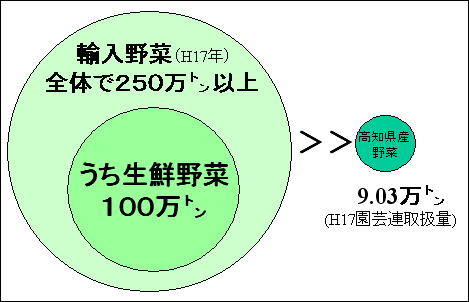
次に、本県のいくつかの品目について、輸入野菜の増加が実際にどのような影響を与えているものなのかを検討した。
3.高知県産野菜 VS 輸入野菜
1)なす
今からちょうど10年前、1996年あたりから韓国から生鮮なすの輸入が開始された。生鮮品としてのなすには、光沢と鮮度感が要求されることもあり、それまでは国内産のみの聖域であった。韓国からの生鮮なすの輸入は、九州産と競合する長なす(筑陽)である。市場からの情報によると、主に業務用の漬物需要などへ利用されているとのことであった。中卵形の普通なすが中心の本県にとっては、比較的影響が少ないのではないかといった楽観的な見方もあった。生鮮なす輸入量は2000年まで年々増加していったが、なすの単価自体はすぐには下がらずそこそこ維持されていたからである。
生鮮なすの単価低迷は、その後に本格的にやってきた。国内の単価が低迷してくると、生鮮の輸入量はあっさりと減少することとなった。実際に、昨年度の生鮮なすの輸入量はピーク時の1/3になっている(図3)。単価が低迷すると、生鮮なすの輸入量が減るので、国内産のなすを圧迫することは少ないのではないかとも思えた。ところが、事態は決してそんな甘いものではなかった。小なすの場合と同様、なすの主力である普通なすについても、価格は低迷を続けることとなってきた。
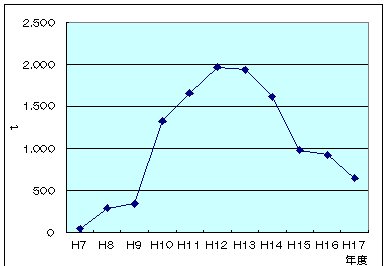
私たちなす産地のなすの単価を圧迫しているのは、やはり生鮮のなすだけではないのだ。ベジ探(農畜産業振興機構提供「野菜情報総合把握システム」)の輸入情報より、なす関連の輸入量を収集して、高知県産の量と比較してみた。(図4)生鮮でのなすの輸入は確かに減少した。ところが、塩蔵のなす、小なすの輸入量は依然として多く、合計すると1万トン以上の輸入があることがわかる。その量は、高知県産の主力である普通なすの量と比較すると1/4以下ではあるが、小なすだけの量で比較すると、塩蔵小なすで高知県産の10倍近くの量が輸入されており、漬物需要のほとんどは輸入で埋め尽くされてきていると言っても過言ではない。また、さらに、これらの数字には、前述した小なすのはさみ揚げや、焼きなす、麻婆なす等のより一層加工度の高い冷凍商品は含まれていない。
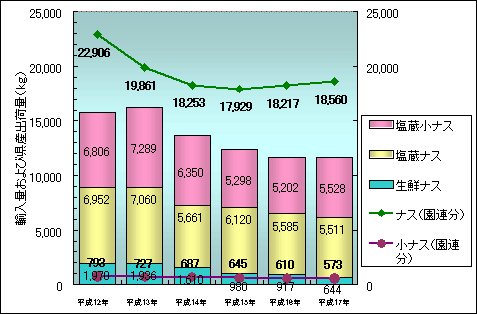
国内市場の生鮮野菜販売単価の高低と生鮮の輸入量は間違いなくリンクする。だが、輸入は生鮮だけではないこと、そして、生鮮以外の輸入は、生鮮以上にそのお客さんと直結しており、市場の生鮮単価が下がっても輸入量は減らないことを我々はもっとしっかりと認識しておく必要がある。
2)きゅうり
きゅうりは、なすよりも前から輸入の影響を大きく受けていた。消費量そのものが減少していることもあり、全国的に国内産地は厳しい状況にある。生鮮の輸入については、なすと同様に韓国産中心であったが、平成13年度がピークで、現在は激減し全輸入量のわずか2%となっている。輸入の中心は塩蔵と酢調製品であり、全国7位である本県生産量の2倍にあたる量が入ってきており、漬物等の業務需要が大きく奪われてしまっている(図5)。
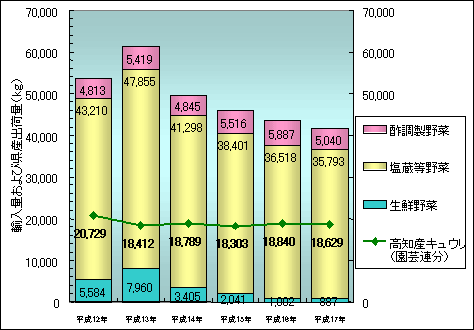
きゅうりの場合、量販店の店頭での一般販売は、完全にバラ売りが主流となっている。従って、まっすぐで光沢があり規格がしっかり揃ったA品でないと量販店では商売にならない。ところが、実際の生産現場はA品ばかりを生産できるわけではない。当然、曲がったきゅうりも出来るし、規格外の品も出来る。漬物やカット野菜などの、業務加工需要でそういった下級品への販売がそこそこの値段で可能であれば、産地や農家は経営が成り立っていくが、そのパイを輸入品が埋めてしまってきており、十分に対応できなくなっているところも販売が厳しい大きな要因となっている。
3)しょうが
しょうがは、雨の多い本県の気候に良く適した作物であり県内の中山間地帯の露地栽培農家にとって重要な換金作物であった。しかしながら長期貯蔵が可能であるし、加工も容易なので早くから輸入の影響を受けた。平成2年には4,370トンであった輸入量が、わずか5年後の平成7年には34,968トンにまで激増した。すし用のガリや、紅しょうがなどみるみるうちに輸入に埋め尽くされていった。平成5年の冬、大田市場に流通研修でお世話になっていた私は、その2ヶ月間の間、市場の担当者の方が、売れ残ってしまった高知産のしょうがを台車に乗せて、毎日のように苦労しながら仲卸さんらに売り歩いてくれていたのをはっきりと覚えている。その後も増減はあったものの輸入は増え続け、平成17年度の輸入量は全国トップである本県生産量と比較して、生鮮分だけで2.8倍の量、塩蔵、酢調製、その他調製など加工品を含めると7.5倍量に増大している(図6)。
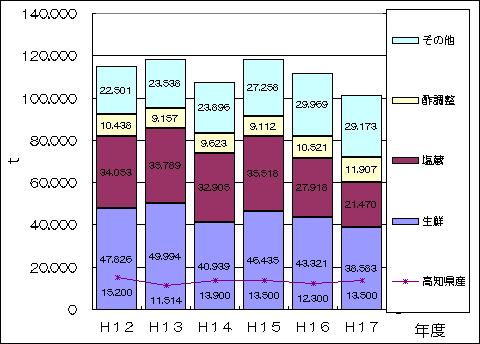
ただ、国内産地にとって少し明るい兆しもある。業務加工部分での状況はかわらないが、生鮮の一般消費の需要面では、品種の系統の違いや、品質面で本県産がやや勝っている点、さらに安全・安心の点から、国内産を選ぶ消費者が増えている傾向がある。輸入品と国産の棲み分けがはっきりしてきたことで、ここ数年の価格はやや回復している。
4)オクラ
オクラは、本県にとってシシトウと並ぶ重要な露地品目である。収穫期には、朝晩に収穫しなければならない程手間がかかるが、その分労働生産性は高い。狭い面積でしかも経費をかけずに取り組めて所得を上げることができるため、昭和60年位までは5,000トンを超える生産量にまで成長していた。ハウス栽培にも取り組み周年出荷もできるようになり、冬場に驚くような高値がつくこともあった。しかしながら、元々高温性の作物であるので、高知でハウス栽培するよりも、フィリピンやタイなど熱帯地域での露地栽培が圧倒的に有利であることは間違いなく、冬場の高単価時にスポット的な輸入が開始された。その後は、他の品目同様、輸入される期間が徐々に長くなり、本県産のシェアは徐々に輸入品に置き換えられ現在は2,300トン程度の出荷量にまで減少してきている(図7)。
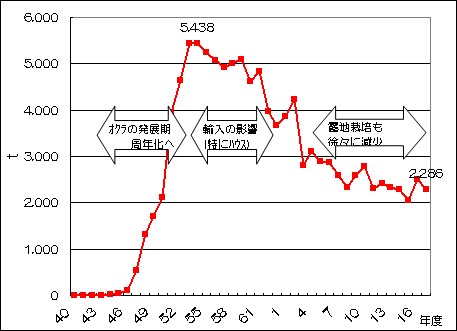
平成17年度の高知県産とフィリピン産のオクラの東京中央卸売市場における月別取扱量を比較してみると(図8)、驚くほどはっきりと、輸入と国産で産地の棲み分けができていることがよくわかる。ただ、ここでもはっきり量がつかめるのは、あくまで一般の市場流通経由での生鮮品だけでの実態である。業務用スーパーなどには、一年中オクラの冷凍品が並んでいるし、外食や中食などで利用されている部分も、大部分は生鮮や冷凍の輸入オクラに埋め尽くされてしまっているのが現実であろう。
高知県産とフィリピン産の比較
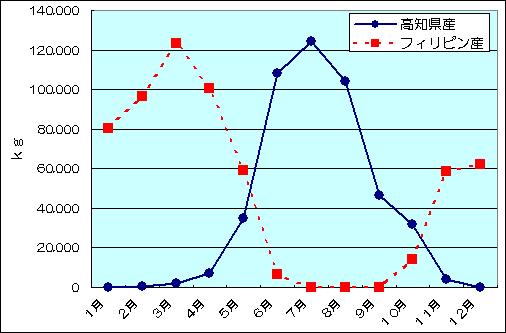
5)ねぎ、にら
ねぎの輸入はまたすさまじい。特に中国からの白ねぎ(長ねぎ)は、品質も急速に向上し、単価面でも今のままでは太刀打ちできない。高知県の主力は、青ねぎと小ねぎで、直接の競合の影響はやや少なく、微減傾向ではあるが周年販売できている。またにらは、もつ鍋ブームは去ったが、根強い消費の定着と韓流ブームなどもあるのか比較的安定している状態である。県では、それらの品目の鮮度保持技術として小袋のパーシャルシール包装を開発し広く普及させた(写真6)。それによって、棚持ちや腐敗事故が改善されたこともあり量販店等での小売り販売は好評をいただいている。

しかしながら、課題は残っている。今の対応で、量販店の棚でのシェアは守れるかもしれない。ところが、外食や中食業界に小袋である必要はないし、そこではカットしたねぎやにらの利用が増加している。輸入業者を訪問して、商品カタログを見せてもらうと、3ミリや5ミリなど様々な用途に応じたカット規格がある(写真7)。また担当者は、自信を持ってこう言った。『冷凍品の場合は、店に冷蔵庫さえあればいい。ゴミもでないし、包丁もいらない。カタログにない規格でも、どんな長さでも切って持ってきますよ。』
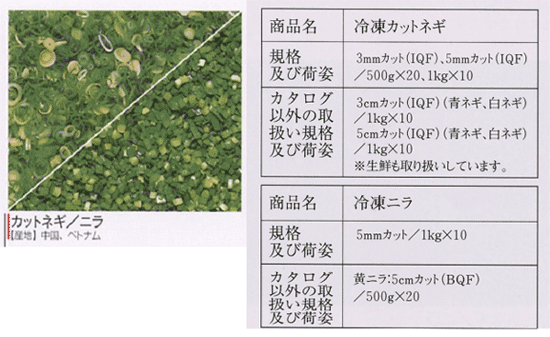
4.わたしたちにできることは何か
1)競争相手をまず知る
本県だけでないが、産地の販売担当者や農家リーダーらが、取引のある卸売市場への視察研修を毎年のように行っている。そして、近くの量販店やデパートなどの売り場を回って、自分たちの作った野菜がきれいに並んでいるのを見て、安心したり、売れ残っていてちょっと不安になったりして帰ってくる。
私たち国内産地は、従来通りのやり方で、その生産物の多くを委託販売してもらっている市場流通の中だけで、『消費者ニーズにあった生産・産地づくり』などを目指してきた。これらの輸入品が市場流通の中で競合しているならば、その実態はもっと現実味を帯びて把握できるし、農家にもその脅威をもっと強く実感として伝えることができる。しかし、特に加工・業務需要向けへの輸入は、大手食品会社や商社が直接開発輸入を行っている場合や、総菜や弁当などの中食、ファミリーレストランや居酒屋などの外食業者へ、市場外流通で取引される場合が多い。国内産地にとっては、まさに競争相手がどこのどんな相手なのかもわからないまま、気づいたときには、『産地の前からお客さんがいなくなっていた!』というような状態が続いているのである。
毎年の市場単価の上下で一喜一憂するだけでなく、自分たちの産地が作っている品目のそれぞれの規格を、どんなお客さんがどういう需要で買ってくれているのかを、国内産地はもっと真剣に再点検していく必要がある。一般の消費者だけでなく、業務加工需要の実需者が本当に求めているのはどういう商品なのか。それに対して輸入品が、どう入り込んできているのか、自分たちが対応できていない部分に、どんな規格や荷姿で入ってきているのかを農家一戸一戸にまでもっと知ってもらう必要がある。
2)国内産地が加工業務需要などにどう対応していくのか。
この5月に、県園芸連とデパ地下の総菜コーナーなどにシェアを持っている大手加工業者と一つの商談が成立した。5月まで全て輸入の冷凍品で対応されていたオクラのメニューの仕入れを、6月から全て高知産に置き換えたのだ(写真8)。その商談には一つの大きな課題があった。本県産のオクラは、70gか100gのネット袋入りでの出荷形態だ。加工業者にとって、ネットや袋は全てゴミになる。産地が一円でも高く売りたいがためにかけた選果・選別・袋詰めの手間は、ここでは意味をなしていない。

園芸連では、JAと協力して特産事業部の中で、この業者向けのバラ出荷対応を実施し、契約をしてもらうことができた。金額にしたらわずかであり、伸びても数十万の話であるかもしれない。しかしながら、私たちは、今後このような商談の対応をどの位伸ばしていけるのかが、本県の園芸の行く末を大きく左右するといえるのではないかと考えている。
その総菜メーカーの年商はなんとすでに400億を超えている。生鮮野菜の仕入れ総額は、その年商のわずか3%程度とのことだが、それでも12億円は野菜を買ってくれているお客さんである。そのうち国産野菜が利用されている割合はわからないが、そこには輸入野菜が多く使われていることだけは間違いない。今や野菜の一般消費は40%そこそこであり、外食や中食業界での消費が55%以上に達しているといわれている。250万トンに上る輸入野菜の多くはそこへ吸い込まれているのだ。そのメーカーのチーフバイヤーさんは私たちにこう言ってくれた。
『私たちは、冷凍の輸入品よりも、常に国産のフレッシュを使いたいと考えている。一円でも高く売りたい、というところは産地も我々も一緒。ようは売り場で商品が売れていくことが大事。私たちのような中食業界が生鮮野菜原料の規格で求めているのは、個数ではないし、アスパラガスなら24cmとかいう長さも関係ない。切って出すわけだから、グラムで考えてもらいたい。』
3)お互いのパートナーシップを再確認
この商談にあたり、市場、仲卸、加工会社、産地が一同に介して情報交換をすることができたことも大きい。お互いの立場と役割分担を確認できた。それぞれの立場で、一致したところは次のとおりである。農産物は、常に一律規格では収穫できない。現状の市場流通の規格(産地の規格)と総菜・加工に求められる規格にもズレがあることも間違いない。お互いにメリットである接点を見つけていき、今の市場流通している規格の10%でもいいので、産地にも会社にもロスのない、価格的にもお互いにメリットのある形で取引がしていけるように、少しずつ近づいていければ商談はやっていける。強く思うのは、まずはこういう会社との"生の話"を産地(生産者やJA担当者ら)にもっともっと伝えていく必要があるということだ。
5.高知県のこれからの戦略
量販店に限らず、産地との商談の相手はますます多様化し大きくなっている。契約のためには柔軟な対応と量の確保が必須となる。産地の個々の農家がそれぞれバラバラではとてもこういう対応はやっていけない。特に本県のような遠隔産地の場合は、小さい産地やJAがそれぞれに動いてもまとまらなくなる。
本県には、園芸連を中心とした全ての品目と産地を県下一本にまとめた出荷販売体制システムがある。一つの品目だけでなく、県内にある全ての品目を電話一本で調達することができる系統共販システムを持っている産地は多くはない。売り手市場であった時代から築き上げてきたこのシステムは、本県の大きな特徴であり販売の力となってきた。県では完全に買い手市場となっているこの厳しい時にこそ、他産地にはすぐにマネのできない大きな強みであるこの県一本の系統共販システムをより強く・柔軟な対応のできる体制としていくことを目指している。3年前より県内全JAの組合長と各農業団体の長に参加してもらって、園芸戦略推進会議を立ち上げ、プロジェクトチームを編成して様々な取り組みを進めている。
また、輸入農産物があふれていると言っても、実際に消費者調査等を実施すると、ほとんどの消費者は間違いなく国産野菜を応援してくれている結果となっている(図9)。そんな消費者を決して裏切らず、本当に安心して『おいしい!』と喜んでもらうために、環境保全型農業の取り組みやトレーサビリティの徹底等も進めている。残留農薬のポジティブリスト制への移行を追い風にするのか、向かい風ととるかは産地自身の姿勢次第である。
アンケート結果
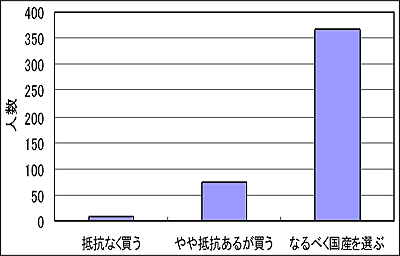
今後も次から次へと、新たなルートで開発輸入が進んでくるだろう。市場や量販店のニーズのみでなく、様々な実需者のニーズ等の『情報収集と分析』が求められている。また常に最新の情報として、生鮮のみでなく、冷凍やフリーズドライあるいは調理加工品等についても、その輸入の詳細な実態把握と分析についても継続して実施していく必要がある。また、最大の輸入国である中国をはじめとして今後急増する可能性もある東南アジア諸国等供給地の実情なども知っておきたい。
また、産地には一般の市場流通での情報しか入りにくいので、商社の動きや、外食・中食業界などでの市場外流通の実態についても、もっと積極的に情報収集をしていく必要があると思う。
国内産地が、じっと現状を守っていく時代は間違いなく終わった。系統流通においても、1%からでもいいので新しいルートを開拓していくことの意義は大きいはずだ。今後も、輸入に埋められていくのか、それとも私たちの農産物で少しでも埋め戻していくチャンスがあるのか。その答えは今すぐにはわからないが、まさに国内産地にこそ求められているビジネスチャンスなのかもしれないと考えている。